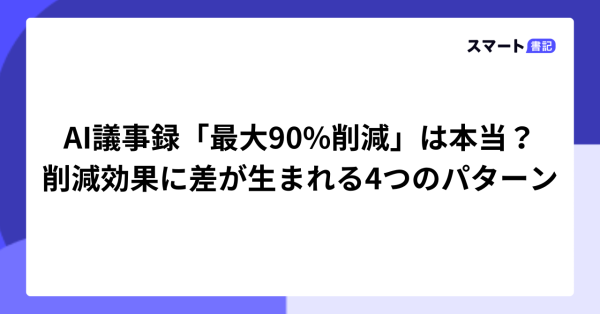【例文&練習法紹介】要約のコツを徹底解説!手順やコツ・注意すべきポイントから便利なツールまで紹介
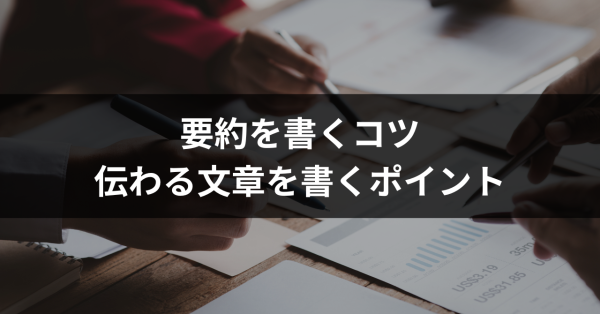
この記事でわかること
- 要約を作成するためのコツ・注意点
- シーン別の要約の具体例と書き方
- 要約が自動でできるおすすめツール
日常生活で膨大な情報が溢れている現代では、「大切なことを短く分かりやすく伝える力」が求められています。学生であればレポートや論文をまとめる力、ビジネスパーソンであれば会議の議事録や報告書の作成のために要点を押さえる力、すなわち「要約するスキル」は欠かせません。
しかし、「要約する」ということは、要約元の文章や発言の意図を正確に理解・分析しまとめる能力が必要な、非常に難易度の高い作業です。「どうすれば完成度の高い要約が作れるのか」「要約の精度を上げる勉強法がわからない」などと、お悩みの方も多いのではないでしょうか。
要約は、ただなんとなくで書くのではなく、しっかりと手順を踏み、コツや注意点を意識することで、より優れたものが書けるようになります。要約にあまり慣れていない方は、事前に書き方やコツ、ポイントなどを抑えておくと、要約が書きやすくなるでしょう。
今回の記事では、学生や社会人、また日本語や英語などの言語を問わず、誰でも・どんな時でも使える
について解説します。
また精度高く要約をしたい方は、ぜひ使えば使うほど精度が上がるOtolio(旧:スマート書記)をお試しください。Otolioは特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、使えば使うほど各社に最適されたAIの活用ができ、議事録作成時間を大幅に削減させることができます。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or 資料を請求する
「要約」とは?
そもそも、要約では何をすることが求められるのでしょうか。
まずはじめに、よく混同しがちな「要約」「要点」「要旨」の違いから解説します。
| 種類 | 意味 | 特徴 |
|---|---|---|
| 要約 | 文章や話の内容を簡潔にまとめたもの | 元の文章構成を崩さずに短くまとめる |
| 要点 | 段落ごとの特に重要な部分・ポイント | 要点をまとめたものが要約 箇条書きで示されることもある |
| 要旨 | 文章や話全体の主な意味・主張・最も伝えたいこと | 元の文章の流れに沿わなくてもOK |
文章や話の内容を簡潔にまとめるために最も大事なのは、要約を作成する側の「理解力」です。
書き手が読み手に最も伝えたい点はなにか、会議の最も重要でマストで共有しなければならないことはなにか、それぞれ物事の全体像とその要点を把握することが、要約作成に必要なスキルです。
要約に必要な5つのSTEP
では、具体的に要約とは具体的にどういった手順で書いていけばよいのでしょうか?ここでは5つのステップに分けて解説します。
STEP 1. 【事前準備】要約文の文字数を設定する
まずは、要約文の文字数をあらかじめ設定することが大切です。文字数を決めることで、元の文章のどこを削るべきか、どれくらい情報を絞る必要があるか、といったことが見えてきます。
特に、試験やレポートなど、事前に字数が指定されている場合は、その指定された字数から「何をどこまで書くべきか」を逆算して考えることがポイントです。
STEP 2. 要約元の全体像を把握し、理解を深める
要約は、元の文章や発言の構成を崩さずにまとめることが重要です。そのためには、全体の内容と流れを的確に把握する必要があります。
文章の要約であれば、まずは全体に目を通して、構成を理解した上で要点を抽出します。会議の要約を作成する場合であれば、会議全体の流れや目的を振り返って、要約の方向性を定めましょう。全体像を把握することで、情報の抜け落ちや過不足を防ぐことができます。
STEP 3. 全体を意味段落で分ける
「意味段落」とは、文章の中で内容の繋がりによってひとつのまとまりになっている部分を指します。形式的に分けられた見た目の段落とは異なり、意味や話題の切れ目で区切られるのが特徴です。STEP2で文章全体の内容が把握できたら、その中にいくつの意味段落があるかを考えてみましょう。
このステップを通じて、筆者や話し手が、どのような順序や方法で主張を展開しているのかがわかりやすくなり、要約を書きやすくなります。
STEP 4. 要点となる部分を見つける
文章であれば書き手が一番伝えたいこと、会議内容であれば会議中で最も重要な点を見つけましょう。見つけるポイントは、STEP 3で分けた意味段落ごとに、何を伝えたいのかをピックアップすることです。意味段落の結論部分をチェックしてみましょう。
また、文章の最終段落などでは、筆者の真意が軽く触れられていることがあります。こうした箇所も要約する上で重要な情報となることがあるため、見落とさないように注意しましょう。
STEP 5. STEP1-4を元に自分の言葉でまとめる
STEP1から4を行なうことで、まずは全体像を把握してから、見えてきた全体像を細分化していき、要点の抽出までできました。ここまできたら、あとはそれを元にまとめることで要約が完成します。
ここでポイントなのは、元の文章をそのまま引用して使わないことです。元の文章をそのまま使用することは、著作権法に抵触する恐れがあります。要約においては、自分の言葉で要点を伝えることが重要です。
ただし、自分の言葉で伝えると言っても、そこに自分の考えや解釈は入れないように注意しましょう。
要約作成の5つのコツ
大体の要約作成の手順や書き方が分かったあとは、要約作成の際のコツを押さえていきましょう。
1. 結論・結果・根拠に注目する
元の文章を読む際は、筆者の結論や主張、それを支える根拠や理由に注目しましょう。それによって、要約をするときに必要な情報が見えやすくなります。特に意見文では、「何を言いたいのか(=結論)」と「何故そう言えるのか(=根拠)」をセットで意識することは非常に重要な作業です。また、小説や物語文などでは、経緯と結果に注目すると、話の展開が理解しやすくなり、適切な要約がしやすくなります。
2. 読み手に「伝える」「伝わる」文章を意識する
要約は、元の文章や会話を知らない人でも意味が伝わるように書くことが求められます。読み手が要約を読んだ際に、内容の全体像や重要なポイントが把握できるか意識して書きましょう。
また、筆者や発言者が独特の表現や専門用語を使っている場合は、読み手が元の情報をどの程度知っているかを想定して、専門用語を言い換えたり、説明の詳しさの文量を調整しましょう。
3. キーワードを拾って文章に含める
要約元の文章中で何度も繰り返されている言葉や重要そうな語句は、その文章のキーワードである可能性が高いです。こうした言葉を要約文に取り入れると、元の主張が伝わりやすくなるでしょう。
ただし、「キーワードを抜き出しでそのまま並べただけ」では要約とはなりません。キーワードを軸に、文章の意味が通るように組み立てていきましょう。これについては「5. キーワードの羅列は要約ではない」で詳しく解説します。
4. 文中の例はうまく活用して要点に変換する
ただし、文字数制限のある要約では、例文をそのまま入れてしまうと文字数が足りなくなってしまうことがあります。そのため、例文を通して筆者が伝えたかった結論・要点を抽出して、自分の言葉で簡潔に記載しましょう。
5. 推敲を徹底する
上で紹介した要約に必要な5つのSTEPとコツを活用して、要約を書き終えたら、必ず最後に推敲しましょう。推敲の際は、内容が正確に伝わっているか、誤字脱字や文法ミスはないか、といったところに加えて、次でご紹介する要約を作成するときの注意点も押さえて確認しましょう。
要約を作成するときの5つの注意点
具体的に文章を書いていく中で注意すべきポイントも押さえておきましょう。
1. 元の文章をそのまま書かない
元の文章や表現をそのまま書き写すと、字数が足りなくなったり、筆者の意見を正確にまとめることが難しくなったりします。また、要約した文章を記事や論文などの形式で世に出す場合、引用の断りなく元の文章の表現を使うと盗作と判断されてしまう危険性もあるでしょう。全ての言葉を置き換える必要性はありませんが、できるだけ自分の言葉で言い換えるようにしましょう。
2. 曖昧な言い回し、くどい文末は避ける
「~と思います」のような曖昧な表現や、「~ではないでしょうか」のような丁寧な言い回しは、字数を無駄に使い、内容もぼやけてしまうため、要約には不要です。要約文では「だ・である」調が用いられることが多く、簡潔かつ断定的に言い切るのが基本です。
3. 元の文章構成・順序を崩さない
「要約」というのは、元の文章や発言の論理構成・順序を保ちつつ簡潔にまとめることを指します。順序を入れ替えたり、情報の配置を変えると、元の文章の意図や主張の流れが損なわれる危険性があります。したがって、元の文章の論理構成を変えないように、元の流れに沿ってまとめましょう。
4. 自分の意見や解釈は入れない
要約は、あくまで筆者や発言者の主張を客観的にまとめる作業です。読み手が、要約に書かれている情報が誰の考えなのか混乱しないように、自分の意見や解釈など本文中に書かれていない主観的な記載は避けて、客観的な記述を心がけましょう。
5.キーワードの羅列は要約ではない
要約の初心者が陥りやすい誤りとして、「文章中のキーワードや重要そうな部分をただくっつけるだけ」というものがあります。しかし、要約は元の文章構成を変えずに、発言や文章の真意をまとめる作業です。そのため、文章全体の意味や論理展開・情報の優先順位などを考慮しながら、要約を作っていく必要があります。
キーワードや重要そうな発言をただ抜き出してくっつけるだけでは、筆者や発言者の主張がわかりにくく、質の低い要約となってしまう可能性が高いため注意しましょう。
シーン別|要約例と練習方法を紹介
ここまで、要約の手順、コツ、注意点をお伝えしてきました。ここからは
- ビジネス用要約
- 勉強・試験対策用要約
- 本・文献要約
の3つに分けて実際の要約例と練習方法をご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
ビジネス用要約
ビジネス用要約では、 会議や報告書の中で最も重要な課題や決定事項に焦点を当て、要約を作成するようにしましょう。また、具体的な結論や数字がある場合はそれも要約に盛り込みましょう。
【要約前の文章】
本日の会議では、プロジェクトの進捗状況が議論された。特にマーケティングチームの進捗が遅れていることが問題視された。リソース不足が原因とされ、次回までに解決策を提出することが求められた。また、予算のコスト削減案についても議論が行われたが、具体的な案の決定は次回に持ち越されることになった。マーケティングチーム以外のチームはおおむね予定通り進行しており、開発チームは目標を上回る成果を挙げている。しかし、マーケティングの遅延が全体の進行に影響を与える可能性があり、迅速な対応が必要とされる。次回の会議では、新たなマーケティング戦略も話し合われ、外部の専門家を招いて解決策を議論する予定である。プロジェクトのスケジュールに遅延が出ないよう、各チームが適切に連携しながら進める必要がある。
【要約後の文章】
会議では、プロジェクト進捗の確認が行われ、特にマーケティングチームの遅延が問題視された。リソース不足が遅延の原因であり、次回までに解決策を提案することが決定された。予算に関するコスト削減案も議論されたが、詳細は次回会議で決定することになった。他のチームは順調に進行しているが、マーケティングの遅延が全体の進行に影響を与えるため、迅速な対応が求められる。
【練習方法】
- 新聞の100文字要約
毎日新聞の記事を1つ選び、100文字で要約します。何について述べているのか、結論は何か、という2点に着目して100文字で内容を要約しましょう。
- 会議後、内容を要約する
会議の後には、内容を箇条書きで要約します。5W1Hに着目し、必要最低限の情報に絞ってまとめましょう。会議に参加しなかった人にも正しく情報共有ができる要約文になっているか、実際に周囲の人からのフィードバックも貰うと良いでしょう。
勉強・試験対策用要約
勉強・試験対策と一言でいっても、教科によって要約のコツや練習法は異なります。以下では、社会科、現代文、英語に分けて要約の例文、練習法をご紹介します。
社会科
社会科の勉強・試験対策用要約では、重要な出来事の順序や影響を時間軸で整理し、余計な背景説明は省くことが重要です。また、以下の例文で示しているように、特に歴史の文章要約では、戦争や事件の原因や結果を短くまとめ、世界への影響を明確に伝えることが重要です。
【要約前の文章】
第二次世界大戦は1939年、ドイツのポーランド侵攻をきっかけに始まった。ナチスドイツの侵攻により戦争が激化し、連合国側にはアメリカ、イギリス、ソビエト連邦などが含まれ、枢軸国側にはドイツ、イタリア、日本が加わった。ヨーロッパではドイツがフランスを占領し、太平洋では日本が真珠湾攻撃を行い、アメリカが参戦した。戦争は6年間に及び、1945年に連合国が勝利を収めた。ヨーロッパではドイツが無条件降伏し、アジアでは原子爆弾が広島と長崎に投下され、日本が降伏した。この戦争は世界中に大きな影響を与え、戦後の国際秩序の再編をもたらした。また、冷戦時代の始まりとなり、戦争後の世界情勢に大きな変化をもたらした。
【要約後の文章】
第二次世界大戦は1939年、ドイツのポーランド侵攻をきっかけに勃発した。連合国にはアメリカ、イギリス、ソビエト連邦が、枢軸国にはドイツ、イタリア、日本が含まれた。戦争は6年間続き、1945年に連合国が勝利を収めた。ドイツはヨーロッパで無条件降伏し、日本は原子爆弾投下後に降伏した。第二次世界大戦は、戦後の国際秩序や冷戦時代の始まりに大きな影響を与えた。
【練習方法】
- 教科書の1章を要約
勉強中の教科書の1章を読み、各段落の要点をメモした後、それを元に200文字で要約してみましょう。重要な情報だけをピックアップしようと意識するため、要約の練習になるだけでなく、その章の内容理解にも大きく役立ちます。
- 自分で問題を作成する
学習範囲から重要ポイントをピックアップし、自分なりに「○○文字で要約しなさい」という問題とその要約回答例を作成してみましょう。回答例を作るときは、試験時同様、時間を意識して作成してみてください。
現代文
現代文の要約では、文章の主張や論理展開を正しく捉え、不要な具体例や説明を省いて、筆者の考えをコンパクトに再構成することが求められます。評論文などでは、比喩や具体例に惑わされず、「主張―理由―結論」の流れに沿って要点を抽出することが大切です。
【要約前の文章】
現代社会において、「効率性」や「計画性」が重視される傾向はますます強まっている。ビジネス、教育、日常生活のあらゆる場面で、無駄をなくし、最短距離で成果を得ることが良しとされる風潮がある。しかし、私たちはそのような価値観の中で、ある重要な要素を見落としてはいないだろうか。それは「偶然性」である。
偶然とは、計画や意図とは無関係に生じる出来事のことであり、一見すると非合理で無駄のようにも思える。しかし、人間の創造性や発見の多くは、まさにこの偶然から生まれている。たとえば、ペニシリンの発見やポストイットの開発は、どちらも偶然の産物であり、それが新たな価値を生んだ。また、日常においても、ふとした寄り道や予定外の出会いが、新しい考え方や選択肢を生むことがある。偶然を完全に排除した環境では、創造的な発想や多様な可能性が閉ざされてしまう恐れがある。
したがって、私たちは効率性だけでなく、偶然性がもたらす価値にも目を向けるべきである。予定外の出来事や非効率な行動の中にこそ、新しい視点や豊かな経験が潜んでいる。現代社会が本当に豊かさを求めるのであれば、「偶然の受け入れ方」こそが鍵となるのではないだろうか。(ChatGPTにより作成)
【要約後の文章】
現代社会は効率性を重視するが、偶然からこそ創造的な発見や多様な可能性が生まれると筆者は述べる。計画外の出来事を排除せず、偶然を受け入れる姿勢が、豊かな社会につながると主張している。
【練習方法】
- 評論文を段落ごとに要点整理
まずは、評論文やコラムを段落ごとに読み、「その段落で一番伝えたいこと」を1文でメモしていきましょう。段落ごとの要点を整理した後、それを組み合わせて100〜200字にまとめてみてください。段落ごとに「主張・理由・具体例」の構造を意識することで、論理的な要約ができるようになります。
- キーワードを残してまとめる
筆者が繰り返し使っている語句や抽象的なキーワード(例文だと「効率」「価値」「偶然」など)を残すようにして要約する練習をしてみましょう。これは、入試や記述問題でも評価されやすい「筆者の語彙を正しく再構成する力」を養うのに役立ちます。
英語
英語の要約では、英文の主旨を正しく読み取り、それを簡潔な文にまとめる力が重要です。特に、定期テストや英検、共通テストなどでは、英文全体の要点をつかんで短く答える問題が多く出題されます。英文要約は、文の構造を意識し、具体例を省いて主張・理由・結論に絞ることが基本です。
【要約前の文章】
Many people believe that using smartphones in class can distract students. However, some studies show that when smartphones are used for educational purposes, such as research or taking notes, they can actually improve learning outcomes. Therefore, it is important not to ban smartphones completely, but to teach students how to use them effectively in the classroom.
【要約後の文章】
スマートフォンは教育目的で使えば学習効果を高める可能性があり、完全に禁止すべきではないと述べられている。
【練習方法】
- パラグラフごとにトピックセンテンスを抜き出す
英文を読むときは、まず各段落の最初や最後にある「トピックセンテンス(主題文)」を見つけます。その内容をもとに、日本語または英語で「何が言いたいのか」を1文でまとめる練習をしましょう。
- 短い英文要約を繰り返す
英語で要約する際は、中学レベルの英語表現でも問題ありません。たとえば、”The author argues that…” や “This article explains that…” の形を使って、20〜30語以内でまとめる練習を繰り返しましょう。ポイントは、具体例や数字ではなく、「筆者の意見・結論」に焦点を当てることです。
本・文献要約
本や文献を要約する際には、まず文章全体のテーマや筆者の主張を掴みましょう。そこから、章ごとのメインポイントや重要な結論に焦点を当て、細部は省略します。物語の場合は一人称視点で描写されることもありますが、要約は客観的な視点で作成しましょう。
【要約前の文章】
ここでは、「走れメロス」を要約します。
青空文庫で公開されているため、要約より先に話の概要を知りたい方は、まずそちらをご覧ください。
参考記事:太宰治 走れメロス
【要約後の文章】
メロスは、暴君ディオニスに反抗し、親友セリヌンティウスを人質に取られた上で、3日以内に戻ることを条件に解放される。故郷に帰り用事を済ませるが、帰路で様々な困難に見舞われる。それでもメロスは全力で走り、約束の時間に間に合う。彼の誠実さに感動したディオニスは、二人を許す。
【練習方法】
- 長編は1章ごと、短編・論文は全体の内容を読了直後に要約
長編小説は1章ごとに、短編小説や論文は全体の内容を、読了後5分以内に200文字以内で要約してみましょう。小説は5W1Hを意識し、論文の場合は背景、目的、方法、結果、考察、結論から重要な点をピックアップするようにしましょう。
- レビュー作成
読み終わった文章について、誰かに内容を説明することを想定してレビューを作成します。主題や結論を入れて100文字程度で内容をまとめ、実際に周囲の人からフィードバックを貰ってみましょう。
ぜひ、自分の状況に合った要約例と練習方法を参考にして、要約文を実際に作成してみましょう。
お悩み別|解決策と練習方法を紹介
ここでは、要約に関する以下の3つのお悩み別に解決策と練習方法をご紹介します。
- どこが要点かわからず、原文を丸写ししてしまう
- 要点は拾えるが、文章が不自然になる
- プレゼン・議事録・論文要旨など場面別要約ができない
どこが要点かわからず、原文を丸写ししてしまう
「どこが大事なのか分からず、全文をそのまま写してしまう」というのは、要約に慣れていない人が最もよく直面する悩みです。文章全体を通して情報が詰まっているように感じ、どれを削ればいいか判断できないため、結果として原文とほぼ同じ文章になってしまいます。
【解決策】
要約に必要なのは、「重要な情報」と「そうでない情報」を見分ける力です。
そのためには、文章の中で筆者が一番伝えたい主張(=結論)と、それを支える根拠・理由に注目することが必要です。段落ごとに「何について書いているのか」をざっくり把握し、例え話や補足説明は一度省いて考えるクセをつけましょう。
【練習方法】
- 文章中で一番言いたいことを15〜20字で抜き出す
まずは、文章の中で「一番言いたいことは何か」を短くまとめる練習から始めましょう。ニュース記事やコラムなどを一つ読んだら、その内容を自分の言葉で15〜20文字程度に言い換えてみてください。文中から主張や結論を探し出し、それを簡潔に表現することで、「要点を抜き出す力」が身についていきます。
- 段落ごとの要点を1行でまとめる
これは、段落ごとの要点を整理する練習です。3〜4段落の文章を読んで、それぞれの段落が何について書かれているのかを一行でメモします。「誰が」「何を」「なぜ」など、情報の中心となる部分を抜き出すよう意識してください。
- 本文を読む前に主題を予想
本文を読む前に、その本や章のタイトルから内容を予想しておくことも要約の練習の一つです。タイトルや見出しだけを見て、「この文章はどんな話題か?」を想像し、キーワードを先にメモしてから本文を読みましょう。これにより、本文を読んだときに自然と要点が浮かびやすくなります。
要点は拾えるが、文章が不自然になる
ある程度要点は押さえられるけれど、書きあがった要約文が読みにくかったり、文章としてつながりが不自然に感じるというのも中級者に多い悩みです。
要約が「箇条書きの寄せ集め」になってしまったり、接続語がなく、読み手にとって論理の流れが見えにくい状態になってしまったりしがちです。
【解決策】
必要なのは、要点同士を自然につなげる「構成力」と「接続表現」の使い方です。
要約では「話の順序」「因果関係」「具体と抽象」を整理することで、文章が通じやすくなります。「何が先に来て、何が理由なのか」といった論理の流れを意識して接続語(たとえば、しかし、つまり、一方で、など)を適切に使うことが、自然な文章への第一歩です。
【練習方法】
- 三文以内で要約
文章の構成力を養うには、「限られた文数で自然につなげてまとめる」練習が効果的です。ニュースやブログなど500~800文字程度の文章を読み、3文以内で要約することを目標にしてみましょう。その際、「まず」「そのため」「結果として」などの接続語を適切に使いながら、話の流れを整理するよう意識すると良いでしょう。
- 音読で違和感を見つける
文章の不自然さを見つけるのに音読は非常に有効な方法です。自分が書いた要約文を声に出して読み上げてみると、不自然なつながりや論理の飛躍に気づきやすくなります。つっかえた部分や読みづらさを感じたところは、接続後を追加したり修飾語を減らしたり、主語述語の順番を変えたりして文章を修正してみましょう。
- 文章の再構成
文章の再構成練習もおすすめです。「結論→理由→具体例」や「問題→原因→対策」といった基本的な構成パターンに当てはめながら、要約文を組み立て直してみてください。論理の流れを意識する習慣が身につき、読み手に伝わる自然な文章に近づけます。
プレゼン・議事録・論文要旨など場面別要約ができない
プレゼンや会議、レポートなど、「場面に合った要約」ができないと悩んでいる人は、「すべての要約を同じ書き方で行おうとしている」ことが多いです。しかし、要約は目的や相手によって、求められるスタイルや内容の深さが大きく異なります。
【解決策】
必要なのは、「誰に、何のために伝えるのか」という目的に合わせて情報の取捨選択を切り替える力です。
たとえばプレゼンでは結論を先に示し、論文要旨では背景から順を追って構成します。どの場面で、どの順序と語調で要約するのが適切かを理解することで、相手に伝わる要約ができるようになります。
【練習方法】
- 同じ内容を3通りで要約
場面に応じて要約の仕方を切り替える力を養うためには、同じ文章を異なる目的・相手に向けて書き換える練習が効果的です。たとえば、「上司への報告メール用」「友人に口頭で説明する用」「SNSに投稿する用」の3パターンでそれぞれ要約してみましょう。伝える相手や目的によって、内容の深さや言葉づかい、順序がどう変わるのかを体感できます。
- 実際のフォーマットを書き写す
実際のフォーマットを使った模写も有効です。議事録やレポート、論文要旨などの具体的な文章をネットなどで探し、それを書き写してみましょう。文章の流れや語尾の使い方、どんな情報が含まれているかを観察しながら写すことで、型を自然と身につけることができます。
- 読み手を想定して自己添削
要約を書き終えた後に「これは誰が読む文章なのか?」と改めて問い直してみましょう。読み手の視点から内容を見直す練習になります。必要な情報が過不足なく含まれているか、言葉づかいは適切かなどを確認し、相手に合わせた要約に仕上げていきましょう。
AI搭載のツールを使って要約を作成する方法も
上記で解説したような方法で要約を書くことはできますが、今すぐに完成度の高い要約を作成したい、という方も多いでしょう。そこで、もうひとつの選択肢として、AIツールを使用して要約を作成するという方法をご提案します。
要約の精度はAIによりけりで、必ずしも正しい要約結果を作成してくれるわけではない点は注意が必要ですが、AIを使用する上での注意点さえ押さえれば、便利に時短で要約を作成できます。
今回は要約するシーン別に
- 会議内容を要約できるAI議事録作成ツール
- 論文やニュースの内容を短時間でインプットできるツール
- 要約から文章作成・資料作成までできるツール
の3つをご紹介します。
会議内容を要約できるAI議事録作成ツール
Otolio(旧:スマート書記)

引用:Otolio
Otolioは使えば使うほどAIの精度が上がるAI議事録ツールです。複雑な設定や用語登録を行わなくても、今まで通り議事録を作成するだけで、各社に最適化された高精度の文字起こしが可能です。
この高精度の文字起こしにより、自動要約や要点抽出が可能なOtolioの機能「AIアシスト」の精度も向上し、議事録やドキュメント作成にかかる時間を大幅に削減することができます。またこれらはAIに学習させることなくAI精度を向上させる特許取得済の独自アルゴリズムを活用しているためセキュリティ面でも安心してご利用できます。
Otolio(旧:スマート書記)の特徴
- 機密情報を学習させることなく、使えば使うほど各社に最適された高精度の文字起こしを提供
- 様々な議事録・ドキュメントの作成時間を削減できるように複数のAI出力形式に対応
- 累計6,000社以上の利用社数。大手企業から自治体まで様々な組織で利用されている信頼性の高いセキュリティ
実際にOtolioを無料で14日間試してみたい方、資料を請求したい方はこちら。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or 資料を請求する
AI議事録ツールについて、機能や選ぶポイントなどを詳しく知りたい方は、こちらの参考記事もぜひご覧ください。
論文やニュースの内容を短時間でインプットできるツール
ChatPDF
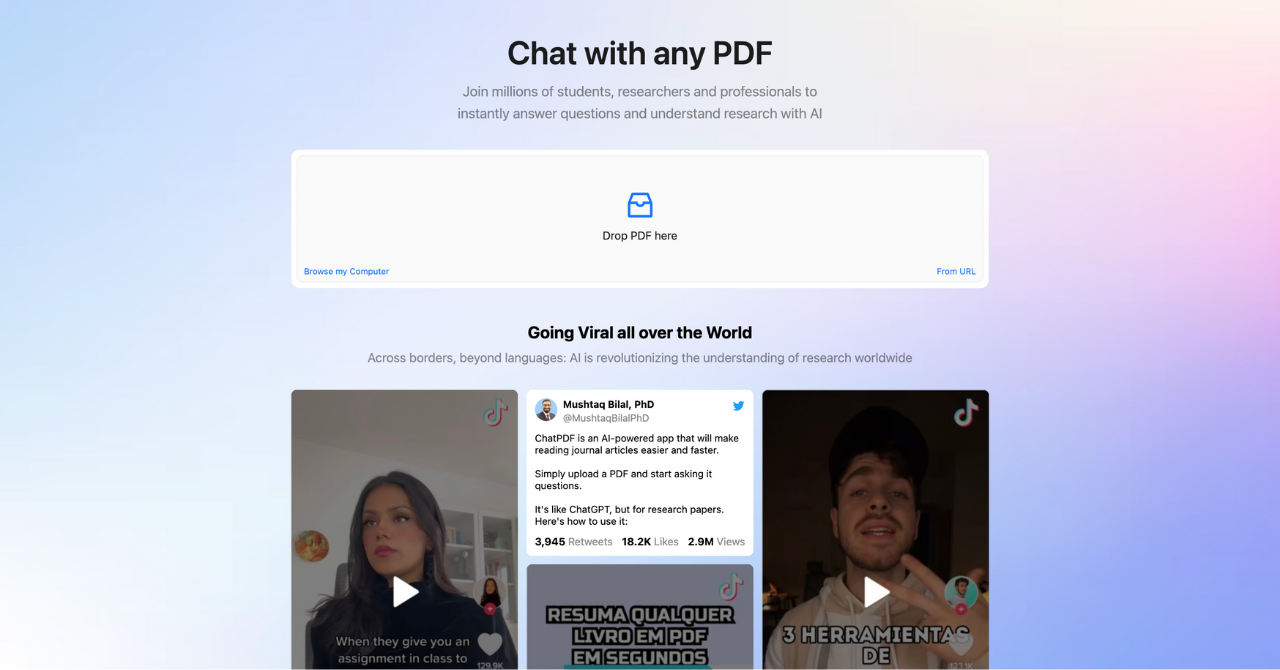
引用:ChatPDF
ChatPDFは、PDFの内容を要約するAIツールです。PDFの内容を要約するだけではなく、その内容について質問をするとチャット形式で回答もしてくれます。
ただ要約して情報収集するだけではなく、自分が気になった点や要約されたものをみて疑問に感じた点などを質問し回答を得ることができるので、論文などの膨大な情報量のもののインプットに役立てることが可能です。
オンラインでの使用はもちろんのこと、アプリもあるため、使いやすいツールとなっています。
ChatPDFの特徴
- PDFの内容を要約するだけではなく、その内容について質問をするとチャット形式で回答
- 英文の文章に対して、日本語で質問しても日本語で回答が得られる
- 無料版があるため気軽に利用でき、有料版でも5ドル/月で利用しやすい
要約から文章作成・資料作成までできるツール
Canva

「Canva」と聞くと、画像編集で使うデザインツールとイメージされる方も多いかもしれませんが、実はCanvaに搭載された「Magic Write」というAI機能を用いることで、文章の要約をすることもできます。
Canvaでは、プレゼン資料やドキュメントなどの作成もできるため、「Magic Write」を活用して、Canva内で要約から資料作成までを一貫して行いたい人におすすめのツールです。
また、「Magic Write」は要約だけでなく、アウトラインの作成、文章続きを自動で作文、見出しや段落の生成機能、言い換えツールなども搭載されており、ブログ記事の作成やアイデア出ししたい人も、一度試してみると良いでしょう。
Canvaの特徴
- デザインツールとAIツールがCanvaでひとつにまとまっている。
- 無料のCanvaサブスクリプションに登録すれば、合計で最大25回利用可能
- Pro、Teams、またはNFPのサブスクリプションに登録すれば、1か月あたり最大250個のクエリを生成可能
今回は抜粋して紹介していますが、要約ができるおすすめのAIツールについては、こちらの記事で詳しく解説しているので、よろしければ参考にご覧ください。
まとめ|読み手に伝わる文章を書こう!
今回は、要約を書く際のコツと具体例を解説しました。
文章を要約するためには、要約元の物事の全体像を把握する「理解力」が必要です。要約力を伸ばすということは、物事を俯瞰して見る理解力も同時に身に付き、また、それを相手に「伝える力」がつきます。
「伝える力」が身につくことは、要約を作成するスキルのみならず、様々なシーンで人とコミュニケーションを取る際に活きてきます。今回ご紹介した要約の書き方のコツを意識しながら、「伝える力」を磨いていきましょう。
また、AI要約ツールを活用することで、議事録や資料作成を効率化したり、論文やニュースなどの内容を短時間でインプットできたりしますので、選択肢のひとつとして考えてみてはいかがでしょうか?
- 会議後の議事録作成に時間がかかっている
- 議事録を作成するために会議中にメモを取っているため、会議に集中できない
- 議事録作成後の言った言わないの確認に時間がかかっている
このような議事録に関するお悩みがあれば、ぜひ一度、使えば使うほどAIの精度が上がる「Otolio」をお試しください。
Otolioは特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、使えば使うほど各社に最適される高精度の文字起こしが可能です。高精度で文字起こしができるため、その後の自動要約や要点抽出などの精度も向上し、議事録作成時間の削減が可能です。
またその他にも、以下のような特徴があります。
- 様々な議事録やドキュメント作成に対応できる
- 要約文章の生成、要点や決定事項やToDo・質疑応答の自動抽出など複数の出力形式を選択できる
- 音声を含めた情報共有で会議の振り返りを効率化できる
- 対面会議、Web会議で利用が可能
- 「えー」や「あの」など意味をなさない発言を最大99%カット
- 発言内容をリアルタイムで文字起こし
- 最大20名までの発話を認識し、誰がどの発言をしたかをAIが自動で可視化
累計利用社数6,000社以上の実績、大手企業から自治体まで様々な組織で利用されており、セキュリティ面でも安心してご利用いただけます。まずは14日間の無料トライアルをお試しください。