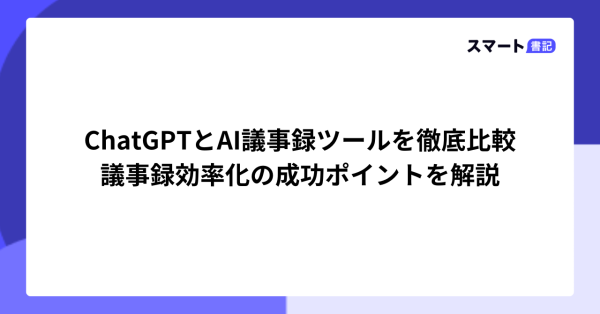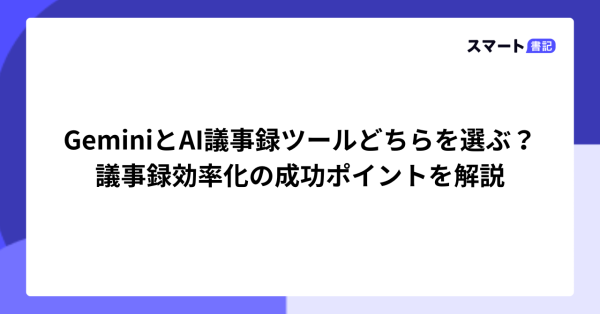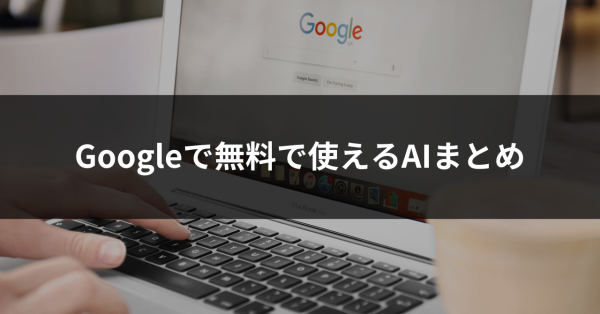【初心者向け】生成AIとは?簡単にわかりやすく解説!生成AIの種類やモデル比較・活用シーンも紹介

ChatGPTなどの生成AIが日々進化しており、今では私たちの日常生活や企業の業務プロセスでも幅広く活用されています。また次々と生成AIを活用した新しいサービスも増えてきていますが、まだまだ生成AIを業務上で利用できていない人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では生成AIの基本的な情報や活用メリットや注意点などを幅広くご紹介していきます。「生成AIの概要について簡単にイメージできるようになりたい」「生成AIについて詳しく知りたい」「どんなふうに活用できるのか知りたい」とお悩みの方はぜひ本記事をご覧ください。
また精度高く要約や要点の整理ができるAIツールを活用したい方は、ぜひ使えば使うほど精度が上がるOtolio(旧:スマート書記)をお試しください。Otolioは特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、使えば使うほど各社に最適される高精度の文字起こしが可能です。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or サービス資料をみる
Otolio(旧:スマート書記)がわかる人気3点セット資料(サービス概要・導入事例・機能詳細)をみる
生成AIとは
生成AIは、大量のデータを学習し、そのデータから文章や画像といった新しいコンテンツを生成するAIの総称です。「何かしらのコンテンツを作成してくれるAI」とイメージすると分かりやすいかもしれません。
今までAI(人工知能)は決まったルールに従って動くことが多い状態でしたが、近年「大規模なデータセット」と「強力なコンピューター」の組み合わせによって、生成AIがより高度な理解力と生成能力を持つようになりました。
生成AIの活用によって、今まで多くの時間がかかっていた議事録作成や、マーケティングのコピー案の作成、営業の提案資料の作成などの業務効率化が期待できます。そのため、多くの企業が生成AIの動向に注目しており、今後も企業での生成AI活用の動きはますます進んでいくとされています。
「AI」と「生成AI」の比較表
AIと生成AIを比較すると、以下のようになります。
| AI | 生成AI | |
|---|---|---|
| 位置づけ | 人工知能全般 | AIの一分野 |
| 主な特徴 | 特定のルールやデータに基づいて予測・分類 | 新しい文章・画像・音声などの生成が得意 |
| 学習方法 | 機械学習ディープラーニング | 教師あり学習自己教師あり学習 |
| タスク例 | スパム判定、需要予測、顔認識 | テキスト生成、イラスト作成、音楽生成、プログラムコード生成 |
| 代表例 | 画像認識AI、金融リスク予測AI | ChatGPT、gemini、Claude |
従来のAIは「機械学習」や「ディープラーニング」で学習してきました。機械学習は、人間が特徴を決め、その基準をもとにAIがパターンを見つける方法です。例えば「無料」「限定」などの単語が多いメールをスパムと判断する仕組みです。これに対しディープラーニングは、人間が特徴を教えなくても、大量のデータからAI自身が重要な部分を学びます。猫と犬の写真を多く与えると、耳の形や毛並みの違いを自動で学び区別できるようになるのです。
つまり従来のAIは、正解のついたデータを使って特定の問題を正確に解くのが基本でした。
一方、生成AIはまず大量の未整理データを使い、文章の一部を予測するなど自分に課題を出して学ぶ「自己教師あり学習」で基盤を作ります。そのうえで、人間が「この質問にはこう答える」と正解をつけたデータを与える「教師あり学習」を行い、より正確で役立つ応答ができるよう仕上げます。
学習を終えた生成AIは、ユーザーの質問や指示を受け取り、次に来る言葉や画像のパターンを予測して新しいコンテンツを作ります。
まとめると、従来のAIは「正解を与えて覚えるタイプ」、生成AIは「自分で問題を作って学び、人間の指導で完成するタイプ」と言えます。AIは専門的で限定的な問題に強く、生成AIは文章や画像を生み出すような創造的分野に優れています。
生成AIの4つの種類
さきほどご紹介したとおり、生成AIとは「新しいコンテンツを生成するAIの総称」です。では具体的にどんなコンテンツを生成してくれるのか、ここでは4つの種類としてご紹介します。
1. テキスト生成
テキスト生成AIは、私たちが書いた文章を学習して、新しい文章を生成できるAIです。たとえば会議の議事録作成においてテキスト生成AIを活用することで、文字起こしした文章をもとに、発言内容を整理して要点をわかりやすく抽出することが可能になります。
またその他にもマーケティング活動で、広告のコピーライティングや記事作成でも活用されています。「こういうターゲットが興味を持つコピーライティングを考えて」と生成AIに指示することで、大量のコピー案を考えてくれることも可能になります。
2. 画像生成
画像生成AIは、私たちの指示に従って、新しい画像を生成できるAIです。画像生成AIは、デザインや広告・コンテンツ制作など画像に関わるさまざまな分野で活用がされています。
たとえば今までは、デザイナーに要件を整理して作成を依頼していた業務も、画像生成AIを活用すればその時間を短縮することが可能になります。もちろん一度の指示で期待どおりのものが生成されるケースはほとんどないのが実情ですが、逆に何度でも修正をしてくれるのも画像生成AIの特徴の一つです。
3. 動画生成
画像生成AIと同じように、私たちの指示に従って新しい動画を生成するAIです。近年、SNSや企業のプロモーション活動において、動画の重要性がますます高まっていることもあり、動画生成AIの活用も急速に広がっています。
もともと動画を作成するには、画像を作成する以上にコストがかかっていましたが、生成AIを活用することでそのコストを大幅に削減することが可能になっています。現時点では短い動画の作成で活用されるケースが多いですが、さらなる技術の進化に伴って、より長い時間の動画を生成できるようになる可能性があります。
4. 音声生成
音声生成AIは、テキストを音声に変換する技術で、ナレーションや音声アシスタント、音声広告などさまざまな用途で活用されています。今までもテキストを読み上げることは可能でしたが、どうしてもどこか機械っぽさが抜けないような声になりがちでしたが、技術の進化によってより自然な読み上げが可能になりました。
企業のカスタマーサポートでは、AIによる自動応答システムの導入で、この音声生成AIが活用されていたり、さきほどの動画生成AIと組み合わせて、動画とナレーション両方AIで対応することも可能になっています。
代表的な生成AI(Gemini・ChatGPT・Copilot・Claude)の比較表
生成AIと一言でいっても、生成AIモデルにはさまざまな種類があります。
たとえば、代表的な生成AIモデルであるGemini、ChatGPT、Copilot、Claudeはどれも大規模言語モデルを基盤とした生成AIですが、それぞれ得意としていることや機能面に違いがあります。
表にまとめると、以下のようになります。(個人利用の場合の比較)
| Gemini | ChatGPT | Copilot | Claude | |
|---|---|---|---|---|
| 強み | テキスト・画像・音声と様々な種類のデータを同時に扱える | 日本語での自然な対話が可能クリエイティブな文章生成 | Microsoft 365アプリと直接連携可能 | 長文処理、人間らしい自然な文章の生成 |
| 料金体系 | 無料 (Gemini)2,900円/月(Gemini Advanced) | 無料 (ChatGPT 無料版)$20/月(ChatGPT Plus)$200/月(ChatGPT Pro) | 無料 (Copilot 無料版)3200円/月(Microsoft Copilot Pro) | 無料 (Claude Free)$20/月(Claude Pro) |
| コンテキスト長(文脈長) | 最大2Mトークン | 最大128Kトークン(Web版) | 不明 | 最大200Kトークン |
| 出力 | テキスト、画像、音声、コード、動画 | テキスト、画像、音声、コード、動画(Sora) | テキスト、画像(Microsoft 365アプリ内) | テキスト |
| セキュリティ | Google Cloudのセキュリティ基準に準拠 | SOC 2 Type 2、CSA STAR Level 1 | Microsoft 365のセキュリティ基準に準拠 | SCIM |
| 無料プランの内容 | 1回の回答は6000文字程度1分あたり最大15回、1日あたり最大1500回のリクエスト制限(Gemini 2.0 Flashモデルの場合)画像生成〇 | 1回の回答は2000文字程度の制限画像生成〇利用回数や応答速度に制限アリ | 1日の合計チャット数300回画像生成1日15回画像生成〇 | 約4~5時間ごとに10回程度のリクエスト制限30MB/1ファイル、最大5ファイル/1チャットの制限画像生成✕ |
| おすすめ用途 | 音声・画像・文章を使った資料作成や分析 | ブログ・企画案の作成、学習支援 | Word・Excel・Outlookの業務効率化 | 契約書レビュー、自然なメール生成 |
生成AIを活用する3つのメリット
さまざまなコンテンツを生成してくれる生成AIですが、これらの技術を企業の業務で活用するとどのようなメリットがあるのでしょうか。最もイメージしやすいのが、今まで人が行っていたコンテンツを作成する時間が削減されるため「業務の効率化」かと思いますが、その他にも2つ生成AIを活用するときのメリットを、具体的な例を交えてご紹介します。
1. 業務の効率化
企業では日々多くの業務が発生しており、その中には反復的に行われるような定型的なタスクも多く含まれます。これらの業務に生成AIを活用することで、大幅な時間短縮を実現することが可能です。
たとえば議事録作成に多大な時間をかけている企業も多いと思います。会議の目的次第ですが、細かく情報を残す必要がある議事録だと、会議の録音データを聞き直しながら、作成していく必要もあるため、1日以上の時間をかけて作成するケースもあります。これらの作業に対して生成AIを活用すれば、録音データからの文字起こし、その文字起こしを要点にまとめる作業も自動化することが可能です。
またその他にもカスタマーサポートの問い合わせに対しても生成AIを活用することができます。問い合わせに対しての適切な返信案をAIが自動で生成することで、担当者の負担を軽減することが可能です。
2. アイディア出しの効率化
新しいアイディアを生み出すことは企業にとって重要な活動です。しかし実際には担当者がゼロからアイディアを生み出すのは容易ではありません。生成AIを活用することで、短時間で多くのアイディアを生み出し、、効率的に選択肢を増やすことが可能になります。
たとえばマーケティングチームが新しいプロモーションやキャンペーンを考えるときに、生成AIに「SaaS向けのプロモーションアイディアを10個提案して」と指示することで、すぐにアイディアを出すことが可能になります。もちろんさらに細かくどんなターゲットに向けてなのか、どんなイメージが現状あるのかなど指示をより詳しくすることで、求めているアイディアを瞬時に出すことができます。
3. コンテンツ作成コストの削減
アイディア以外にもコンテンツ作成のコストを削減することができます。たとえばブログ記事を定期的に発信している場合、外部のライターに依頼すると一定のコストがかかりますが、生成AIを活用すれば、記事の下書きを瞬時に作成し、それを人間が修正・ブラッシュアップすることで、従来の半分以下の時間とコストで記事を完成させることが可能になります。
またその他にもプレゼンテーション資料でも、生成AIに過去の成功した提案資料と似たようなコンテンツを作成してもらい、それをベースにさらにカスタマイズすることで、資料作成の手間を削減することもできます。生成AIはアイディア出しだけではなく、コンテンツ作成を効率化することが可能です。
企業における生成AIの主な活用シーン3選
さきほどは生成AIを活用するメリットをご紹介しました。そのメリットの中で活用シーンについても一部触れましたが、具体的にどのようなシーンで生成AIを活用できるのかについて改めてご紹介します。
1. 議事録作成の自動化
企業の会議では、議論の内容を記録し、あとでその情報を共有したり活用するためにも議事録の作成が必要不可欠になっています。この議事録があることで、決定事項やタスクの認識を組織で合わせることが可能になります。しかしこの議事録作成には多くの時間と労力が必要になり、また重要なポイントの抜け漏れや表現の曖昧さなどの課題も発生しています。これらの議事録作成における課題を解決するために、生成AIが活用されています。
議事録作成の自動化における生成AIの活用方法はまず、会議の音声をリアルタイムで文字起こしする音声認識技術が活用されます。その技術によって文字起こしをもとに、会議の内容を要約したり、重要なポイントや決定事項のみを抽出することで議事録作成を自動化することが可能です。これによって会議終了後、すぐに議事録が完成している状態が実現できるので、参加者はすぐに内容を確認・共有することができるようになります。
ただし議事録作成において生成AIを活用する場合は、セキュリティ面を考慮する必要があります。というのも社内の会議では重要な情報を扱うケースも多いと思いますが、その情報が生成AIの機械学習に活用されてしまうと情報漏洩のリスクとなってしまいます。
生成AIを活用することで多大に時間がかかっていた議事録作成を自動化することは可能になってきていますが、一方で活用する場合はその生成AIまたは生成AIを活用したツール側のセキュリティ方針がどうなっているかを確認することも必要不可欠です。
2. プレゼン資料などの構成案作成
ビジネスの現場では、企画の提案や戦略の説明、顧客への提案など、さまざまな場面でプレゼン資料の作成が求められます。ただプレゼン資料を作成するためには、適切な構成を考え、分かりやすい内容に整理し、かつ視覚的にも伝わりやすいデザインにする必要があります。この業務は多くのビジネスパーソンにとって時間と労力のかかる業務であり、特に短い時間で作成する必要があるケースでは、大きな負担となっています。
生成AIを活用すれば、このプロセスを効率化することが可能です。たとえば、プレゼン資料の目的や誰への説明かを入力すると、生成AIが適切な構成案を作成してくれます。また構成案だけではなく、スライドごとに必要な内容の概要も提案してくれることが可能です。プレゼン資料に特化した生成AIであれば、そのまま簡単なデザインまでもを作成してくれます。
生成AIを活用することで、プレゼン資料の作成プロセスを大幅に効率化し、本来私たちがすべき戦略的な業務により集中することが可能になります。
3. バナーなどのコンテンツの作成
マーケティングや広報PRの活動では、ユーザーに企業からのメッセージを適切に伝えるためにも、様々なビジュアルコンテンツを作成する必要があります。これらのコンテンツを作成するためにはデザインスキルが必要であり、社内や外部のデザイナーに依頼すると時間がかかることも少なくはありません。特に中小企業やスタートアップといった小規模なチームで構成されている場合は、スピード感持ってコンテンツを作成するのが難しいケースも存在します。
こうした課題を解決するのが、生成AIを活用したコンテンツ作成です。生成AIに広告の目的やターゲットを伝えると、その指示に従ってデザインコンテンツを生成するものがあります。またコンテンツの作成だけではなく、キャッチコピーや広告文の作成にも、そのまま生成AIを活用することができます。
また、コンテンツ作成において生成AIを活用すると異なるデザイン案を複数作成することができるため、効果検証をしやすいという特徴もあります。広告のシーンにおいては異なるバナーをAIで作成して、クリック率を比較することで、最も効果的なデザインを選ぶことも可能です。このように生成AIを活用すれば、コンテンツ作成の時間を削減するだけではなく、より効果的なマーケティング施策を実施することも可能になります。
生成AIを活用するときの3つの注意点
ここまで生成AIのメリットや具体的な活用シーンについてご紹介しました。ここまでの情報だと生成AIを今後業務で活用することで、大きく業務を変革し、とても大きな可能性を秘めていると感じることができますが、一方で生成AIを活用するうえで、まだまだ注意すべきポイントも存在するのが実情です。そこでここでは生成AIを活用するときに特に注意しなければいけないポイントを3つご紹介します。
1. ハルシネーション(AIがもっともらしい嘘をつく)のリスク
生成AIは文章や画像、音声などのコンテンツを生み出すためにもとても便利な技術ですが、一方で「ハルシネーション」と呼ばれる現象が発生することがあります。これは生成AIが作成したコンテンツが本当らしく聞こえるが実際には誤った情報を作り出してしまうことを指します。
たとえば、ある企業が自社製品のプロモーションのために生成AIを活用して、記事を作成していたとします。記事の素案を生成AIに作成してもらったときに「この製品は2025年である賞を受賞しました」と素案が作成されるケースがありますが、実際にはその製品は賞を受賞していないのにも関わらず、AIが過去のデータや類似情報をもとに、もっともらしい内容を作り上げてしまうケースがあります。
このようなハルシネーションは、特に信頼性が重要な分野では大きな問題を引き起こす可能性があります。医療分野や法律関連の文章では、誤った情報が命や権利に関わるリスクを伴ってしまいます。また、ビジネスにおいても、誤情報の発信は企業の信頼を損なうことになるため、生成AIを活用する際は、AIが出力した内容をそのまま信用せず、必ず事実確認を行うことが不可欠です。
2. 著作権の問題
生成AIを活用するときには、著作権に関するリスクも考慮する必要があります。AIは膨大なデータを学習することで新しいコンテンツを生み出しますが、その学習データの中には著作権のある文章や画像が含まれていることがあります。そのため、こちら側が意図せずに生成AIが作成したコンテンツが第三者の著作物を無断で使用しているという状態になるケースがあります。
たとえば、ある企業がAIを使って広告用の文章を作成したとします。その文章を公開したところ、他の企業の人から「これは私の著作物と酷似している」と指摘されるようなイメージです。このようなケースでは、著作権侵害のリスクが発生し、最悪の場合、法的措置を取られる可能性もあります。特に、生成された文章や画像が意図せず既存の作品と似てしまうことがあるため、特に注意が必要です。
著作権問題を回避するためには、ハルシネーション(AIがもっともらしい嘘をつく)のリスク回避と同様に、まずは生成AIが作成したコンテンツを公開前にしっかりとチェックし、既存の著作物と類似していないかを確認することが重要です。
3. セキュリティリスク
生成AIを活用する際にもう一つ注意すべき点が、セキュリティリスクです。AIは、大量のデータを処理し学習するため、企業の機密情報や個人情報が不適切に扱われる可能性があります。
たとえば、企業が社内の会議の議事録を自動化するために、生成AIに会議内容を文字起こしした情報をアップロードしたとします。このときに十分なセキュリティ対策をされていない生成AIだと、これらのデータが第三者に漏えいする危険があります。
このようなリスクを回避するためには、まず利用する生成AIのツールのセキュリティ方針を確認することが重要です。たとえば、データの暗号化が行われているか、データを一定期間後に削除するポリシーがあるかなどをチェックするようにしましょう。
まとめ|生成AIは新しいコンテンツを生成し、業務プロセスの変革で注目されている
本記事では生成AIの種類や活用シーン、活用するうえで注意すべきポイントと生成AIに関して幅広くご紹介しました。生成AIは簡単にいうと「何かしらのコンテンツを作成してくれるAI」で、生成AIを活用することで今まで私たちが多くの時間をかけて対応していた、議事録作成やデザインコンテンツの作成、アイディア出しといった業務を瞬時に対応してくれるようになります。
私たちの業務を変革するうえで、生成AIの活用はとても注目されていますが、一方でセキュリティリスクや著作権の問題など、事前に注意すべきポイントもあります。生成AIを上手く活用するためにも、リスクはきちんと理解しておきましょう。
今後生成AIの活用を検討している方はぜひ本記事のご紹介した内容を参考にして、自社の生成AI活用を進めてみてはいかがでしょうか。
生成AIを活用して、上手く自動要約や要点抽出をするには、ベースとなる文字起こしの精度が高いことが必要不可欠です。
- 固有名詞や専門用語の変換が上手くいかない
- 「えー」や「あの」などの意味をなさない言葉も文字起こしされてしまう
- 文字起こしを修正してから生成AIを活用しているが修正に時間がかかっている
このような文字起こし精度にお悩みを抱えている方は、ぜひ一度、使えば使うほどAIの精度が上がる「Otolio」をお試しください。
またOtolioのAIアシスト機能を活用して自動要約・要点抽出も自動化できます。自動化することが可能です。AIアシストを活用すれば以下を自動化することができます。
- 要約文章の生成
- 要点の自動抽出
- 決定事項やToDo、質疑応答の抽出
Otolioは特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、使えば使うほどAIの精度が向上します。累計利用社数6,000社以上の実績、大手企業から自治体まで様々な組織で利用されており、セキュリティ面でも安心してご利用いただけます。
よくある質問とその回答
Q. 無料で使える生成AIはありますか?
ChatGPTやGemini、Copilot、Claudeなど、代表的な生成AIモデルには、ほとんど無料プランがあるため、無料で利用可能です。無料プランでは基本的に、一日にアップロードできるファイルや質問回数などに制限がありますが、試しに少し使ってみたい、という方には十分な機能が備わっていることが多いです。
Q. 英語が苦手でも生成AIは使えますか?
もちろん利用可能です。ChatGPTやGemini、Copilot、Claudeなど代表的な生成AIモデルは日本語対応しているため、日本語での質問には日本語で返してくれます。また、基本的なUIも日本語に対応しているため、英語が苦手でも生成AIを使うことができます。
Q. 生成AIを使うのにパソコンは必要ですか?
必要ありません。生成AIモデルの種類にもよりますが、基本的にはアプリ版やWeb版があるため、スマートフォンやタブレットからでもアクセスが可能です。