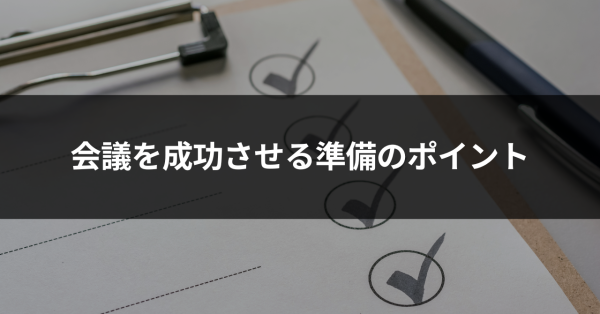定例会議を開催する目的とは?無駄にしないための効率的な進め方も紹介

週次、月次、四半期などあらかじめ決められたスケジュールに基づいて、定期的に開催する「定例会議」を多くの企業が実施していると思います。ただし、定例会議を開催しているものの「定例会議の目的がよくわからない」「定例会議を実施しているけど意味があるのか」「もっと効率よく定例会議を実施したい」と考えている方もいるかもしれません。
本記事では「定例会議」の目的や無駄と言われてしまう理由、効率的に開催する方法についてご紹介します。定例会議を今一度見直したい、定例会議の開催を検討している方は、ぜひ本記事をご覧ください。
- ミーティング中は話に集中したいため、メモが取れない
- ミーティング後に話をした内容をまとめるのに時間がかかっている
- ミーティングの発言の温度感やニュアンスを共有したい
このような議事録やメモに関するお悩みがあれば、ぜひ一度AI議事録サービス「Otolio」をお試しください。
Otolioは議事録などのドキュメント作成に関する作業を自動化・効率化することができ、作成時間を最大90%以上削減することが可能です。
定例会議とは
定例会議とは週次、月次、四半期などあらかじめ決められたスケジュールに基づいて、定期的に開催される会議のことを指しています。会議を開催する日時をあらかじめ固定することで、継続的に実施されることが特徴です。議題はその都度変わることがあるものの、定期的に会議を行うことで、組織内での情報共有や進捗確認、意思決定の効率化を実現することが可能です。
企業によっては「ウィークリーミーティング」「月次会議」など呼び方が「定例会議」とは異なるケースもありますが、基本的な目的は共通しています。特にBtoBビジネスのように複数の関係部署が連携してプロジェクトを進めるような環境では、プロジェクトの関係者が定期的に顔を合わせ、現状を共有する機会としてとても重要な役割を担っています。
定例会議が注目されるようになった背景には、ビジネスのスピードが加速し、日々の変化に迅速に対応する必要がある現代のビジネス環境があります。毎回、議題が発生してから会議を設定するようでは、スピード感が損なわれてしまいますが、定例会議はあらかじめ予定されているため、出席者も予定を確保しやすく、継続的なコミュニケーションの場として定着がしやすいのも定例会議の特徴の一つです。
定例会議を開催する3つの目的
定例会議を開催する目的は多岐にわたりますが、多くは以下の3つの目的に集約されます。それぞれの目的について詳しく解説していきます。
1. 進捗確認と課題の早期発見
定例会議の最も基本的な目的の一つが自分のチームやプロジェクトの業務の進捗状況を確認し、発生しつつある課題をできるだけ早いタイミングで発見することです。日々業務に追われる中で、進捗状況の可視化が疎かになってしまうケースがありますが、定例会議を開催することで、関係者が集まり、ほぼ強制的に各自の進捗を報告し合う機会が生まれます。
このような場があることで、遅れが出ている箇所やリスクに早いタイミングで気づくことができ、必要に応じて軌道修正やサポート体制を強化し、遅れを取り戻す対応が可能になります。課題が表面化する前に対応すれば、手遅れになる前に打ち手を打つことが可能になります。
また、進捗状況を定期的に確認することは、担当者自身のタスク管理能力の向上にもつながります。「来週の定例会議までにどこまで終わらせるべきか」といった短期的な目標意識を持つことになり、結果的に全体の生産性を上げることに繋がります。
2. 情報共有・意思決定をする場の確保
定例会議は単に自分の進捗を報告する場に留まらず、業務上必要な情報を共有し、意思決定を行うという重要な目的があります。特に、部署間で連携する業務が多い場合は、円滑に業務を進めるためにも、それぞれの状況や方針を理解しておくことはとても重要です。
たとえば、マーケティング部と営業部の連携が必要な企業では、互いのKPIや成果、課題を共有することで、次のアクションプランの整合性を保ちやすくなります。定例会議を通じて「どのような見込み顧客が増えているか」「顧客からどんな要望が寄せられているか」などの情報がリアルタイムに共有されれば、より精度の高い施策を考えたり、適切な判断が可能になります。
また、定例会議をあらかじめ決められたスケジュールで開催されるため、「どのタイミングで意思決定をすればよいか」といった迷いが減り、意思決定のプロセスも効率的になります。毎回、会議を設定する手間が省けるだけでなく、情報が一元化されることで議論の土台が揃いやすくなるというメリットもあります。
3. コミュニケーションの活性化
定例会議には業務に直結する報告や意思決定以外にも、組織内のコミュニケーションを活性化するという重要な目的があります。特に近年では、コミュニケーションツールが普及し、普段はメールやチャットでのやり取りが中心になってしまっていますが、対面もしくはオンラインでリアルタイムで顔を合わせる機会は、関係性の構築に大きく貢献します。
特に、リモートワークが浸透している企業やチームにおいては、定例会議が「人とつながる」ための貴重な場になります。ちょっとした雑談や表情の変化から得られる情報は、業務には直接関係しないようでいて、実は信頼関係やチームワークにおいて大きな意味を持ちます。
また、会議中の何気ないやりとりが、他部署との協業のヒントになったり、新たなアイデアのきっかけになることもあります。特に複数の職種や役割が関わるプロジェクトでは、他者の視点や考えに触れること自体が価値となります。さらに定例会議には「組織の空気感」が伝わるという側面もあります。たとえば、上司がメンバーの意見にどうリアクションするか、発言のしやすさ、議論のテンポなどは、ドキュメントやメールからは決して読み取れない情報を、新人や新しく参加したメンバーにとってはとても重要な情報になります。
定例会議は無駄だと言われる5つの理由
定例会議は企業が業務を進める上で、重要な会議です。一方で「定例会議は無駄だ」と言われてしまうケースも多くあります。なぜそのようなことを言われてしまうケースがあるのか、定例会議が無駄だと言われる主な理由を5つご紹介します。
1. 目的が曖昧になっている
定例会議が無駄だと感じられてしまう大きな理由のひとつに、「定例会議を開催する目的が曖昧になっている」があげられます。このように感じられてしまう会議では、会議の冒頭に「今日は何のために集まったのか」が明確に説明されることがなく、参加者の多くが何となく、「毎週あるから参加している」という状態になりがちです。会議の目的を明確に定める人がいない、または会議の開催自体が目的になってしまっているときに、このような状態に陥ってしまうケースがあります。
「話すことがなければとりあえず近況報告をする」など、目的が形骸化してしまっている状態のときは注意が必要です。その状態で会議をしても、会議の中で議論が発散しやすくなり、終了時に「結局この会議で何が決まったのか」が分からないという状態に陥ってしまいます。
これを防ぐためにも、「毎回冒頭でしっかりと定例会議の目的を共有する」ということと、「報告することがないのではなく、報告するためにも業務を前に進める」ことが重要になります。
2. 時間がかかりすぎる・頻度が多い
定例会議が無駄だと言われてしまう原因の一つに、時間的コストがかかりすぎている状態があげられます。定例会議の設定時間は企業によって異なりますが、多くの企業で毎週決まった時間に1時間、あるいはそれ以上の定例会議を設定しているケースが見受けられます。その実態をよく見てみると、全体のうち実質的に意味のある議論が行われているのはほんの数分、ということも少なくありません。
このような会議が日常化すると、社員の時間を膨大に消費することになります。たとえば、10人が参加する1時間の定例会議は、社内リソースとしては10時間を使っていることに相当します。しかも、その中で有益な情報共有や意思決定がなければ、その時間はまるごと無駄になってしまうのです。
さらに問題なのは、「頻度が多すぎる」ことです。たとえば、週次の定例会議に加えて、チームミーティング、プロジェクトミーティング、部門会議などが複数の定例会議が頻繁に設定されると、社員のカレンダーは会議で埋まり、実作業に使える時間が大幅に削られてしまいます。これは「会議疲れ」を引き起こす原因にもなり、社員のモチベーションや生産性に悪影響を与えることになります。
定例会議が本当に必要であるならば、その時間と頻度を見直すことが重要です。たとえば、30分以内のスタンディングミーティングにする、アジェンダを事前に共有して無駄なやりとりを減らすなどの工夫が効果的です。
3. 発言しにくい雰囲気になっている
定例会議そのものの空気感によって会議が無駄と感じてしまうケースがあります。特にありがちなのが、「発言しにくい雰囲気」が形成されてしまっているケースです。たとえば、上司が長々と話すだけで部下が発言しづらい、特定のメンバーばかりが発言していて他のメンバーが黙っている、あるいは誰かの意見が否定されやすくなっているなどです。
このような空気の中では、せっかく有益な意見を持っている人でも発言を控えてしまい、結果として「声の大きい人だけが主導する場」になってしまいます。会議本来の目的が「情報の共有」や「複数人の知見を集めた意思決定」にあるとすれば、これは大きな損失であり、発言をしたいが、発言ができない人からすれば無駄と思われてしまう可能性があります。
「発言がしづらい」というのは単に心理的な問題にとどまりません。たとえば、「誰がいつ発言していいのか分からない」「意見を出すタイミングがない」という形式面の問題も多く見受けられます。特にオンライン会議では、会話にタイムラグが生じたりすることで、発言のハードルが上がる傾向があります。
こうした雰囲気が放置されてしますと、会議そのものへの信頼も失われていきます。参加者の中には「どうせ何を言っても聞いてもらえない」と感じるようになり、発言しないだけでなく、真剣に話を聞かなくなる人も出てきます。
この状態を防ぐためにも、会議の冒頭に「意見を歓迎する」という姿勢をファシリテーターが明示することや、発言を引き出す仕組みを設計することが重要です。たとえば、1人ずつ意見を求める、チャット欄で匿名の意見を募る、時間を区切ってブレイクアウトルームで議論するなど、形式を工夫することで空気を変えることができます。
4. 特定の人しか関係がない議題が多い
定例会議では多くの関係者が参加することがよくありますが、「その場で扱われている議題の多くが、参加している全員に関係しているわけではない」という状態になってしまうと、定例会議そのものが無駄だと感じられてしまう可能性があります。
この状態が続いてしまうと、モチベーションの低下にもつながります。特にオンライン会議の場合、参加のハードルが低いために「とりあえず全員参加」となりがちですが、実際の会議を振り返ってみると、意味のある参加者は一部だけというケースも少なくありません。そうなると、参加者全体のモチベーションが下がり、発言も少なくなり、ますます会議が非効率になるという悪循環に陥ります。
このような事態を防ぐためには、会議のアジェンダを事前に共有し、必要な人だけが参加する仕組みを整えることが重要です。また、議題ごとに関係者が入退室できるようにしたり、情報共有は会議外のドキュメントやチャットで済ませるといった工夫も有効です。定例会議は「全員で集まること」ではなく、「必要な人が集まり、効果的に意思決定すること」が目的であるという原則を見直すことが、無駄を減らし、組織全体のパフォーマンスを高める鍵となります。
5. 議事録が作成・共有されない
定例会議が終わった後に「結局、何が決まったんだっけ?」「あの話、どうするって言ってたっけ?」という会話が社内で飛び交っているなら、その会議は無駄に終わっている可能性が高いです。どれだけ中身のある議論が行われたとしても、それが正確に記録され、関係者全員に共有されなければ、会議の意味は半減してしまいます。議事録の共有は、定例会議を有意義なものにするためにも重要なステップです。
議事録が作成・共有されないと、せっかく定例会議で決まった決定事項が忘れられたり、あとから参加したメンバーや他の関係者が内容を把握できない、議題が次回に持ち越され、同じ議論が繰り返されるなどの問題が発生します。
議事録を作成するためには、一定時間が必要になりますが、近年、AIを活用して自動で議事録を作成・要約するAI議事録ツールも普及しており、手間を大きく削減することが可能です。重要なのは議事録を「あとで読むもの」ではなく、「会議の延長線上で活用するもの」として位置づけることです。共有の文化を根づかせることで、定例会議が「有意義な時間」へと生まれ変わります。
実際にAI議事録ツールを活用して、会議の議事録作成時間をほぼゼロにし、会議後すぐに議事録を確認できる状態を実現した事例もあるので、気になる方はぜひ以下の事例記事もご覧ください。
効率よく定例会議を進めるための3つのポイント
定例会議を開催することを「無駄」と思われずに、効率よく開催するためには、どのような方法があるのでしょうか。ここでは効率よく定例会議を進める他の方法を3つのポイントに分けてご紹介します。
1. 定例会議の目的を明確にする
さきほどの「定例会議は無駄だと言われる理由」でもお伝えしている通り、最初にして最も重要なステップが「目的の明確化」です。そもそも定例会議とは、特定のメンバーが定期的に集まり、情報共有や意思決定、課題の整理などを行う場ですが、目的が不明確なままでは意味のない会議が続いてしまい、参加者のモチベーション低下や無駄な時間の消費につながります。会議の時間はコストであり、その価値を最大化するには「この会議は何のために存在するのか」を参加者全員が理解しておく必要があります。
ご紹介した目的のどれに該当する定例会議なのか、その目的を達成するためにも、それぞれで必要な準備や参加者の姿勢、会議の進行方法がまったく異なります。目的が曖昧だと、会議後に「で、何が決まったの?」という状況にもなりかねません。
また、明確にした内容を議事録の冒頭部分に記載して会議の冒頭で共有することも効果的です。「本日の会議の目的は前回の残論点のこの部分を決定することです」と伝えるだけでも、参加者の意識が揃いやすくなり、会議の進行もスムーズになります。定例会議は一度習慣化すると長期的に継続する傾向があります。だからこそ「この会議の目的は何か?」と最初に立ち返るべきことは定例会議を効率的に進めるためにも、とても重要な観点です。目的の明確化がすべての土台となり、会議の質を左右します。
2. 事前準備を徹底する
定例会議を効率的に進めるためにも、定例会議の事前準備を徹底するようにしましょう。多くの企業でありがちなのが、会議の直前になって議題を考えたり、必要な資料をその場で共有したりするというパターンです。これでは参加者も会議中にしかその内容を理解しきれず、質の高い議論にはつながりません。事前準備をどれだけ丁寧に行うかが、会議の成否を大きく左右します。
特に重要なのは、議題の共有です。会議の数日前には、どのような内容を扱うか、誰が話すのか、各議題にどれだけの時間を割くのかを明らかにした議題を全員に共有するようにしましょう。これにより参加者は、自分が何に備えるべきかを明確に理解でき、必要な資料を準備したり、事前に社内で確認を取っておいたりすることができます。
また、最近では議事録を事前に作成するというアプローチも注目されています。これは予定している議題やアクションアイテムをあらかじめ議事録形式でまとめておき、会議中にその場で更新・修正していく方法です。こうすることで、会議終了と同時に議事録のたたきが完成し、後からまとめる手間が大きく軽減されます。定例会議は開催する前から勝負が始まっています。参加者全員が「準備して臨む会議」という共通認識を持てるような文化づくりを目指しましょう。
3. 関係者だけを招待する
定例会議が無駄と言われる理由に「特定の人しか関係がない議題が多い」という原因をあげました。これを避け、効率的な定例会議を実施するためにも、なんとなく関係がありそうな人を会議に招待するのではなく、議題に関係がある人のみが参加してもらうようにしましょう。
参加者が多くなると、発言の機会が減る、議論が脱線しやすくなる、時間が長引くといった弊害が生じます。そのため事前準備を徹底した上で、参加する人だけを招待することが重要です。定例会議はあらかじめ決められたスケジュールに基づいて会議を実施するため、同じように決められた参加者が招待されていますが、都度必要な人のみが参加してもらうように意識しましょう。
まとめ
定例会議は「進捗確認と課題の早期発見」「情報共有・意思決定をする場の確保」「コミュニケーションの活性化」を目的とした会議です。定例会議は週次、月次、四半期などあらかじめ決められたスケジュールに基づいて、定期的に開催されます。
多くの企業が定例会議を実施していますが、一方で定例会議が無駄と言われてしまうケースも存在します。原因は企業によって異なりますが、多くは定例会議の目的が曖昧になっていたり、定例会議の時間が長いまたは頻度が多い、発言しにくい雰囲気になっており特定の参加者のみが発言しているなどがあげられます。
効率的に定例会議を開催するためにも、しっかりと目的を明確化にして、事前準備を徹底することが重要です。また会議中に発言がしやすい雰囲気作りや、「関係者のみ参加してもらう」といった仕組みの設計も重要になります。本記事でご紹介した内容をもとに、よりより定例会議を実践していきましょう。
- ミーティング中は話に集中したいため、メモが取れない
- ミーティング後に話をした内容をまとめるのに時間がかかっている
- ミーティングの発言の温度感やニュアンスを共有したい
このような議事録やメモに関するお悩みがあれば、ぜひ一度AI議事録サービス「Otolio」をお試しください。
Otolioは議事録などのドキュメント作成に関する作業を自動化・効率化することができ、作成時間を最大90%以上削減することが可能です。