BPRとは?導入のタイミング・手順・成功のコツまで徹底解説
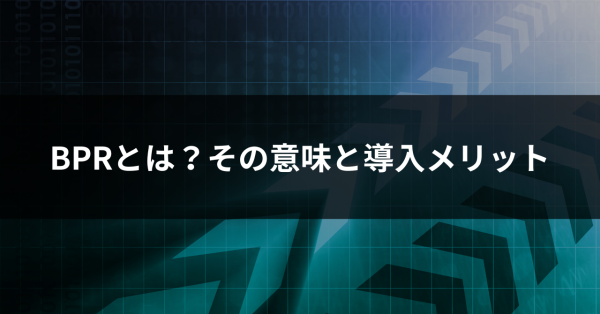
この記事でわかること
- BPRとは?BPR導入のメリット・デメリット
- BPRの導入ステップ
- BPRを成功に導くツールや支援サービス
企業活動の効率化や競争力強化が叫ばれる中で、注目を集めているのが「BPR(Business Process Reengineering)」です。これは、単なる業務の見直しや改善ではなく、企業の業務プロセス全体を根本から見直し、最適化・再構築を図る取り組みを指します。
業務フローや組織体制、利用するシステムなど、あらゆる側面を抜本的に変革することで、大幅な生産性向上やコスト削減、サービス品質の向上などを実現することが可能になります。
しかし、いざ「BPRを導入しよう」と考えたとき、多くの企業担当者は「業務改善とどう違うの?」「うちの会社に本当に必要?」「導入にどれだけの労力やコストがかかるのか?」「BPRの進め方がわからない」といった課題に直面します。理解が不十分なまま取り組むと、期待した成果が出ないどころか現場の混乱を招く可能性すらあります。
そこで本記事では、BPRとは何かという基本から始まり、業務改善やBPM(Business Process Management)、DX(デジタルトランスフォーメーション)など類似概念との違い、自社にとって導入すべきタイミングや向いている企業の特徴、メリット・デメリット、具体的な導入ステップ、成功のためのポイント、活用できるITツールや外部支援までを解説します。
全体像を正しく理解することで、自社にとって本当に必要な変革かどうか、また成功のためにどのような準備が必要かを見極めるヒントが得られるので、ぜひ参考にしてみてください。
また、BPRにお悩みの方は、ぜひ議事録作成時間を削減できるOtolio(旧:スマート書記)をお試しください。Otolioは使えば使うほど精度が上がる特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、社内の専門用語や固有名詞の認識精度を向上させることが可能です。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or 資料を請求する
BPRとは?
現代のビジネス環境において、注目されているのが「BPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)」という概念です。まずはBPRの基本について解説していきます。
BPRの正式名称と意味
BPRとは「Business Process Re-engineering(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)」の略で、日本語では「業務改革」や「業務再設計」と訳されることが多い言葉です。
1990年代にアメリカの経営学者マイケル・ハマーとジェームズ・チャンピーによって提唱されたこの概念は、企業の業務プロセスを根本から見直し、抜本的に再構築することによって、業績の劇的な改善を目指すという考え方です。単なる業務の見直しや小規模な改善ではなく、ビジネスモデルそのものに手を加えるレベルの改革を指すため、企業にとっては大きな転換点となる取り組みです。
BPRの基本的なアプローチは、「現状の業務フローや組織構造を前提にしない」点にあります。従来の慣習や既存のシステムを尊重するのではなく、顧客価値の最大化を目的として、ゼロベースで業務全体を再設計します。たとえば、製造業であれば生産から納品までの全工程、サービス業であれば顧客対応からアフターサポートまでを再構成するのがBPRです。
また、BPRではITの活用も重要な要素となります。業務の効率化を図る際、最新のテクノロジーを用いることで人手に頼らない体制を構築し、迅速かつ柔軟な対応が可能となります。そのため、BPRはDX(デジタルトランスフォーメーション)とも密接に関係しています。
なぜBPRが注目されているのか
BPRが再び注目されている理由は、現代のビジネス環境が急速に変化していることにあります。市場のグローバル化、顧客ニーズの多様化、デジタル技術の進化、そしてパンデミックや災害といった予測不可能な外的要因によって、従来の業務プロセスでは柔軟な対応が難しくなってきているのです。
たとえば、コロナ禍によりリモートワークの導入を余儀なくされた企業では、これまで対面で完結していた業務フローが機能しなくなりました。その結果、「そもそもこの業務は本当に必要なのか?」という根本的な問い直しがなされ、BPRが一つの答えとして浮上しました。
また、慢性的な人手不足や労働人口の減少といった社会的背景も、企業にとって業務効率の向上が急務であることを意味しています。単なるツール導入や表面的な業務改善では限界があるため、抜本的な再設計=BPRが不可欠となっているのです。
BPRと業務改善の違い
「業務改善」と「BPR」は似た言葉として混同されがちですが、実際にはアプローチや目的に大きな違いがあります。
業務改善とは、既存の業務フローを前提とした部分的な最適化を指します。たとえば、作業手順の見直しや帳票の電子化といった、小さな変更を積み重ねていく方法です。
一方のBPRは、業務全体をゼロベースで再構築することを目的としています。既存の仕組みに縛られず、理想的な状態を定義してそこへ向かって業務を抜本的に再設計するのです。このため、BPRは業務改善に比べて変革のインパクトが大きく、組織文化や人員配置、さらには経営戦略にも大きく影響を及ぼします。
もう一つの大きな違いは「取り組む単位」です。業務改善が現場レベルで行われることが多いのに対し、BPRは経営層が主導し、全社的な取り組みとして進められます。BPRは単なるオペレーションの見直しではなく、企業の存在意義やバリューチェーン全体を再定義するような壮大な改革です。したがって、BPRを成功させるには現場だけでなく、経営陣の強い意志とリーダーシップが不可欠となります。
BPRとBPM・DX・業務自動化の違い
BPR(業務改革)と混同されやすい言葉に、BPM(Business Process Management:業務プロセス管理)、DX(Digital Transformation:デジタルトランスフォーメーション)、業務自動化(RPAなど)がありますが、それぞれ目的やスコープが異なります。
まずBPMは、業務プロセスを可視化し、PDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルによって継続的に改善していくフレームワークです。BPRが「一度きりの大規模な再設計」であるのに対し、BPMは「日常的な業務改善を継続する」ための管理手法といえます。BPMの中にBPRの成果を取り入れ、継続的に改善する流れが理想的です。
次にDXは、企業活動のあらゆる場面でデジタル技術を活用し、ビジネスモデルや企業文化そのものを変革していく取り組みです。DXの一環としてBPRを実施することも多く、BPRはDX推進の初期段階における土台作りともいえます。
そして業務自動化は、具体的な業務タスクをツールやシステムによって効率化・無人化する取り組みです。RPA(Robotic Process Automation)などが代表的ですが、これもまたBPRの施策の一つとして活用されることが多いです。
つまり、BPRは企業のビジネスプロセスを再設計するための「思想・アプローチ」であり、BPMやDX、業務自動化はその実現手段あるいは関連する取り組みという位置づけになります。これらを混同せず、役割の違いを理解することが、成功する変革の第一歩となります。
以下の記事でDXと業務自動化について詳しく解説していますので、より掘り下げて知りたいという方は、ぜひ参考にご覧ください。
BPRを導入するべき企業とは?
BPRは、業務の根本的な見直しと再構築を行う取り組みであり、企業にとって一時的な業務改善ではなく、長期的な変革を目指す戦略的手法です。では、具体的にどのような企業がBPRを導入すべきなのでしょうか?このセクションでは、BPRが必要になるタイミングと、導入に向いている企業の特徴について詳しく解説していきます。
BPRが必要になる4つのタイミング
1. 現行の業務プロセスに限界を感じるとき
売上が伸び悩んでいる、顧客満足度が低下している、社内の業務フローが複雑で非効率になっているといった状態は、まさにBPRを検討すべきタイミングです。これらの問題は、単なる業務改善では解決が難しく、根本的な設計の見直しが必要になります。属人化が進んでいる業務も、特定の担当者がいないと回らないというリスクがあるため、BPRによる再構築が有効です。
2. 急成長や事業多角化による混乱が生じているとき
急速に拡大した企業では、もともとの業務フローが新たな事業モデルや規模に対応できず、混乱や属人化が生じやすくなります。これを放置すると、業務の品質低下や従業員の疲弊、情報共有の欠如といった問題が深刻化します。成長スピードに組織構造や業務設計が追いつかないというジレンマを抱える企業にとって、BPRは体制を立て直す絶好の機会となります。
3. 外部環境による大きな変化があったとき
業界の競争激化、法規制の変更、テクノロジーの進化(AIやIoTの台頭など)により、従来のやり方では通用しなくなったとき、企業は業務プロセスを一から見直す必要に迫られます。とくにデジタル化が加速する中で、紙やExcelに依存した業務を放置していると、大きな機会損失につながることもあります。
4. 企業文化を刷新したいとき
BPRは業務だけでなく、組織構造や意思決定プロセス、従業員の意識改革にも波及するため、古い慣習を脱却し、より柔軟で革新的な文化を醸成したい企業にとって、強力な変革ツールとなり得ます。たとえば「前例主義」から脱却したいとき、業務自体の再設計が企業文化を変える突破口となることもあります。
BPRが向いている企業の4つの特徴
1. 変化への意欲が高い企業
BPRは従来のやり方を否定し、ゼロベースで再設計する必要があるため、現場や経営層の強い覚悟と協力が不可欠です。現状維持を好む風土では、抵抗が強く、プロジェクトの推進が困難になることもあります。そのため、変革を歓迎する文化やトップのリーダーシップがある企業は、BPRの効果を最大化しやすいのです。変化を前向きに捉える姿勢が、BPR成功の重要な土台となります。
2. 部門をまたぐ業務課題を抱える企業
部門ごとの部分最適に陥っていたり、部門間の連携が取れていない場合、全体最適を目指すBPRのアプローチは非常に有効です。業務の流れを全社的に俯瞰し、部門の壁を超えた統合的な再構築を図ることで、劇的な効率化や顧客体験の向上が期待できます。結果として、部門間の断絶を乗り越えた柔軟な協働体制の構築にもつながります。
3. データ活用が不十分な企業
情報が部門ごとに分断されていたり、アナログな業務が残っていたりして、意思決定に必要なデータが適切に活用されていない企業も、BPRを通じて業務と情報システムを一体的に見直すことで、デジタル化・可視化が促進されます。その結果、客観的なデータに基づいて判断や改善を行える経営体制が構築されます。データの整備は、今後のAI活用にも直結する重要な要素です。
4. 人材育成や働き方改革を目指す企業
BPRによって業務の属人化を解消し、標準化・自動化が進むことで、従業員がより創造的な業務に集中できるようになります。これにより、社員のスキル向上やエンゲージメントの向上が期待でき、組織全体の生産性が底上げされる可能性があります。新人教育や新しいスキルの習得(リスキリング)の効率も向上するため、人的資本経営の視点からも有効です。
このように、BPRの導入は単なる業務の見直しにとどまらず、経営戦略や組織文化、人材育成といった広範なテーマにも波及する大きなインパクトを持っています。自社が抱える課題を多角的に見つめ直し、BPRの適用可能性を慎重に判断することが重要です。
BPR導入のメリット・デメリット
BPRを導入することで、企業は従来のやり方を根本から見直し、大きな変革を遂げることができます。しかし、その反面、実施にはリスクや課題も伴います。ここでは、BPR導入における主なメリットとデメリットについて詳しく解説します。
BPR導入の4つのメリット
1. 業務効率の抜本的改善
BPRを導入する最大のメリットは、企業の業務プロセスを根本から見直し、飛躍的な業務効率化やコスト削減、顧客満足度の向上を実現できる点にあります。従来の部分的な改善活動(いわゆる業務改善)とは異なり、BPRはプロセス全体を再設計するアプローチです。そのため、一部の工程だけでなく、部署間の連携や情報の流れ、人材の配置など、業務全体を横断的に最適化することが可能です。
2. IT活用による業務の自動化と標準化
たとえば、受注から納品までの一連の流れをITを活用して自動化・一元管理することで、人的ミスの削減、対応スピードの向上、在庫ロスの削減など複数の課題を一挙に解決できる可能性があります。また、従来は「当たり前」とされていた非効率な業務や、部門ごとに属人化されていたノウハウの可視化と標準化も進みやすくなります。
業務の自動化や標準化について、より詳しく知りたい方は、下記の記事で掘り下げて解説していますので、ぜひ参考にご覧ください。
3. 組織活性化と文化改革
さらに、BPRを通じて社内の組織構造や評価制度まで見直すことで、従業員のモチベーションやエンゲージメントの向上に繋がることもあります。プロセスの見直しによって、単なる業務効率化にとどまらず、企業文化や価値観の転換を促す効果も期待できる点は、BPRならではの大きな魅力といえるでしょう。
4. 競争優位性の強化
もうひとつ見逃せないメリットは、企業が持つ競争力の強化です。市場の変化が激しく、顧客ニーズも多様化する現代において、変化への柔軟な対応力は企業にとって不可欠です。BPRを実施することで、変化に強いプロセス設計や、迅速な意思決定を可能にする情報基盤の整備が進み、環境変化に対する耐性を高めることができます。
このように、BPRは単なる業務改善にとどまらず、企業のビジネスモデルや競争優位性そのものを変革する可能性を秘めており、特に大きな変革を求められる局面において、非常に効果的な手段となります。
BPR導入の3つのデメリット
1. 導入コストと工数の大きさ
一方で、BPRにはいくつかの注意すべきデメリットやリスクも存在します。まず第一に、BPRは業務プロセスを根本から再設計する取り組みであるため、非常に多くの時間と労力、そしてコストがかかるという点が挙げられます。現状の業務を一度分解し、ゼロベースで設計し直す作業は簡単ではありません。現場のヒアリングやデータ収集、分析、プロトタイピング、トライアル導入、本格展開など、全体的に長期のプロジェクトとなる傾向があります。
2. 社内の抵抗と合意形成の難しさ
また、BPRの実施には経営層の強力なリーダーシップと、組織全体の合意形成が必要不可欠です。というのも、プロセスの抜本的な見直しは多くの場合、既存のやり方に慣れた従業員の抵抗を招くためです。
とくに長年同じ業務を担ってきた現場担当者や管理職ほど、変更に対して懐疑的になるケースが多く、BPRの推進が頓挫するリスクもあります。人間は基本的に変化を好まない生き物であるため、変革の意図や意義を丁寧に説明し、納得を得ながら進める必要があります。
3. 設計ミスによる業務混乱
さらに、BPRの設計段階でのミスや想定外の要素によって、逆に業務が非効率化する可能性も否定できません。新しいプロセスが導入されたにもかかわらず、それに伴うシステムや組織体制が不十分であれば、業務が混乱し、従来以上に手間が増えてしまうことすらあります。
特に、ITツールの導入とBPRを並行して進める場合、要件定義や運用設計が甘いと、ツールに業務が縛られる「システム依存型の非効率」に陥ることもあります。
このように、BPR導入には多大なリターンが期待できる一方で、明確な戦略と推進体制、そして全社的な協力が不可欠であり、慎重に計画・実行しなければ失敗のリスクも大きくなってしまう点には注意が必要です。
BPRの導入ステップをわかりやすく解説
BPRを成功させるためには、計画から実行、定着までの一連のステップを丁寧に踏むことが重要です。単に業務を見直すのではなく、企業の仕組みそのものを根本から変える取り組みであるため、計画性と全社的な協力体制が不可欠です。ここでは、BPR導入の全体的な流れと、成功に導くための重要なポイントについて解説します。
BPR導入の全体フロー|5ステップ
BPR導入のプロセスは、大きく分けて以下の5つのステップで構成されます。
STEP. 1|現状分析と課題の明確化
まず、現在の業務プロセスを詳細に洗い出す作業から始まります。この段階では、部門間での情報共有やヒアリングを通じて、実際の業務がどのように行われているのか、どこにムダや非効率が潜んでいるのかを把握します。ここで得られた現場の声は、机上の空論にならない改革案を作るための重要なヒントになります。
STEP. 2|目指すべき業務像の設計(To-Beモデルの策定)
現状の課題を踏まえ、「理想の業務フロー」を描きます。この段階では、最新のIT技術や業界で広く評価されている成功事例も参考にしながら、従来の枠組みにとらわれない発想で業務プロセスを再設計します。ポイントは、「今の延長線」ではなく、「ゼロベースで設計する」という視点です。
STEP. 3|ギャップ分析と変革戦略の策定
現状(As-Is)と理想(To-Be)の間に存在するギャップを明確にし、それをどう埋めていくかを戦略的に検討します。ここでは、業務手順の見直しだけでなく、人材配置や組織体制の再編成、ITインフラの再構築まで踏み込んだ施策が必要になることもあります。
STEP. 4|実行計画の立案と実施
ギャップを埋めるための施策を実行に移すため、段階的な計画を策定します。関係部署との調整や研修、システムの導入・移行といった実務的なプロジェクト管理が求められるフェーズです。特に現場の混乱を避けるために、段階的な展開(パイロット運用→全社展開)を採用するケースが多く見られます。
STEP. 5|定着化と継続的改善
BPRの効果を一時的なものにしないためには、プロセスの定着とPDCAサイクルによる継続的な改善が欠かせません。新しい業務プロセスが実際に活用されているか、目標とする成果に結びついているかを定期的に検証し、必要に応じて見直す体制を構築します。
BPR推進を成功させる4つのポイント
BPRは単なる業務改善とは異なり、企業文化や組織構造にまでメスを入れる大胆な取り組みです。そのため、導入を成功させるためには以下のようなポイントが重要になります。
1. 経営層のコミットメント
BPRを実行する上で最も重要なのが、経営層の強力なリーダーシップです。業務現場では変化に対する抵抗がつきものです。トップが自ら改革の旗を振ることで、全社的な意識改革と協力体制を築くことができます。また、予算や人材などのリソース配分を円滑に行う上でも、経営層の関与は不可欠です。
2. 現場の巻き込みと納得感の醸成
改革が成功するかどうかは、最終的には現場の理解と協力にかかっています。したがって、現場スタッフを初期段階から巻き込み、意見を取り入れながら改革案を策定することが重要です。納得感のない施策は形だけの運用に終わり、長期的な成果には結びつきません。
3. IT活用と業務の標準化
BPRの効果を最大化するには、ITの活用が不可欠です。業務の可視化や効率化、情報共有を加速するために、ワークフロー管理ツールやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)、ERP(基幹業務システム)などを積極的に導入することが推奨されます。また、業務を標準化し、属人化を排除することで、再現性のあるプロセスを実現できます。
おすすめの業務可視化ツールは、下記の参考記事でご紹介していますので、よろしければ参考にご覧ください。
4. 想定外の抵抗や変化への柔軟な対応
改革を進める中では、当初想定していなかった技術的課題や社内の反発、外部環境の変化など、さまざまな障壁が現れます。重要なのは、それらを「失敗」ではなく「学びの機会」として捉え、柔軟に方向修正できるマネジメント体制を整えることです。このような適応力こそが、BPRを持続可能なものにします。
BPRは、単なる業務の改善ではなく、「企業の未来を形作る再設計」です。だからこそ、導入ステップと成功要因をしっかり理解し、地に足のついた実行力で進めることが求められます。
BPRを成功に導くためのツール・支援サービス
BPRを成功に導くためには、戦略や計画だけでなく、それを支える実践的なツールや外部からの支援が重要になります。BPRは単なる業務の改善ではなく、既存の業務プロセスをゼロベースで見直し、根本的に再設計する取り組みです。そのため、従来の改善活動と比べて膨大な情報整理と分析が必要となり、関係部門との調整も複雑になりがちです。
こうした課題を乗り越えるためには、ITツールを活用した業務の可視化・自動化や、第三者の専門的な視点を取り入れることが、BPRを円滑かつ効果的に進めるうえで不可欠です。
BPRを社内だけで完結させようとすると、現場の抵抗や、既存の枠組みにとらわれた発想に陥りやすく、真に革新的なプロセス変革を実現するのが困難になることもあります。そこで、以下に紹介するITツールや支援サービスの活用は、単なる作業効率化にとどまらず、BPRの成果そのものを左右する重要な要素といえるのです。
BPRに活用できるITツール例
BPRの実行には、現状分析から業務設計、施策実行、効果検証まで一貫して支援できるITツールが数多く存在します。まず最初に役立つのが、業務フローを可視化するためのBPM(Business Process Management)ツールです。これは業務の流れや関係者の役割を図式化し、無駄やボトルネックの発見を容易にします。
次に、RPA(Robotic Process Automation)ツールもBPRにおいては非常に有効です。これは、定型的で繰り返しの多い作業をソフトウェアロボットにより自動化するもので、人的リソースの削減と業務のスピードアップを実現します。
BPMツールやRPAツールは以下の記事でもご紹介していますので、ぜひ参考にご覧ください。
また、データ分析ツールもBPRには欠かせません。現状の業務データを収集・分析し、定量的な根拠に基づいて改善策を立案するには、BI(Business Intelligence)ツールの導入が効果的です。これにより、感覚に頼らない客観的な判断が可能になります。
さらに、業務プロセスのシミュレーションや改善案の効果を事前に検証するためには、プロセスマイニングツールの活用も近年注目されています。これは実際の業務ログをもとに、リアルな業務プロセスの実態を可視化し、改善ポイントを特定できます。
こうしたツールの選定にあたっては、企業の業種や規模、ITリテラシーなどを踏まえて、自社に適したものを選ぶことが重要です。機能面だけでなく、操作性や既存システムとの連携性も判断基準に加えるべきです。
専門家・外部コンサルティングの活用も選択肢
BPRは、既存のビジネス構造を再定義する高度な変革プロジェクトであり、自社だけで進めるには限界があるケースも少なくありません。そこで、有効な手段として挙げられるのが、外部の専門家や経営コンサルタント会社の活用です。
BPRに特化したコンサルタントは、業務改革の豊富な経験と成功ノウハウを持ち、第三者の中立的な視点から企業の課題を的確に診断します。加えて、自社では気づきにくい非効率やリスク、組織文化の問題まで掘り下げて指摘してくれることもあります。これは単なる改善提案にとどまらず、企業の変革に必要な意識改革まで支援する点が大きな特徴です。
また、BPRを単発のプロジェクトに終わらせず、継続的な業務改善へとつなげるためには、運用フェーズにおける定期的なレビューや、改善サイクルの仕組み化が重要になります。外部の支援者が伴走することで、プロジェクト終了後も継続的な成果を生み出しやすくなるのです。
特に、中小企業や専門人材の不足する組織においては、リソースの限界からBPRの計画が頓挫するリスクもあります。その点、外部支援を活用することで、短期間で高い専門性を導入でき、社内リソースの負担を抑えながらプロジェクトを進行できます。
まとめ|自社にとってBPRが必要かを判断するために
BPR(Business Process Re-engineering)は、単なる業務改善にとどまらず、企業活動全体を根本から見直し、大きな変革をもたらす手法です。この記事では、BPRの概要から導入が向いている企業、メリット・デメリット、導入ステップなどを解説してきました。
では、自社にBPRが必要かどうかをどう判断すればよいのでしょうか。
まず注目すべきは、現在の業務フローが成長や顧客満足度の向上を妨げていないかという点です。業務が特定の人に依存していたり、部門間の情報共有がうまくいかず、全体として非効率な状態に陥っている場合、BPRによって全体の業務設計を見直すことが有効です。
また、外部環境の変化に柔軟に対応できないと感じている企業も、BPRを検討するべきです。市場ニーズの変化やデジタル技術の進化、労働人口の減少といった要素に対し、従来のやり方のままでは限界があると感じたら、根本的な業務の見直しが必要です。
しかし、BPRには時間・コストの負担や社内の抵抗といったリスクも伴います。したがって、導入には経営層の明確なビジョンと覚悟、そして中長期的な視野を持って取り組んでいきましょう。
Otolioは議事録作成時間を最大90%以上削減できるAI議事録サービスです。議事録作成時間の削減だけではなく「会議の要点の音声をピンポイントで共有」することもでき、業界問わず大手企業、自治体など様々な累計6,000社以上で利用されています。
DXを始めたいけど、何から着手すればいいか分からない方は、ぜひAI議事録サービス「Otolio」をお試しください。
よくある質問とその回答
Q. BPRを導入するのにどれくらいの期間がかかりますか?
BPRは、企業の現行業務を根本から見直し、抜本的に再設計する取り組みです。そのため、導入にかかる期間は企業の規模や目的、既存の業務の複雑さによって大きく異なります。
計画から実行まで数か月から長くて1年以上かかるケースもあり、全社的に大規模な変革を行う場合はさらに長期化することもあります。段階的に進めることが多く、初期段階では一部部門に絞って試験的に導入し、その後に全社展開を行う流れが一般的です。
Q. BPRを進めるために社内に専門チームは必要ですか?
BPRは従来の業務や組織体制に大きな変更を加える取り組みであるため、社内に専任チームがあると推進しやすくなります。特に現場の課題や業務の流れを熟知したメンバーと、プロジェクト管理のスキルを持つ人材を中心にチームを構成するのが理想です。
しかし、社内に十分なリソースやノウハウがない場合は、外部の専門家やコンサルティング会社に支援を依頼することも効果的です。中立的な立場から課題を洗い出し、現実的な改善提案をしてくれるため、プロジェクトの成功確率が高まります。



