営業効率化の第一歩|目的・ステップ・アイデア・ツールを一挙解説
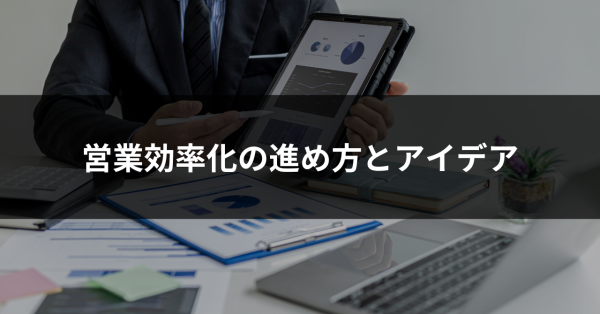
この記事でわかること
- 営業効率化を進める実践4ステップ
- 営業を効率化するアイデア
- 営業効率化に役立つツール
- 営業効率化を成功させるポイント
営業活動は、企業の売上を左右する重要な業務である一方、商談獲得から成約までのプロセスが複雑であり、人的リソースや時間を多く消費するため、営業活動の質と量をどのように両立させるかが常に課題となっています。こうした背景の中で注目されているのが「営業効率化」です。
営業効率化とは、営業活動にかかる手間や時間、コストを削減しながらも、より高い成果を上げるための取り組みを指します。属人的な業務の標準化、ITツールの導入、営業とマーケティングの連携強化など、さまざまな手法が検討されており、企業の競争力を高める鍵として重要視されています。
しかしながら、「営業効率化を進めたいとは思っているけれど、何から手をつければよいのか分からない」「社内にノウハウがなくて計画が立てられない」といった悩みを持つ方も少なくありません。特に、いざ取り組みを始めようとしても、具体的な目的や手順、ツールの選び方が曖昧なままでは、思うような効果を得ることは難しいのが現実です。
本記事では、営業効率化の基本的な考え方から、具体的な目的、実施手順、実践アイデア、役立つITツール、そして成功のポイントまでを体系的に解説します。ぜひ参考にしてみてください。
また、営業効率化にお悩みの方は、営業の議事録作成を削減できるOtolio(旧:スマート書記)をお試しください。Otolioは機密情報を学習させることなく、使えば使うほどAIの精度が上がり、商談の議事録を会議後すぐに作成することができます。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or 資料を請求する
営業効率化とは
営業効率化とは、営業活動におけるムダを削減し、限られた資源で最大限の結果を出せるように行動を最適化することを指します。この効率化とは、ただ営業の速度を上げるだけでなく、営業プロセス自体を見直し、事務作業や重複タスクなどの無駄を排除することで実現されます。
例えば、商談ごとに話す内容を一から考えるのではなく、事前にスクリプトやマニュアルを用意しておくことで準備時間を短縮し、営業の質も安定させることができます。こうした事前準備の工夫も、営業効率化の重要な取り組みのひとつです。
この効率化は、個人の行動に留まらず、組織全体の動き方にも影響を与えます。そのため、教育フローや資料内容の標準化、開発コストの見直し、技術力を含めたチームの組織力の向上など、広い視点で全体最適を目指すことが重要です。
営業効率化の意味
営業効率化の意味は、「いかに少ないコストで、最大の営業成果を生み出すか」を追求することです。ここでいう「コスト」とは、金銭に限らず、人員や時間、情報といった経営資源全般を指します。限られたリソースでより大きな価値を創出するためには、戦略的な視点が欠かせません。
加えて、効率化は単に営業スタイルの違いや手法に左右されるものではなく、データに基づいた継続的な実践と改善を支える仕組みづくりも重要です。たとえば、最近では企業のDX推進の一環として、SFAやCRMといったITツールの活用が不可欠となり、資料作成のテンプレート化や行動ログの可視化といった取り組みが広がっています。
営業効率化が求められる背景
営業の効率化が求められる最大の背景は、営業環境の大きな変化です。インバウンドの長期化、社会経済状況の不確定性、そして対面営業からオンライン商談への移行などが進む中で、これまでの成功体験に頼るだけでは通用しなくなってきています。
また、営業要員の人手不足や、若手世代を中心に広がる効率性を重視する働き方の価値観も、大きな影響を及ぼしています。こうした中では、「上司の指示を待ってから動く」のではなく、「状況に応じて自律的に優先順位を判断し行動する」「必要な情報を自ら集めて整理する」といったスキルが、営業パーソンに強く求められるようになってきています。
それによって、教育体制や情報共有の標準化、ツールの適切な活用と運用、そして実行プロセス全体の最適化など、個人任せではなく組織全体で営業力を底上げする取り組みが必要とされる時代になっています。
営業効率化の3つの目的
現代のBtoB営業においては、限られたリソースで最大限の成果を出すことが求められており、そのためには戦略的かつ全体最適を視野に入れた効率化が欠かせません。以下では、営業効率化の目的を3つの観点から詳しく解説します。
1. 営業成果の最大化
営業効率化の最も大きな目的は、成果の最大化です。単に「早く終わらせる」ためではなく、「より多くの受注を、より高い精度で得る」ための業務プロセスの最適化が本質です。
たとえば、見込み客の購買フェーズに合わせたコンテンツの提供や、SFAを活用した見込み顧客の優先度付けにより、受注確度の高い商談にリソースを集中できます。
また、営業担当がルーチンワークから解放されることで、提案内容の質を高めるための時間が確保され、顧客ニーズの本質に迫る深い洞察をもとにした対応が可能になります。つまり、営業効率化は単なる業務削減ではなく、付加価値の高い活動に時間を再配分する戦略的アプローチなのです。
2. チーム効率の向上
個人プレーに依存した営業体制では、担当者の経験やスキルによって成果にばらつきが生じがちです。営業効率化は、属人的な営業活動を脱し、チーム全体で成果を出す体制を構築することにもつながります。
たとえば、営業資料やトークスクリプトのテンプレート化、進捗の可視化によって、メンバー間で情報共有が円滑になり、引き継ぎやフォローもスムーズになります。さらに、営業プロセスの標準化は新人教育の効率向上にも貢献し、現場への即戦力化までの期間を大きく短縮します。
結果として、チーム全体のパフォーマンス底上げが可能となり、安定した成果が出せる組織へと進化していきます。
一例としてAI議事録ツールを活用してチーム効率を向上した事例を知りたい方は以下の記事も合わせてご確認ください。
3. 開発コストの抑制
一見すると営業活動と開発コストは無関係に思えるかもしれませんが、実は密接に関連しています。たとえば、顧客からの要望を正しくヒアリングできていないと、プロダクト開発チームが的外れな改善を繰り返してしまい、結果として無駄な開発コストが発生します。
営業効率化により、顧客のインサイトを的確にキャッチアップし、フィードバックを構造的に開発部門へ伝える体制を整えることで、開発の無駄打ちを防ぐことができます。
特にSaaSビジネスにおいては、営業が収集する顧客データがそのままプロダクト改善のヒントになるため、この連携は経営効率の観点からも極めて重要です。効率化された営業体制は、単なるコスト削減ではなく、開発を含む全社的なリソース配分の最適化を支える基盤となるのです。
営業効率化の4ステップ
営業活動を効率化するには、闇雲にツールを導入したり、施策を展開するのではなく、戦略的なステップに沿って着実に進めていくことが重要です。特にBtoB営業では、組織体制、商談プロセス、ナレッジの共有状況など、複数の要素が複雑に絡み合っており、1つの改善が全体に与える影響も大きくなります。ここでは、営業効率化を実現するための4つのステップを解説します。
STEP 1|現状の課題を整理する
営業の非効率を改善するためには、まず現場で「何がうまくいっていないか」を明確にする必要があります。たとえば、アポイント獲得率が低い、商談フェーズでの失注が多い、提案書の作成に時間がかかっているなど、業務プロセスの中でボトルネックとなっている部分を可視化します。
ここで重要なのは、現場担当者の感覚や経験則だけに頼らず、データに基づいて実態を把握することです。
また、単なる業務負担だけでなく、心理的な課題や組織文化も見逃してはいけません。たとえば、過去の失敗から新しい提案を避ける雰囲気があることや、ナレッジが属人化していて、他のメンバーが活用しにくいことなども、営業活動の非効率を生む原因です。こうした構造的な課題を明らかにし、チームで共有することが第一歩となります。
STEP 2|指標を設定し、KPIを明確にする
課題が明確になったら、次は改善状況を正しくモニタリングするための指標(KPI)を設定します。指標がなければ、どの施策が有効だったのか、どこが改善されたのかを判断できず、感覚的な運用になってしまいます。たとえば「訪問件数」「商談数」「受注率」「リード獲得単価」など、営業プロセスごとに分解し、数値として追える指標を定義します。
このとき重要なのは、KPIが「現場の行動と直結しているか」を確認することです。たとえば「売上」は最終的な結果であり、営業担当者が日々改善しにくい項目です。それよりも、「週に◯件のヒアリングを実施する」「提案書作成にかかる平均時間を削減する」など、具体的で管理可能なKPIを設けることで、改善意識が現場に根づきやすくなります。
さらにKPIは、短期と中長期の両方を設定することが重要です。短期指標で行動レベルの改善を評価しつつ、中長期の成果として受注数や成約率の変化を追っていくことで、持続的な改善サイクルが構築されます。
STEP 3|何が効率化を始めるボトルネックになるかを見極める
次に行うべきは、「そもそもなぜ効率化が進まないのか?」というボトルネックの特定です。課題が分かっていても、それを解消することを阻む障壁が必ず存在します。例えば、「営業資料がバラバラで、どれを使えばいいか分からない」「意思決定者が不在でツール導入が進まない」「ツールはあるが使いこなせていない」など、表面的な課題の奥に根深い問題が潜んでいることが多いのです。
このボトルネックを見極めるには、現場のヒアリングだけでなく、業務フローの図解や業務時間のログ分析なども有効です。
さらに、ボトルネックの中には「無意識のうちに正当化されている非効率」もあります。たとえば、「資料は自分で作るほうが安心」や「引き継ぎに時間をかけるのは信頼関係を築くため」といった思い込みも、営業の足かせになりかねません。
真のボトルネックを特定することで、初めて「何を、どの順番で変えるべきか」が明確になり、効率化の取り組みに本当の意味で着手できるのです。
STEP 4|実行プロセスを計画する
課題とKPI、ボトルネックが整理できたら、いよいよ改善施策の実行プロセスを具体的に設計していきます。ここで重要なのは、「段階的な実行」と「定期的な評価」です。いきなり全社的な改革に着手するのではなく、特定のチームやプロセスから小さく始め、PDCAを回しながら展開範囲を広げていくことが現実的かつ効果的です。
たとえば、まずは営業資料のテンプレート化を行い、次に営業日報のデジタル化、続いてSFAの導入といったように、改善施策をステップ化して設計します。その際、誰がリーダーとなって実行し、誰が数値をモニタリングするかといった役割分担も明確にしておきましょう。
また、実行プロセスには「現場への納得感」を盛り込むことも忘れてはいけません。現場メンバーが「自分ごと化」できなければ、施策は形骸化してしまいます。そのためには、定期的な振り返りの場を設け、現場の声を反映させながら柔軟にプロセスを更新していく必要があります。
このように、営業効率化は単なるツール導入ではなく、組織とプロセス、そして人の意識改革を伴う全体設計の改善活動であることを忘れてはなりません。
営業を効率化する6つのアイデア
営業活動をより効率的に進めるためには、実行可能で効果的な対策を講じることが重要です。ここでは、すぐにでも取り入れられる6つのアイデアを紹介します。
1. 営業資料・準備項目のテンプレート化
営業活動において、顧客に提出する資料や提案書の作成は、時間と労力を大きく消費する業務の一つです。案件ごとにゼロから作り始めてしまうと、内容の重複や見落としが発生しやすくなり、非効率につながります。
そこで効果的なのが、営業資料や準備項目のテンプレート化です。過去に使用された資料の中で成果の高かった構成をベースにテンプレートを作成し、必要に応じてカスタマイズすることで、作業時間の大幅な短縮と品質の均一化が図れます。
また、準備項目のチェックリストを作成することも有効です。訪問前の持ち物確認、顧客情報の整理、ヒアリング事項など、抜け漏れが許されない工程を一目で確認できるため、新人営業でも高いレベルで準備が整えられます。さらにテンプレートをナレッジとして共有することで、個人のスキルに依存しない組織力の底上げにもつながります。
2. 営業プロセスのテンプレート化
営業活動は多くの工程で構成されており、「アポイント取得→ヒアリング→提案→クロージング→フォローアップ」といった流れが一般的です。これらのプロセスを可視化し、標準化された営業プロセスとしてテンプレート化することにより、個人ごとの差異によるパフォーマンスのばらつきを防ぐことができます。
特に新入社員や経験の浅いメンバーにとって、標準的なプロセスは有効な指針となります。どのタイミングでどのようなアクションをとるべきかが明確になるため、スムーズに営業活動を進められます。
加えて、プロセスごとにKPIを設定することで、どの段階での離脱が多いのか、どのアクションが成約率に影響しているのかといった分析も可能になります。
テンプレート化されたプロセスをベースにPDCAを回すことで、組織全体の営業力が持続的に成長する体制を築くことができます。
3. 営業とマーケティングの連携
営業とマーケティングは本来、顧客の獲得と育成という共通の目標に向かって動いている部門ですが、実務レベルでは分断されがちです。例えば、マーケティングが獲得したリードの質が営業の期待とズレていたり、営業が得た顧客の声がマーケティングに届かなかったりすることが少なくありません。
営業効率化を実現するためには、この両部門の連携が欠かせません。たとえば、マーケティングがリードスコアリングを用いて商談化の可能性が高い見込み顧客を特定し、営業に引き渡すことで、無駄なアプローチを減らすことができます。
逆に営業が現場で得た具体的な顧客ニーズや課題をマーケティングにフィードバックすれば、より的確なコンテンツやキャンペーンが設計可能になります。
また、KPIを共通化し、部門を越えた目標管理を行うことで、連携意識が強まり組織全体のパフォーマンス向上に寄与します。
4. 社内情報共有と連携体制の最適化
営業現場では、過去の顧客対応履歴や成功事例、競合情報など、さまざまなナレッジが散在しています。これらが個人単位で管理されていると、属人化が進み、同じ失敗を繰り返したり、成功パターンが共有されない、といった非効率が生じやすくなります。
情報共有の文化と仕組みを整えることは、営業効率化の要です。具体的には、社内Wikiやナレッジベース、CRMシステムを活用して、案件ごとの進捗や対応履歴、提案内容などをリアルタイムで記録・共有することが効果的です。また、定例ミーティングや社内チャットでの報告ルールを整備し、重要な情報が埋もれないような運用設計も欠かせません。
さらに、営業だけでなくカスタマーサポートやプロダクトチームとも情報を共有することで、顧客の声を起点にしたプロダクト改善やサービスの高度化が可能になります。これにより、組織全体の顧客対応力が底上げされます。
5. 営業スキルの継続的な強化・育成
どれほど業務が効率化されても、最終的に顧客と直接関わるのは営業担当者です。営業担当者一人ひとりの能力向上は、チーム全体の生産性や成果に大きく影響するため、継続的かつ体系的なスキル育成が不可欠です。
例えば、ロールプレイングを取り入れた実践的なトレーニングや、優秀な営業担当者の商談を録画・共有しナレッジとして活用するなど、スキル習得の場を体系化することが重要です。また、OJTだけでなくeラーニングや社外研修など、学習の機会を多様に用意することで、自律的な成長を促す環境が整います。
特に重要なのは、感情認識や傾聴力などの「非言語的コミュニケーション」の価値を再認識することです。AIでは再現が困難な人間的なふるまいや共感力は、顧客との信頼を築く上で他社との差別化に直結する強力な武器となるため、数値化しにくいスキルを育成対象に含めることが、これからの営業組織にとって極めて重要です。
6. ITツールの導入・活用
ITツールの活用は、営業効率化の根幹を支える要素です。具体的には、SFA(営業支援ツール)による案件管理、CRMによる顧客情報の一元化、MAツールを活用したリードナーチャリングなど、業務ごとに最適なツールを導入することで、作業時間の短縮と精度向上を実現できます。
また、近年ではAI議事録ツールやオンライン商談ツールも注目を集めています。商談の内容を自動で文字起こし・要約してくれるAI議事録ツールは、議事録作成にかかる手間を大幅に削減します。オンライン商談ツールは移動時間の削減だけでなく、全国各地の顧客と瞬時につながることで、アプローチ数の最大化にも寄与します。
ただし、ツール導入にあたっては「導入して終わり」にならないことが重要です。運用ルールの整備や社内教育を徹底し、定期的な活用状況のモニタリングと改善を繰り返すことで、初めて真の効果を発揮します。
営業効率化に役立つ5つのツール
営業活動の生産性を高めるためには、適切なITツールの導入が欠かせません。以下では、営業効率化に特に役立つ5つのツールを紹介します。それぞれの役割や導入効果、導入時のポイントについて詳しく解説します。
1. SFA (Sales Force Automation)
SFAは、日本語では「営業支援システム」と訳され、営業活動を自動化・可視化するためのツールです。主に商談の進捗管理、タスクの割り当て、訪問記録や報告書の管理、見積書の作成などを一元的に管理できる点が特長です。
例えば、営業担当者が商談内容をSFAに記録することで、上司やチームメンバーはリアルタイムで進捗を把握できます。また、蓄積されたデータをもとに受注確度の高い案件や、成約率の高いアプローチ手法などを分析することが可能になります。
これにより、「勘と経験」に頼った営業スタイルから「データドリブン型」の営業スタイルへとシフトできるのです。注意点としては、ツール導入だけで効果が出るわけではなく、現場での運用ルールの徹底や入力負担の最小化など、社内での活用体制を整備することが求められます。
2. CRM (Customer Relationship Management)
CRMは、顧客情報を一元管理し、関係性を強化するためのツールです。顧客の企業情報、担当者情報、過去のやり取り、購買履歴、問い合わせ履歴など、顧客に関するあらゆる情報を蓄積・活用できます。
CRMを活用すれば、営業担当者の異動や退職があっても顧客対応の継続性が保たれ、顧客満足度の向上に貢献します。また、マーケティング部門と連携することで、休眠顧客へのアプローチやクロスセル・アップセルの機会創出にも繋がります。
特にサブスクリプション型ビジネスや長期契約が前提のBtoB企業では、顧客との継続的な関係構築が利益に直結するため、CRMの導入は不可欠です。ただし、情報が分散したままではCRMの真価を発揮できないため、SFAやMAとの連携設計がカギとなります。
3. MA (Marketing Automation)
MAは、見込み顧客の獲得から育成、営業への引き渡しまでを自動化・効率化するツールです。メールマーケティング、スコアリング、ホワイトペーパーの配布、Web行動のトラッキングなど、マーケティング活動を体系的に管理できます。
営業効率化との関係で言えば、MAにより「確度の高いリード」を絞り込んで営業に提供できる点が大きなメリットです。これにより、営業は見込みの薄いリードに時間を割くことなく、成約可能性の高いターゲットに集中できます。
また、リード育成の過程で取得した行動履歴や興味関心は、営業トークの精度を高める材料にもなります。近年はAIを搭載したMAも登場しており、より高度なパーソナライズドマーケティングが可能になっています。
4. オンライン商談ツール / Webミーティングツール
オンライン商談ツールは、コロナ禍以降、対面営業からオンライン営業へのシフトが加速し、今や営業活動に欠かせないインフラとなりました。
移動時間や交通費が不要となり、1日に対応できる商談数が増えることで生産性が飛躍的に向上します。また、録画機能や画面共有機能を活用すれば、ヒアリング内容や提案資料をその場で確認・記録することも可能です。
さらに、上司や専門職との参加もしやすくなり、組織的な営業活動の強化にも繋がります。これまでの「個人営業」から「チーム営業」への転換を促すツールとも言えるでしょう。
オンライン商談ツールは下記記事で掘り下げて解説していますので、より詳しく知りたい方はぜひ参考にご覧ください。
5. AI議事録ツール
AI議事録ツールは、商談や打ち合わせの内容を音声から自動で文字起こししたり、それを元に議事録として自動生成するツールです。
最大の魅力は、議事録作成にかかる時間と労力を大幅に削減できる点です。営業担当者は会話に集中できるうえ、記録の精度も高く、顧客との齟齬を防ぐことにも貢献します。また、商談の録音・文字起こしデータは、トークスクリプトの改善や新人教育、ナレッジ共有にも活用できます。
商談議事録の書き方や、AI議事録ツールについては、下記の記事でも解説していますので、それぞれ詳しく知りたいという方は、ぜひ参考にご覧ください。
営業効率化を成功させる3つのポイント
営業効率化は、多くの企業にとって重要な課題です。ただツールを導入するだけでは、期待通りの成果が出ないこともあります。そこで、営業活動を本当に効率化し成果を上げるために、押さえるべき3つのポイントをご紹介します。
1. スモールスタートから始める
営業効率化を回す上で、大きな変革やシステム入れ替えを一気に行うのは、大きなリスクを伴います。そのため、最初は「スモールスタート」から始めるのが有効です。
たとえば、営業資料をテンプレート化する、定型メールやトーク内容をあらかじめ準備しておくといった、少ない努力で成果を得られる領域からはじめましょう。
また、小さな成功体験を経験することで、チーム全体の拡散力や同意度が高まり、のちの大きな変更も準備しやすくなります。
2. リーダーの役割と責任範囲を明確にする
営業効率化は経営戦略の一環として行われることが多く、その成否はチームの気質に大きく依存します。ここで重要なのが、実行を管理するリーダーの存在です。
ただし、リーダーにすべてを任せるのではなく、役割や責任の範囲を明確にしておくことが必須です。
- 誰が日程の調整や計画立案を担当するのか
- 誰がKPIを監視するのか
- 誰が誰に向けてフィードバックをするのか
といった分担の規定が、質の高い効率化の道を開きます。
3. 実践と振り返りの循環を作る
効率化は一度行ったら終わりという性質のものではありません。時代や環境、社内体制は変化し続けます。そのため、効率化の実行には定期的な振り返りと改善のサイクルが一体となっていることが不可欠です。
例えば、月一のミーティングで効果を確認し、問題点を共有、次回の改善方針を確定するなど、少なくても月単体でのサイクルの実施が効率的です。
さらに、振り返りの過程自体が「営業スキルの共通化」を促します。営業成果をどのように判断するか、その基準をチーム全体で共有し、結果や工夫を話し合う習慣ができると、個人ごとのやり方の違いが明確になり、経験やノウハウをメンバー間で共有しやすくなります。これにより、特定の人に依存しない営業体制が築けます。
まとめ|ITツールも活用して営業を効率化しよう
営業効率化とは、限られた資源で最大限の成果を上げるために、営業プロセスを見直し、無駄を排除することを指します。その実現には、現状の課題を深く探り出し、適切なKPIを設定し、各ステップでボトルネックを見極めながら、こつこつ実行していくことが重要です。
その上で、効率化の効果を最大限にしていくためには、ITツールの活用が必須の戦略となります。SFAやCRM、MAなどのツールを用いれば、お客様の状況をリアルタイムで把握し、ゼロベースから精密に組み立てられた効率的な営業体系を実現できるようになります。
ただし、ツールはあくまで手段であり、本質的な問題は「何が無駄なのか」を見極める視点です。たとえば、営業マンの仕事の7割は、販売と直接関係のない任務に消耗されているとも言われており、この非効率な状態を改善することが効率化の本質です。
経験を重ねることで、営業の意思決定はより正確になり、行動はデータに裏打ちされたものへとなっていきます。その結果、精度と効率は好循環を生み出し、継続的な改善が自然と組織文化として根づいていきます。こうしたプロセスを積み重ねて、実践的かつ持続可能な成果へと導いていきましょう。
Otolioは議事録作成時間を最大90%以上削減できるAI議事録サービスです。議事録作成時間の削減だけではなく「会議の要点の音声をピンポイントで共有」することもでき、業界問わず大手企業、自治体など様々な累計6,000社以上で利用されています。
DXを始めたいけど、何から着手すればいいか分からない方は、ぜひAI議事録サービス「Otolio」をお試しください。
よくある質問とその回答
Q. 営業効率化を始める際に、最初に取り組むべきことは何ですか?
最初に取り組むべきは、「現状の活動におけるムダと無駄をすべてリストアップする」ことです。「STEP 1|現状の課題を整理する」で記述した内容がこれに当たります。無駄を知らずして効率化を言っても、実効を生まないどころか、すれ違った効率化はむしろ既存の良いプロセスを壊してしまいます。
さらに、課題を整理することは、同じ集団で効率化に取り組む意識を一つの方向に揃える上でも重要です。課題を共に深く掘り下げて議論することで、現場の感覚と経営の視点が的確にすり合わされていきます。
Q. ツールを導入しても営業成績が上がらないのはなぜですか?
よくある原因は、「ツールを使うことが目的化してしまっている」ことです。本来ツールは、明確に定義された課題を解決するための一手段であり、それによって何がどう良くなるかの仮説と計画がなければ、成績につながらないのは自然なことです。
さらに言えば、ツールは導入すれば即座に成果が出る魔法の道具ではありません。実際には、それを使いこなすための運用ルールの整備や教育体制の構築、データ入力の流れを標準化する作業などが求められます。こうした基盤が整っていなければ、かえって業務負担が増えてしまうことすらあります。
また、戦略と合致していないツールの選定もよくある失敗です。たとえば、BtoB型のように長期的な顧客育成が求められる営業モデルに対し、短期成果を重視するツールを導入しても、そのポテンシャルを十分に発揮できません。自社のビジネスモデルに合ったツールを、「どのように」「なぜ」使うのかを併せて検討することが、成果を引き出すうえで欠かせません。



