ドキュメント管理ツールとは?導入メリット・選び方・人気サービス比較

この記事でわかること
- ドキュメント管理ツールとは?主な機能
- ドキュメント管理ツールのメリットと選び方
- おすすめのドキュメント管理ツール
社内の契約書や請求書、会議資料など、日々増え続けるドキュメントの管理に頭を悩ませていませんか?
「最新版のファイルがどれかわからない」「必要な資料が見つからない」「権限管理が不十分でセキュリティが心配」──こうした課題は、多くの企業が直面している現実です。特にリモートワークやペーパーレス化が進む中で、従来のフォルダ管理や紙ベースの運用では限界が見えてきています。
そこで注目されているのが ドキュメント管理ツール です。文書管理システムとも呼ばれますが、要するに「企業内のあらゆる文書を一元管理し、必要な人が必要なときに安全に利用できるようにする仕組み」のことを指します。
本記事では、ドキュメント管理ツールの基本からメリット・主な機能・おすすめサービス比較・選び方のポイント、導入のステップまでをわかりやすく解説します。この記事を通じて、自社に合ったツールを選ぶ際の参考にしてみてください。
また、業務効率化にお悩みの方は、ぜひ議事録作成時間を削減できるOtolio(旧:スマート書記)をお試しください。Otolioは使えば使うほどAIの精度が上がる特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、議事録作成時間を最大90%削減することが可能です。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or サービス資料をみる
Otolio(旧:スマート書記)がわかる人気3点セット資料(サービス概要・導入事例・機能詳細)をみる
ドキュメント管理ツールとは?
企業や組織では、日々大量のファイルや資料がやり取りされています。これらを効率的かつ安全に保管・共有するために活用されるのが「ドキュメント管理ツール」です。ここでは、その基本的な定義や関連する用語の違い、そしてなぜ今注目を集めているのかを解説します。
ドキュメント管理ツールの基本定義
ドキュメント管理ツールとは、社内外で作成・共有される文書やファイルを一元的に管理できる仕組みを指します。紙の書類や個人PC内に散らばっているファイルをまとめることで、
- 必要な情報をすぐに検索できる
- 関係者間でスムーズに共有できる
- セキュリティや権限管理を徹底できる
といったメリットがあります。単なるストレージではなく「効率化」「安全性」「利便性」を同時に実現できる点が特徴です。
「文書管理システム」との違い・使われ方のニュアンス
「ドキュメント管理ツール」とよく混同される言葉に「文書管理システム」があります。両者は重なる部分も多いですが、ニュアンスが少し異なります。
- 文書管理システム:官公庁や大企業などで導入されることが多く、契約書・稟議書など、法的に保存が義務付けられている文書を対象にすることが中心。
- ドキュメント管理ツール:より広い概念で、ビジネス文書に限らず、企画書や営業資料、画像・動画なども含め、幅広いファイルを扱える柔軟性がある。
つまり、文書管理システムは「堅牢でルール重視」、ドキュメント管理ツールは「利便性や業務効率重視」という違いで使われるケースが多いです。近年ではクラウドサービス型のツールも増え、より身近な存在になっています。
なぜ今ドキュメント管理が注目されているのか|DX・法令対応・リモートワーク
近年、ドキュメント管理ツールの需要が急速に高まっている背景には、以下のようないくつかの社会的・経営的要因があります。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速
企業活動のデジタル化が進み、従来の紙・ローカル保存では対応しきれなくなっています。情報をクラウドに集約し、部門横断で活用できる仕組みが不可欠になりました。さらに、AIや自動化ツールとの連携により、単なる保存にとどまらず、業務プロセス全体を効率化する基盤としての役割も期待されています。
法令対応の必要性
電子帳簿保存法や個人情報保護法の改正など、企業に求められる法的対応は年々厳格化しています。適切なドキュメント管理は「コンプライアンス対策」の第一歩ともいえます。さらに、監査対応や内部統制の観点からも、文書の真正性や改ざん防止機能を備えたツールの導入が求められるようになっています。
リモートワーク・ハイブリッドワークの普及
社外からも安全にアクセスできる環境整備が求められています。ドキュメント管理ツールは、場所を問わず同じ資料にアクセスし、共同編集や承認作業を可能にするため、働き方改革の基盤となります。さらに、モバイル端末やタブレットからの利用も一般化しており、現場や外出先でもスムーズに業務を進められるようになっています。
さらに、ドキュメント管理ツールが注目されている理由のひとつに「ナレッジの蓄積」が挙げられます。ファイルを正しく整理・保存することで、過去の知見や失敗事例を社内に残し、新人教育や業務改善にも役立ちます。単なるファイル保管庫ではなく、「企業の知識資産を守る仕組み」としての役割が強まっているのです。
ドキュメント管理ツールを導入するメリット
ドキュメント管理ツールを導入することで、企業は情報共有のスピードやセキュリティを大幅に改善できます。単なる「便利な保管庫」ではなく、組織全体の生産性やリスク管理に直結する仕組みです。ここでは代表的なメリットを具体的に解説します。
最新版のファイルを誰でも簡単に確認できる
従来のファイル管理では、メールで複数回やり取りを行う中で「どれが最新版か分からない」という問題が頻発していました。誤って古いバージョンを参照すると、顧客提案や契約業務で大きなトラブルにつながることもあります。
ドキュメント管理ツールを導入すれば、常に最新バージョンが一元管理され、閲覧や更新がリアルタイムで反映されます。更新履歴や差分も確認できるため、誰がいつ修正したのかも明確です。これにより、社内外のメンバーが誤った情報を参照するリスクが減り、意思決定のスピードも向上します。
アクセス権限・セキュリティ強化
企業文書には、契約書や顧客情報など機密性の高いファイルが多く含まれます。ドキュメント管理ツールでは、ユーザーごとにアクセス権限を設定でき、必要な人だけが必要な情報にアクセス可能です。
さらに、ログの記録や暗号化機能により、不正アクセスや情報漏洩を防止します。監査証跡を残せるため、内部統制やコンプライアンス面でも強みがあります。セキュリティ基準が厳格化する今、こうした機能は必須といえるでしょう。
ペーパーレス化と電子帳簿保存法への対応
近年は環境配慮だけでなく、法的要件への対応も求められています。特に電子帳簿保存法に準拠するためには、電子データでの保存・検索・監査対応が可能であることが重要です。
ドキュメント管理ツールを利用すれば、紙文書のスキャン保存から、検索性の高い電子化、監査対応までスムーズに行えます。また、書類保管に必要だったキャビネットや倉庫スペースを削減でき、コスト削減にも直結します。コンプライアンス強化と業務効率化を同時に実現できるのは大きな魅力です。
承認フローや業務効率の改善
社内での稟議や承認作業は、多くの場合「誰がいつ承認したのか」が曖昧になりがちです。ドキュメント管理ツールには承認フロー機能が搭載されているものもあり、申請から承認までのプロセスを可視化できます。これにより、ボトルネックの把握やプロセス改善が可能になり、社内全体の業務効率が向上します。
さらに、モバイルやリモート環境からも承認作業を進められるため、意思決定の遅延を防止できます。働き方が多様化する今、円滑な承認フローの仕組みは企業にとって欠かせない存在になりつつあります。
ドキュメント管理ツールの主な機能
ドキュメント管理ツールは、単にファイルを保存しておく場所ではありません。情報の整理・共有・活用を効率化し、さらにセキュリティや業務プロセスの最適化にもつながる多彩な機能を備えています。ここでは、代表的な機能を詳しく紹介します。
ファイル検索・タグ付け
日常業務の中で「どこに保存したのか分からない」「最新版が見つからない」といった経験は誰にでもあるものです。ドキュメント管理ツールでは、ファイル名や文書内テキストを対象とした全文検索が可能で、紙の資料や共有サーバーを探し回る手間を大幅に減らせます。
さらに、ツールによっては搭載されているタグ付け機能を活用すれば「顧客名」「プロジェクト名」「年度」など複数の切り口で情報を分類でき、状況に応じた柔軟な検索が可能です。特定の部署やプロジェクトに必要な情報を瞬時に取り出せることで、作業効率が飛躍的に向上します。
アクセス権限管理
企業で扱う文書には契約書や個人情報など、取り扱いに注意が必要な機密情報が含まれることも多くあります。そのため「誰がどの文書にアクセスできるのか」を明確にコントロールすることが欠かせません。
ドキュメント管理ツールでは、閲覧専用・編集可・共有不可など細かな権限設定が可能で、情報漏洩リスクを大幅に低減できます。さらに、アクセスログを記録しておくことで、不正利用や内部不正の抑止にもつながります。
バージョン管理・履歴管理
共同作業で最も多いトラブルが「どれが最新版かわからない」という問題です。ドキュメント管理ツールにはバージョン管理機能が搭載されており、過去のファイルを自動保存してくれるため、上書きミスや消失があっても安心です。必要に応じて以前の状態に戻すことも可能で、編集者や変更日時も確認できます。これにより、修正履歴を追跡しながら効率的に共同作業を進められ、業務の透明性や責任の所在も明確になります。監査や社内報告の際にも履歴が証拠となるため、信頼性を確保できます。
承認・ワークフロー機能
契約書や稟議書、社内規程の改訂などは、関係者の承認を経て初めて正式な文書として効力を持ちます。従来は紙の回覧やメールで承認依頼をしていたため、承認者が不在だとフローが滞りがちでした。
一部のドキュメント管理ツールやエンタープライズ型のシステムでは、承認ルートを設定して自動的に回付できるワークフロー機能が搭載されています。これにより、承認状況をリアルタイムで把握でき、履歴も残るため監査対応やトラブル防止に有効です。
ただし、クラウドストレージ系のサービスでは標準機能として搭載されていない場合が多く、必要に応じてワークフロー専用ツールと組み合わせるケースもあります。
セキュリティ・バックアップ
企業にとってドキュメントは「知的財産」であり、万が一の流出や消失は大きな損失につながります。ドキュメント管理ツールはデータ暗号化や多要素認証など高度なセキュリティ機能を備え、不正アクセスを防止します。
また、多くのクラウド型サービスでは自動バックアップや冗長化が標準化されており、障害や災害時でも迅速に復元可能です。一方、オンプレミス型や小規模ツールでは自社でバックアップ体制を整える必要があるため、導入時には確認が欠かせません。
おすすめのドキュメント管理ツール8選
ドキュメント管理ツールにはさまざまな種類があり、企業規模や利用シーンによって最適な選択肢が異なります。ここでは代表的なカテゴリに分けて、具体的なツールを複数ご紹介します。
クラウド型ストレージ系
Google Drive

引用:Google Drive
Google Driveは、Googleが提供するクラウドストレージサービスで、世界的に広く利用されています。Google Workspaceと統合されており、ドキュメント・スプレッドシート・スライドなどをオンライン上でリアルタイムに共同編集できます。検索機能も強力で、大量のファイルからでも目的のデータを迅速に見つけ出せます。リモートワークや在宅勤務でも最新版のファイルにアクセスできるため、業務効率化に直結します。
また、Google Driveはモバイルアプリとも連携しており、外出先からでもファイル閲覧や編集が可能です。二段階認証や詳細なアクセス権限管理といったセキュリティ機能も備えているため、中小企業から大企業まで幅広く導入されています。
Google Driveの特徴
- 無料枠から利用できるため導入しやすい
- Google Workspaceとのシームレスな連携
- リアルタイム共同編集と強力な検索機能
Dropbox Business

Dropbox Businessは、Dropboxの法人向けプランで、ファイル共有や共同作業に特化したクラウド型ドキュメント管理ツールです。直感的で分かりやすいUIを持ち、非IT部門でもすぐに利用できる点が強みです。さらに「スマートシンク」機能を利用すれば、ローカル容量を節約しながらクラウド上のファイルを必要に応じて活用できます。外部パートナーとのファイル共有も容易で、パスワード付きリンクや有効期限設定などセキュリティ対策も充実しています。
加えて、Dropbox Paperを利用すれば簡単なドキュメント作成や共同編集も可能になり、チームのコミュニケーションやプロジェクト進行をサポートします。小規模から大規模組織まで幅広く導入されており、シンプルかつ高機能なクラウドストレージとして定評があります。
Dropbox Businessの特徴
- シンプルで直感的なUIと操作性
- スマートシンクによる効率的なデータ管理
- 外部共有に強くセキュリティ機能も充実
エンタープライズ型
Box
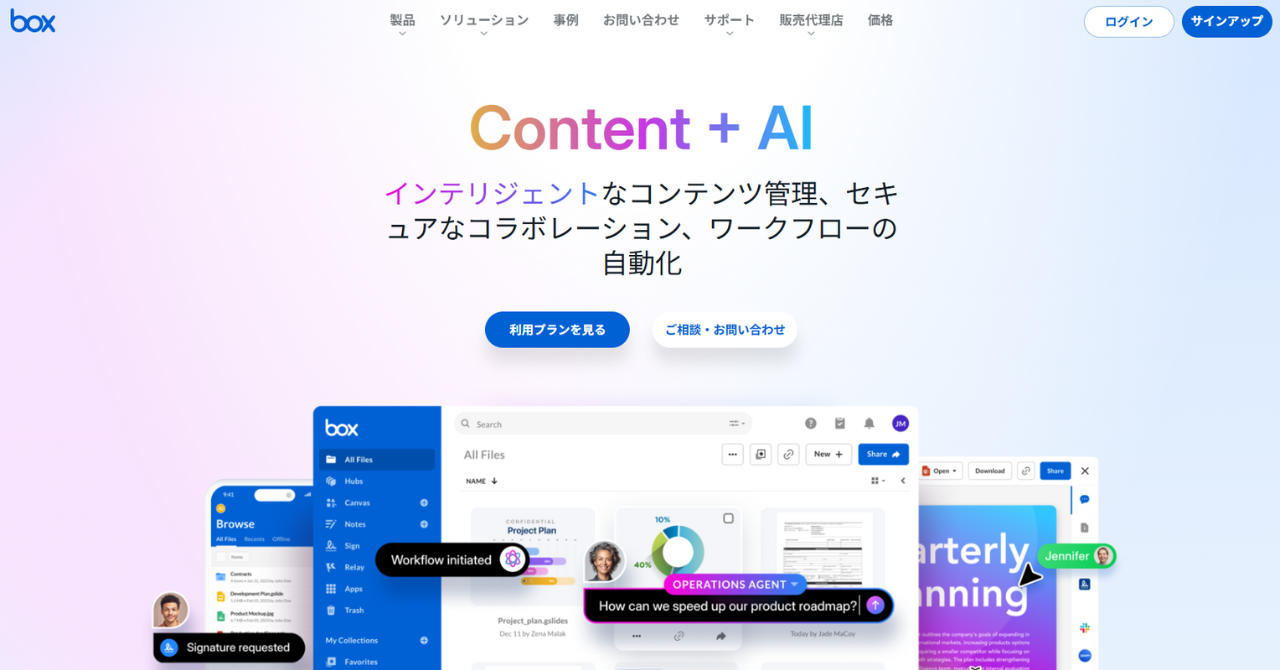
引用:Box
Boxは、大企業向けに開発されたクラウド型ドキュメント管理ツールで、グローバル企業や規模の大きい組織に多く導入されています。ユーザーやグループ単位で細かいアクセス制御ができ、強固なセキュリティ対策を備えているため、金融や医療など高いセキュリティが求められる業界でも信頼されています。SalesforceやMicrosoft 365、Slackなど、主要な業務アプリケーションとの連携も豊富です。
さらに、Boxは法令遵守を前提とした監査ログやデータ保持ポリシーを提供しており、国際的なコンプライアンス基準に対応できます。世界規模での情報共有とガバナンスを両立させたい企業にとって、非常に有効な選択肢です。
Boxの特徴
- 大企業向けの強固なセキュリティと権限制御
- SalesforceやSlackなど外部サービスとの統合
- コンプライアンス対応や監査ログ機能が充実
Microsoft SharePoint

Microsoft SharePointは、Microsoftが提供するエンタープライズ向けの情報共有・文書管理プラットフォームです。Officeアプリケーションとの統合が強力で、WordやExcelの共同編集はもちろん、社内ポータルやチームサイトの構築にも利用可能です。組織の情報を一元的に管理し、部門ごとにカスタマイズしたワークスペースを構築できるため、複雑な業務にも対応できます。
また、SharePointはワークフロー機能を備えており、承認プロセスや業務フローを自動化できます。柔軟な権限管理やセキュリティ機能も整っており、大企業の多様なニーズに応えられるシステムです。
Microsoft SharePointの特徴
- Office 365との統合による高い利便性
- 社内ポータルやワークフロー自動化に対応
- 大規模組織でも使える柔軟なカスタマイズ性
専門的な文書管理システム
DocuWare

引用:DocuWare
DocuWareは、電子文書管理(DMS)とワークフロー自動化を提供するソリューションで、契約書や請求書などの重要文書を安全に管理できます。電子帳簿保存法やGDPRなどに準拠しており、法令対応が必要な部門でも安心して導入できます。紙文書をスキャンして自動分類し、電子化する仕組みを提供しているため、オフィス全体のペーパーレス化を推進可能です。
さらに、DocuWareはクラウド版とオンプレミス版の両方を提供しており、企業のセキュリティポリシーや運用方針に応じた柔軟な選択が可能です。承認フローの自動化機能は特に経理や総務での効率化に効果を発揮します。
DocuWareの特徴
- 電子帳簿保存法やGDPRに対応
- 契約書や請求書など重要文書を効率的に管理
- クラウド・オンプレミス両対応
中小企業向けのコストパフォーマンス重視ツール
Evernote Teams

Evernote Teamsは、ノートベースで情報を整理・共有できる中小企業向けのコラボレーションツールです。議事録やメモ、タスク管理などを一元的に記録し、チームでの知識共有を効率化できます。シンプルなUIで導入コストも低いため、小規模チームでも導入しやすいのが特長です。
さらに、Google DriveやSlackとの連携も可能で、複数のツールを組み合わせて使うことで利便性が向上します。小規模ビジネスが抱える「情報が散在して把握できない」といった課題を解決するソリューションです。
Evernote Teamsの特徴
- シンプルで直感的なUI
- ノート形式で情報を柔軟に管理
- Google DriveやSlackとの連携が可能
Notion

引用:Notion
Notionは、ドキュメント管理・タスク管理・データベース作成を1つにまとめたオールインワン型のツールです。社内Wikiやマニュアル、ナレッジベースの構築に適しており、柔軟なページ設計が可能です。無料プランでも多機能を活用できるため、コストを抑えながら導入できます。
また、NotionはUIが直感的で、文書・タスク・データベースを統合して表示できるため、情報の分断を防ぎます。スタートアップや小規模チームが効率的に業務を進めるための強力な基盤となります。
Notionの特徴
- ドキュメント・タスク・データベースを一元管理
- 柔軟なカスタマイズが可能
- 無料プランでも幅広く利用可能
ドキュメント管理ツールの選び方
ドキュメント管理ツールは業務効率化やセキュリティ強化に欠かせない存在です。ただし、多くの選択肢があるため、自社に合うものを見極めるにはいくつかの視点が必要です。ここでは導入時に押さえておきたい主要ポイントを解説します。
セキュリティと法令対応は必須チェック
顧客情報や契約書などの機密データを扱う以上、暗号化・アクセス制御・多要素認証・ログ管理といった基本的なセキュリティ機能は必須です。さらに、電子帳簿保存法や個人情報保護法などの国内法令への対応も欠かせません。
海外展開を視野に入れる企業ならGDPRなど国際規制への準拠も確認しておくと安心です。法令対応が不十分なツールは、利便性が高くてもリスクを抱えることになります。
社内の利用シーンを想定して選ぶ
導入を成功させるには「誰がどの場面で使うか」を具体的にイメージすることが大切です。営業部門ならモバイルからのアクセスや取引先との共有、法務や経理部門なら承認フローや改ざん防止といった機能が重視されます。
部門ごとに必要な機能を洗い出すことで、利用定着が進みやすくなります。加えて、社外とのコラボレーションを見据えた共有のしやすさも考慮すると、将来的な業務効率が高まります。
費用対効果・スケールのしやすさ
ツールは長期的に使うため、初期費用だけでなくランニングコストや拡張性も見ておく必要があります。ユーザー数や容量が増えても柔軟に拡張でき、料金体系がシンプルであるかがポイントです。
また、アップデートや保守費用が基本料金に含まれるかどうかも確認すると安心です。「安さ」ではなく、長期的な投資効果を基準に選ぶことが重要です。
既存システムとの連携性
すでに稼働しているメールやチャット、会計ソフトなどとスムーズに連携できるかは業務効率に直結します。Microsoft 365 や Google Workspace との統合が可能なら、社員が慣れた環境で利用でき、学習コストを抑えられます。
さらに、API連携で自社独自のシステムと結びつけられるツールであれば、二重入力を防ぎ、効率性を大きく高めることができます。
導入ステップと失敗しないポイント
ドキュメント管理ツールは導入して終わりではなく、社内に根付かせてこそ効果を発揮します。ここでは導入のステップと、よくある失敗を避けるためのポイントを解説します。
導入目的と要件を明確にする
まず最初に取り組むべきは「なぜドキュメント管理ツールを導入するのか」を明確にすることです。目的が曖昧なまま導入すると、期待する効果が得られなかったり、ツールが形骸化してしまう恐れがあります。
例えば、「電子帳簿保存法への対応」「社外とのスムーズなデータ共有」「業務効率化」といった具体的なゴールを設定しましょう。その上で、必要な機能(検索性、アクセス権限管理、ワークフロー機能など)を要件として整理することが重要です。
小規模導入からテスト運用する
全社展開をいきなり行うと、混乱や抵抗が大きくなりがちです。まずは一部の部署やプロジェクトでテスト導入を行い、実際の運用で問題点や改善点を洗い出しましょう。
小規模な導入を経て調整することで、全社展開時にスムーズに進めやすくなります。特に、検索スピードやファイル整理のルールが実際の業務フローに合っているかを確認することがポイントです。
社内ルール・運用フローを整える
ツールを導入しても、ルールがなければかえって混乱を招きます。例えば「ファイル名の付け方」「保存先フォルダの階層」「アクセス権限の設定基準」など、統一ルールをあらかじめ作成しておくことが欠かせません。
また、承認フローや更新頻度のルールを明確化することで、情報の鮮度と信頼性を保てます。加えて、退職者や異動者のアカウント管理で、権限の棚卸しを定期的に行うルールも導入初期に決めておくと安心です。
社員教育と定着化がカギ
最後に重要なのが「社員への教育と定着化」です。どんなに優れたツールでも、使う人が理解していなければ成果は出ません。導入時には操作マニュアルや研修を用意し、継続的にサポートできる体制を整えましょう。また、利用状況を定期的にチェックし、使われていない機能や課題をフィードバックして改善する仕組みも有効です。
さらに、ツールを「業務効率を上げるための必須インフラ」として認識してもらうために、経営層からのメッセージ発信や成功事例の共有も大きな効果を発揮します。
まとめ|ドキュメント管理ツールは業務効率化とセキュリティ強化の第一歩
ドキュメント管理ツールは、単なる「ファイル置き場」ではなく、情報を効率的かつ安全に活用するための基盤です。最新版の資料を誰でもすぐに確認できることで、業務スピードが向上し、無駄な手戻りやミスを防ぐことができます。加えて、アクセス権限や履歴管理により、情報漏洩リスクを最小限に抑えられる点も大きな特徴です。
さらに、電子帳簿保存法や個人情報保護法といった法令対応に役立つ点も重要です。監査や取引先からの求めに迅速に対応できることで、企業の信頼性向上にも直結します。特にリモートワークが普及した現在では、「どこからでも安全にアクセスできる」環境を整えることが、事業継続性を支える大きなポイントとなります。
このように、ドキュメント管理ツールはコスト削減にとどまらず、営業活動や新規事業のスピード向上、ナレッジ共有などを支える成長基盤でもあります。業務効率化とセキュリティ強化を両立させる面でも、自社に合ったツール導入はDX推進の第一歩と言えるでしょう。
Otolioは議事録作成時間を最大90%以上削減できるAI議事録サービスです。議事録作成時間の削減だけではなく「会議の要点の音声をピンポイントで共有」することもでき、業界問わず大手企業、自治体など様々な累計6,000社以上で利用されています。
DXを始めたいけど、何から着手すればいいか分からない方は、ぜひAI議事録サービス「Otolio」をお試しください。
よくある質問とその回答
Q. ドキュメント管理ツールと文書管理システムは同じものですか?
一般的にはほぼ同じ意味で使われますが、ニュアンスには違いがあります。ドキュメント管理ツールは幅広い用途を持ち、日常的なファイル共有や共同編集に強みがあります。一方、文書管理システムは「文書の正確性・完全性」を重視し、契約書や規程類など改ざんが許されない文書の管理に特化する傾向があります。
つまり、前者は利便性や使いやすさ、後者は厳格な管理やコンプライアンス対応に軸足を置いていると考えると分かりやすいでしょう。
Q. 中小企業でもドキュメント管理ツールは必要ですか?
はい、中小企業にこそ導入するメリットがあります。従業員数が少ないからこそ「誰がどのファイルを持っているのか分からない」といった属人的な業務リスクが大きくなりがちです。ドキュメント管理ツールを導入すれば、ファイルの一元管理やアクセス権限の制御が可能になり、業務の属人化を防止できます。
さらに、取引先や監査対応の際に「必要な資料をすぐに提示できる」ことは信頼性向上にもつながります。意外な観点としては、社外からの問い合わせ対応スピードが上がることで営業機会の損失を防げる点も見逃せません。



