業務プロセスとは?業務フローとの違いから可視化・分析・改善まで徹底解説
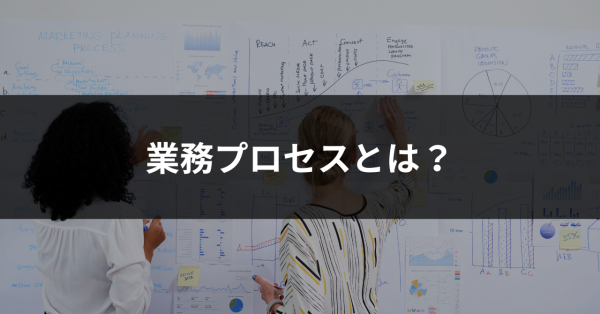
この記事でわかること
- 業務プロセスの基礎理解
- 業務プロセスと業務フローの違い
- 業務プロセスの可視化と分析方法
企業が円滑に活動を進めるためには、日々の業務がどのように流れ、成果へと結びついているのかを理解することが欠かせません。その中心にあるのが「業務プロセス」です。業務プロセスとは、組織が目標を達成するために設計された一連の活動や手順を指し、単なる作業の積み重ねではなく、企業の効率性や競争力を左右する重要な仕組みです。営業活動や顧客対応、製品開発などあらゆる分野のプロセスが、成果に直結しています。
しかし現場では、「業務が属人化している」「手順が曖昧で人によってやり方が異なる」「どこに課題があるのか把握できない」といった悩みが多く見られます。業務が複雑化するほど全体像が見えにくくなり、改善の糸口をつかめないまま非効率が積み重なるのです。こうした状況を解決するには、まず業務プロセスの基本を理解することが必要不可欠です。
本記事では、業務プロセスの定義や役割、業務フローとの違いといった基本知識から、可視化や分析の方法、さらに改善手法までを体系的に解説します。フローチャートやプロセスマップの作成、プロセスマイニングツールの活用、KPI設定、ボトルネックの特定など、実務に直結する具体的なアプローチを紹介します。またBPMやワークフローとの関連も整理し、混同しやすい概念を分かりやすく説明します。
また、業務効率化や生産性の向上にお悩みの方は、ぜひ議事録作成時間を大きく削減できるOtolio(旧:スマート書記)をお試しください。Otolioは機密情報を学習させることなく、使えば使うほどAIの精度を上げることができるため、議事録作成時間を大きく削減することができます。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or サービス資料をみる
Otolio(旧:スマート書記)がわかる人気3点セット資料(サービス概要・導入事例・機能詳細)をみる
業務プロセスの基本理解
企業活動を理解するうえで「業務プロセス」は重要な概念です。ここでは、その定義や役割、企業への影響を分かりやすく解説します。
業務プロセスの定義と役割
業務プロセスとは、企業や組織が目標を達成するために行う一連の業務の流れを体系化したものです。例えば「新商品を企画し販売する」という大きな活動は、調査、設計、製造、販売、サポートといった複数のステップで構成されます。これらを点ではなく線として結ぶことで「価値を生み出す仕組み」として理解できるのが業務プロセスです。
業務プロセスの役割
業務プロセスの役割は主に以下の3つに整理できます。
- 業務の明確化:誰が、いつ、どのように作業を行うかを可視化し、属人的な判断に依存しない仕組みをつくる。
- 品質と効率の確保:作業の標準化によって、同じ品質で効率的に成果を出すことができる。
- 改善の土台:無駄や重複を見つけやすくなり、継続的な業務改善につながる。
加えて、プロセスが明確であれば従業員は自分の役割を理解しやすくなり、安心感やモチベーションの向上にもつながります。単なる効率化の道具ではなく、組織文化や人材育成に寄与するという点も意外と重要です。
業務プロセスが企業活動に与える影響
業務プロセスが企業に与える影響は多岐にわたります。以下では、具体的な側面ごとに解説します。
効率とコスト削減
明確なプロセスに従うことで業務の無駄が減り、人的・時間的リソースを有効活用できます。その結果、単なるコスト削減にとどまらず、余剰リソースを新規事業やサービス改善といった前向きな投資に振り向けることが可能になります。これは競争が激しい市場環境において、持続的な成長を実現するための重要な要素です。
品質の安定
製造やサービスにおいて、業務プロセスを整備することで成果物の品質に一貫性を持たせられます。顧客は「いつ、どこでサービスを受けても同じレベルの品質」を求めます。業務プロセスが曖昧であれば、この期待に応えられず信頼を失うリスクがあります。
一方で、標準化されたプロセスを持つ企業は安定した品質を提供し続けることで、顧客からの信頼を強固なものにできます。業務の標準化についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にご覧ください。
リスク管理
承認フローやセキュリティ対策が不十分なまま業務を進めると、コンプライアンス違反や情報漏洩といった重大なリスクにつながります。業務プロセスを明確化することは、そうしたリスクを「見える化」し、未然に防ぐ仕組みを作ることでもあります。業務プロセスの整備が事業の信頼性や存続を左右することさえあります。
変化への対応力
ビジネス環境は常に変化しており、新しい技術や市場の変動に対応できる柔軟さが求められます。業務プロセスが整理されていれば、変更が必要な部分を迅速に特定し、スムーズに新しいやり方を導入できます。近年ではITツールやAIを取り入れた「業務プロセスの再構築(BPR)」が注目されています。
組織の学習
業務プロセスを通じて蓄積されるデータや知見は、単なる業務記録ではなく企業にとっての知的資産です。失敗の記録も改善の糧となり、同じ過ちを繰り返さない仕組みを作れます。さらに、この学習を次の戦略立案や新規プロジェクトに活かすことで、組織全体が「進化し続ける企業」へと成長していきます。
このように、業務プロセスは効率や品質だけでなく、リスク回避、変革推進、組織学習といった多面的な観点から企業活動に大きな影響を与えています。
業務プロセスと業務フローの違い
「業務プロセス」と「業務フロー」は似ているようで異なる概念です。両者を正しく理解することは、日々の業務の効率化だけでなく、組織全体の改善やデジタル化を進める上でも欠かせません。
業務フローの定義
業務フローは、業務を実際に進める手順を時系列で示したものです。フローチャートのように「誰が」「どの順番で」「何をするか」を明確にし、日々の作業がスムーズに進むようにします。新人教育や作業の標準化に特に役立ち、担当者が迷わずに作業を遂行できるようになります。また、業務フローを整理することでボトルネックを発見でき、改善のきっかけになるという点も重要です。
ただし、業務フローはあくまで「どのように進めるか」にフォーカスしているため、「なぜその業務を行うのか」「その業務が企業全体の成果にどう貢献するのか」といった上位の目的までは示しません。そのため、フローの整備だけでは部分的な効率化にとどまり、全体最適につながらないこともあります。
2つの概念の関係性と使い分け
業務プロセスと業務フローの違いをまとめると以下のようになります。
| 項目 | 業務プロセス | 業務フロー |
|---|---|---|
| 視点 | 目的や成果に着目 | 作業手順に着目 |
| 内容 | 「何のためにやるのか」を示す | 「どうやってやるのか」を示す |
| 対象範囲 | 企業活動や価値創造全体 | 個々の業務や手続きの流れ |
| 利用者 | 経営層・管理者 | 現場担当者 |
| 活用場面 | 戦略立案・改善活動・全体最適化 | 日常業務の遂行・教育・マニュアル代替 |
このように、業務プロセスは「目的地」を示し、業務フローは「そこに至る道筋」を示す存在と言えます。業務プロセスが企業全体の戦略や価値創造に直結するのに対し、業務フローは現場のオペレーションを正確かつ効率的に進めるための道具です。どちらか一方だけでは不十分であり、両方を意識することで「全体最適」と「現場の実行精度」を両立できます。
特に近年では、RPA(自動化ツール)やワークフローシステムなどデジタル技術を活用する動きが広がっています。その際、プロセスを明確にせずにフローだけを整備してしまうと、一部の作業は効率化できても組織全体の生産性は上がらないことがあります。
逆に、プロセスを整理した上でフローを構築すれば、RPAなどを用いた業務の自動化の効果を最大限に引き出すことが可能です。
関連する概念の整理
業務プロセスを深く理解するためには、関連する概念との関係性を整理しておくことが重要です。特に「BPM(ビジネス・プロセス・マネジメント)」や「ワークフロー」「オペレーション」といった用語は、日常的に使われながら混同されやすいポイントです。それぞれの違いを押さえることで、実務において正しく使い分けられるようになります。
BPM(ビジネス・プロセス・マネジメント)とは
BPMとは、企業活動における業務プロセスを継続的に改善・最適化していくためのマネジメント手法を指します。「どのプロセスが付加価値を生み出しているか」「どこに無駄があるか」を見極め、仕組みとして改善を繰り返していく点に特徴があります。
BPMの目的は、効率化だけではなく、顧客満足度やサービス品質の向上、さらには変化の激しい市場環境への柔軟な対応力を高めることにもあります。BPMは、業務プロセスを「現場の作業レベル」で終わらせず「経営資源の活用戦略」として扱うための考え方とも言えます。
ワークフローやオペレーションとの違い
「業務プロセス」という言葉と近い意味で使われがちなものに「ワークフロー」や「オペレーション」があります。これらは関連性はあるものの、指している範囲や目的が異なります。
ワークフローは、特定の業務の手順や処理の流れを定義したものです。例えば「請求書の承認フロー」や「新入社員の入社手続きフロー」のように、比較的狭い範囲で誰が・いつ・何をするかを明確にすることに焦点を当てます。これに対して業務プロセスは、より広い視点から部門横断的な活動全体を含み、価値の創出に直結する流れを対象とします。
一方、オペレーションは日々の実務そのものを意味します。つまり業務プロセスが「設計図」、ワークフローが「手順書」、そしてオペレーションが「実際の作業」と捉えると違いが理解しやすくなります。
業務プロセス可視化の重要性
業務プロセスの全体像は複雑で、担当者ごとに理解の仕方が異なることも多いため、可視化が欠かせません。見える化することによって、初めて気づける課題や改善点が浮かび上がります。
可視化による課題発見のメリット
業務プロセスを図やフローで可視化することで、普段は気づきにくい非効率や重複作業が明らかになります。例えば、承認フローに不要なステップが含まれている場合、それを削減することで処理速度が大幅に向上することがあります。
さらに、可視化は属人的な業務の洗い出しにも有効です。ある特定の担当者にしか分からない作業が見える形になることで、引き継ぎや教育がスムーズになり、リスク分散にもつながります。
経営層・現場双方の意思疎通の促進効果
業務プロセスを可視化すると、経営層と現場の間で共通の「地図」を持つことができます。経営層は戦略レベルでの意思決定に必要な情報を把握しやすくなり、現場は自分たちの課題や改善ニーズを具体的に伝えやすくなります。これにより、抽象的な議論ではなく、事実に基づいた建設的なコミュニケーションが実現します。
さらに、部署を横断した連携にも大きな効果があります。例えば、営業とバックオフィスの間で「どのタイミングで情報を共有すべきか」が可視化されていれば、ミスや遅延を防ぎやすくなります。結果として、組織全体の意思疎通がスムーズになり、改善サイクルを素早く回せる環境が整います。
業務プロセスの可視化と分析方法
業務プロセスを理解するだけでなく、実際に可視化して分析することが改善の第一歩になります。ここでは、代表的な手法やツールの活用例について具体的に解説します。
フローチャート作成の手順
フローチャートは、業務の流れを図示する最も基本的な方法です。最初に現場担当者や関係部門からヒアリングを行い、業務の開始点と終了点を明確にします。その上で、処理の順序や分岐を矢印で結び、誰がどの作業を担当するかを整理していきます。
フローチャートを作成することで、冗長な作業や不要な手戻りが一目で分かり、改善対象が見えてきます。さらに、シンプルな業務でも可視化することで、属人化していた作業が客観的に整理され、教育やマニュアル化にも役立ちます。
プロセスマップの描き方
プロセスマップは、フローチャートよりも広い視点で業務全体のつながりを表現する手法です。部門ごとの役割や情報の流れを俯瞰的に描くことで、サイロ化した業務の関係性が明らかになります。
描く際には、縦軸に関係部門、横軸に業務の時間軸を置き、どこで情報が受け渡されているかを明示するのが効果的です。特に、部門間での引き継ぎや承認フローの多さは非効率の温床になりやすく、プロセスマップを通じて可視化することで改善の糸口が見つかります。
プロセスマイニングツールの活用例
近年注目されているのが、システムのログデータを解析して自動的に業務プロセスを可視化する「プロセスマイニング」です。ERPやCRMといった業務システムに蓄積されたデータを活用することで、人手によるヒアリングでは見落としがちな実際の処理時間や例外対応の発生状況が把握できます。
例えば、ある申請業務が承認待ちで平均3日間停滞しているといった事実をデータで示せるため、経営層に改善提案をする際の説得力が増します。さらに、理想的な業務フローとの乖離を定量的に示すことができる点も大きなメリットです。
KPI・指標設定のポイント
業務プロセスを分析する際には、必ず「何をもって改善成功とするか」を示す指標を設定する必要があります。例えば、処理時間の短縮、コスト削減、エラー率の低下、顧客満足度の向上などが代表的なKPIです。
ただし、定量的な指標に加えて、従業員の業務負担感や意思決定のスピードといった定性的な視点を含めることも重要です。数字に表れにくい部分を無視すると、短期的には効率化しても長期的に現場が疲弊し、結果的に生産性が下がるリスクがあるからです。
ボトルネック特定の手法(タイムスタディ、ワークサンプリング)
業務改善において最も重要なのは、全体の流れを遅らせている「ボトルネック」を特定することです。
タイムスタディは、特定業務の処理時間を詳細に計測し、作業手順ごとに無駄を洗い出す方法です。一方、ワークサンプリングは一定の時間間隔で作業状況を観察し、どの業務にどれだけ時間が割かれているかを統計的に把握する手法です。
これらを組み合わせることで、単純に時間のかかる工程だけでなく、「待ち時間が長い」「承認に滞留する」といった隠れたボトルネックを見つけることができます。
業務プロセス改善の概要
業務プロセス改善とは、企業が日々行っている業務の流れを見直し、効率性や品質を高めるための取り組みを指します。単なるコスト削減やスピード向上だけでなく、企業の競争力強化や従業員の働きやすさにも直結する重要な活動です。
改善の必要性と基本アプローチ
業務プロセスを改善する必要性は、主に
- 非効率な作業の削減
- 顧客満足度の向上
- 従業員の負担軽減
という観点から生じます。たとえば、無駄な承認フローや手入力の多い業務は時間を浪費し、結果的に生産性の低下を招きます。
また、業務プロセスが複雑すぎると、顧客への対応が遅れたり、従業員がストレスを抱えたりする原因にもなります。したがって、改善は単に効率化のためではなく、企業全体の健全な成長と持続可能性を支える基盤づくりでもあるのです。
基本アプローチとしては、まず現状を「可視化」し、ボトルネックや無駄を発見することから始まります。そのうえで、改善すべきポイントを特定し、小さな改善から着手するのが効果的です。
さらに、改善後も継続的にモニタリングし、必要に応じて再度見直すことで、プロセスは常に最適化され続けます。特に近年では、AIや自動化ツールを活用して人的リソースを解放し、創造的な業務に注力できる体制を整える動きが加速しています。
主な改善手法の紹介(PDCA・BPRなど)
業務プロセス改善にはいくつかの代表的な手法が存在します。最も広く知られているのは「PDCAサイクル」です。
Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の流れを繰り返すことで、継続的な改善を実現します。小規模な改善や日常業務の見直しに特に有効です。
一方で、大幅な変革が求められる場合には「BPR(Business Process Re-engineering)」が用いられます。既存の業務プロセスをゼロベースで見直し、抜本的に再設計するBPRは、単なる部分最適ではなく、組織全体の構造や役割分担まで踏み込むこともあり、大胆な改革によって劇的な効率化や顧客価値の創出を実現できます。
さらに、リーン(Lean)やシックスシグマ(Six Sigma)といった品質改善や無駄削減に特化した手法も存在し、業務の性質や改善目的に応じて使い分けられます。
業務プロセスの改善について詳しく知りたい方は、以下の記事で掘り下げて解説していますので、ぜひ参考にご覧ください。
まとめ|業務プロセス理解が改善の第一歩
業務プロセスは、企業活動のあらゆる場面で「何を、誰が、どの順番で、どのように行うか」を明らかにする基本的な枠組みです。効率的でミスの少ない業務運営を実現するためには、このプロセスを正しく理解し、全体像を把握することが欠かせません。
さらに、業務プロセスを把握することは、単なる効率化だけでなく、組織全体のコミュニケーション改善や新しいビジネスモデルの発見につながることもあります。たとえば、プロセスの可視化によって、これまで個人依存だった暗黙知が形式知化され、属人化リスクを軽減できるのも大きなメリットです。
また、業務プロセスを理解することは、企業の競争力強化という観点からも重要です。市場環境が変化するなかで、プロセスを柔軟に見直し、改善できるかどうかは、企業の成長スピードに直結します。特にデジタル化が進む現代においては、プロセスを正しく設計・改善できる企業ほど、データ活用や自動化の恩恵を最大限に享受できます。
言い換えれば、業務プロセスの理解は「現在の業務を効率化するため」だけではなく、「未来の変化に対応する力を備えるため」にも不可欠なのです。改善の出発点は「現状を理解すること」にあります。業務プロセスを理解・可視化し、課題を発見し、改善につなげ、企業の持続的成長の第一歩を踏み出しましょう。
Otolioは議事録作成時間を最大90%以上削減できるAI議事録サービスです。議事録作成時間の削減だけではなく「会議の要点の音声をピンポイントで共有」することもでき、業界問わず大手企業、自治体など様々な累計6,000社以上で利用されています。
DXを始めたいけど、何から着手すればいいか分からない方は、ぜひAI議事録サービス「Otolio」をお試しください。
よくある質問とその回答
Q. 業務プロセスと業務フローは同じ意味ですか?
業務プロセスと業務フローは似ていますが、同じ意味ではありません。業務プロセスは「業務の全体的な流れや仕組み」を指し、組織全体でどのように価値が生み出されているかを表す広い概念です。
一方、業務フローはそのプロセスの中で「具体的な手順や処理の流れ」を図解化したものを意味します。簡単に言えば、業務プロセスが「地図」であるならば、業務フローは「ルート案内」にあたります。両者を正しく区別して使うことで、経営戦略レベルの改善と現場レベルの効率化をバランスよく実現できます。
Q. 業務プロセスを可視化するとどんなメリットがありますか?
業務プロセスを可視化する最大のメリットは、現状の課題を客観的に把握できる点にあります。業務のどこで時間がかかっているのか、誰に負荷が集中しているのか、どの工程でミスが発生しやすいのかを明確にできるため、改善策を立てやすくなります。
さらに、可視化は経営層と現場の共通認識を生み出し、意思決定のスピードを高める効果もあります。加えて、業務プロセスを見える化することで、外部パートナーや新入社員への説明が容易になり、スムーズな連携や教育にもつながります。



