ビジネスに最適なファイル共有ソフト|安全な選び方と注意点も解説
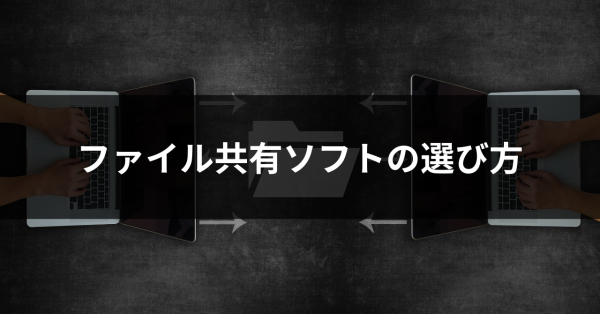
この記事でわかること
- ファイル共有ソフトの基礎知識
- おすすめのファイル共有ソフト
- ファイル共有ソフト利用時の注意点
近年、テレワークやリモートワークの普及により、社内外でのデータのやり取りが増えています。従来はメール添付やUSBメモリでの受け渡しが一般的でしたが、容量制限やセキュリティリスクといった課題から、多くの企業が「ファイル共有ソフト」の導入を検討するようになりました。
ファイル共有ソフトを利用すれば、大容量ファイルのやり取り、共同編集、アクセス権限の管理まで一元化でき、業務効率と安全性の両立が可能になります。しかし市場には多くのサービスが存在し、「どれを選べばいいのか」「自社に合うのはどのソフトなのか」と迷う方も多いでしょう。
本記事では、
- ファイル共有ソフトの基本知識
- P2P型との違いと法人利用での注意点
- おすすめの主要サービス比較
- 導入前に確認すべきポイント
をわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
また、業務効率化にお悩みの方は、ぜひ議事録作成時間を削減できるOtolio(旧:スマート書記)をお試しください。Otolioは使えば使うほどAIの精度が上がる特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、議事録作成時間を最大90%削減することが可能です。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or サービス資料をみる
Otolio(旧:スマート書記)がわかる人気3点セット資料(サービス概要・導入事例・機能詳細)をみる
ファイル共有ソフトとは?
ビジネスにおいて複数人でファイルをやり取りする場面は日常的に発生します。そこで役立つのが「ファイル共有ソフト」です。メールやUSBメモリに頼らず、安全かつ効率的にデータを共有できる仕組みを提供します。
ファイル共有ソフトの基本機能
ファイル共有ソフトには以下のような基本機能があります。
- データの保存と共有:ファイルをクラウドやサーバーに保存し、指定した相手と共有できます。
- アクセス権限の設定:閲覧のみ、編集可能、ダウンロード禁止など、利用者ごとに細かく権限を設定できます。
- バージョン管理:更新履歴を自動で保存し、誤って上書きした場合でも以前の状態に戻せます。
- 共同編集:複数人が同時にファイルを編集でき、リアルタイムで変更が反映されます。
また、一部の法人向けサービスでは、操作ログの取得や不正アクセス検知などのセキュリティ機能も備わっており、情報漏洩対策にも対応しています。
クラウド型とオンプレミス型の違い
ファイル共有ソフトは大きく分けて「クラウド型」と「オンプレミス型」があります。
- クラウド型:DropboxやGoogle Driveのように、インターネット上のサーバーにデータを保存する方式。導入コストが低く、テレワークとの相性も良いのが特徴です。インターネット環境さえあれば、どこからでもアクセスできます。
- オンプレミス型:自社サーバーを設置して運用する方式。セキュリティやデータ管理を自社で完全にコントロールできるため、金融や医療など高いセキュリティ基準が求められる業界で選ばれることが多いです。
クラウド型は「利便性・低コスト重視」、オンプレミス型は「安全性・独自要件重視」と考えると選びやすいでしょう。最近では、両者のメリットを組み合わせたハイブリッド型も登場しており、利用シーンに応じて使い分ける企業も増えています。
メール添付との違い(なぜソフトが必要なのか)
「ファイル共有はメール添付で十分では?」と考える方もいるかもしれません。しかし、業務で扱うファイルは年々大容量化しており、メールでは送信できないケースが増えています。さらに、メール添付では誤送信による情報漏洩リスクも高まります。
一方、ファイル共有ソフトを使えば以下のようなメリットがあります。
- 大容量ファイルの送受信が可能
- アクセスリンクの共有により誤送信リスクを軽減
- 暗号化や権限設定でセキュリティを担保
- 誰がいつアクセスしたかログを確認できる
さらに、ファイル共有ソフトは単なるファイルの「受け渡し」だけでなく、ナレッジ共有や業務プロセス改善の基盤になる点も見逃せません。例えば、同じプロジェクトフォルダに全員がアクセスできることで、最新資料を探す手間が減り、コミュニケーションコストが大幅に削減されます。結果的に「働き方改革」や「業務効率化」に直結します。
P2Pファイル共有ソフトとは?
ファイル共有ソフトにはさまざまな仕組みがありますが、その中でも代表的なのが「P2P(Peer to Peer)型」です。個人利用で普及しましたが、ビジネス利用には注意が必要です。ここではP2P型の仕組みやリスク、そして法人向けファイル共有との違いを解説します。
P2P型の仕組み
P2P(Peer to Peer)型ファイル共有ソフトは、サーバーを介さずにユーザー同士が直接データをやり取りする仕組みです。たとえば、あるユーザーが持っているファイルを、別のユーザーが直接そのパソコンからダウンロードする形で共有します。ネットワーク上の多数のユーザーが同時にデータをやり取りするため、効率的にファイルを分散して送受信できるのが特徴です。
一般的な例としては、音楽や動画の交換を目的としたP2Pソフトが過去に流行しました。データを分割して複数の相手から同時に取得できるため、大容量ファイルの高速な転送が可能になります。
ビジネス利用におけるリスク(セキュリティ・法的問題)
P2P型ソフトは便利な反面、ビジネス利用には大きなリスクがあります。P2P型ソフトは、ネットワーク上で不特定多数と接続するためウイルスやマルウェアの感染経路となりやすく、設定を誤れば社内機密ファイルが意図せず共有される危険性があります。
さらに、著作権で保護されたファイルを配布する行為は法的に問題となり、知らないうちに違法共有に加担してしまう可能性もあります。加えて、接続相手を制御しにくいため社外秘データが流出すれば取り返しのつかない損害につながるリスクも抱えています。
法人向けファイル共有との違い
法人向けファイル共有ソフトは、P2Pとは根本的に仕組みが異なります。クラウド型やオンプレミス型の仕組みをベースに、以下のような特徴を備えています。
- アクセス制御:誰がどのファイルにアクセスできるかを厳密に設定可能。
- 暗号化:通信や保存データを暗号化することで安全性を確保。
- ログ管理:誰がいつファイルを閲覧・編集したかを記録。
- サポート体制:企業利用を前提にしたセキュリティ・サポート体制が整っている。
つまり、P2P型は個人ユーザーの利便性に寄った仕組みであるのに対し、法人向けファイル共有ソフトは「セキュリティ・コンプライアンス・管理性」を重視して設計されています。
ビジネスでの利用には、P2Pではなく法人向けサービスを選ぶことが必須です。
法人向けファイル共有ソフトのメリット
企業にとってファイル共有ソフトは単なるデータ保存や送信手段ではなく、業務の効率化と情報資産の保護を両立させるための重要なツールです。ここでは、法人向けに特化したファイル共有ソフトのメリットを3つの観点から解説します。
セキュリティ面(暗号化・アクセス制御・ログ管理)
法人向けのファイル共有ソフトは、個人向けサービスと比べて強固なセキュリティ機能を備えています。データの送受信や保存時には暗号化が施され、第三者による盗聴や改ざんを防止できます。また、アクセス制御機能により「誰が・どのファイルに・どの権限でアクセスできるか」を細かく設定でき、情報漏洩のリスクを最小限に抑えられます。
さらにログ管理機能を活用すれば、ファイルの閲覧・編集・ダウンロード履歴を追跡でき、万が一の不正アクセスや内部不正の調査にも役立ちます。セキュリティ対策は外部攻撃だけでなく、内部統制やコンプライアンス遵守の観点からも重要です。
利便性(大容量ファイル共有・バージョン管理・共同編集)
法人利用では数百MBから数GB単位の大容量ファイルを扱うケースも多く、メール添付では対応できません。ファイル共有ソフトなら容量制限を気にせず送受信でき、動画・設計図・CADデータなどもスムーズに共有可能です。
さらにバージョン管理機能によって過去のファイル履歴を保存できるため、誤って上書きしてしまった場合でも以前の状態に戻すことができます。
共同編集機能を活用すれば、複数人が同時にファイルを更新でき、リアルタイムでの意見交換や修正が可能になります。これにより社内外でのコラボレーションが加速し、業務効率が大幅に向上します。
コスト・導入のしやすさ
法人向けファイル共有ソフトは、オンプレミス型と比べてクラウド型が主流となりつつあります。クラウド型であればサーバー構築やメンテナンスの負担が不要で、初期コストを大幅に抑えられます。また利用人数や容量に応じて料金プランを柔軟に選択できるため、企業の成長段階に合わせてスケールアップ可能です。
さらに、導入のしやすさも大きな魅力で、インターネット環境さえあれば数時間で運用を開始できます。特にリモートワークが普及する中で、クラウド型の手軽さと拡張性は大きな強みとなっています。
おすすめのファイル共有ソフト7選
法人で利用されるファイル共有ソフトは、海外製だけでなく国内発のサービスも多数あります。ここでは代表的なグローバルサービスに加え、日本企業のニーズに特化した国内製品も紹介します。
1. Dropbox Business

Dropbox Businessは、個人向けとしても広く知られるDropboxの法人向けサービスです。シンプルで直感的な操作性が特徴で、誰でもすぐに使いこなせるのが大きな魅力です。クラウド型の代表的サービスであり、世界中で利用されています。セキュリティ機能やチーム管理機能も充実しており、スタートアップから大企業まで幅広く対応可能です。
さらに、外部との安全なファイル共有やデバイスを問わないアクセス環境も整備されており、リモートワークやモバイルワークにも強い点が特徴です。シンプルさと柔軟さを兼ね備えているため、導入企業の業種を選ばず利用できます。
Dropbox Businessの特徴
- シンプルで直感的な操作性
- ファイル復元やバージョン履歴機能
- 高度なセキュリティ管理とチーム管理機能
2. Box
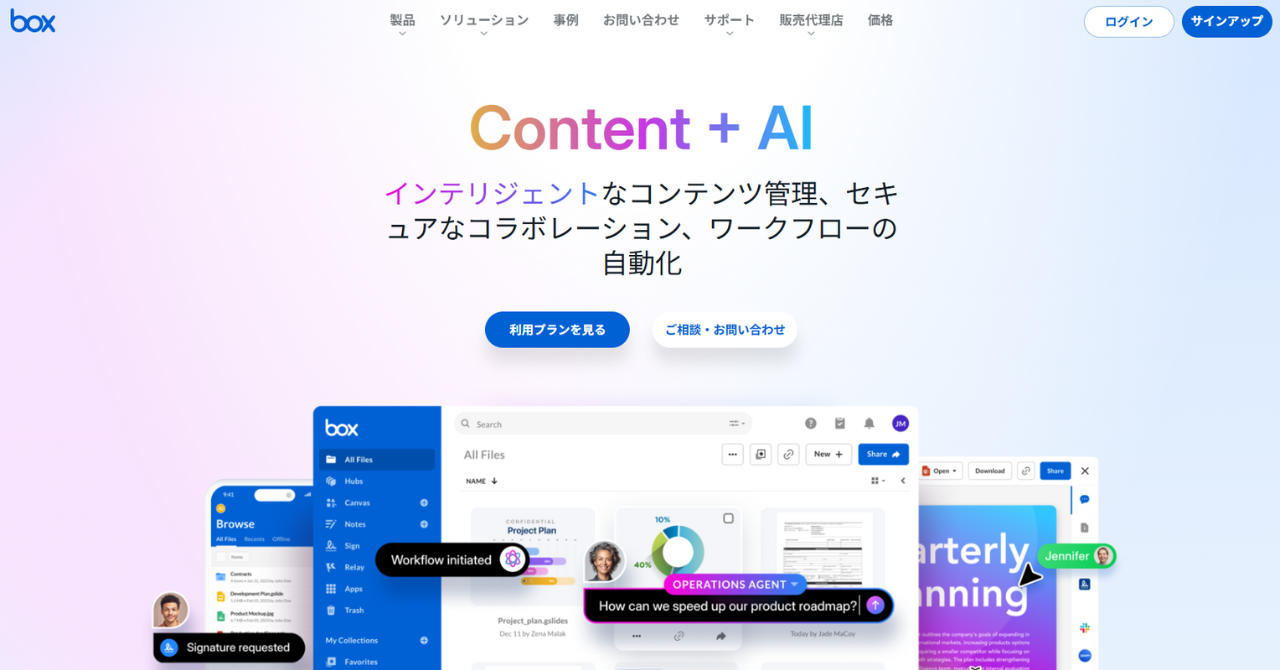
引用:Box
Boxは、特に法人利用に強いクラウド型ファイル共有サービスです。セキュリティとコンプライアンス対応に定評があり、金融や医療など厳しい基準が求められる業界でも導入が進んでいます。API連携が豊富で、既存システムとの統合もしやすいため、DX推進の基盤としても活用されています。
また、Boxはコンテンツ管理プラットフォームとしての側面もあり、単なるファイル共有にとどまらず、ワークフローの効率化や情報資産の一元管理を実現します。グローバル企業から信頼される堅牢なセキュリティ設計が、導入の後押しとなっています。
Boxの特徴
- 業界水準を満たす高度なセキュリティとコンプライアンス
- 豊富な外部サービスとの連携(Salesforce、Slackなど)
- 大企業での導入実績が豊富
3. Google Drive / Google Workspace

引用:Google Drive
Google Driveは、Google Workspaceの一部として提供されているクラウドストレージです。ドキュメント、スプレッドシート、スライドなどとシームレスに連携できるため、共同編集やリアルタイムでの情報共有に強みがあります。既にGmailやGoogleカレンダーを利用している企業であれば導入がスムーズです。
加えて、AIによる検索機能が優れており、必要なファイルをすぐに探し出せる点も利便性を高めています。多言語対応や多国籍企業での利用に適した柔軟性も備えており、グローバル展開する企業にも適しています。
Google Drive / Google Workspaceの特徴
- Googleの各種サービスとシームレスに連携
- リアルタイムでの共同編集が可能
- 直感的でわかりやすいUI
4. Microsoft OneDrive for Business

引用:Microsoft OneDrive for Business
Microsoft OneDrive for Businessは、Microsoft 365の一部として提供される法人向けクラウドストレージです。Word、Excel、PowerPointとの相性が抜群で、Office製品を日常的に利用している企業にとって自然な選択肢となります。セキュリティ機能や管理機能も強化されており、エンタープライズ利用にも耐えられます。
さらに、Windows OSとの統合がスムーズな点も特徴で、すでにMicrosoft製品を利用している環境であれば導入のハードルが低いです。大規模なユーザー管理やガバナンス機能が整っており、数千人規模の組織でも問題なく利用可能です。
Microsoft OneDrive for Businessの特徴
- Office製品との抜群の連携性
- 法人向けのセキュリティ・管理機能を搭載
- Microsoft Teamsなどとの統合利用が可能
5. セキュアSAMBA

引用:セキュアSAMBA
セキュアSAMBAは日本発の法人向けオンラインストレージサービスです。国内サーバーでの運用にこだわっており、国内法に準拠した運用体制を整えています。日本語サポートが充実しているため、中小企業から大企業まで幅広く安心して利用できます。
また、日本企業の商習慣に合わせた細やかな設定やサポートがある点も魅力です。海外製品に比べて「使いやすさ」と「安心感」を両立しており、初めてクラウド型ファイル共有ソフトを導入する企業にも適しています。
セキュアSAMBAの特徴
- 国内サーバー運用による安心感
- 日本語での充実したサポート体制
- シンプルで使いやすいUI
6. DirectCloud

引用:DirectCloud
DirectCloudは、法人向けに特化したクラウドストレージサービスです。国内データセンターを利用し、通信の暗号化やアクセスログ管理など高度なセキュリティ機能を標準搭載しています。大容量データの共有や外部との安全なファイル受け渡しにも適しており、日本企業の導入実績も豊富です。
さらに、外部パートナーや顧客とのファイル共有に特化した機能が揃っており、BtoBのやり取りが多い企業に最適です。導入支援やサポート体制も手厚く、ITリソースが限られた中小企業でも安心して活用できます。
DirectCloudの特徴
- 国内データセンターを利用した高セキュリティ
- 最大30GBの大容量ファイル高速転送に対応
- 日本企業での豊富な導入実績
7. PrimeDrive

引用:PrimeDrive
PrimeDriveは、ソフトバンクが提供する法人向けオンラインストレージサービスです。国内データセンターで運用されており、高度なセキュリティ基準(ISO 27001やISMAPなど)に準拠しています。大手企業や公共機関での導入実績も多く、安心感のあるサービスです。
また、誤送信防止のための「リンク無効化」「二重パスワード設定」「承認機能」「IP制限」「シングルサインオン対応」など、法人利用に必要な機能を網羅しています。災害対策(DR対応)も整っており、安定した運用が可能です。
PrimeDriveの特徴
- 国内データセンターでの安全運用、災害対策も対応
- ISO27001/ISMAP認定取得で高いセキュリティ基準
- リンク無効化や承認機能など誤送信防止機能が充実
ファイル共有ソフト利用時の注意点
法人でファイル共有ソフトを導入する際には、便利さだけでなく注意すべきポイントも存在します。セキュリティや運用ルールを軽視すると、大きなリスクにつながる可能性があるため、事前に理解しておくことが重要です。
セキュリティリスク(情報漏洩・不正アクセス)
ファイル共有ソフトを利用するうえで最も大きな懸念はセキュリティリスクです。社外からの不正アクセスや社内の不注意による情報漏洩は、企業にとって致命的なダメージとなり得ます。特にパスワードを使い回す、アクセス権限を適切に設定しないといった運用ミスは、外部からの攻撃を招きやすい要因です。
また、クラウド型サービスでは、提供元のサーバー障害や脆弱性が影響する可能性もあるため、暗号化や二段階認証といったセキュリティ機能を十分に活用することが求められます。
社員教育・運用ルールの必要性
どれだけ高性能なファイル共有ソフトを導入しても、使う人が誤った操作をすれば意味がありません。例えば「個人の私用デバイスに業務ファイルをダウンロードしない」「アクセス権限は必要最低限に設定する」といった基本ルールを明確にすることが重要です。
さらに、定期的に社員教育を実施し、フィッシングメールへの注意喚起や最新のセキュリティトレンドを共有することで、リスクを最小限に抑えることができます。実際に情報漏洩事故の多くは「ヒューマンエラー」が原因であるため、社員教育とルール整備は必須と言えます。
容量制限や料金プランの落とし穴
ファイル共有ソフトは無料プランから有料プランまで幅広く提供されていますが、注意すべきは「容量制限」と「料金体系」です。無料プランでは保存容量が数GB程度に限られているケースが多く、業務で使うには不十分です。また、ユーザー数が増えると追加料金が発生する仕組みのサービスも多いため、成長を見越したコストシミュレーションが欠かせません。
さらに、容量が逼迫すると「古いデータを削除しなければならない」「別サービスに移行する必要がある」といった余計な手間が発生する可能性もあります。したがって、導入前に自社の利用規模や将来的な拡張性を考慮したプラン選定が重要です。
自社に合ったファイル共有ソフトを選ぶポイント
法人向けのファイル共有ソフトは種類が豊富で、それぞれに特徴や強みがあります。そのため、自社に最適なものを選ぶには「何を重視するか」を明確にすることが重要です。ここでは選定の際にチェックすべき3つの観点を解説します。
企業規模や用途に応じた選び方
スタートアップや中小企業では、シンプルな操作性と導入コストの低さが重視される傾向にあります。一方、大企業では数千人規模の利用を前提に「アクセス権限の細かい設定」や「監査ログの充実」といった高度な管理機能が必要になることが多いです。
また、用途によっても求められる機能は異なります。例えば、デザインや動画制作を行う企業は大容量ファイルのやり取りが必須となるため、アップロード容量の上限が大きいソフトが適しています。逆に文書やスプレッドシート中心の企業では、リアルタイム共同編集が可能なものが生産性向上に直結します。
既存ツールとの連携可否
業務効率を高めるためには、既存で利用しているツールとの連携可否も重要な判断材料です。例えば、Microsoft 365 を中心に業務を行っている企業は OneDrive for Business との親和性が高く、Google Workspace を利用している企業であれば Google Drive が自然にフィットします。
さらに、Slack やTeamsなどのビジネスチャットと連携できると、ファイル共有が会話の流れの中でシームレスに行えます。また、API連携の可否や社内システムとの統合可能性を確認しておくと、後々の運用トラブルを防げます。
料金と機能のバランス
ファイル共有ソフトには無料から有料まで幅広いプランがあります。無料プランはコストがかからない反面、容量や機能制限があるため、法人利用には不向きな場合もあります。有料プランを選ぶ際は「必要な機能がすべて揃っているか」と「コストに見合った効果が得られるか」を比較検討しましょう。
例えば、数十名規模の会社であれば、上位プランの高度な管理機能は必ずしも必要ないかもしれません。逆にコンプライアンスが厳しい業界では、セキュリティ機能を最優先して高額プランを選ぶことが長期的なコスト削減につながるケースもあります。単に料金の安さで決めるのではなく、投資対効果を意識して選ぶことが大切です。
まとめ|法人利用は「セキュリティ・利便性・コスト」のバランスが重要
法人でファイル共有ソフトを導入する際に最も重要なのは、セキュリティ・利便性・コストのバランスです。セキュリティ面では、暗号化やアクセス制御、ログ管理などの機能があるかを確認することが必須です。また、利便性の面では、大容量ファイルの送受信やバージョン管理、共同編集といった機能がスムーズに利用できるかがポイントになります。
そしてコストについては、月額利用料やユーザー数に応じた課金体系が自社の予算に合っているかを見極める必要があります。これら3つの観点を総合的に判断することで、自社に最適なファイル共有ソフトを選ぶことができます。
加えて、企業によっては既存の業務システムやツールとの連携可否も大きな決定要因になります。例えば、CRMやプロジェクト管理ツールと連動できれば、情報の一元管理が可能となり業務効率が大幅に向上します。単なる「ファイルを送るためのソフト」ではなく、業務基盤の一部としてどう機能するかを意識することが、法人利用で成功するためのカギとなります。
Otolioは議事録作成時間を最大90%以上削減できるAI議事録サービスです。議事録作成時間の削減だけではなく「会議の要点の音声をピンポイントで共有」することもでき、業界問わず大手企業、自治体など様々な累計6,000社以上で利用されています。
DXを始めたいけど、何から着手すればいいか分からない方は、ぜひAI議事録サービス「Otolio」をお試しください。
よくある質問とその回答
Q. 無料のファイル共有ソフトでも法人利用はできますか?
無料版のファイル共有ソフトでも利用は可能ですが、法人利用にはあまりおすすめできません。理由として、無料版は容量制限が厳しかったり、セキュリティ機能(アクセス権限やログ管理など)が不十分である場合が多いからです。
また、サポート体制が整っていないため、万が一トラブルが発生した際に迅速な対応を受けられないリスクもあります。小規模の社内利用や試験的な利用なら問題ありませんが、本格的な業務利用では有料プランや法人向けサービスを検討する方が安全で安心です。
Q. ファイル共有ソフトとオンラインストレージの違いは何ですか?
一般的に「ファイル共有ソフト」は、特定の相手と効率的にファイルをやり取りすることに特化したツールを指します。一方「オンラインストレージ」は、クラウド上にデータを保存して長期的に保管・管理することを目的としたサービスです。つまり、前者は“共有”に強みがあり、後者は“保存”に強みがあると考えると分かりやすいでしょう。
ただし近年では、両者の境界が曖昧になりつつあります。DropboxやGoogle Driveのように、保存と共有の両方を兼ね備えたサービスが主流となっており、利用者は目的に応じて「共有重視」「保存重視」を選ぶことが重要です。特に法人利用では、共有と保存を一体的に運用できるサービスを選ぶことで、業務効率化とセキュリティ強化の両立が可能になります。



