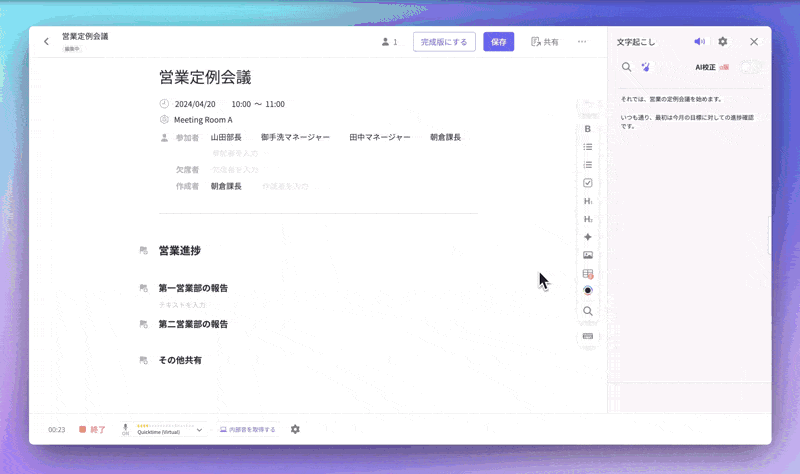業務効率化の進め方を5ステップで解説|ツール導入・業務改善の具体的な事例も紹介
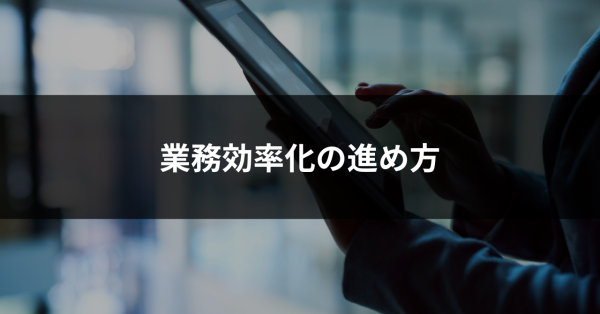
この記事でわかること
- 業務効率化で得られるメリットと進め方
- 業務効率化「AI議事録ツール」導入事例
- 業務効率化がうまくいかない落とし穴
日々の業務に追われ、やるべきことが山積みになっている、そんな状況に心当たりはありませんか?限られた時間の中で成果を出すことが求められる現代のビジネスシーンにおいて、「業務効率化」は欠かせないテーマとなっています。
業務効率化とは、単に作業スピードを上げるだけでなく、無駄を省き、重要な仕事にリソースを集中させることで、組織全体のパフォーマンスを向上させる取り組みです。
とはいえ、「業務効率化を進めたい」と考えていても、実際にどこから手をつければいいのか分からず、結局いつものやり方のまま…という方も多いのではないでしょうか。
また、効率化の必要性を感じつつも、「ツールを導入しても使いこなせなかった」「一部の業務しか改善できず、全体的な変化を感じられなかった」など、過去の取り組みが思うようにいかなかった経験を持つ方もいるかもしれません。
本記事では、業務効率化の基本的な考え方から、具体的なメリット、そして誰でも実践できる5ステップの進め方を丁寧に解説します。「業務をもっとスムーズにしたい」「チームの生産性を高めたい」「日々の仕事に追われるのを終わらせたい」そんなお悩みを抱える方はぜひ参考にしてください。
また、業務効率化にお悩みの方は、ぜひ議事録作成時間を削減できるOtolio(旧:スマート書記)をお試しください。Otolioは使えば使うほど精度が上がる特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、使えば使うほど各社に最適される高精度の文字起こしが可能です。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or 資料を請求する
業務効率化とは
業務効率化とは、企業や組織が日々行っている業務プロセスを見直し、無駄を省き、より少ない時間やリソースで高い成果を上げられるようにする取り組みのことを指します。
単に業務を早くこなすという意味だけでなく、「質を落とさずに、よりスマートに働く」ための仕組み作りや体制改善を含む、総合的な改革活動です。たとえば、アナログな作業をデジタル化したり、繰り返しの多い手作業を自動化したり、社内の情報共有をスムーズにしたりといった施策が挙げられます。
このような業務効率化の背景には、ビジネス環境の急速な変化があります。働き方改革、リモートワークの普及、人材不足、そしてグローバル競争の激化により、「いかに少ない工数で成果を最大化するか」が多くの企業にとって今まさに直面している重要な課題となっています。
また、業務効率化は単に「作業の高速化」だけを目的とするのではなく、社員が創造的な業務に時間を使えるようにすることで、企業全体の価値創出力を高めるという狙いもあります。
近年では、AIやクラウドツールの導入によって、従来では考えられなかったような効率化が可能になっています。たとえば、AI議事録ツールを使えば、会議内容の記録・要約・共有がほぼ自動で行え、時間と労力を大幅に削減できます。このようなテクノロジーの活用は、業務効率化の「質」と「速度」を大きく向上させる武器となっています。
業務効率化について、以下の記事でも掘り下げて解説していますので、ぜひ参考にご覧ください。
業務効率化で得られる5つのメリット
業務効率化には、単に作業時間を短縮する以上の効果があります。ここでは、業務効率化によって得られる5つの主なメリットを詳しく解説します。
1. 時間とコストを大幅に削減できる
業務効率化の最大のメリットのひとつは、時間とコストを大きく削減できることです。
企業の中には、日常的に繰り返される単純作業や無駄な手続きが数多く存在しています。例えば、請求書の手動処理、紙ベースの申請書類、何度もやり取りされるメールでの確認作業などが挙げられます。これらは「慣例だから」という理由で放置されがちですが、実はムダな時間の発生源となっています。
仮に一つの作業に1時間かかっていたものが、ツールの導入やワークフローの見直しで30分になれば、それだけで50%の時間削減です。それが年間数百回行われるような業務であれば、削減される時間は数百時間単位になります。それに伴い、人件費も削減でき、浮いた時間を他の生産的な活動にあてることが可能になります。
2. 生産性・集中力が高まり本来の業務に注力できる
業務効率化は、従業員一人ひとりの生産性向上にも直結します。ムダな作業を減らすことで、社員は本来やるべき重要な業務に集中できるようになります。たとえば、商品開発や営業提案、顧客対応など、成果に直結する業務に多くの時間を割けるようになります。こうした仕事に集中できることで、組織全体のパフォーマンスも向上します。
また、業務の整理・仕組み化により、タスクの見える化や優先順位の明確化が進むことで、日々の仕事に対する「段取り力」も高まります。段取りが良くなれば、集中力を保ちながら仕事に取り組めるようになり、ミスや抜け漏れのリスクも減少します。
さらに、業務効率化によって「意思決定の速度」も速くなります。作業の流れが整理されていることで、上司への確認や承認プロセスもスムーズになり、無駄な時間が削られるのです。
3. 社内コミュニケーションがスムーズになり、連携力が向上する
業務効率化は個人の仕事にとどまらず、チームや部署間の連携にも良い影響を与えます。たとえば、業務プロセスを見直す中で、誰が・どのタイミングで・何を行うのかが明確になると、社内の情報伝達がスムーズになります。属人的な「あの人に聞かないと分からない」という状況が減るため、チーム内での混乱や認識ズレが減少します。
さらに、業務に必要な情報をクラウドや社内ポータルなどで一元管理することで、リアルタイムに進捗状況を共有できるようになります。これにより、メールやチャットで何度も同じやり取りをする必要がなくなり、無駄なコミュニケーションコストを削減できます。
加えて、業務が見える化されると、他部署への理解も深まり、部門を超えた協力体制が築きやすくなります。
4. 顧客対応のスピードと質が向上し、満足度もアップする
業務効率化は、社内だけでなく、顧客対応の品質にも大きく影響します。たとえば、問い合わせ対応のフローが標準化されていないと、誰がどのように対応すべきかが曖昧になり、返信が遅れたり、内容にバラつきが出たりします。これでは顧客満足度が下がり、クレームにつながる恐れもあります。
一方、業務効率化により対応プロセスが明確になれば、迅速かつ的確な対応が可能となります。たとえば、顧客対応履歴の管理をCRMツールで一元化すれば、過去のやり取りをすぐに把握でき、二重対応や説明の重複を防げます。また、問い合わせ内容ごとのテンプレートを用意しておくことで、対応速度もアップします。
さらに、「業務効率化=顧客視点の強化」につながる点も注目です。業務が効率化されることで、顧客との接点により多くの時間を使えるようになり、ヒアリングや提案の質が向上します。それによって顧客の継続的に利用しようという意欲も高まり、結果として売上の増加にもつながるのです。
5. 属人化を防ぎ、ナレッジを資産として蓄積できる
業務効率化の過程で必ず行われるのが、「業務の可視化」と「標準化」です。これは、ある業務を誰か一人だけができる状態(属人化)から脱却し、誰でも同じように再現できるようにすることを意味します。属人化は担当者の異動や退職時に業務が止まるリスクを孕んでおり、企業にとっては大きな損失となり得ます。
業務フローや手順をマニュアル化・共有化することで、誰が対応しても一定の品質を担保できるようになります。また、作業の記録やノウハウをデジタル上に蓄積していけば、それは企業の「知的資産」となり、将来的に新人教育や業務改善にも活用できます。
また、属人化の解消が「公平な評価」や「働きやすさの向上」にもつながることもあります。業務の成果が可視化されれば、評価基準が明確になり、従業員の納得感ある人事制度の構築にもつながるのです。
業務の可視化や標準化については、以下の記事で掘り下げて解説していますので、ぜひ参考にご覧ください。
業務効率化の進め方5ステップ
業務は、やみくもに改善を図っても効果が出にくく、部分最適に終わってしまう可能性もあります。ここでは、業務効率化を効果的に進めるための5つのステップを紹介します。
Step 1|現状の業務を正確に把握し、棚卸しする
業務効率化の第一歩は、現状の業務を「見える化」することです。これには、日々の業務を洗い出し、どの業務が誰によって、どのような手順で行われているのかを正確に把握する作業が含まれます。具体的には、Excelや業務フロー図、業務日報などを用いて、ひとつひとつの業務を棚卸ししていくと把握しやすくなります。
この段階では、業務量や頻度、所要時間だけでなく、関係者や使用するツール、発生頻度が不定期な業務も含めて網羅的に把握することが大切です。見落としがちな「非公式業務」や「なんとなくやっている作業」も含めると、思わぬ改善ポイントが浮き彫りになることもあります。
ここでの丁寧な作業が、後のステップの精度を大きく左右します。
Step 2|課題を明確化し、ボトルネックを見つける
業務の棚卸しが完了したら、次に各業務が抱えている課題や非効率な部分を明確にしていきます。例えば、「承認フローが遅い」「情報が分散していて探すのに時間がかかる」「同じ作業を複数人が重複して行っている」といった問題点がないかを見つけ出します。
ポイントは、単に問題を指摘するだけでなく、その根本原因まで掘り下げて分析することです。ここで特に注目すべきは、業務全体の流れを妨げている「ボトルネック」です。
一見、些細に見える作業の遅れが、他の業務全体に影響を及ぼしていることもあります。定量的なデータ(時間・回数など)と定性的なヒアリングを組み合わせて、多角的に課題を洗い出すとよいでしょう。
Step 3|改善アイデアを出し、実行優先度を整理する
課題が明らかになったら、それを解決するための改善アイデアを洗い出します。アイデアの洗い出しには、たとえばブレインストーミング形式でチーム内の多様な視点を取り入れることで、現場に即した実行可能なアイデアが得られやすくなることもあります。
次に、洗い出したアイデアに対して「インパクト(業務への効果)」「実行コスト(時間・お金・リソース)」の2軸で評価を行い、優先順位をつけます。
ここで重要なのは、最初から完璧な解決策を求めすぎないことです。むしろ「今すぐできる小さな改善」から着手することで、改善の連鎖を起こしやすくなります。また、実行にあたっては担当者を明確にし、期限や成果の指標(KPI)を設定することで、改善活動の定着を促します。
Step 4|最適なツール・仕組みを導入して業務を仕掛け化
改善案を具体化したら、それを支える仕組みやツールを導入し、業務の仕掛け化を行います。仕掛け化とは、「人に頼らず、仕組みが自動的に動く状態」をつくることです。
たとえば、定型業務にはRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やワークフロー自動化ツールを活用し、情報共有にはクラウド型のプロジェクト管理ツールを導入するなどです。
ただし、ツール導入はあくまで手段であり、目的ではありません。現場の業務に合ったものを選び、導入後の運用や教育体制も見据えておく必要があります。
Step 5|改善の効果を検証し、継続的な仕組みに落とし込む
業務効率化の最終ステップは、実行した改善施策の効果を検証し、それを継続的な仕組みに落とし込むことです。検証では、あらかじめ設定したKPIや目標数値をもとに
- どれだけ時間が短縮されたか
- ミスがどれだけ減ったか
- 業務負荷がどれだけ軽減されたか
といった成果を評価します。この結果をもとに、必要であれば改善案の見直しや調整を行い、継続的なPDCAサイクルに組み込んでいきます。
また、改善の成果や学びを社内で共有することで、他部署への横展開も期待できます。重要なのは、「一度きりの改善」に終わらせず、効率化を企業文化として根付かせることです。そのためにも、評価と改善を定期的に実施し、常にアップデートされる業務環境を目指しましょう。
ツール導入の例:AI議事録ツールが業務効率化に与える影響
業務効率化を実現するうえで、ツールの活用は欠かせない要素です。その中でも、近年多くの企業で導入が進んでいるツールとして「AI議事録ツール」が挙げられます。
これは会議の音声を自動で文字起こしし、AIが議事録に適した形で要点をまとめてくれるツールで、特に情報共有や記録業務に時間がかかっている企業にとって、大きな業務効率UPの効果をもたらしてくれます。
この記事では、AI議事録ツール「Otolio」の導入事例をもとに、どのような課題が解決され、どのような成果につながったのかを具体的にご紹介します。
AI議事録ツール以外で、業務効率化ツールが知りたい方は以下の記事も参考にご覧ください。
AI議事録ツール「Otolio(旧:スマート書記)」とは

引用:Otolio
Otolioは使えば使うほどAIの精度が上がるAI議事録ツールです。複雑な設定や用語登録を行わなくても、今まで通り議事録を作成するだけで、各社に最適化された高精度の文字起こしが可能です。
この高精度の文字起こしにより、自動要約や要点抽出が可能なOtolioの機能「AIアシスト」の精度も向上し、議事録やドキュメント作成にかかる時間を大幅に削減することができます。またこれらはAIに学習させることなくAI精度を向上させる特許取得済の独自アルゴリズムを活用しているためセキュリティ面でも安心してご利用できます。
Otolio(旧:スマート書記)の特徴
- 機密情報を学習させることなく、使えば使うほど各社に最適された高精度の文字起こしを提供
- 様々な議事録・ドキュメントの作成時間を削減できるように複数のAI出力形式に対応
- 累計6,000社以上の利用社数。大手企業から自治体まで様々な組織で利用されている信頼性の高いセキュリティ
実際にOtolioを無料で14日間試してみたい方、資料を請求したい方はこちら。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or 資料を請求する
導入事例|Otolioを導入する前の業務課題とは
ここからは、実際にAI議事録ツール「Otolio」を導入した株式会社東京ドーム様が、業務効率化に成功した事例をご紹介します。

議事録の作成時間を削減しようと思ったきっかけを教えてください
経営会議は約1〜2時間ほど行われるのですが、その議事録を作成するのに約3〜6時間かかってしまっていました。毎週開催されるので月間だと最大で約24時間ほど議事録作成に時間をかけています。
経営会議は各議題で行われる質疑応答の発言を、「誰が」「どんな発言」をしたのか議事録としてまとめる必要があります。発言内容を一字一句そのまま議事録に残すのではなく、重複している内容の発言は削除したり、発言の主語・述語を整理するなど、あとで誰が確認しても分かるように発言を校正して、議事録にまとめる必要があるのでかなり大変な時間がかかっていました。
2023年9月に今の秘書室に異動になり、そこから経営会議の議事録を作成するようになりましたが、異動してから約一ヶ月くらいは録音のみで議事録を作成していました。ただ毎週約3〜6時間も議事録作成に時間を費やしているので、この時間を削減しないと他の業務にも支障が出ると思い、議事録作成を効率化する方法を検討し始めました。
導入事例|Otolioの導入で得られた具体的な改善効果
Otolioの導入前は1〜2時間の経営会議の議事録作成に3〜6時間、月間にして24時間ほどかかっていたとのことですが、導入後はどのくらい議事録作成業務は効率化されたのか見ていきましょう。
Otolio導入後、どのように議事録作成は変化しましたか
一番の変化はツール間を行き来してコピペを繰り返す作業がなくなったことですね。それ以外にもOtolioの機能を利用して会議中のメモ作業が一部変化しました。Otolioは会議中にリアルタイムで文字起こしされた文章をドラッグ&ドロップで編集画面に貼り付けることができるので、あとでどの発言から議事録をまとめる必要があるのか?と探す作業をなくすことができました。
▼Otolioの「ドラッグ&ドロップ」とは?
会議中にリアルタイムで表示されていく文字起こし文章の必要な箇所だけ、編集画面に貼り付けることができる機能。会議中のメモ作業をゼロにすることができ、より会議に集中することができる。
また文字起こしされた文章をクリックするだけで会議中の音声を聞き直すこともできるので、音声を探すという作業もゼロにすることができました。
ストレスだと感じていた部分がすべて解消され、またこれらの細かな作業に費やしていた時間を削減できたことで、より集中的にどう校正するか?を考えることができるようになりました。
Otolio導入後の効果について教えてください
もともと約3〜6時間かかっていた議事録作成は、約1.5〜3時間になり、約50%議事録作成時間を削減することができました。文字起こしツール導入後も約2〜4時間かかっていたので、それと比較してもさらに25%削減することができています。
なによりも文字起こしツールと比較して細かな作業のストレスがゼロになったのが何よりの効果だと感じています。「議事録を作成する」というのは企業にとって重要な業務です。ただ業務をするにあたって、ストレスに感じる作業があるだけで、集中力の低下にも影響すると思っています。
Otolioを導入したことで重要業務に対する多くのストレスを解消することができたとともに、より「どう校正するか?」という本質的な業務に集中し議事録を作成することができるようになりました。
株式会社東京ドーム様では、まず秘書室の業務において導入されたAI議事録ツール「Otolio」ですが、社内掲示板で導入事例を告知したことがきっかけで他部署での導入も決定したそうです。
業務効率化がうまくいかない3つの落とし穴
業務効率化に取り組んでいるにもかかわらず、思うように成果が出ない…そんな悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?最後に、業務効率化がうまく進まない主な理由を3つ取り上げ、それぞれの問題点と対処法を解説します。
1. ツールを導入しただけで満足してしまう
問題点
業務効率化という言葉を聞くと、多くの人は真っ先に「便利なツールを導入すること」と連想しがちです。たしかに、最新のSaaSツールやAIサービスには魅力的な機能が数多く備わっており、それらを活用することで業務を劇的に改善できる可能性があります。しかし、ツールを導入しただけで「効率化できた」と満足してしまうのは大きな落とし穴です。
たとえば、プロジェクト管理ツールを導入したものの、現場では従来のExcelやメールを併用し続けてしまい、かえって情報が分散して混乱が生じるケースも少なくありません。
対処法
ツールはあくまで手段であり、目的ではありません。重要なのは、業務プロセス全体の設計と現場への浸透です。ツールを活かすためには、
- 社内ルールの明文化
- 使用方法の統一
- 定着のための教育とサポート
が不可欠です。また、導入後に定期的な振り返りや利用状況の分析を行い、活用度をチェックする仕組みを設けることも大切です。
2. 一部だけ改善して、全体最適ができていない
問題点
業務効率化では「部分最適」ではなく「全体最適」を目指すことが重要です。たとえば、営業チームだけが業務フローを改善しても、その先の見積・契約・請求などのバックオフィスとの連携が滞れば、結局は全体としての効率は上がりません。
対処法
業務フロー全体を部門横断的に見渡す視点が必要です。部門間の連携不足を解消し、業務プロセスの一連の流れを俯瞰することで、本当のボトルネックや改善のインパクトが大きいポイントが見えてきます。
さらに、部門をまたいだ業務改善には、明確な共通目標やKPIの設定も欠かせません。部門と部門の「つなぎ目の効率化」にも目を向けることで、業務効率化が実現できます。
3. 改善効果を測定せず、継続できる仕組みがない
問題点
業務効率化を進める際、多くの企業が見落としているのが「改善の継続性」と「成果の見える化」です。業務改善の取り組みは、一度やったら終わりではありません。むしろスタート地点に過ぎず、改善を定着させ、さらにブラッシュアップしていくサイクルを回すことこそが、本当の意味での業務効率化です。
対処法
PDCAサイクルを組織文化として根付かせ、改善の成果を定量・定性的に測定することが必要です。たとえば、「このツールを導入したことで本当に時間が短縮されたのか?」「業務の正確性は向上したのか?」といった検証を行ったり、改善アイデアを共有・蓄積する仕組み作りをしていくと良いでしょう。
まとめ|業務効率化は“やり方”次第。小さな一歩から始めよう
業務効率化に大切なのは、「何を」「どのように」見直すか、という視点です。ただ単に便利そうなツールを導入したり、場当たり的な対応をするのではなく、自社の業務の実態をしっかりと把握し、課題を明確にした上で改善策を講じることが成功への第一歩です。
今回ご紹介した5ステップは、業種・業態を問わずあらゆる組織に応用できる実践的なフレームワークです。特に見落としがちなのは、「効果測定」と「継続性」です。改善後の変化を数値で把握しないと、その施策が本当に有効だったのか判断できず、習慣として定着しないとすぐに元の状態に戻ってしまいます。
また、業務効率化は単に「作業を早く終わらせる」ことではなく、社員ひとりひとりがより創造的な仕事に集中できる環境をつくることでもあります。
もし、「何から始めればいいかわからない」と感じているなら、まずは日々の業務の中で「無駄だと感じる作業」「繰り返し行っている作業」を一つだけ挙げてみてください。そして、それをどうすれば省力化・自動化できるかを考えることが、業務効率化への第一歩です。
業務効率化は、やり方次第で大きく成果が変わります。完璧を目指すのではなく、小さな改善を積み重ねることで、結果として大きなインパクトをもたらします。まずは、できることから一つずつ始めてみましょう。
Otolioは議事録作成時間を最大90%以上削減できるAI議事録サービスです。議事録作成時間の削減だけではなく「会議の要点の音声をピンポイントで共有」することもでき、業界問わず大手企業、自治体など様々な累計6,000社以上で利用されています。
DXを始めたいけど、何から着手すればいいか分からない方は、ぜひAI議事録サービス「Otolio」をお試しください。
よくある質問とその回答
Q. 「業務効率化の進め方」を始める前に、まず何をすればいいですか?
まずは、現状の業務を正確に把握することが出発点です。多くの企業やチームが、漠然とした不満や「忙しい」という感覚だけで改善を進めようとしがちですが、それでは的確なアプローチが取れません。
現状を棚卸しし、業務の種類やフロー、関係者、時間配分などを可視化することで、本当の課題や改善ポイントが浮き彫りになります。そのうえで、次のステップとして課題の明確化と改善策の優先順位付けに進むのが理想的な流れです。
Q. 「業務効率化」はツールを入れればすぐ実現できるのでしょうか?
ツールはあくまで手段であり、目的ではありません。ツールの導入だけで業務効率化が実現するわけではなく、まずは業務プロセスの見直しや改善の方向性を定めることが重要です。
たとえば、会議時間が長いという課題に対してAI議事録ツールを導入する場合も、「誰が使うのか」「どう活用するのか」「どのようなアウトプットが必要か」を明確にしておくことで、導入後にしっかりと効果を実感できます。ツールは業務の仕掛け化や自動化を助けてくれるパートナーとして位置づけましょう。
Q. 「業務効率化」は一度やれば終わりですか?継続する必要はありますか?
業務効率化は一度きりのプロジェクトではなく、継続的な取り組みです。なぜなら、業務内容や人員構成、外部環境(市場やテクノロジー)の変化に応じて、業務の課題も常に変化するからです。
記事内でも紹介した「Step 5|改善の効果を検証し、継続的な仕組みに落とし込む」ことが、まさにこの継続性を担保する要となります。定期的に効果を見直し、小さな改善を積み重ねていくことで、組織としての生産性が根本から底上げされていきます。