会議をペーパーレス化する方法|メリットと導入ステップを徹底解説
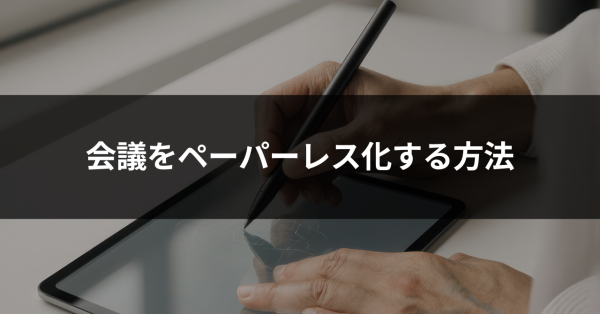
この記事でわかること
- 会議をペーパーレス化する前に押さえておきたい課題と対策
- 会議をペーパーレス化する5つのステップ
- 会議のペーパーレス化をスムーズに進めるためのポイント
日本の多くの企業では、今でも紙の資料を印刷・配布し、回収してファイリングする会議スタイルが根強く残っています。しかし、働き方の多様化や環境配慮、業務効率化の観点から、こういったやり方を見直す流れが加速しています。特にリモート・ハイブリッドワークの拡大により、紙ベースでは対応しきれない場面も増えました。
一方で、「ペーパーレス会議を始めたいけれど、何から手をつけていいかわからない」「社内にデジタルに不慣れな人がいて不安」といった悩みも少なくありません。資料をPDF化するだけでは、業務がスムーズになるとは限らず、運用・セキュリティ・教育など乗り越えるべき課題があります。
そこで本記事では、「会議のペーパーレス化」をテーマに、基本的な仕組みからメリット、課題、導入ステップ、運用のコツまでをわかりやすく解説します。社内会議をスマート化し、業務効率とコスト削減を両立したい方は、ぜひ参考にしてください。
また、会議の運営業務の効率化にお悩みの方は、ぜひ議事録作成時間を削減できるOtolio(旧:スマート書記)をお試しください。Otolioは使えば使うほどAIの精度が上がる特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、議事録作成時間を最大90%削減することが可能です。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or 資料を請求する
Otolio(旧:スマート書記)がわかる人気3点セット資料(サービス概要・導入事例・機能詳細)をみる
ペーパーレス会議とは?
近年、多くの企業で注目されているのが「ペーパーレス会議」です。紙の資料を印刷・配布するのではなく、タブレットやPCなどのデジタル端末を使って資料を共有・閲覧しながら進める会議のことを指します。
資料はクラウド上に保存され、参加者はその場で閲覧・コメント・修正が可能です。紙のように印刷や配布の手間がなく、修正もリアルタイムで反映できるため、時間とコストを大幅に削減できます。
また、資料が一元管理できるためセキュリティ面も強化しやすく、リモート会議とも相性が良いのが特徴です。最近では、単なる紙の削減にとどまらず、会議全体の効率化や働き方の見直しにもつながる手段として導入が進んでいます。
会議をペーパーレス化する主なメリット
近年、多くの企業や自治体が「ペーパーレス会議」に移行しています。ここでは、ペーパーレス会議の代表的なメリットを詳しく解説します。
印刷・配布コストを大幅に削減できる
従来の会議では、資料の印刷や製本、配布に多くの時間とコストがかかっていました。特に参加人数が多い会議では、1回の開催で数百枚もの紙資料が必要になるケースもあります。ペーパーレス化すれば、印刷費や紙代だけでなく、資料準備にかかる人件費も削減可能です。
また、紙資料を事前に印刷する必要がなくなるため、急な内容変更にも柔軟に対応できます。たとえば、会議直前に最新の数値やグラフを差し替える場合でも、デジタル資料なら即時反映が可能です。
資料の修正・共有がリアルタイムで可能
ペーパーレス会議では、資料をクラウド上で管理・共有するのが一般的です。これにより、資料の更新や修正が即時に反映され、参加者全員が常に最新の情報を確認できます。
また、会議中に出た意見や追加資料をその場で共有することで、意思決定のスピードが大幅に向上します。特に複数拠点で同時に会議を行う場合にも、情報の齟齬が発生しにくくなります。
情報漏洩リスクを軽減できる
紙の資料は、置き忘れや紛失による情報漏洩のリスクが常に伴います。ペーパーレス会議では、アクセス権限の設定やパスワード管理を徹底することで、機密情報を安全に取り扱うことが可能です。
また、資料の閲覧・編集履歴を残せるため、「誰がいつ何を見たか」のログを追跡することも容易です。セキュリティ事故が発生した場合も、迅速な原因究明と対策が可能になります。
エコ・SDGsへの貢献で企業価値を高める
ペーパーレス化は単なるコスト削減策にとどまらず、環境への配慮という社会的価値を企業にもたらします。紙の使用量を減らすことで、森林資源の保全やCO₂排出削減に貢献でき、SDGs(持続可能な開発目標)の達成にも寄与します。
特に近年では、環境への取り組みが企業評価の一部となっており、CSR(企業の社会的責任)やESG経営の観点からもペーパーレス化は重要な戦略の一つです。対外的なイメージ向上にもつながります。
リモート・ハイブリッドワークにも柔軟に対応
リモートワークやハイブリッドワークが普及する中、物理的な紙資料では対応が難しいケースが増えています。ペーパーレス会議であれば、インターネット環境さえあれば、どこからでも会議に参加し、資料を閲覧・共有できます。さらに、オンライン会議ツールやAI議事録ツールとの連携により、出席できなかったメンバーへの情報共有も容易になります。
会議をペーパーレス化する前に押さえておきたい課題と対策
ペーパーレス会議は多くのメリットがありますが、導入前にしっかりと課題を把握し、対策を講じておくことで、スムーズな運用と定着につなげることができます。以下では、企業が直面しやすい4つの代表的な課題と、その具体的な対策を紹介します。
社員のデジタルリテラシー格差への対応
ペーパーレス会議を導入する際、最も大きな障壁のひとつが「社員のITスキルの差」です。特に紙資料での会議に慣れたベテラン層のなかには、タブレット操作やクラウドツールの活用に抵抗を感じる人も少なくありません。
この課題に対しては、全社員一律の研修ではなく、レベルに応じた段階的なトレーニングを行うことが効果的です。基本操作に慣れるための少人数制ワークショップを実施したり、実際の会議を想定したシミュレーションを取り入れたりすることで、安心して移行できる環境を整えましょう。
また、マニュアルやFAQを社内ポータルに常設し、いつでも参照できる仕組みをつくることも重要です。さらに、「ツールの操作を覚える」という観点だけでなく、「なぜペーパーレスにするのか」という目的意識を共有することで、社員の理解と協力を得やすくなります。
セキュリティ設定・アクセス管理の徹底
ペーパーレス会議では、議事録や会議メモがデジタル化されるため、情報漏洩のリスク管理が不可欠です。特に外部との共有やリモート会議が増えると、アクセス権限の設定やデータの持ち出し管理が重要になります。
具体的には、資料へのアクセス権限を「閲覧のみ」に制限したり、会議参加者ごとにアクセスログを残したりするなどの対策が考えられます。また、端末の紛失や盗難に備えて、リモートワイプ機能(遠隔データ削除)を活用できる環境を整えることも有効です。
加えて、会議資料を個人の端末にダウンロードさせるのではなく、セキュリティの高いクラウド上で閲覧・編集できる仕組みを採用すると、情報管理の精度が格段に高まります。
ネットワーク環境やデバイス整備
ペーパーレス会議を成功させるには、安定したネットワーク環境と使いやすいデバイスの整備が欠かせません。特に大人数が同時接続する会議室では、Wi-Fiの帯域不足や接続不良が会議の進行を妨げる可能性があります。
事前に社内ネットワークの負荷テストを行い、必要に応じて回線増強やアクセスポイントの追加を検討しましょう。また、全員が快適に資料を閲覧できるように、会議専用のタブレットやノートPCを整備しておくことも重要です。
私物端末の持ち込みを認める場合は、セキュリティルールを明確に定め、必要なソフトウェアを統一することでトラブルを防止します。さらに、オフラインでも資料を参照できるような仕組みを準備しておくと、急なネットワークトラブルにも柔軟に対応できます。
コスト試算と社内への説明
「紙の削減=コスト削減」というイメージがありますが、ペーパーレス会議の導入には初期投資が必要です。タブレットやネットワーク機器の整備、ツールのライセンス費用、研修コストなど、トータルの費用を事前に明確化し、社内で合意を得ることが重要です。
このとき、単に導入コストだけを伝えるのではなく、「年間の印刷コスト削減額」や「会議準備時間の短縮による生産性向上」など、定量的な効果を数値化して提示すると、社内の理解が得やすくなります。特に経営層には、ROI(投資対効果)の観点から説明すると効果的です。
また、全社一斉導入ではなく、まずは小規模な会議から段階的に導入することで、コストを抑えながらノウハウを蓄積し、最終的に全社展開へとつなげる戦略も有効です。
会議をペーパーレス化する5つのステップ
会議をペーパーレス化するには、単に紙をなくすのではなく、会議運営の仕組みそのものを見直すことが欠かせません。以下の5つのステップを踏むことで、コスト削減・効率化・セキュリティ強化を同時に実現することが可能になります。
STEP1|現状の課題を洗い出す
まず最初に行うべきは、現在の会議運営における課題を明確にすることです。紙の資料を使用していることで、印刷コストの増大や準備にかかる時間、資料のバージョン管理の煩雑さといった非効率が生じているケースが多く見られます。
また、資料の持ち帰りによる情報漏洩リスクも見過ごせません。現場の声を丁寧にヒアリングし、「なぜペーパーレスにしたいのか」をチーム全体で共有することが、成功への第一歩です。
課題を洗い出す際には、会議の種類(定例会議、役員会議、営業会議など)ごとに整理し、どのプロセスに紙が必要なのかを具体的に把握しましょう。これにより、ペーパーレス化の対象範囲と優先順位を明確にすることができます。
STEP2|ペーパーレス化の目的を明確にする
ペーパーレス化の「目的」が曖昧なまま進めると、導入後に効果が見えず、定着しないリスクがあります。例えば、「印刷コストの削減」を最優先とするのか、「会議準備の効率化」や「セキュリティ強化」を重視するのかによって、選ぶツールや運用設計も大きく変わります。
さらに、単なるコスト削減だけでなく、「意思決定のスピード向上」や「ハイブリッドワークへの対応力強化」など、戦略的な視点を盛り込むことで、社内の賛同を得やすくなります。目的を明文化し、関係者全員が共通認識を持つことが重要です。
STEP3|ツール・システムを選定する
ペーパーレス会議を実現するためには、適切なツールやシステムの選定が欠かせません。代表的なものとしては、クラウドストレージ、オンラインホワイトボード、AI議事録ツールなどがあります。目的に応じて、資料の共有・閲覧・編集・記録といった機能をどこまでカバーするかを整理し、比較検討しましょう。
また、セキュリティ対策やアクセス権限の管理がしやすいかも重要なポイントです。操作が複雑なツールは定着しづらいため、社内のITリテラシーに合ったものを選ぶことが成功のカギとなります。
STEP4|デバイス(タブレット・PC)を準備する
システムが決まったら、次に必要となるのがデバイスの整備です。多くの企業ではタブレット端末やノートPCが主流ですが、利用するツールとの互換性や操作性を事前に確認しておくことが大切です。特に役員会議や顧客向けのプレゼンでは、画面の見やすさや軽さ、バッテリー持ちも重要な要素となります。
また、社内共有用の端末を整備するのか、社員の私物デバイスを活用するのかといった運用ルールも事前に検討しましょう。私物端末の持ち込みを認める場合は、セキュリティ対策をより強化する必要があります。
STEP5|運用ルールを整備して試験導入する
最後に、実際に運用を始める前に「ルール設計」と「試験運用」を行いましょう。具体的には、資料のアップロード期限、アクセス権限、会議中の操作ルール、議事録の保存場所などを明確にしておく必要があります。
いきなり全社導入するのではなく、小規模な会議からテスト的にスタートすることで、実運用での課題を洗い出しやすくなります。その結果を踏まえて改善を重ねることで、スムーズな全社展開が可能になります。最初から完璧を目指すよりも、柔軟な改善サイクルを意識することが成功のポイントです。
ペーパーレス会議に最適なタブレットの選び方
会議を完全にペーパーレス化するには、紙の代わりとなる「タブレット端末」の選び方が非常に重要です。端末の性能や使い勝手は、会議の効率や参加者の満足度を大きく左右します。ここでは、選定ポイントと2025年10月時点のおすすめ機種を紹介します。
選定ポイント
ペーパーレス会議で使用するタブレットを選ぶ際は、以下のポイントを押さえることが大切です。
1. 画面サイズと解像度
資料の閲覧や書き込みを快適に行うためには、10インチ以上の画面サイズと高解像度(フルHD以上)が理想的です。複数ページの資料を拡大縮小する手間を減らし、細部まで見やすくなります。
2. ペン入力・タッチ操作の精度
会議資料へのメモ書きや図表への追記がスムーズにできるよう、スタイラスペン対応モデルを選ぶと便利です。特に、筆圧感知や手のひら検出機能があると紙に近い感覚で書き込めます。
3. バッテリー持続時間
長時間の会議や出張先での利用を想定し、最低でも8時間以上の連続稼働が可能なモデルが望ましいです。モバイルバッテリー不要で運用できると、管理の手間も減ります。
4. セキュリティと管理機能
ペーパーレス会議では機密資料を扱うケースが多いため、端末ロック、リモートワイプ、MDM(モバイルデバイス管理)対応など、セキュリティ機能の充実が欠かせません。
5. 連携アプリとの相性
議事録の共有や資料の同時閲覧には、会議システムとの連携がスムーズであることが重要です。特にクラウドストレージやAI議事録ツールとの相性を確認しておきましょう。
6. コストパフォーマンス
全社員が利用するケースでは、1台あたりのコストも重要な判断材料です。高性能モデルだけでなく、必要十分なスペックを満たした中価格帯モデルを組み合わせるのも一つの戦略です。
おすすめ機種
1. iPad Air(第6世代)
最新チップを搭載し、処理速度がさらに向上しました。軽量で持ち運びやすく、高解像度のLiquid Retinaディスプレイと第2世代Apple Pencilに対応しています。資料閲覧・メモ・共有が非常にスムーズで、セキュリティ機能も企業利用に最適です。
2. Galaxy Tab S10
Sペンの書き心地がさらに進化し、紙に近い感覚で会議のメモが取れます。バッテリー性能と冷却機能が強化され、長時間の会議にも安心です。Androidアプリとの連携も柔軟で、コスト面でもバランスが取れたモデルです。
3. Galaxy Tab S10 FE(コスト重視モデル)
上位モデルの使い勝手を保ちつつ、価格を抑えた「Fan Edition」モデル。資料閲覧・注釈・共有といった基本機能をしっかりカバーし、大量導入にも適しています。教育機関や営業部門などでの採用例が増加中です。
4. Surface Go 4
Windows 11搭載でPCとの親和性が高く、Office系ソフトを活用する企業に特におすすめです。軽量かつ堅牢なデザインで、社内外の会議やプレゼンテーションに最適です。
5. Pixel Tablet
Google製の純正タブレットとして人気上昇中です。シームレスなクラウド連携と音声アシスタント機能により、会議の効率化を強力にサポートします。ハイブリッドワークにも最適なモデルです。
スムーズな導入のためのポイント
ペーパーレス会議は、環境への配慮やコスト削減だけでなく、業務効率を大きく高める可能性を秘めています。しかし、いきなり全社導入を進めると、現場に混乱が生じることもあります。ここでは、スムーズに運用を定着させるための3つのポイントを紹介します。
小規模会議から始める
ペーパーレス会議の導入は、まず小規模な会議から始めるのが効果的です。最初から大規模な会議で運用すると、トラブルや戸惑いが発生した際に対応が難しくなる可能性があります。少人数のチーム会議や定例ミーティングから始めることで、運用上の課題や必要な改善点を把握しやすくなります。
また、初期段階で成功事例を作ることで、社内全体への展開がスムーズになります。「実際に便利だった」という声が社内に広がることで、他部署への導入も加速しやすくなるのです。
社員への説明・トレーニングを丁寧に
ツールやデバイスを用意するだけでは、ペーパーレス会議は定着しません。社員が安心して活用できるよう、導入前後でしっかりと説明やトレーニングを行うことが重要です。特に、ITに不慣れな社員が取り残されないよう、基礎的な操作説明を丁寧に行いましょう。また、社内マニュアルや動画チュートリアルを用意するのも効果的です。
AI議事録ツールなどを併用して業務を自動化
ペーパーレス会議のメリットを最大限に引き出すには、単に紙をなくすだけでなく、業務そのものを効率化する工夫が必要です。例えば、AI議事録ツールを活用すれば、議事録の自動作成や共有がスムーズになり、会議後の作業負担を大幅に軽減できます。AI議事録ツールについて、より詳しく知りたいという方は、下記の記事も参考にご覧ください。
さらに、タスク管理ツールやクラウドストレージと連携することで、資料の更新・共有・検索といった業務を自動化し、よりスマートな会議運営が可能になります。ペーパーレス化と同時にデジタル活用による業務の効率化を意識することで、現場の満足度と生産性を高めることができます。
まとめ|ペーパーレス会議で会議をもっとスマートに
ペーパーレス会議は、単なる「紙の節約」ではありません。印刷・配布コストの削減や、情報共有のスピードアップ、セキュリティ強化、さらにはエコや企業価値の向上といった多くのメリットをもたらします。紙の資料に縛られず、どこにいても同じ情報にアクセスできる環境は、リモートワークやハイブリッドワークが一般的になった今、企業にとって欠かせない仕組みといえます。
一方で、社員のデジタルスキルの差やセキュリティ対策、インフラ整備といった課題もあります。しかし、これらは計画的なステップと適切なツール選定で十分に解決可能です。まずは小規模な会議から試験的に導入し、徐々に全社展開していくことで、負担を抑えながら移行を進められます。
また、タブレット端末の活用やAI議事録ツールの併用によって、単なる「紙の置き換え」にとどまらず、会議全体の生産性向上も実現できます。資料探しや議事録作成にかかる時間を短縮し、より本質的な議論に集中できる環境を整えていきましょう。
Otolioは議事録作成時間を最大90%以上削減できるAI議事録サービスです。議事録作成時間の削減だけではなく「会議の要点の音声をピンポイントで共有」することもでき、業界問わず大手企業、自治体など様々な累計6,000社以上で利用されています。
DXを始めたいけど、何から着手すればいいか分からない方は、ぜひAI議事録サービス「Otolio」をお試しください。
よくある質問とその回答
Q. ペーパーレス会議の導入にはどれくらいの費用がかかりますか?
導入費用は、利用するツールやデバイスの規模によって大きく変わります。例えば、既に社内にPCやタブレットが整備されている場合は、クラウドストレージや会議ツールの利用料程度に抑えられるケースもあります。一方、全社員分のデバイス購入やシステム構築を行う場合は、初期費用が数十万〜数百万円規模になることもあります。
また、ペーパーレス会議は一度導入すれば印刷・紙資料の配布コストが不要になるため、中長期的にはコスト削減効果が期待できます。印刷代・紙代・配布時間・資料の保管スペースなど、「隠れたコスト」を見える化して比較することで、投資対効果を明確にする企業も増えています。
Q. 社員がデジタルに不慣れでも運用できますか?
導入時には「使いやすいツールの選定」と「段階的な教育」が重要なポイントになります。まずは操作がシンプルなツールを選び、小規模な会議からスタートすることで、デジタルに不慣れな社員でもスムーズに慣れていくことができます。
また、社内マニュアルや簡単な操作ガイドを用意し、トレーニングを行うことで不安を軽減できます。慣れてくると、紙の資料よりも検索・共有がスムーズになるため、「思ったより便利だった」と感じる社員も多くいます。
Q. セキュリティ面が不安ですが大丈夫ですか?
セキュリティは、ペーパーレス会議導入における重要なポイントです。適切な対策を講じることで紙の会議よりも安全性を高めることができます。具体的には、アクセス権限の設定、資料の暗号化、ログ管理などが有効です。
さらに、万が一デバイスを紛失した場合も、リモートでアクセス制限やデータ削除ができるツールを選定すれば、情報漏洩リスクを最小限に抑えられます。紙の資料は一度紛失すると取り戻せませんが、デジタル化された情報は守る手段が多いことが大きなメリットです。



