【完全版】RPAとは?仕組み・メリット・導入事例をわかりやすく解説
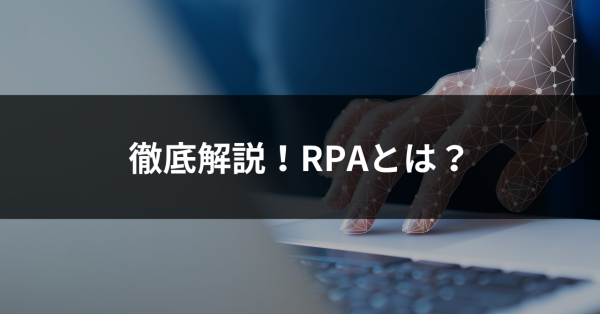
この記事でわかること
- RPAの定義
- RPAのメリットと注意点
- RPAツールの代表例と選び方のコツ
近年、ビジネスの現場では「業務効率化」「生産性向上」というキーワードを耳にする機会が急増しています。人材不足や残業規制、急速なデジタル化といった環境変化に対応するため、限られたリソースで最大限の成果を出す仕組みづくりが企業の命題となっています。
しかし、現場ではいまだに人の手で繰り返し行われる単純作業が多く残っており、担当者が本来取り組むべき企画・分析業務に時間を割けないという課題も少なくありません。「作業に追われて改善が進まない」「人手不足で対応が回らない」と悩む声は多く、経営層にとっても生産性のボトルネックとなっています。
そこで注目されているのが「RPA(Robotic Process Automation)」です。RPAは、パソコン上で行う定型作業をソフトウェアロボットに任せることで、業務をスピードアップし、ヒューマンエラーを防止する革新的な技術です。
本記事では、RPAの基本的な仕組みから、具体的な活用事例、導入のメリット・注意点、他の自動化技術との違いまでを網羅的に解説します。初めてRPAを知る方でも「RPAとは何か」「自社のどの業務に使えるのか」を理解し、次の一歩を踏み出すためのヒントが得られる内容になっています。
また、業務効率化にお悩みの方は、ぜひ議事録作成時間を削減できるOtolio(旧:スマート書記)をお試しください。Otolioは使えば使うほどAIの精度が上がる特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、議事録作成時間を最大90%削減することが可能です。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or サービス資料をみる
Otolio(旧:スマート書記)がわかる人気3点セット資料(サービス概要・導入事例・機能詳細)をみる
RPAの定義|Robotic Process Automationとは
RPA(Robotic Process Automation)は、ソフトウェアロボットが人間の代わりにPC上で行う定型的な作業を自動化する技術です。データ入力やコピー&ペースト、ファイルの移動、アプリケーション間の操作など、ルールに基づいて繰り返し行う業務を高速かつ正確に実行します。
人手に頼る必要があった「単純作業」をデジタルレイバー(仮想労働者)に置き換えることで、企業の業務効率化やコスト削減に貢献します。
RPAの正式名称と意味
RPAは Robotic Process Automation の略で、直訳すると「ロボットによるプロセスの自動化」です。ここでいうロボットは物理的なロボットではなく、ソフトウェアとして動作する「デジタルワーカー」を指します。
人間がマウスやキーボードで行っている作業手順を記録・再現することで、あたかも人が作業しているかのように業務を遂行します。
RPAの最大の特長は、既存システムを改修する必要がない点です。人間と同じようにUIを操作するため、ERPや基幹システム、クラウドサービスなど、複数のシステムをまたぐ業務もスムーズに自動化できます。
RPAが解決する課題
RPAは、現代のビジネス現場が抱える次のような課題を解決します。
- 単純作業の負担軽減:データ入力や伝票処理などの反復作業を自動化し、従業員が付加価値の高い業務に集中できるように
- ヒューマンエラーの防止:人為的なミスを減らし、正確なデータ処理を実現
- 業務スピードの向上:24時間365日稼働可能なため、業務処理時間を大幅に短縮
- 人手不足への対応:少ない人員でも業務を回せる体制を構築でき、採用や残業の負担を軽減
さらに、RPAはコンプライアンス強化にも役立ちます。操作ログが自動的に記録されるため、監査対応や業務プロセスの透明性向上にもつながります。これにより、単なる業務効率化ツールにとどまらず、ガバナンスや内部統制の強化にも寄与する点が企業から注目されています。
RPAが注目される背景と市場動向
近年、RPAは日本国内外で急速に普及しています。その背景には、社会全体の労働環境の変化と、企業が直面する課題があります。ここでは、RPAが特に注目を集める理由を「働き方改革と人手不足」「デジタル化の加速」という2つの観点から解説します。
働き方改革と人手不足
日本では少子高齢化が進み、労働人口は年々減少しています。このような状況下で、企業は限られた人員で生産性を維持・向上させる必要に迫られています。特に、単純作業や繰り返し作業に多くの時間を割いていると、社員の負担が増え、残業時間やストレスも増加します。
そこでRPAの導入が注目されています。RPAは、人間が行っていた定型業務をソフトウェアロボットが自動で処理するため、社員はより付加価値の高い業務に専念できます。
これにより、働き方改革の目標である「長時間労働の是正」や「生産性向上」が実現しやすくなります。さらに、企業にとっては採用難の中でも業務を回す仕組みを作れるため、慢性的な人手不足問題の解消にも貢献します。
加えて、RPAは人間が行うよりも正確に作業をこなすため、ミスによる再作業が減り、結果的に業務品質も向上します。働き手の満足度と企業の競争力を同時に高めるソリューションとして、RPAは社会的なニーズに合致しているのです。
デジタル化の加速
もう一つの大きな要因は、ビジネス環境全体で進むデジタル化です。コロナ禍をきっかけに、テレワークやオンライン取引が急速に普及し、企業は紙や対面中心の業務プロセスをデジタルに置き換える必要に迫られました。
このデジタル化の流れの中で、RPAは重要な役割を果たします。既存の業務システムを大幅に改修することなく、現在のプロセスに自動化を追加できる点が魅力です。システム間のデータ転記や帳票処理など、デジタル化で生じる膨大な事務作業を効率化し、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進を加速させます。
RPAとDXの関係についてより深く掘り下げて知りたい方は、ぜひ以下の記事も参考にご覧ください。
さらに、RPAは中小企業にとっても導入しやすい技術です。大規模なIT投資を必要とせず、スモールスタートで効果を確認しながら徐々に適用範囲を広げることができます。結果として、企業全体のデジタル化成熟度を底上げし、将来的にはAIや機械学習など、より高度な自動化技術との連携も視野に入れることが可能になります。
これらの要因により、RPAは単なるコスト削減ツールではなく、企業の成長戦略や働き方改革の中核を担う存在として位置づけられています。
RPAでできること|具体的な活用事例7選
RPAは単なる「業務自動化ツール」ではなく、現場の働き方そのものを変革するソリューションです。ここでは、導入効果が特に高い7つの具体例を詳しく解説します。導入を検討している方が「自社ならどこに使えるか」をイメージできるように、効果や導入時のポイントもあわせて紹介します。
データ入力・集計
RPA活用の王道ともいえるのがデータ入力や集計作業です。例えば、紙やPDFから顧客情報や売上データを抽出し、基幹システムやExcelへ転記する作業を完全自動化できます。複数システムに散らばったデータを定期的に収集し、日次・月次レポートを自動生成することも可能です。
特に金融、保険、物流といったデータ量の多い業界では、人的ミス防止や監査対応にも効果的です。導入時には、どのシステムのどの項目を抽出・転記するかを明確に定義し、処理フローを標準化してからRPAを設計すると失敗が少なくなります。
請求書処理
経理業務の中でも時間を奪う請求書処理は、RPAとOCRの組み合わせで大幅に効率化できます。受領した請求書をスキャンすると、取引先名・金額・日付などの情報を自動で読み取り、会計システムへ登録することが可能になります。承認フローとも連携すれば、支払依頼や稟議も自動化できます。
これにより、月末月初に集中していた請求処理業務が平準化され、残業削減や二重払い防止につながります。製造業や小売業など請求書が大量に発生する業界では、処理時間が半分以下になったケースもあります。導入時には、請求書フォーマットの統一や例外処理ルールをあらかじめ整備しておくと効果が最大化します。
定型メール送信
毎日送る定型的なメール業務もRPAの得意分野です。例えば、在庫報告や進捗共有、支払通知、顧客へのフォローアップメールなど、内容がパターン化されているものを自動生成・送信できます。Excelやデータベースから最新情報を差し込み、テンプレートを使って送信するため、ヒューマンエラーや送信漏れを防止できます。
営業部門では、顧客への定期フォローを自動化することで、担当者は提案活動や商談準備に時間を使えるようになり、売上向上につながったという事例もあります。導入時には、送信条件(誰に、いつ、どのタイミングで送るか)を明確に設定することが成功の鍵です。
Webスクレイピング
競合サイトの価格情報や在庫状況、官公庁サイトの公告、最新法令などを定期的に収集する作業もRPAで効率化できます。人がブラウザを操作して情報をコピーするのと同じ手順をロボットが再現し、最新情報を社内システムやスプレッドシートに取り込みます。
これにより、従来週1回だった調査が毎日実施できるようになり、より迅速な意思決定が可能となります。マーケティングや調査部門では、収集結果を自動でグラフ化したり、一定条件を満たしたときにアラートを出す仕組みを作るとさらに効果的です。
マスタデータ更新
複数システムにまたがるマスタデータ更新は、意外と工数がかかる作業です。例えば、従業員の異動情報を人事システムと給与計算システムの両方に反映する、在庫数を販売システムと購買システムに同時更新するなどの作業は、手作業ではミスが発生しやすい領域です。RPAを使えば、1つの更新依頼から関連するすべてのシステムへ自動反映でき、データ整合性を保てます。
顧客サポート対応
顧客からの問い合わせ対応もRPAの活用が進んでいます。よくある質問に対してはRPAがFAQデータベースを参照して自動返信、複雑な問い合わせはオペレーターに振り分けるといった仕組みが可能です。
これにより、オペレーターは高度な対応に集中でき、応答スピードと顧客満足度が向上します。導入時には、FAQの整備やチャットボットとの連携を合わせて行うと効果が高まります。
システム間データ連携
異なるシステム間でデータをやり取りする「橋渡し」業務もRPAが得意とする分野です。たとえば、受注システムのデータを在庫管理システムへ、さらに出荷システムへと連携するフローを自動化できます。
これにより、システム改修にかかるコストを抑えつつ、リアルタイムでデータ連携が可能になります。IT部門では開発リソースを節約でき、現場部門では情報更新のタイムラグが解消されます。導入時には、連携対象となるシステムのAPIや操作仕様を正確に把握しておくことが重要です。
RPAの導入メリット
RPAを導入する最大の魅力は、業務効率化と品質向上を同時に実現できる点にあります。ここでは、特に企業が実感しやすい3つのメリットについて解説します。
生産性向上
RPAは、定型的で繰り返し発生する作業を人の代わりに自動で処理します。これにより、単純作業に費やしていた時間を削減し、担当者は企画立案や顧客対応といった、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。結果として、チーム全体の生産性が飛躍的に向上し、組織全体のパフォーマンスが底上げされます。
さらに、RPAは24時間365日稼働可能なため、夜間や休日にも処理を進めることができます。これは特に大量のデータ処理や締め切りが集中する月末業務などにおいて大きな効果を発揮します。処理が滞らずスピードが上がることで、リードタイム短縮や顧客への迅速なレスポンスが可能になり、サービス品質の向上にもつながります。
コスト削減
人が行っていた定型作業をRPAに置き換えることで、作業時間を大幅に削減できます。残業時間の削減や外注費用の圧縮が可能となり、人件費全体の最適化に寄与します。また、追加人員を採用する必要がなくなるため、採用コストや教育コストの削減にもつながります。
さらに、RPAは安定した速度と品質で業務を行うため、ミスによる再作業ややり直しが減り、隠れたコストも低減します。結果的に、企業は限られたリソースを戦略的施策や新規事業開発に再投資できるようになり、長期的な収益力強化が期待できます。
ヒューマンエラー防止
RPAは、一度設定した手順を正確に繰り返すため、作業ミスを大幅に削減できます。人間が陥りやすい疲労や集中力低下による入力ミス、処理漏れ、二重計上などを防ぐことができ、業務品質が安定します。
また、誤ったデータが基幹システムに登録されるリスクが減るため、監査対応やコンプライアンス遵守の負担も軽減されます。正確で一貫した処理結果が蓄積されることで、経営層が利用するデータの信頼性が高まり、意思決定のスピードと精度が向上する点も重要なメリットです。
RPA導入の注意点・失敗しないポイント
RPAは強力な業務効率化ツールですが、導入に失敗すると「思ったより効果が出ない」「運用コストが逆に増えた」といった結果に陥ることもあります。実際に「担当者が異動した途端、誰もロボットを管理できなくなった」「システム更新のたびにロボットが止まり、業務が混乱した」といった事例も少なくありません。
ここでは、RPA導入を成功させるために押さえておきたい重要なポイントを解説します。
適用業務の見極め方
RPA導入の最初の関門は、「どの業務を自動化するか」を見極めることです。
すべての業務がRPAに向いているわけではありません。RPAに適した業務は、ルールが明確で、手順が固定化されており、繰り返し発生する作業です。例えば、毎月の請求書発行、受注データの転記、定期的なレポート作成などが典型的です。
一方で、判断や例外処理が多い業務、頻繁にルールが変わる業務はRPAに向きません。そうした業務を無理に自動化すると、頻繁なシナリオ修正が必要になり、メンテナンス負荷が高まります。
また、「業務をそのまま自動化する」のではなく、まず業務プロセスを整理・標準化してからRPAを導入するのが成功の近道です。現状の非効率なやり方をそのまま自動化すると、ムダが残ったまま高速化されるだけで、根本的な改善にはつながりません。
さらに、適用業務の優先順位をつけることも重要です。ROI(投資対効果)が高い業務、担当者の負担が大きい業務から着手すると、早期に効果を実感でき、社内でのRPA活用のモメンタムを作ることができます。
保守・運用体制の重要性
RPAは導入して終わりではなく、日々の運用と継続的な改善が必要です。RPAが稼働している環境は、業務システムの仕様変更や組織改編などによって常に変化しています。そのため、保守・運用体制を事前に整えることが不可欠です。
具体的には、ロボットの稼働状況を監視し、異常停止やエラーが発生した際に迅速に対応できる仕組みを用意しましょう。運用担当者やサポート窓口を明確にし、障害対応やシナリオ更新のフローをあらかじめ決めておくことが重要です。
また、業務部門とIT部門が連携し、定期的にRPAの稼働状況や改善ポイントをレビューする体制を作ることで、長期的な安定稼働と継続的な効果創出が可能になります。
さらに、将来的な拡張を見据えて、ナレッジを蓄積する仕組みを導入初期から整備しておくと安心です。ロボットのシナリオやエラー対応履歴、運用マニュアルを共有できるようにしておくことで、新規メンバーの教育や引き継ぎがスムーズになります。結果として、属人化を防ぎ、RPAの全社展開をスピーディーに進めることができます。
RPAツールの代表例と選び方のコツ
RPAを導入する際、どのツールを選ぶかは成功の鍵を握ります。ここでは、国産ツールと海外ツールの代表例を紹介し、それぞれの特徴や選び方のポイントを解説します。
国産RPAツール
BizRobo!

引用:BizRobo!
BizRobo!は、日本市場で長年支持されてきたRPAテクノロジーズ社の製品です。中堅〜大企業向けに幅広い導入実績があり、高い拡張性と安定性が評価されています。金融、製造、物流など複雑な業務プロセスにも対応可能で、オンプレミスとクラウドの両方に対応しているため、企業のセキュリティポリシーに合わせた柔軟な運用が可能です。
ライセンスは年間契約型が中心で、導入前に試せるトライアル環境も提供されています。また、専任のカスタマーサクセスチームによる導入支援や教育プログラムも整備されています。
ツールの特徴
- 高い拡張性で複雑業務にも対応
- オンプレ・クラウド両対応で柔軟
- 日本市場で豊富な導入実績
WinActor

引用:WinActor
NTTデータが開発した国産RPAツールで、国内シェアNo.1を誇ります。日本語でのサポートやドキュメントが充実しており、IT部門だけでなく現場担当者でも直感的に操作できます。GUIベースのシナリオ作成画面が分かりやすく、プログラミング知識がない人でもロボット開発が可能です。
価格はロボット単位のライセンス制で、一定期間利用できる評価版やトライアルも用意されています。全国で開催されるユーザー会やセミナーが活発で、成功事例を共有しながら活用ノウハウを高めることができます。
ツールの特徴
- 国内シェアNo.1で安心感
- 日本語サポート・ドキュメントが充実
- ノーコードでシナリオ作成が容易
ロボパットDX

引用:ロボパットDX
中小企業や現場部門でのスモールスタートに向いているツールです。インストール不要のクラウド型で、低コストかつ短期間で導入できます。月額サブスクリプション制で初期投資を抑えられるうえ、無料トライアルも提供されているため、効果検証が容易です。現場担当者が自らロボット作成できる設計になっており、社内の業務改善文化を醸成しやすい点も特長です。
ツールの特徴
- クラウド型でインストール不要
- 導入コストが低くスモールスタート可能
- シンプルUIで現場主導の活用に最適
海外RPAツール
UiPath

引用:UiPath
UiPathは世界的に最も広く利用されているRPAプラットフォームの一つです。豊富な機能とコミュニティサポートがあり、スケーラビリティやAPI連携の柔軟性に優れています。
無料で試せるCommunity版が提供されており、個人や小規模チームでも気軽に始められます。エンタープライズ版はロボット数や機能に応じたサブスクリプション料金で提供され、大規模展開にも対応可能です。
プロセスマイニングやタスクキャプチャ機能など、業務分析から自動化まで一貫してサポートする機能も充実しています。
ツールの特徴
- 豊富なアクティビティと拡張機能
- 大規模展開に強いスケーラビリティ
- Community版があり学習コストを抑えやすい
Automation Anywhere

Automation Anywhereはクラウドネイティブな設計で導入・運用の負荷が軽く、Bot Insightによるリアルタイム分析で業務改善サイクルを素早く回せます。料金はクラウド利用数に応じたサブスクリプション制で、無料デモ環境も提供されています。
ツールの特徴
- クラウドネイティブで運用が容易
- AI/分析機能との統合が得意
- 最新版A360でUXとスピードが改善
Blue Prism

引用:Blue Prism
Blue Prismは堅牢性とガバナンス機能に定評があり、金融や公共機関など高いセキュリティ基準が求められる業界で多く採用されています。再利用可能なコンポーネント設計で大規模展開にも強く、セキュリティ認証や監査ログ機能も充実しています。価格は年間ライセンス制が主流で、PoC(概念実証)用の短期契約も可能です。
ツールの特徴
- セキュリティ重視の設計
- ガバナンス機能が豊富
- 複雑業務にも対応可能な柔軟性
比較時のチェックポイント
RPAツールを選定する際は、以下の観点をチェックすると失敗を防げます。
操作性と学習コスト
現場担当者が直感的に操作できるかどうかは、導入後の定着率に大きく影響します。UIがシンプルで分かりやすいか、シナリオ作成や修正が簡単にできるかを確認しましょう。教育にかかる時間が短いほど、早期に効果を発揮できます。
スケーラビリティと保守性
最初は小規模で導入しても、成功すれば全社的に展開するケースが多いです。そのため、ライセンス形態や管理機能が拡張に対応しているか、保守やアップデートがしやすいかを事前にチェックしておくと安心です。
サポート体制とコミュニティ
トラブル時に迅速に相談できるサポート窓口の有無は重要です。日本語対応があるか、ナレッジベースやフォーラムが整備されているかも導入後の安心感につながります。コミュニティが活発なツールは情報共有やノウハウ獲得もしやすいです。
コストとライセンス形態
初期導入費用だけでなく、ライセンス更新料やロボット数の増加に伴うコストも考慮しましょう。従量課金制かサブスクリプション制かによって長期的な運用コストが異なるため、予算計画に合わせた選定が重要です。
セキュリティとガバナンス
業務データを扱う以上、ログ管理やアクセス権限設定などセキュリティ機能が備わっているかを確認しましょう。特に個人情報や機密情報を扱う業務では、ガバナンス機能が充実したツールを選ぶと安心です。
RPAと他の自動化技術との違い
RPAは便利な自動化ツールですが、似たような技術と混同されやすいのも事実です。ここでは、特によく比較されるマクロ、AI、BPMとの違いを整理し、RPAの立ち位置を明確にします。
マクロとの違い
マクロは、Excelなどの特定のアプリケーション内で繰り返し作業を自動化する仕組みです。一方RPAは、複数のアプリケーションをまたいで操作できる点が大きな違いです。
たとえば、マクロはExcel内でのデータ加工には強いものの、そこからブラウザを開きWebシステムにログインして結果を登録するといった一連の業務は苦手です。
また、マクロはプログラミングの知識が必要になることが多いですが、RPAはGUIベースで操作フローを記録・作成できるため、非エンジニアでも扱いやすい点が特徴です。つまり、RPAは現場の業務担当者が自ら作れる業務ロボットと表現できます。
AIとの違い
AI(人工知能)は、人間の学習や推論、認識といった知的行動を模倣する技術です。画像認識、自然言語処理、予測分析などを得意とします。一方RPAは「判断」ではなく「作業の再現」が得意で、あらかじめ決められたルールに従って正確に業務を実行します。
ただし、近年はAIとRPAを組み合わせる「IPA(Intelligent Process Automation)」の活用も増えています。例えば、AIでメール内容を分類し、RPAで自動返信や社内システム登録を行う、といった連携が可能です。この組み合わせにより、より複雑で非定型な業務も自動化できるようになります。
BPMとの違い
BPM(Business Process Management)は、業務プロセス全体を設計・最適化するためのマネジメント手法です。業務を改善するのがBPM、業務を代行するのがRPAと考えると分かりやすいでしょう。
BPMは長期的な業務改革に強みがある一方、導入には時間とコストがかかることもあります。RPAはまず既存の業務をそのまま再現する形で導入できるため、短期間で成果を出しやすいのが利点です。多くの企業では、まずRPAで現状業務を効率化し、その後BPMで根本的なプロセス改善を行うというステップを踏んでいます。
また、RPAとDXの違いや関係性に関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、より掘り下げて知りたい方はぜひ参考にご覧ください。
まとめ|まずは小さく試して拡大するのが成功の鍵
RPA導入を成功させるためには、「いきなり大規模に導入しない」ことが重要です。まずは、現場で負担が大きい定型業務や、担当者が日々繰り返し行っている作業を1つ選び、小さく始めましょう。
パイロット導入で効果を検証し、どの程度の工数削減やミス削減が実現できるかを数値で把握することが大切です。成功事例を社内で共有することで、他部署の協力や経営層の理解も得やすくなります。
さらに、RPAは導入して終わりではなく、継続的な改善が欠かせません。業務フローの変更やシステムアップデートがあれば、ロボットの動作も見直しが必要です。保守・運用体制を整え、定期的にメンテナンスを行うことで、安定稼働を維持できます。
小さく始めて、効果を確認しながら少しずつ自動化の範囲を広げる「スモールスタート&スケール」の考え方が、失敗しないRPA導入の王道です。段階的に拡大することで、社内の人材育成や運用ルール作りも同時に進められ、企業全体の生産性向上につながります。
Otolioは議事録作成時間を最大90%以上削減できるAI議事録サービスです。議事録作成時間の削減だけではなく「会議の要点の音声をピンポイントで共有」することもでき、業界問わず大手企業、自治体など様々な累計6,000社以上で利用されています。
DXを始めたいけど、何から着手すればいいか分からない方は、ぜひAI議事録サービス「Otolio」をお試しください。
よくある質問とその回答
Q. RPAとAIの違いは何ですか?
RPAは、決められたルールに従って作業を自動化する技術です。一方AIは、データから学習して判断や予測を行う技術です。例えば、RPAは請求書から日付や金額を正確に入力する作業を得意としますが、フォーマットが異なる請求書の解釈や仕分けはAIと組み合わせることでより柔軟に対応できます。近年は、OCR+AI+RPAの連携によって、複雑な業務を自動化する「知的自動化」が広がっています。
Q. 中小企業でもRPAは導入できますか?
はい、導入可能です。むしろ人手不足や限られたリソースの中で業務効率化を求める中小企業にとって、RPAは大きな助けになります。最近は初期費用がかからないクラウド型RPAも増えており、IT部門がなくても始めやすい環境が整っています。まずは単純な業務から導入し、効果を確認して少しずつ範囲を広げるのがおすすめです。



