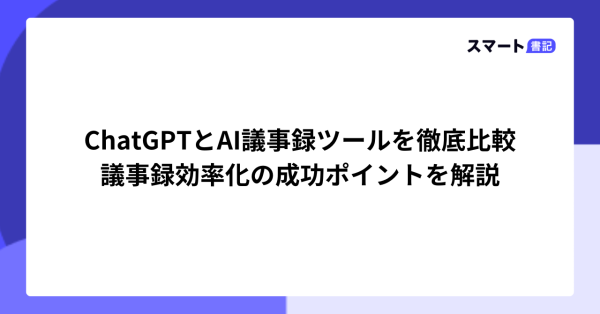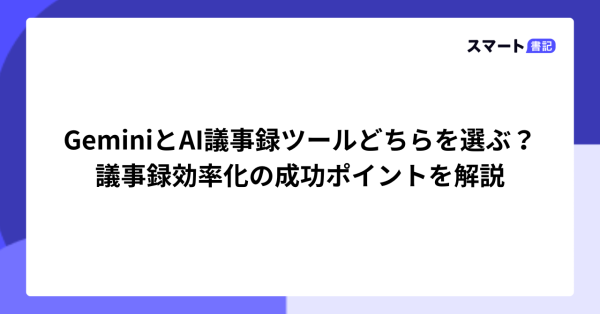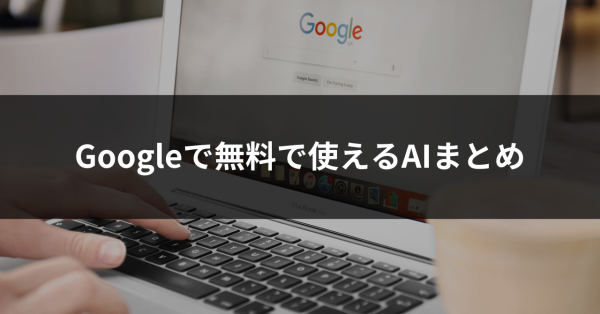【徹底解説】生成AIの7つのメリットと活用方法!職種・部門別のメリットも紹介

この記事でわかること
- そもそも生成AIとは?
- 生成AIの7つのメリットと活用例
- 生成AIのメリットを最大限に引き出すための3つのコツ
「生成AIで業務効率化できる」と耳にする一方で、具体的な生成AIのメリットや自社業務への落とし込み方が分からず悩む経営者・管理職の方も多いでしょう。導入を検討していても、「ROI(投資対効果)は出るのか」「何から始めるべきか」で止まってしまいがちです。
本記事では、生成AIの主なメリット7つを活用例・職種別の実践方法とともに解説します。さらに注意点やデメリット、効果を最大化するコツまで整理するので、導入判断に必要な視点が一通りそろいます。
人手不足やコスト圧力が高まる今、生成AIを適切に使えるかどうかは競争力に直結します。ぜひ最後まで読み進め、貴社の業務改善にお役立てください。
また、生成AIで業務を改善したい方の中でも、特に負担になりやすい議事録作成を効率化したい場合は、ぜひ最大90%の議事録作成時間を削減できるOtolio(旧:スマート書記)をお試しください。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or サービス資料をみる
Otolio(旧:スマート書記)がわかる人気3点セット資料(サービス概要・導入事例・機能詳細)をみる
そもそも生成AI(ジェネレーティブAI)とは?
生成AIとはAI(人工知能)技術の一種で、テキストや画像、音声、動画といったコンテンツを自動で作成する技術の総称を指しています。本記事で紹介する「生成AIのメリット」を理解するために、まずは生成AIが何を得意とする技術なのかを押さえておきましょう。
従来のAIは、データをもとに分類や予測を行う用途で発展してきました。一方で生成AIは、文章作成・要約・アイデア出しなどの「アウトプット生成」を得意とし、業務の下書き作成や情報整理を効率化できることから、ビジネスシーンでの活用が広がっています。
生成AIの種類や活用シーンなど、基礎からもう少し詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。
【一覧表】まず押さえるべき生成AIのメリット7選
ここからは、ビジネスで押さえておきたい生成AIのメリットを7つに整理して解説します。まずは一覧表で全体像をつかみ、自社で効果が出そうな項目をチェックしてみてください。
| メリット | 得られる効果 | 活用例(業務) |
|---|---|---|
| 圧倒的な生産性向上と業務効率化 | 定型業務の自動化・高速化 | メール作成、データ集計、情報収集 |
| 新規アイデアの創出と企画力強化 | ブレインストーミングとアイデア発想支援 | 商品企画、マーケティング、イベント企画 |
| 高品質なコンテンツの迅速な作成 | 様々なビジネス文書・資料の効率作成 | ブログ、レポート、提案書、SNS投稿 |
| 複雑な情報の要約と意思決定の迅速化 | 長文情報の瞬時要約・分析 | 報告書要約、市場調査、競合分析 |
| 属人化の解消とナレッジ共有の促進 | 暗黙知の言語化・マニュアル化 | 議事録、商談記録、ノウハウ共有 |
| コスト削減への貢献 | 外注費・人件費の最適化 | 翻訳、ライティング、カスタマーサポート |
| パーソナライズされた顧客体験の提供 | 個別最適化されたサービス提供 | メルマガ、商品レコメンド、営業提案 |
当てはまるものが多いほど、生成AI導入の投資対効果(ROI)を得やすい傾向があります。では、1つずつ具体例とともに見ていきましょう。
1. 圧倒的な生産性向上と業務効率化
生成AIの大きなメリットは、メール作成・情報収集・データ整理などの定型業務を高速化し、工数を大幅に削減できる点です。たとえば、市場調査や競合情報の収集は、要点の抽出と整理まで含めて短時間で進められるため、これまで1時間かかっていた作業が10〜15分程度に短縮されるケースもあります。
定型業務が軽くなることで、社員は本来注力すべき業務に時間を回せます。営業なら顧客との関係構築や提案準備、マーケティングなら戦略立案、管理職なら意思決定やメンバー育成など、付加価値の高い領域に集中しやすくなります。
ポイント:AIの出力はそのまま使わず、最終確認(事実関係・数値・社内ルール)を挟むと品質が安定します。
2. 新規アイデアの創出と企画力強化
生成AIは、企画の「たたき台」を短時間で出せるため、アイデア出しの量と速度を一気に引き上げられるのがメリットです。たとえば、新商品のキャッチコピーなら、ターゲット層・特徴・訴求ポイントを伝えるだけで複数案を提示できます。イベント企画でも、目的・予算・参加者層を入力すれば切り口の異なる案が揃います。
重要なのは、生成AIの提案を「答え」ではなく「素材」として扱うことです。複数案から良い要素を選び、組み合わせたり磨いたりすることで、検討の質を保ったまま企画スピードを上げられます。
ポイント:生成AIに役割(例:マーケティング責任者として)と制約(予算/トーン/NG表現)を渡すと、案の精度が上がります。
3. 高品質なコンテンツの迅速な作成
生成AIは、ブログ記事・レポート・提案書・SNS投稿などの下書きを短時間で作成でき、制作スピードと品質の底上げに貢献します。文章作成が得意でない人でも、構成案や初稿をベースに編集できるため、制作のハードルが下がります。
また、プロンプト次第で文体や読者層に合わせた調整がしやすい点も強みです。「20代向けカジュアル」「管理職向けフォーマル」「技術者向け専門的」など、同じ内容でも伝え方を切り替えられます。
ポイント:生成結果は必ず「事実確認+自社の体験/事例」を追記し、独自性を足すとSEO評価が上がりやすいです。
4. 複雑な情報の要約と意思決定の迅速化
生成AIは、長文資料を要約して重要ポイントを抽出できるため、情報収集〜判断までの時間を短縮できるのがメリットです。市場調査レポートや業界記事、社内議事録などを読み込ませ、要点・論点・数字を整理したサマリーを作ることで、意思決定に必要な材料を素早く揃えられます。
さらに、複数の情報源を横断して比較の観点を出したり、論点やリスクを洗い出したりする用途でも効果的です。スピードが求められる局面で、判断材料の準備を前倒しできるのは大きな強みです。
ポイント:要約は「誰向け(経営/現場)」「欲しい観点(結論/根拠/リスク)」を指定すると、使える形になりやすいです。
5. 属人化の解消とナレッジ共有の促進
生成AIは、ベテランの暗黙知を言語化し、マニュアルやナレッジとして整理することで、属人化の解消に役立ちます。
たとえば、営業のヒアリング手順や切り返し、技術者のトラブルシュート手順などを、対話しながら再現可能な形に落とし込めます。これにより、育成・引き継ぎの質が安定し、特定の個人に依存しない体制を作りやすくなります。
ポイント:入力データに機密が含まれる場合は、匿名化・社内ルールの順守・利用環境の確認を徹底してください。
6. コスト削減への貢献
生成AIは、外注していた業務の一部を内製化したり、作業時間を短縮したりすることで、コスト最適化に貢献します。ただし「人を置き換える」ではなく、「人の作業を減らして高付加価値業務に寄せる」発想が前提です。
翻訳なら一次訳を生成AIで作り、人が最終チェックすることで外注費を抑えられます。カスタマーサポートでも、回答案の下書きや問い合わせ分類を補助して、対応効率を上げられます。
ポイント:削減額だけでなく、浮いた時間を何に再配分するか(売上/品質/採用など)まで決めるとROIが説明しやすくなります。
7. パーソナライズされた顧客体験の提供
生成AIは、顧客の属性や行動に合わせたメッセージを生成できるため、提案の精度と体験価値を高められるのがメリットです。ECでは購入/閲覧履歴をもとにレコメンド文やオファー文を作成し、開封率・クリック率・CV向上が期待できます。
BtoBでも、業界・企業規模・課題に合わせた提案資料や営業メールの下書きを短時間で作れるため、アプローチ数と提案品質の両立がしやすくなります。
ポイント:パーソナライズは「やり過ぎ」が逆効果になることもあるので、顧客が不快に感じない表現・運用基準を先に決めておくと安心です。
【職種・部門別】業務別にわかる生成AIの活用例
ここからは、生成AIを自分の業務にどう活用できるかをイメージできるよう、職種・部門別の活用例を紹介します。自分に近い職種だけ拾い読みしてもOKなので、気になるところからご覧ください。
営業職:商談準備の高速化と質の向上
営業職にとって生成AIは、商談準備を短縮しつつ提案の質を安定させるパートナーになります。商談前に、ターゲット企業のニュース・IR情報・業界動向を収集・要約させれば、企業研究にかかる時間を圧縮できます。
- 企業研究:最新ニュース/IR要点/業界トレンドの整理
- 想定QA:顧客の業界・課題をもとに、質問候補と回答案を作成
- 提案の下書き:提案ストーリーや訴求ポイントのたたき台を用意
ポイント:企業名や機密情報を入力する場合は、社内ルールに沿って伏せ字・要約で扱うと安全です。
マーケティング職:コンテンツ制作と分析の効率化
マーケティング職では、生成AIが制作(アウトプット)と分析(インサイト)の両面を支援します。構成・下書き・コピー案の作成をスピードアップしつつ、情報整理や比較の手間も減らせます。
- コンテンツ制作:ブログ構成案/SNS下書き/広告コピーの案出し
- 企画:ターゲットと訴求を入力し、切り口を複数パターン生成
- 分析:競合調査の要約/アンケート自由記述の分類/レポート要点整理
ポイント:AIの文章は一見もっともらしく見えるので、数字・固有名詞・根拠のファクトチェックだけは必ず挟みましょう。
開発・エンジニア職:コーディング支援とデバッグ
開発・エンジニア領域では、生成AIが実装の下書き・原因調査・学習を支援し、開発スピードを上げます。繰り返し作業の多いコード生成や、既存コードの改善提案にも活用できます。
- 実装支援:関数のひな形/テストコードのたたき台/コメント生成
- デバッグ:エラーメッセージから原因候補と修正案を提示
- 学習:新言語・新FWの概念をコード例付きで理解しやすくする
ポイント:社外秘コードをそのまま貼るのは避け、再現用に一般化したサンプルへ置き換えるのが安全です。
人事・総務職:採用業務と社内規定の効率化
人事・総務職では、生成AIが定型文書の作成と個別対応の効率化に向きます。求人票やメール文、社内FAQの下書きを作るだけでも負荷を下げられます。
- 採用:求人票の下書き/面接質問案/評価コメントのたたき台
- 応募者対応:日程調整・合否連絡・質問返信のメール文案
- 社内問い合わせ:規定・制度のFAQ整備(チャットボット含む)
ポイント:個人情報(応募者情報など)は入力せず、テンプレ化・匿名化して扱うのが基本です。
カスタマーサポート職:問い合わせ対応とFAQ整備の効率化
カスタマーサポート職にとって生成AIは、一次対応のスピードと品質を安定させる強力な支援ツールになります。よくある質問への回答案を作ったり、問い合わせ内容を分類して担当へ振り分けたりする作業を効率化できるため、繁忙期の負荷軽減にもつながります。
- 回答文の下書き:過去の回答例や規約文をもとに、丁寧な文面のたたき台を作成
- 問い合わせ分類:内容を「請求」「不具合」「解約」などに自動で整理し、対応優先度を付ける
- FAQ・ナレッジ整備:問い合わせログから頻出テーマを抽出し、記事案や見出し案を作成
ポイント:社外への返信は、誤情報や言い回しのズレがクレームにつながるため、最終確認(規約・価格・対応可否)を必ず挟みましょう。個人情報を入力する場合は匿名化が前提です。
法務・経理職:文書チェックと定型業務の効率化
法務・経理職では、生成AIを「判断の代替」ではなく、確認・整理・下書きの補助として使うことで効果が出やすくなります。専門性が求められる領域ほど、まずはたたき台作成や要点整理から始めるのが安全です。
- 要点整理:契約書・規程・請求関連資料などの長文を要約し、論点を抜き出す
- チェックリスト化:確認観点(支払条件、責任範囲、解約条項など)を一覧にして漏れを減らす
- 定型文書の下書き:社内向け説明文、依頼メール、社内手続き案内などの文面を作成
ポイント:法務判断・会計判断そのものは生成AIに任せず、最終判断は必ず担当者/専門家が行う運用にしてください。社外秘情報はそのまま入力せず、条文の一部を抽象化・匿名化して扱うのが基本です。
生成AIのメリットを最大限に引き出すための3つのコツ
生成AIを単に導入するだけでなく、その効果を最大化するための実践的なノウハウをお伝えします。これらのコツを押さえることで、投資対効果を高め、組織全体でのAI活用を成功に導くことができるでしょう。
より詳しく生成AIの使い方について知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しているので、合わせてご覧ください。
1. 「目的」を明確にする:AIはあくまで道具
生成AI活用で最も重要なのは、「何のためにAIを使うのか」という目的を具体的に定義することです。単に「効率化したい」という漠然とした目標ではなく、「月20時間の議事録作成時間を5時間に短縮し、浮いた時間で新規開拓に15時間投入する」といった定量的で具体的な目標設定が必要です。
また、どのような成果物を得たいのかも明確にしておきましょう。「顧客向け提案書の品質を向上させる」のか、「社内報告書の作成スピードを上げる」のかによって、活用方法や評価指標も変わってきます。目的が曖昧なまま導入を進めると、期待した効果が得られないだけでなく、組織内での活用が定着しないリスクもあります。
成功している企業では、部門ごとに具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的に効果測定を行うことで、AI活用の改善と最適化を継続的に実施しています。
2. 「指示の出し方」を工夫する(プロンプトエンジニアリング)
生成AIの回答品質は、与える指示(プロンプト)の質に大きく左右されるため、効果的な指示の出し方を身につけることが重要です。これは「プロンプトエンジニアリング」と呼ばれる技術で、ビジネスでAIを活用する上で必須のスキルと言えるでしょう。
良い指示のポイントとしては、まずAIに具体的な役割を与えることが挙げられます。「マーケティング担当者として」「新入社員に説明するつもりで」といった前置きをすることで、回答の視点や詳細レベルが適切に調整されます。
また、背景情報や制約条件を詳しく提供することも重要です。業界、会社規模、ターゲット層、予算などの情報を含めることで、より実用的で具体的な回答を得ることができます。さらに、出力形式を明確に指定する(「箇条書きで3つのポイント」「800文字程度の文章で」など)ことで、そのまま活用できる形での回答を得やすくなります。
3. 用途に応じて複数のAIツールを使い分ける
生成AIツールにはそれぞれ得意分野があるため、目的に応じて最適なツールを選択し、使い分けることが効果最大化の鍵となります。万能なツールは存在しないという前提で、戦略的にツール選択を行うことが重要です。
文章生成においては、ChatGPTやGoogle Geminiが高い性能を発揮します。特に長文のレポート作成や複雑な分析が必要な場合は、これらの大規模言語モデルが適しています。一方、画像生成にはMidjourneyやDALL-Eが優秀で、プレゼンテーション資料やマーケティング素材の作成に活用できます。
また、無料版から始めて効果を確認してから有料版に移行するというスモールスタート方式もおすすめです。多くのツールで無料版が提供されているため、まずは小規模な実験から始め、ROIを確認してから本格導入を検討することで、投資リスクを最小化できるでしょう。
知っておくべき生成AIのデメリットと注意点
生成AIの多くのメリットをお伝えしましたが、導入を成功させるためにはデメリットや注意点も正しく理解しておくことが重要です。適切なリスク管理を行うことで、生成AIの恩恵を安全に享受することができます。
情報の正確性(ハルシネーション)
情報の正確性(ハルシネーション) の問題は、最も注意すべき点です。生成AIは時として、もっともらしく聞こえるが実際には間違っている情報を生成することがあります。これは「ハルシネーション」と呼ばれる現象で、特に統計データや固有名詞、最新情報において発生しやすい傾向があります。そのため、生成AIの出力をそのまま使用するのではなく、必ずファクトチェックと裏付け確認を行うことが必要です。
セキュリティリスク
セキュリティリスクも重要な検討事項です。機密情報や個人情報を生成AIに入力することで、意図しない情報漏洩が発生する可能性があります。特に外部のクラウド型AIサービスを利用する際は、情報の取り扱いポリシーを十分確認し、社内での利用ガイドラインを策定することが重要です。
著作権・倫理的な問題
著作権・倫理的な問題についても注意が必要です。生成AIが作成したコンテンツが、既存の著作物と類似している場合、著作権侵害のリスクがあります。また、学習データに含まれるバイアスにより、差別的や偏見的な内容を含む回答を生成する可能性もあります。企業として利用する際は、出力内容の倫理的妥当性を確認するプロセスを確立することが重要です。
コストの問題
コストの問題も見過ごせません。高機能なAPIを大量利用したり、企業向けの有料ツールを導入したりする場合、月額数万円から数十万円のコストが発生することがあります。導入前には、期待される効果とコストを比較し、ROI(投資対効果)を慎重に検討することが必要です。
まとめ|生成AIのメリットを理解して業務を効率化しよう
本記事では、生成AIがビジネスにもたらす7つの主なメリットについて、具体的な活用例とともに詳しく解説してきました。圧倒的な生産性向上からパーソナライズされた顧客体験の提供まで、生成AIは現代のビジネスのあらゆる場面で大きな価値を創出する強力なツールであることがお分かりいただけたと思います。
同時に、情報の正確性やセキュリティリスクといったデメリットを正しく理解し、適切な対策を講じることが重要であることもお伝えしました。生成AIは魔法のような万能ツールではなく、人間の判断力と専門知識と組み合わせることで、初めてその真価を発揮するのです。
「目的の明確化」「効果的な指示の出し方」「用途に応じたツール選択」という3つのコツを実践することで、生成AIの投資対効果を最大化できるでしょう。特に、各職種・部門の特性に合わせた具体的な活用方法を見つけることが、組織全体でのAI活用定着の鍵となります。
人手不足やコスト圧力が高まる現代において、生成AIの適切な活用は競争優位性を築く重要な戦略となります。まずはスモールスタートでも構いませんので、自社の業務にAIを取り入れることから始めてみてはいかがでしょうか。
生成AIを活用して、上手く自動要約や要点抽出をするには、ベースとなる文字起こしの精度が高いことが必要不可欠です。
- 固有名詞や専門用語の変換が上手くいかない
- 「えー」や「あの」などの意味をなさない言葉も文字起こしされてしまう
- 文字起こしを修正してから生成AIを活用しているが修正に時間がかかっている
このような文字起こし精度にお悩みを抱えている方は、ぜひ一度、使えば使うほどAIの精度が上がる「Otolio」をお試しください。
またOtolioのAIアシスト機能を活用して自動要約・要点抽出も自動化できます。自動化することが可能です。AIアシストを活用すれば以下を自動化することができます。
- 要約文章の生成
- 要点の自動抽出
- 決定事項やToDo、質疑応答の抽出
Otolioは特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、使えば使うほどAIの精度が向上します。累計利用社数6,000社以上の実績、大手企業から自治体まで様々な組織で利用されており、セキュリティ面でも安心してご利用いただけます。
よくある質問と回答
Q. 結局、ChatGPTとGoogle Geminiはどちらを使えば良いのでしょうか?
一概にどちらが優れているとは言えず、目的によって使い分けるのが最適です。 一般的に、ChatGPTは創造的で自然な文章生成に強いとされています。一方、Google Geminiは最新情報へのアクセスやGoogleの各種サービス(検索、ドキュメントなど)との連携に優れています。まずは両方の無料版を試してみて、ご自身の業務で使いやすいと感じる方、あるいは求める回答が得意な方を選択するのが良いでしょう。
Q. 社員がAIを使いこなせるか不安です。どのような教育が必要ですか?
全員をAI専門家にする必要はありません。まずは、基本的な使い方と、社内で定めた利用ガイドライン(特にセキュリティ関連)を周知することから始めましょう。その後、各部門で具体的な活用事例を共有する勉強会を開いたり、効果的な指示(プロンプト)のパターンを共有したりするのが効果的です。成功事例を社内で共有することで、「自分も使ってみよう」という意識が広がり、組織全体の活用レベルが向上していきます。
Q. とりあえず導入してみたいのですが、何から始めるのがおすすめですか?
まずは、日常業務の中で時間がかかっている定型業務を一つ見つけることから始めるのが最もおすすめです。例えば、「毎日のメール返信」「週次の定例会議の議事録作成」「SNSの投稿文作成」など、成果が分かりやすく、かつリスクの少ない業務から試してみましょう。無料のツールでこれらの作業を効率化できることを実感できれば、他の業務への応用や本格的なツール導入の検討もスムーズに進みます。