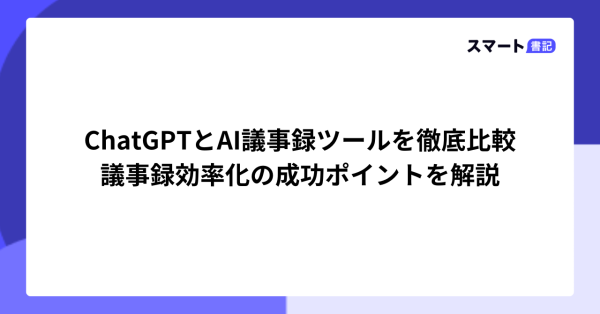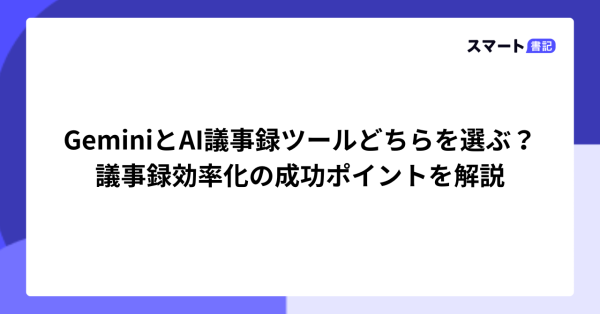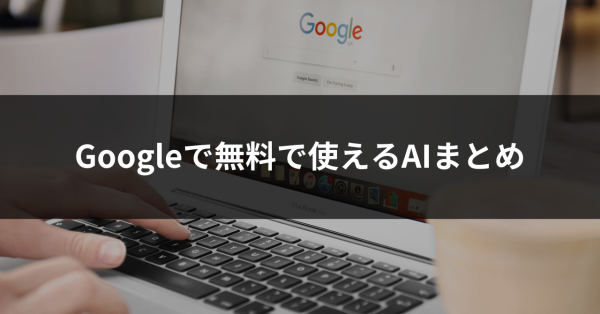生成AIの使い方完全ガイド!初心者でもすぐに業務効率化できる7つのコツを紹介
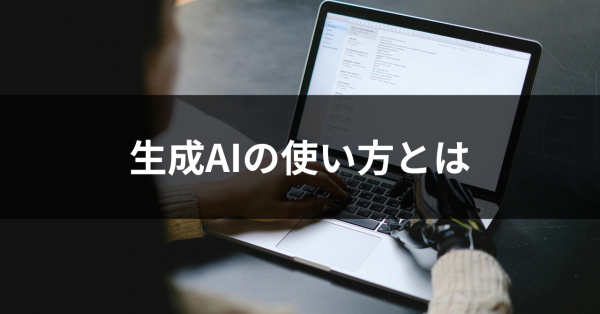
この記事でわかること
- 生成AIの基本的な使い方
- 業務で使える生成AIの活用方法
- 効果的に生成AIを使うコツ
「生成AIを使って業務効率化したいけれど、どこから始めればいいかわからない」「ChatGPTなどのツールは知っているけれど、具体的な使い方がわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
実際に、多くの企業や個人が生成AIの導入を検討している一方で、「思うような結果が得られない」「業務でどう活かせば良いのかわからない」という声も少なくありません。
そこで本記事では、生成AI初心者の方でも今すぐ実践できる使い方から、業務で活用できる具体的な方法、そして効果的に使うためのコツまで、網羅的に解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。
また、生成AIを活用して議事録作成の時間を削減したい方は、ぜひ機密情報を学習させることなく、使えば使うほどAIの精度が上がるOtolio(旧:スマート書記)をお試しください。Otolioを活用すれば面倒なプロンプト入力をせずに、議事録作成時間を削減できます。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or サービス資料をみる
Otolio(旧:スマート書記)がわかる人気3点セット資料(サービス概要・導入事例・機能詳細)をみる
生成AIとは?初心者でも分かる基礎知識
生成AI(Generative AI)とは、テキストや画像、音声、動画など、さまざまなコンテンツを自動で生成できる人工知能技術のことです。代表例として、文章を生成できるChatGPTなどが知られています。
生成AIが得意なのは、文章の作成・編集・要約といったテキスト処理に加えて、アイデア出しや情報整理、データの整理・分析の補助などです。さらに、翻訳、多言語対応、プログラムコードの生成、画像・イラストの生成、プレゼン資料の構成案作成などにも活用できます。うまく使えば、多くの業務で時間短縮と品質向上を同時に狙えます。
一方で、生成AIには注意点もあります。たとえば、回答は学習データに基づくため、最新情報の取り扱いには限界があり、内容が常に正しいとは限りません。また、個人情報や機密情報の扱い、法的責任を伴う判断などは人間側での確認が不可欠です。
このように、生成AIは非常に強力なツールですが万能ではありません。特徴と限界を理解したうえで適切に使うことで、業務効率化の大きな武器になります。次の章では、初心者でも迷わず始められる「生成AIの使い方」を基本ステップに沿って解説していきます。
より詳しく生成AIの種類や活用シーンまで把握しておきたい方は、以下の記事でわかりやすく解説しています。基礎をもう一段深めたい場合は、あわせてご覧ください。
生成AIの使い方!基本4ステップ
生成AIを効果的に活用するための基本的な流れを4つのステップでご紹介します。初心者の方でも、この順番で試すとスムーズに活用を始められます。
STEP1|無料ツールを活用して生成AIの使い方を学ぶ
まずは無料で利用できる生成AIツールから始めることをおすすめします。現在、多くの企業が高品質な生成AIサービスを無料で提供しており、初心者の方でも気軽に試すことができます。
代表的なツールとしては、OpenAI社が開発したChatGPTが最も有名で、利用者が多く情報も豊富なため、初心者の方に特におすすめです。また、Anthropic社が開発したClaudeは高性能で自然な対話が可能で、Google社のGeminiは検索機能との連携が優れています。さらに、Microsoft社のCopilotにはWeb検索(Bing)と連携して最新情報を参照できるタイプがあります(利用形態により異なります)。
これらのツールはどれも基本機能を無料で利用できるため、まずは気になるものを一つ選んで試してみましょう(機能や回数には制限があります)。使い慣れてきたら、用途に応じて複数のツールを使い分けることも可能です。
各ツールの使い方を詳しく知りたい方は以下の記事で詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にご覧ください。
STEP2|シンプルな質問から始める
最初は複雑な指示を出すのではなく、日常的な業務で使えそうなシンプルな質問から始めてみましょう。たとえば、「お客様への謝罪メールの文面を考えてください」といった身近な業務から始めることで、生成AIの便利さを実感できます。
ほかにも、
- 会議の議題を整理してもらう
- 資料の要点を3つにまとめてもらう
- 新商品のキャッチコピーを複数提案してもらう
など、普段時間をかけている作業を任せてみることから始めるとよいでしょう。このような小さなタスクから試すことで、生成AIがどの程度の品質で、どのような回答を返してくれるのかを体感でき、徐々に生成AIの使い方のコツがつかめるようになります。
STEP3|役割設定で生成AIの回答精度を上げる
生成AIの回答精度を大幅に向上させるテクニックが「役割設定」です。AIに具体的な役割や立場を与えることで、より専門的で的確な回答を得ることができます。
たとえば、「あなたは経験豊富なマーケティング担当者として回答してください」と指定すれば、マーケティングの専門知識や視点を活かした提案を受けることができます。人事部の責任者の立場で新入社員向けの説明を求めたり、ITコンサルタントとしてシステム導入の提案をしてもらうなど、その分野の専門性を活かした回答を期待できます。
役割を明確にすることで、単なる一般的な回答ではなく、その分野の専門知識や経験を反映した、より実用的で価値の高い回答を得ることができるようになります。
STEP4|フィードバックで改善する
生成AIの大きな特徴は、対話を通じて回答を改善できることです。最初の回答が期待通りでなくても、具体的なフィードバックを与えることで、理想的な結果に近づけることができます。
たとえば、「もう少し具体的にしてください」「ビジネス向けの丁寧な表現に変更してください」「箇条書きで整理し直してください」「文字数を500文字以内にまとめてください」といったように、修正してほしいポイントをはっきり伝えるのがコツです。
このプロセスを繰り返すことで、最終的に満足度の高い結果を得られるだけでなく、自然と効果的な生成AIの使い方(指示の出し方)も身についていきます。
業務で役立つ生成AIの使い方8選
ここからは、実際の業務で今すぐ活用できる生成AIの具体的な使い方を、業務別にご紹介します。まずは自分の業務に近いものから試してみてください。
1. 議事録の作成
会議の議事録作成は、多くのビジネスパーソンが時間を取られる業務の一つです。生成AIを活用することで、この作業を大幅に効率化できます。
従来は、会議中にメモを取りながら話を聞き、会議後に整理して清書するという二重の作業が必要でした。しかし、生成AIを活用すれば、会議の録音データの文字起こしテキストから重要なポイントを自動で抽出・整理することが可能になります。さらに、決定事項とアクションアイテムを明確に分類することもできます。
どのような議事録を作成してほしいか、自分の議事録の形式に合わせて具体的に指示をしていくことが、重要です。もし指示を入力する手間自体もなくしたい場合は、生成AIを活用している「Otolio」のようなAI議事録サービスの活用を検討しましょう。これらのツールはワンクリックで要約文章や要点の整理をすることができます。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or サービス資料をみる
2. メール文章の作成
ビジネスメールの作成は、適切な敬語や文体を考える必要があり、意外と時間がかかる業務です。新規取引先への挨拶メールや会議の日程調整メール、プロジェクト進捗報告メール、お客様への謝罪メールなど、相手や状況に応じて適切なトーンで書き分ける必要があります。
生成AIに状況を説明すれば、相手との関係性や目的に応じて、適切な文体とトーンでメール文面を作成してくれます。また、複数のバリエーションを提案してもらうことで、最も適切な表現を選択することも可能です。
3. プレゼン資料の構成案
プレゼン資料の構成を考える際も、生成AIが強力なサポートツールとなります。テーマと目的、対象者を伝えるだけで、論理的で説得力のある全体構成を提案してもらえます。
さらに、各スライドの内容案を詳細に作成してもらったり、聞き手の関心を引く導入部分や、印象に残る締めくくりの提案を受けることも可能です。また、聞き手のレベルや関心に応じた内容調整のアドバイスを受けることで、より効果的なプレゼンテーションを作成できます。
4. アイデア出し・ブレスト
新しいアイデアが必要な場面で、生成AIは優秀なブレインストーミングパートナーになります。新商品・サービスの企画、マーケティング施策、業務改善、イベント企画など、幅広い分野でアイデアを提案してくれます。
特に価値があるのは、一人では思いつかない視点や切り口が得られる点です。異なる業界の事例を参考にした提案や、ターゲット層を変えた場合のアプローチなど、創造性を刺激する多角的な視点を得ることができます。
5. データ分析のサポート
複雑なデータの分析や解釈においても、生成AIは有効です。売上データの傾向分析では、数値の変化から読み取れる市場動向や季節要因を解説してもらえます。また、アンケート結果の要約・考察では、回答者の傾向や隠れたニーズを発見する手助けをしてくれます。
競合分析レポートの作成やKPI改善のための提案など、データに基づく戦略立案にも活用できます。ただし、データの正確性については必ず人間が最終確認を行うことが重要です。
6. 情報収集・要約
特定のテーマについて情報を整理・要約する際にも活用できます。業界トレンドの整理では、複数の情報源から重要なポイントを抽出し、体系的にまとめてもらえます。競合他社の情報まとめや法規制の変更点整理、技術動向の調査など、時間のかかる情報収集作業を効率化できます。
ただし、情報の鮮度や正確性については、必ず最新の情報源で確認することが大切です。
7. 翻訳
多言語対応が必要な業務でも、生成AIは強力なサポートツールです。ビジネス文書の翻訳では、単純な直訳ではなく、文脈や文化的背景を考慮した自然な翻訳を提供してくれます。
ウェブサイトコンテンツの多言語化や海外取引先とのメール対応、プレゼン資料の翻訳など、様々な場面で活用できます。特に、専門用語の適切な翻訳や、相手国の商習慣に配慮した表現の提案など、単なる翻訳ツール以上の価値を得られるケースもあります。
8. 画像生成
テキスト生成だけでなく、画像生成AIも業務で活用できます。プレゼン資料用のイラスト作成では、説明したい概念を視覚的に表現するイメージを生成できます。SNS投稿用の画像生成や商品イメージの作成、ウェブサイト用の素材作成など、デザイン業務の効率化にも貢献します。
ただし、著作権や商用利用の規約については、各サービスの利用条件を必ず確認することが重要です。
効果的に生成AIを使うコツ7選
生成AIの性能を最大限に引き出すための実践的なコツをご紹介します。生成AIの精度は、指示の出し方で大きく変わるため、ここで紹介するポイントを押さえておきましょう。
1. 具体的な指示を出す
曖昧な指示では、期待通りの結果を得ることは困難です。「良い提案書を作って」という漠然とした依頼ではなく、「新規顧客向けのITシステム導入提案書を作成してください。対象は従業員50名の製造業で、予算は500万円、導入期間は3ヶ月を想定しています」といった具体的で詳細な指示を心がけましょう。
対象者の属性、予算や期間などの制約条件、求める成果物の形式など、できるだけ多くの情報を提供することで、より精度の高い回答を得ることができます。
例(短い指示例):
「謝罪メールを作って。相手は取引先、原因は納期遅れ、200字、丁寧、再発防止も入れて」
2. 例を出す(テンプレートを提供する)
理想的な形式や内容の例を示すことで、より精度の高い結果を得ることができます。過去の成功事例を参考として提示したり、希望する文体やトーンの例文を示すことで、生成AIは求められている品質や方向性を理解しやすくなります。
また、フォーマットやレイアウトの見本を提供することで、統一感のある成果物を作成してもらうことも可能です。特に、企業の文書作成では一貫性が重要なため、このテクニックは非常に有効です。
例(テンプレ提示):
「以下の形式で作って:①結論 ②背景 ③提案 ④ネクストアクション(担当・期限)」
3. 役割を与える
前述の通り、AIに具体的な役割や専門性を与えることで、回答の質が大幅に向上します。「10年の経験を持つ営業マネージャーとして」「顧客満足度向上の専門家として」「効率化コンサルタントの視点で」といった具体的な役割設定により、その分野の専門知識や経験を反映した回答を期待できます。
また、複数の役割を組み合わせることで、より多角的な視点からの提案を受けることも可能です。
例(役割指定):
「あなたはBtoBのSaaSマーケ担当。CV改善の観点でLPの改善案を出して」
4. 条件を明確にする / 制約を先に書く
出力に関する条件を明確に指定することで、より実用的な結果を得られます。文字数や文章量の指定、対象読者のレベル設定、使用する場面や目的の明確化、避けるべき表現や内容の指示など、詳細な条件を設定することが重要です。
特に、ビジネス文書では読み手のレベルや使用場面に応じて適切な表現レベルを選択する必要があるため、これらの条件設定は不可欠です。
例(条件指定):
「500字以内/初心者向け/専門用語は注釈/箇条書き多め」
5. 段階的に改善する
一度で完璧な結果を求めるのではなく、段階的に改善していくアプローチが効果的です。まず初回の回答を確認し、不足している点を具体的に指摘します。その後、追加要求や修正点を明確に伝え、満足できる結果になるまで繰り返し改善を重ねていきます。
このプロセスを通じて、生成AIとの効果的なコミュニケーション方法も身につけることができ、今後の活用がより効率的になります。
例(改善指示):
「導入が長いので半分にして。結論を先に。具体例を1つ追加して」
6. 進め方を明確にする
複雑なタスクの場合は、作業の進め方や手順を明確に指示することが重要です。「以下の手順で進めてください:まず全体の構成案を提示、各章の詳細内容を順番に作成、最後に全体の整合性を確認」といった具体的なプロセスを示すことで、体系的で一貫性のある成果物を得ることができます。
また、各段階での確認ポイントを明示することで、品質管理も効果的に行うことができます。
例(手順指定):
「まずは見出し案だけ出して→OKなら各見出しの要点→最後に本文」
7. フィードバックを繰り返す
最後に生成AIを使う上で重要なコツは「フィードバックを繰り返す」ことです。というのも生成AIは一度の指示で私たちが求めている完璧なコンテンツを作成するとは限りません。最初に生成されたコンテンツが意図と少しズレていたとしても、適切にかつ何度かフィードバックを与えることで、改善されていきます。
たとえば、議事録作成で生成AIを使っていたときに、AIが出力した文章に対して、「この部分をもっと詳しく書いてほしい」「決定事項を明確に箇条書きで整理してほしい」「表記をですます調にしてほしい」といったフィードバックを生成AIに与えることでより質の高い議事録を作成することが可能になります。
また、生成AIを使うときは具体的な指示を出したり、例を示したりすることが重要とお伝えしましたが、このフィードバックをするときも今までご紹介したコツを活用することができます。
例(フィードバック):
「決定事項を先頭にまとめて。ToDoは担当者と期限を追加。全体を箇条書き中心に」
生成AIを使うときに注意したい3つのポイント
生成AIを上手に使うためには、便利さだけでなく注意点もセットで理解しておくことが大切です。ここでは、生成AIの使い方で特に押さえておきたい注意点を3つご紹介します。
1. AIが嘘をついている可能性を考慮する(ハルシネーションリスク)
生成AIは文章や音声、画像などを瞬時に生み出せる便利な技術ですが、一方で「ハルシネーション」と呼ばれる現象が起こることがあります。これは、もっともらしい内容を出力しているのに、実際には誤りや根拠のない情報が混ざっている状態を指します。
たとえば、存在しない人物や出来事を事実のように語ったり、架空のデータや論文名を作り出したりするケースがあります。生成AIは学習データをもとに文章を組み立てるため、学習データに古い情報や誤情報が含まれていたり、未学習の領域を推測で補ったりすると、結果的に誤りが生まれることがあります。
特に、医療・法律・金融など高い信頼性が必要な分野では大きな問題につながりかねません。生成AIを使うときは、出力をそのまま鵜呑みにせず、必ず人間が事実確認(一次情報・公式情報での確認)を行うことが必要不可欠です。
2. 著作権に気をつける
生成AIが作成するコンテンツを扱うときは、著作権にも注意が必要です。生成AIは大量のデータをもとに学習しているため、場合によっては著作権のある文章や画像に似た表現が出力されてしまう可能性があります。その結果、意図せず第三者の著作物と類似した表現を使ってしまうリスクがあります。
たとえば、生成AIで作成した広告コピーが既存のコピーと似てしまい、「自分の作品と類似している」と指摘されるケースもあり得ます。著作権侵害に該当すると、法的措置や企業信用への影響につながる可能性もあるため注意が必要です。
生成AIを使うときは、重要な成果物ほど既存の著作物と類似していないかの確認(検索・社内チェック・ツール利用など)を行い、必要に応じて「参考にしたい雰囲気」は伝えても「既存作品の模倣」にならないように運用しましょう。
3. セキュリティに問題ないか確認する
ここまでご紹介した注意点は生成AI側で起きる問題でしたが、生成AIを使うときはそもそも使っていいかどうかを確認するようにしましょう。特に企業に所属した人が活用する場合、企業側のセキュリティポリシーがどうなっているかを確認することが重要です。
生成AIは大量のデータを処理し学習するため、私たちが指示した内容や例として示した内容が学習に活用されるケースがあります。そうすると意図せずに企業の機密情報や個人情報が不適切に扱われたり情報漏洩してしまうというリスクが存在します。
企業のセキュリティ方針がどうなっているか、しっかりと確認し、使いたい生成AIのセキュリティ方針とマッチしているかを確認するようにしましょう。
まとめ|使うときのコツを実践して生成AIを使いこなそう
生成AIは、適切な使い方を理解すれば、業務効率化の強力なツールとなります。本記事でご紹介した基本4ステップと8つの活用方法、そして7つのコツを実践することで、今すぐにでも生成AIを業務に取り入れることができます。
特に重要なのは、まずは無料ツールで気軽に始めること、具体的で明確な指示を心がけること、そして段階的に改善していく姿勢を持つことです。これらのポイントを意識することで、生成AIの真価を実感できるはずです。
生成AIは日々進化を続けており、今後さらに多くの場面で活用できるようになることが予想されます。早めに使い方に慣れておくことで、将来的な競争優位性を築くことができるでしょう。まずは今日から、簡単な業務で生成AIを試してみることをおすすめします。生成AIを上手く活用するためにも、注意すべきポイントを理解しながら本記事でご紹介した使い方で活用してみましょう。
生成AIを活用して、上手く自動要約や要点抽出をするには、ベースとなる文字起こしの精度が高いことが必要不可欠です。
- 固有名詞や専門用語の変換が上手くいかない
- 「えー」や「あの」などの意味をなさない言葉も文字起こしされてしまう
- 文字起こしを修正してから生成AIを活用しているが修正に時間がかかっている
このような文字起こし精度にお悩みを抱えている方は、ぜひ一度、使えば使うほどAIの精度が上がる「Otolio」をお試しください。
またOtolioのAIアシスト機能を活用して自動要約・要点抽出も自動化できます。自動化することが可能です。AIアシストを活用すれば以下を自動化することができます。
- 要約文章の生成
- 要点の自動抽出
- 決定事項やToDo、質疑応答の抽出
Otolioは特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、使えば使うほどAIの精度が向上します。累計利用社数6,000社以上の実績、大手企業から自治体まで様々な組織で利用されており、セキュリティ面でも安心してご利用いただけます。
よくある質問と回答
Q. 無料で使える生成AIツールは?
現在、多くの企業が高品質な生成AIサービスを無料で提供しています。ChatGPTは無料でも高性能モデルを回数制限付きで利用でき、情報も豊富です(提供モデルや制限は変更される場合があります)。ClaudeはAnthropic社が提供する高性能なAIで、自然な対話が得意です。GeminiはGoogle社が開発したAIで、検索機能との連携が優れています。CopilotはMicrosoft社が提供し、Bingと統合されているため最新情報へのアクセスが容易です。
どのツールも基本的な文章生成や質問応答は無料で利用できるため、まずは複数試してみて、使いやすいものを選ぶことをおすすめします。
Q. 社内で使うときに注意すべきことは?
社内で生成AIを活用する際は、セキュリティ面、品質管理面、運用面の3つの観点から注意が必要です。セキュリティ面では、機密情報や個人情報を入力しないことが最も重要です。また、社内ガイドラインを策定して全社に周知し、利用ログの管理・監視体制を整備することも大切です。
品質管理面では、生成された内容の事実確認を必ず行い、重要な文書については人間による最終チェックを実施することが不可欠です。さらに、著作権や法的リスクについても十分に確認する必要があります。
運用面では、利用目的と範囲を明確化し、従業員への教育・研修を実施することが重要です。また、定期的に利用状況を見直し、ガイドラインの更新や改善を行うことで、安全で効果的な活用を継続できます。
Q. 求めているものが出力されないときは?
期待通りの結果が得られない場合は、まず指示の見直しから始めましょう。より具体的で詳細な指示に変更し、例や参考資料を提供することで、生成AIが求められている内容を理解しやすくなります。また、出力形式や条件を明確に指定することも効果的です。
次に、段階的なアプローチを試してみてください。大きなタスクを小さな単位に分割し、一つずつ確認しながら進めることで、より精度の高い結果を得ることができます。フィードバックを重ねて改善していくプロセスも重要です。
それでも改善されない場合は、質問の仕方を変えてみたり、異なる役割設定を試したり、他の生成AIツールも活用してみることをおすすめします。多くの場合、指示の仕方を工夫することで、満足できる結果を得ることができます。