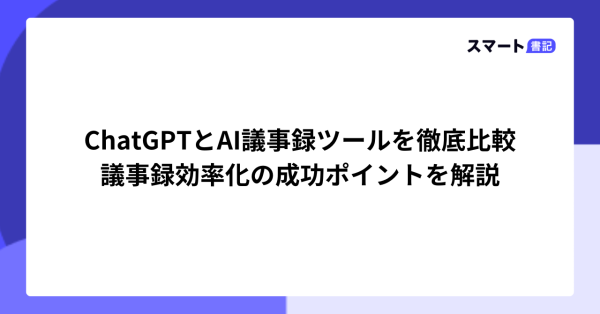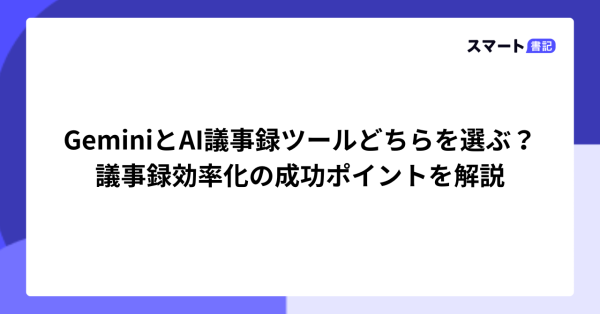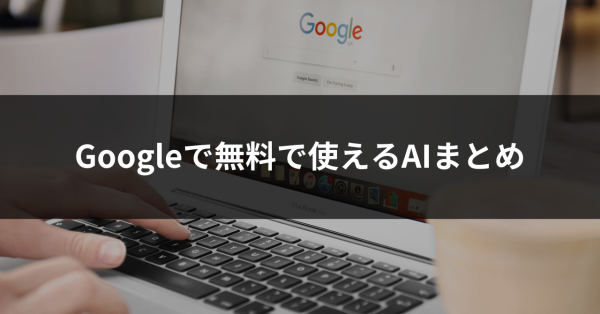【徹底解説】生成AIの7つの種類を解説!ビジネスでの活用方法から選び方まで紹介

「生成AIが話題になっているけれど、実際にどんな種類があるのかわからない」「自社にとって最適なAIはどれなのか判断がつかない」そんなお悩みをお持ちの経営者や管理職の方も多いのではないでしょうか。
ChatGPTの登場以降、生成AIは単なる技術革新を超えて、企業の競争力を左右する重要な経営戦略の一つとなりました。しかし、生成AIと一口に言っても、テキストを生成するものから画像、動画、音声、さらには3Dモデルまで、その種類は多岐にわたります。
本記事では、ビジネスで活用できる生成AIの7つの主要な種類について、それぞれの特徴、代表的なサービス、そして具体的な業務活用法を詳しく解説します。
また生成AIの中でもテキスト生成AIで、議事録作成を効率化したい方は、ぜひ一度AI議事録ツール「Otolio(旧:スマート書記)」をお試しください。Otolioは会議後ワンクリックで要約文章や要点を自動で整理することができ、最大90%議事録の作成時間を削減することが可能です。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or サービス資料をみる
Otolio(旧:スマート書記)がわかる人気3点セット資料(サービス概要・導入事例・機能詳細)をみる
そもそも生成AI(ジェネレーティブAI)とは?
生成AIとはAI(人工知能)技術の一種で、テキストや画像、音声、動画といったコンテンツを自動で作成する技術の総称を指しています。OpenAIが対話型AI「ChatGPT」を発表したことから、特に注目を集めています。
今までのAIといえば、決められたルールに従って動くのが特徴でしたが、生成AIはコンテンツを作成できること、またその出力内容の精度が向上したことによって、ビジネスシーンで活用されることも多くなりました。
より詳しく生成AIについて知りたい方は以下の記事で生成AIの種類やメリットなど、より詳しくご紹介していますので、気になる方はぜひ以下の記事もご覧ください。
【一覧表】一目でわかる!生成AIの7つの種類とできること
まず、本記事で紹介する生成AIの全体像を一覧表で確認しましょう。この表を参考に、あなたの関心や課題に最も近い分野から読み進めていただくことをおすすめします。
| AI種類 | 生成できるもの | 代表的なサービス | 主なビジネス用途 |
|---|---|---|---|
| テキスト生成AI | 文章、メール、企画書、翻訳文 | ChatGPT、Gemini、Claude | 資料作成、メール対応、議事録作成 |
| 画像生成AI | イラスト、写真風画像、図表 | Midjourney、DALL-E 3、Stable Diffusion | プレゼン資料、Webデザイン、広告素材 |
| 動画生成AI | 実写風動画、アニメーション | Sora、Gen-2、Pika | 製品紹介、SNS投稿、研修動画 |
| 音声生成AI | 音声合成、文字起こし、音声翻訳 | ElevenLabs、Whisper、VALL-E X | ナレーション、電話応答、議事録作成 |
| 音楽生成AI | BGM、効果音、楽曲 | Suno AI、Udio、Amper Music | 動画BGM、店舗BGM、企業PR音楽 |
| コード生成AI | プログラムコード、SQL文 | GitHub Copilot、CodeWhisperer、Claude | システム開発、業務自動化、データ分析 |
| 3Dモデル生成AI | 3Dオブジェクト、空間デザイン | Luma AI、Meshy、Spline | 製品設計、空間シミュレーション、VR/AR |
この表からもわかるように、現在の生成AIは単一の機能に特化したものから、複数の機能を統合したプラットフォーム型のものまで、さまざまな形態で提供されています。重要なのは、自社の課題や目標に最も適した種類を選択することです。
なお、これらの生成AIは単体での利用だけでなく、組み合わせて使うことでより大きな効果を発揮することも可能です。たとえば、テキスト生成AIで企画書の文章を作成し、画像生成AIで説明図を作成し、音声生成AIでプレゼンテーション用のナレーションを制作するといった連携活用も実現できます。
【生成データ別】生成AIの代表的な7つの種類とサービス例
ここからは、各種類の生成AIについて、その特徴と具体的な活用方法を詳しく見ていきましょう。
テキスト生成AI
テキスト生成AIは、テキストによる指示(プロンプト)から文章を生成できるツールであり、最も身近で導入しやすい生成AIの一つです。大量のテキストデータを学習することで、人間が書いたような自然な文章を生成することができます。主な使い方として、文章の作成、要約、翻訳、質問応答、アイデア出しなどがあります。
ビジネスでの活用例を見ると、まずメール文面の作成が挙げられます。営業メール、お客様対応メール、社内連絡メールなど、目的や相手に応じた適切な文面を短時間で生成できます。また、ブログ記事の執筆では、キーワードやトピックを指定するだけで、構成から詳細な内容まで一気通貫で作成することも可能です。
代表的なサービスとして、OpenAIの「ChatGPT」、Googleの「Gemini」、Anthropicの「Claude」などが挙げられます。各ツールの比較は以下の通りです。
| ChatGPT | Gemini | Claude | |
|---|---|---|---|
| 主な特徴 | 画像生成、音声、高度な推論など、AIでできることが全て詰まったツール。 | 最新検索との親和性が高く、動画や大量の文書を一度に読み込む力に長ける。 | 人間のような自然な文体と、論理的な思考能力の高さが最大の売り。 |
| メリット | ・共感力の高い返答。・画像生成(DALL-E 3)やデータ分析がチャット内で完結。・複雑な数学やパズル、コードの論理問題を解く力が極めて高い。 | ・Gmail、ドキュメント、ドライブ等との連携が非常にスムーズ。・1時間を超える動画や数千ページの資料を一気に要約できる。 | ・日本語が非常に自然。翻訳やブログ執筆など、文章作成において修正が少ない。・複雑な条件を指定しても、意図を正確に汲み取って回答する。 |
| デメリット | ・表現が硬かったり、独特のAIっぽさが文章に残りやすい。 | ・検索結果に引っ張られすぎて、ハルシネーションの発生が稀にある。・長文の指示を与えると、一部の条件を忘れてしまうことがある。 | ・チャット内で直接画像を作成する機能を持っていない。・最新モデルの利用回数が厳しく、すぐに制限がかかりやすい。 |
画像生成AI
画像生成AIは、テキストによる指示(プロンプト)から高品質な画像を自動生成するツールです。Text-to-Image技術と呼ばれるこの仕組みにより、「青空の下で桜が咲いているオフィスビル」といった具体的な指示を文章で入力するだけで、それに対応した画像を作成できます。
ビジネス活用の場面では、まずプレゼンテーション資料の挿絵作成が大きな効果を発揮します。今までであれば、適切な画像を見つけるために画像検索に時間をかけたり、有料のストックフォトサービスを利用したりする必要がありましたが、画像生成AIを使えば、資料の内容に完全に合致したオリジナル画像を即座に作成できます。
広告バナーのデザイン案作成においても、複数のパターンを短時間で生成し、A/Bテストによる効果検証を効率的に行うことが可能です。デザイナーが一から制作する場合と比較して、大幅な時間短縮とコスト削減を実現できます。
代表的なサービスには「Midjourney」「DALL-E 3」「Stable Diffusion」があります。各ツールの比較は以下の通りです。
| Midjourney | DALL-E 3 | Stable Diffusion | |
|---|---|---|---|
| 主な特徴 | 芸術的・高品質な画像生成。光や質感の表現に優れる。 | ChatGPTとの連携による高い理解力。日本語で指示が可能。 | オープンソースで自由度が極めて高い。拡張機能が豊富。 |
| メリット | ・圧倒的な画質とデザイン性・写真のようなリアルさも得意 | ・初心者でも意図通りの絵が出やすい・対話で微調整ができる | ・無料で利用可能(PC環境による)・制限なく自由にカスタマイズ可能 |
| デメリット | ・月額制の有料プランが基本・Discordの操作に慣れが必要 | ・画像の細かな構成の微調整がしにくい場合がある | ・高スペックなPCが必要・導入や設定のハードルが高い |
動画生成AI
動画生成AIは、テキストや静止画像から動画コンテンツを自動生成するツールです。今までの動画制作に必要だった撮影、編集、エフェクト処理などの専門的なスキルや機材がなくても、高品質な動画を作成することができます。
ビジネスでの活用例として、製品紹介動画の作成が挙げられます。新商品の特徴や使用方法を説明するデモンストレーション動画を、実際の撮影なしで作成することができます。特に、まだ製品化前のコンセプト段階でも、イメージ動画を作成してプレゼンテーションや営業活動に活用することが可能です。
現在注目を集めているサービスには、OpenAIの「Sora」、Runwayの「Gen-2」、「Pika」などがあります。各ツールの比較は以下の通りです。
| Sora | Gen-2 | Pika | |
|---|---|---|---|
| 主な特徴 | 圧倒的なリアリズムと物理法則の再現。最大60秒の生成が可能。 | 映像制作の多機能性。プロ向けの編集ツール(Gen-3、Gen-4.5)が強力。 | アニメ調やコミカルな表現が得意。物理的な破壊表現なども可能。 |
| メリット | ・物理法則に忠実で違和感が少ない・長時間(1分)の連続生成 | ・プロ向けのカメラワーク指定が可能・特定の部分だけ書き換える機能が優秀 | ・リップシンク(口パク)機能が強力・エフェクト(爆発や溶解)が豊富 |
| デメリット | ・一般公開が限定的(または順次拡大中)・生成に時間がかかる場合がある | ・高度な機能は有料プランが前提・プロンプトにコツが必要 | ・写実的なリアルさではSora等に一歩譲る |
音声生成AI
音声生成AIは、プロンプトを入力することにより、人間が話すような自然な音声を生成できるツールです。テキストから自然な音声を合成するText-to-Speech機能、音声認識による文字起こし機能、さらには特定の人の声を再現する音声クローン機能などの技術により、音声に関わる様々な業務を自動化・効率化することができます。
ビジネス活用の最も身近な例は、プレゼンテーションや動画コンテンツのナレーション作成です。今までであれば、ナレーターの手配、録音スタジオの予約、収録作業といった工程が必要でしたが、音声生成AIを使えば、原稿を用意するだけで即座にプロ品質のナレーションを生成できます。
代表的なサービスには「ElevenLabs」「VALL-E X」「Whisper」があります。各ツールの比較は以下の通りです。
| ElevenLabs | VALL-E X | Whisper | |
|---|---|---|---|
| 主な特徴 | 感情表現が非常に豊か。高精度な声のコピーができる。 | 3秒の声でコピー可能。声質を維持した多言語翻訳。 | 音声を文字にする(文字起こし)。翻訳も可能。 |
| メリット | ・人間の肉声に近い表現力・日本語を含む多言語対応が強力 | ・他言語への「声質を維持した」翻訳生成が可能・学習なしで声のコピーが可能 | ・背景に雑音があっても精度が高い・長い音声も一括で処理できる |
| デメリット | ・高度な利用は有料プランが必要・クレジット制で費用がかかる | ・環境構築に専門知識が必要・生成される音声にノイズが入る場合がある | ・読み上げ機能はない・ハルシネーションが稀に発生する |
音楽生成AI
音楽生成AIは、テキストによる指示やメロディの指定から、完全なオリジナル楽曲を自動生成するツールです。楽器演奏や作曲の専門知識がなくても、商用利用可能な高品質な音楽コンテンツを制作することができます。
ビジネスでの活用例として、まず動画コンテンツのBGM作成が挙げられます。企業のプロモーション動画、製品紹介動画、ウェビナーなど、様々な動画コンテンツにおいて、内容やブランドイメージに完全にマッチしたオリジナルBGMを制作できます。既存の楽曲を使用する場合の著作権処理や使用料の問題も解決できます。
企業PR動画のオリジナル楽曲制作では、会社の理念やメッセージを音楽に込めることで、より感情的な訴求力を持った映像コンテンツを作成することができます。楽曲制作会社に依頼する場合と比較して、大幅なコスト削減と制作期間の短縮を実現できます。
主要なサービスには「Suno AI」「Udio」「Amper Music」があります。各ツールの比較は以下の通りです。
| Suno AI | Udio | Amper Music | |
|---|---|---|---|
| 主な特徴 | 歌声入り楽曲の生成に極めて強く、歌詞・メロディ・伴奏を数秒で同時生成する。 | 圧倒的な音質と音楽性。プロレベルのボーカル表現と緻密な編曲が特徴。 | 実用的なBGM作成に特化。楽器構成やテンポを細かく調整できる。 |
| メリット | ・日本語の歌詞も自然に歌い上げる・生成速度が非常に速い | ・音質が極めてクリアでプロ級・ボーカルの感情表現が非常に豊か | ・著作権リスクが低く商用利用が容易・動画の長さに合わせた微調整が可能 |
| デメリット | ・音質が少しこもる場合がある・細かいメロディの修正がしにくい | ・生成プロセスが少し複雑(32秒ずつの継ぎ足し)・人気のため生成待ちが発生しやすい | ・歌入りのポップス制作には不向き・現在はShutterstockに統合され、単独利用が制限 |
コード生成AI
コード生成AIは、自然言語による指示からプログラミングコードを自動生成するツールです。プログラミング初心者でも複雑なシステム開発が可能になるほか、経験豊富なエンジニアにとっても開発効率の大幅な向上を実現できます。
ソフトウェア開発における活用では、要件定義書や仕様書からの自動コード生成が可能です。これにより、エンジニアは設計に集中し、実装作業の大部分を自動化することができます。また、バグの修正やリファクタリング、テストコードの作成なども効率化でき、開発サイクル全体のスピードアップを実現できます。
代表的なサービスには「GitHub Copilot」「Amazon CodeWhisperer」「Claude」があります。各ツールの比較は以下の通りです。
| GitHub Copilot | Amazon CodeWhisperer | Claude | |
|---|---|---|---|
| 主な特徴 | IDE(VS Code等)でのリアルタイムコード補完。業界標準のツール。 | AWS環境との親和性。セキュリティスキャン機能を標準搭載。 | 高度な論理的推論。Artifacts機能による即時プレビュー。 |
| メリット | ・世界で最も利用されている業界標準・複数モデル(GPT-4o, Claude等)の選択が可能 | ・個人利用は無料・無制限・AWS開発の効率を最大化できる | ・人間らしい自然な日本語と高い推論能力・「Artifacts」で生成したコードを即プレビュー可 |
| デメリット | ・個人は有料が基本(無料版は回数制限あり)・プロジェクト全体の構造把握に限界がある | ・AWS以外(フロントエンド等)の精度はCopilotに劣る・チャット機能がまだ発展途上 | ・エディタへの直接挿入には別のプラグインが必要・API利用の場合はコスト計算が複雑 |
3Dモデル生成AI
3Dモデル生成AIは、テキストや画像から三次元のデジタルモデルを自動生成するツールです。今までの3Dモデリングに必要だった専門的なスキルや高価なソフトウェアがなくても、高品質な3Dコンテンツを作成することができます。
製品デザインのプロトタイピングにおいては、アイデア段階から3Dモデルを作成し、関係者との認識合わせやプレゼンテーションに活用できます。実際の試作品を作る前に、様々な角度からデザインを検証することで、開発コストの削減と品質向上を同時に実現できます。
【課題解決のヒント】ビジネス目的から探す!あなたに合う生成AI活用法
ここまで各種類の生成AIの特徴を見てきましたが、実際にビジネスで活用する際は、技術ありきではなく課題ありきで考えることが重要です。あなたの企業が抱える具体的な課題から逆算して、最適な生成AI活用法を見つけていきましょう。
会議の生産性を劇的に向上させたい
「発言の聞き漏らし」「作成時間の増大による業務圧迫」「品質のばらつきによる不十分な情報共有」など、会議に関する課題を抱える企業は非常に多いのが現実です。
こうした課題には、音声認識AIとテキスト生成AIを組み合わせた活用が効果的です。具体的なワークフローは、会議音声を自動でテキスト化し、そこから重要ポイントを抽出して構造化された議事録に仕上げる流れとなります。
ただし、生成AIへの指示内容によって完成度が変わる点には注意が必要です。もし指示の手間を省き効率化したい場合は、ワンクリックで対応できる専用のAI議事録ツールの導入も検討してみましょう。
AI議事録ツール「Otolio」であれば、複数の議事録の形式に合わせて自動でAIが議事録をまとめてくれます。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or サービス資料をみる
マーケティングコンテンツを効率的に作成したい
「ブログ記事の投稿リソース不足」「SNSの発信ネタ切れ」「広告コピーのA/Bテスト効率化」といったマーケティングの課題は、多くの企業が直面している問題です。
この分野では、テキスト生成AIと画像生成AIの組み合わせが威力を発揮します。ワークフローを自動化することで、質の高い素材を効率的に量産可能です。
具体的なアプローチとして、まずはペルソナとキーワードをテキスト生成AIに入力し、読者に響く構成と文章を生成します。次に画像生成AIで、内容に合うオリジナルのアイキャッチや説明図を作成します。このプロセスにより、外部依頼していた作業を内製化でき、コストと時間の大幅な削減を実現できます。
SNSでも同様に、テーマ指定だけで各プラットフォームの特性に応じた文章と画像のセットを自動生成できます。InstagramやXなど、各SNSの文字数制限や推奨サイズに合わせた最適なコンテンツ制作を効率化することが可能です。
企画書・プレゼン資料の作成を効率化したい
「企画構成の遅滞」「資料作成の工数過多」「画像選定の難航」これらの課題は、特に企画・営業・マーケティング部門でよく聞かれる悩みです。
このような課題に対しては、テキスト生成AI(構成案・文章作成)と画像生成AI(スライド用イラスト作成)の連携活用が効果的です。企画のコンセプトや目的を入力するだけで、論理的な構成案から詳細な説明文、さらには視覚的に訴求力のある図表まで、一気通貫で作成することができます。
具体的なワークフローとしては、まず企画の背景、目的、ターゲット、予算などの基本情報をテキスト生成AIに入力し、企画書の基本構成と各章の概要を生成します。次に、各章の詳細な内容執筆を依頼し、さらに重要なポイントを視覚化する図表やイラストを画像生成AIで作成します。
ソフトウェア開発を高速化したい
「開発要員不足での遅延」「コーディング・テストの停滞」「ドキュメント作成による開発時間の圧迫」このような開発現場の課題は、IT業界全体で深刻な問題となっています。
コード生成AIの活用により、これらの課題を大幅に改善することができます。要件定義書や仕様書からの自動コード生成、既存コードのリファクタリング、テストコードの自動作成、技術ドキュメントの自動生成など、開発サイクルのあらゆる段階で効率化を図ることが可能です。
自社に最適な生成AIの種類を選ぶための3つのステップ
ここまで様々な生成AIの活用法をご紹介してきましたが、実際に導入を検討する際には、体系的なアプローチで最適なソリューションを選択することが重要です。以下の3つのステップに沿って、自社にとって最も効果的な生成AI活用法を見つけていきましょう。
Step1. 解決したい「業務課題」を明確にする
生成AI導入で最も重要なのは、「AIを導入すること」自体ではなく「課題を解決すること」です。技術の新しさに目を奪われるのではなく、まずは自社の具体的な業務課題を洗い出し、その解決策として生成AIが本当に適切かどうかを慎重に見極める必要があります。
課題の特定にあたっては、各部門へのヒアリングを通じて、業務プロセスに潜む「過度な時間を要する作業」「属人化した業務」「品質のばらつき」「定型的な非創造的作業」などを明確にします。
ここで特に重要なのが課題の定量化です。単に「議事録作成が大変」とするのではなく、「月間50時間の工数が発生している」といった具体的な数値で現状を把握することで、導入後の効果測定も正確に行えるようになります。また、すべての課題に一度に取り組むのではなく、「影響度」「緊急性」「投資対効果」の観点から優先順位をつけることが、導入を成功させるための鍵となります。
Step2. セキュリティとコストを比較検討する
生成AIの導入検討では、機能面だけでなく、長期的な運用成功に直結するセキュリティ要件とコスト構造の詳細な比較検討が不可欠です。
セキュリティ面では、クラウド型とオンプレミス型の選択が重要です。クラウド型は低コストで常に最新機能を利用できる一方、データ送信による情報漏洩リスクを伴います。対してオンプレミス型は自社内処理により高い安全性を確保できますが、導入コストや運用負荷は高まります。
コスト面では、月額料金に加え、従量課金による実費、初期費用(システム統合、研修、体制構築)、運用費用(管理、セキュリティ、更新)などを総合的に評価すべきです。特に従量課金制では、利用量急増に備えた年間シミュレーションや上限設定が重要になります。また、複数AIの統合コストや将来の機能拡張に伴う追加費用も、あらかじめ考慮に入れておく必要があります。
Step3. まずは無料で試せるツールからスモールスタートする
生成AI導入の成功率を高めるには、いきなり大規模な導入をせず、まず無料プランやトライアル版を活用して小規模なチームで効果検証を行うことが重要です。この段階的アプローチにより、リスクを抑えつつ自社に最適な活用方法を見出すことができます。
スモールスタートの対象には、特定部門の議事録や社内資料作成など、失敗時のダメージが小さい業務を選びます。検証期間中は作業時間の短縮や品質向上を定量的に測定し、利用者からのフィードバックも詳細に収集して、投資対効果を客観的に判断します。
成功事例が確認できたら、その成果を社内で共有しながら段階的に適用範囲を拡大します。このプロセスを経て、他部門への展開や高度な有料版への移行を検討することで、組織全体に生成AIを活用する文化を無理なく醸成することが可能となります。
生成AIをビジネスで利用する上での注意点
生成AIの導入効果が大きい一方で、ビジネス利用においては十分に理解しておくべきリスクと注意点があります。これらの課題に適切に対処することで、安全で効果的な生成AI活用が可能になります。
ハルシネーション(誤った情報生成)のリスクと対策
生成AIの最も重要な課題の一つが、ハルシネーションと呼ばれる現象です。これは、AIが事実に基づかない情報や存在しないデータを、あたかも真実であるかのように生成してしまう現象を指します。特に専門的な内容や最新の情報について質問した場合、正確性に欠ける回答が生成される可能性があります。
この問題への対策として、生成された情報は必ず人間が事実確認を行うことが重要です。特に外部公開資料や意思決定に関わる重要情報については、複数の情報源を用いた裏付け確認を徹底しなければなりません。
あわせて、社内ガイドラインを策定し、生成結果の無断使用を禁止する用途を明確に定義することも不可欠です。法的文書、医療アドバイス、投資判断といった領域では、専門家の確認なしに使用すべきではありません。
著作権・知的財産権に関する注意点
生成AIが作成したコンテンツの著作権については、現在も法的に曖昧な部分が多く、慎重な対応が必要です。特に学習データに含まれる著作物の影響を受けた出力が生成される可能性があり、意図せぬ著作権侵害のリスクを孕んでいます。
画像生成AIでは、著名なアーティストの作風模倣や既存の著作物への類似に注意が必要です。商用利用の際は、生成物の独創性を慎重に評価し、必要に応じて法的確認を行うことが重要です。音楽生成AIについても同様で、既存楽曲の旋律やリズムに類似する場合があるため、商業利用前には専門家の確認を推奨します。
対策として、各AIの利用規約を精読し、商用利用の条件や責任範囲を把握しておくことが不可欠です。また、生成されたコンテンツに独自の編集や修正を加え、オリジナリティを高めることも有効な手段となります。
情報漏洩リスクと対策
多くの生成AIサービスでは、利用者が入力した情報が学習データとして利用される可能性があります。企業の機密情報や個人情報を入力すると、それらが他者への回答に流用されるリスクを伴います。
このリスク回避には、機密データを入力しない原則の徹底が不可欠です。ガイドラインで「入力禁止情報」を明確に定義し、全社員へ周知する必要があります。
また、エンタープライズ向けプランやオンプレミス版の選択も有効です。これらは入力データが学習に使用されない設定や、高度な暗号化、アクセスログ管理など強固なセキュリティを提供します。
さらに、定期的な従業員研修による意識向上も重要です。機密情報の定義や安全な利用法、誤入力時の対処法を具体的な事例で教育することが、組織としての防御力を高める鍵となります。
まとめ|自社の課題解決ができる生成AIの種類を理解しよう
本記事では、ビジネスで活用できる生成AIの7つの主要な種類について、その特徴と具体的な活用方法を詳しく解説してきました。生成AIは単なる技術的な進歩を超えて、企業の競争力向上と業務効率化を実現する重要な経営戦略ツールとなっています。テキスト生成から3Dモデル作成まで、それぞれの生成AIには独自の強みがあり、企業の課題に応じた適切な選択が成功の鍵となります。
特に会議の生産性向上、マーケティングコンテンツ作成、企画書作成、ソフトウェア開発といった分野では、すでに劇的な効率化効果が実証されており、早期導入による競争優位性の確保が可能です。一方で、ハルシネーションリスク、著作権問題、情報漏洩といった課題についても、適切な対策を講じることで安全な活用が実現できます。
重要なのは、生成AIは万能ではなく、目的に合った種類を選び、段階的に導入し、継続的に効果検証を行いながら活用することです。まずは無料のトライアル版から始め、自社の課題解決に最も効果的なAI活用法を見つけることから始めることをおすすめします。
生成AIの急速な発展により、今後さらに多様で高性能なサービスが登場することが予想されます。この技術革新の波に遅れることなく、自社のビジネス成長につなげていくために、今こそ生成AI活用の第一歩を踏み出せるようにしましょう。
生成AIを活用して、上手く自動要約や要点抽出をするには、ベースとなる文字起こしの精度が高いことが必要不可欠です。
- 固有名詞や専門用語の変換が上手くいかない
- 「えー」や「あの」などの意味をなさない言葉も文字起こしされてしまう
- 文字起こしを修正してから生成AIを活用しているが修正に時間がかかっている
このような文字起こし精度にお悩みを抱えている方は、ぜひ一度、使えば使うほどAIの精度が上がる「Otolio」をお試しください。
またOtolioのAIアシスト機能を活用して自動要約・要点抽出も自動化できます。自動化することが可能です。AIアシストを活用すれば以下を自動化することができます。
- 要約文章の生成
- 要点の自動抽出
- 決定事項やToDo、質疑応答の抽出
Otolioは特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、使えば使うほどAIの精度が向上します。累計利用社数6,000社以上の実績、大手企業から自治体まで様々な組織で利用されており、セキュリティ面でも安心してご利用いただけます。
よくある質問と回答
Q. 生成AIを初めて導入する場合、どの種類から試すべきですか?
まずはテキスト生成AIから試すことをおすすめします。ChatGPTやGemini、Claudeといったサービスは、無料プランでも高機能なものが多く、特別な専門知識がなくても直感的に利用を開始できます。メール作成、文章の要約、アイデア出しといった日常業務にすぐに活用でき、生成AIの効果を最も手軽に実感できるでしょう。
Q. ITの専門家がいなくても、生成AIを導入・活用することは可能ですか?
はい、可能です。現在提供されている多くの生成AIサービスは、プログラミングなどの専門知識がなくても、直感的な操作で利用できるように設計されています。より効果的に活用するためには、AIに的確な指示を出す「プロンプト」のコツを学ぶことをおすすめします。
Q. 生成AIが作成した文章や画像は、そのまま商用利用できますか?
A3. 利用には注意が必要です。生成AIの出力には、著作権を侵害する内容や、事実と異なる情報(ハルシネーション)が含まれるリスクがあります。商用利用する際は、必ず以下の2点を確認してください。
生成されたコンテンツに著作権侵害や誤情報がないか、必ず人間がチェックし、必要に応じて修正・加筆する。 そのまま利用するのではなく、あくまで「下書き」や「たたき台」として活用し、最終的な責任は利用者が負うという認識が重要です。
利用するAIサービスの利用規約で、商用利用が許可されているかを確認する。