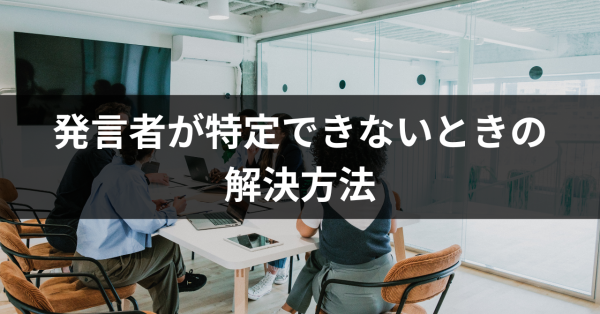AI議事録「最大90%削減」は本当?削減効果に差が生まれる4つのパターン
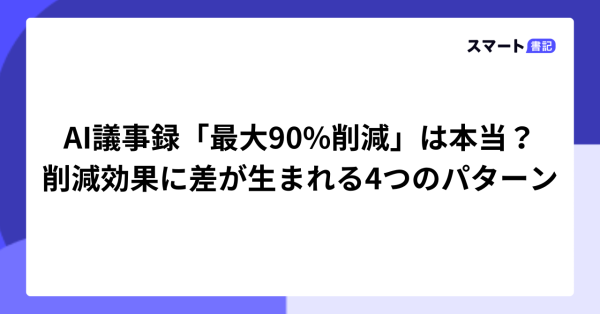
「AI議事録で最大90%の時間削減!」「議事録作成時間を劇的短縮!」こうした謳い文句を目にして、「本当にそんなに削減できるの?」と疑問に感じた方も多いのではないでしょうか。実際に、多くの企業担当者が同じような疑問を抱いており、AI議事録ツールの導入を検討する際の大きな判断材料となっています。
この記事では、AI議事録の削減効果に関する疑問を解消し、あなたの会社の議事録タイプに応じた現実的な削減効果をご紹介します。なぜ削減率に幅があるのか、その構造的な理由を明確にし、より良い導入判断ができるよう詳しく解説していきます。
またAI議事録ツールを検討している方は、ぜひ使えば使うほどAIの精度が上がる「Otolio(旧:スマート書記)」をお試しください。議事録や多様なドキュメント作成の時間を大幅に削減し、業務効率化を実現します。すぐに試してみたい方、資料を確認したい方は以下のリンクからお問い合わせください。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or サービス資料をみる
Otolio(旧:スマート書記)がわかる人気3点セット資料(サービス概要・導入事例・機能詳細)をみる
あなたも疑問に感じた「最大◯◯%削減」という表現の裏側
「最大90%削減」「最大80%削減」といった表現を見て、多くの担当者が「本当にそんなに削減できるの?」という疑問に感じることも少なくはありません。これは誇大広告ではなく、削減率に幅が生まれる構造的な背景が存在するため、このような表現になっています。
理由として、企業や会議によって求められる議事録が根本的に異なるという現実があります。一言で「議事録」といっても、社内の定例会議で使用する簡潔な記録から、クライアントや株主と共有する詳細な正式記録まで、その性質は大きく異なります。
当然のことながら、それぞれの議事録に求められる精度や詳細度も変わるため、AI議事録による削減効果にも差が生まれます。この構造を理解することで、あなたの会社の議事録に最適な削減効果を予測することが可能になります。
議事録は一つじゃない!会議の目的で変わる「議事録の正体」
多くの方が見落としがちなのが、議事録の多様性です。企業内で作成される議事録は、会議の目的や参加者、そして最終的な用途によって、全く異なる性質を持っています。
例えば、毎週開催される社内の進捗会議で作成する議事録と、重要なクライアントとの契約に関わる会議の議事録では、求められる正確性や詳細度が大きく異なります。前者は情報共有と次回までのアクションを明確にすることが主目的である一方、後者は正式な記録として法的な意味を持つ場合もあります。
この違いこそが、AI議事録の削減効果に幅が生まれる根本的な理由です。議事録の性質を正しく理解することで、あなたの会社にとって最適なAI議事録の活用方法が見えてきます。
削減効果を左右する2つの分類軸とは
AI議事録の削減効果を正確に予測するためには、議事録を2つの軸で分類して考える必要があります。この分類によって、削減効果の範囲が明確になり、より現実的な導入計画を立てることができます。
【軸1】議事録を確認する人の範囲による2パターン
議事録の確認者の範囲は、削減効果に大きな影響を与える重要な要素です。確認者が社内に限定されるか、外部関係者も含むかによって、求められる正確性のレベルが変わるためです。
社内完結型:自分+社内メンバーで確認
社内完結型の議事録は、他の従業員や上司との情報共有が主な目的となります。内部調整や振り返りでの活用が中心となるため、完璧な文章よりも要点の共有と次のアクションの明確化が重視されます。
このタイプの議事録では、参加者全員が会議の背景を理解しているため、多少の表現の曖昧さや省略があっても問題にならないことが多く、AIが生成した文字起こしや要約をベースに、最小限の編集で完成させることが可能です。結果として、比較的高い削減効果が期待できます。
対外共有型:自分+社内+外部関係者で確認
対外共有型の議事録は、クライアントや株主、パートナー企業などの外部関係者も確認する正式な記録としての性格を持ちます。このため、誤解を招く表現や不正確な情報は避ける必要があり、より高い精度が求められます。
外部関係者は会議の背景情報を十分に理解していない場合があるため、文脈を丁寧に説明し、専門用語には注釈を加える必要があります。また、企業の信頼性に関わる文書として、文章の品質や体裁にも気を配る必要があります。これらの要因により、人の手による入念な確認と編集が必要となり、削減効果に制約が生まれる構造的な理由があります。
【軸2】議事録の文章量による2パターン
議事録の文章量は、文字数での判定は困難なため、感覚的な「多い・少ない」で判断するのが実用的です。会議の性質と議事録の詳細度には密接な関係があり、この関係を理解することで適切な削減効果を予測できます。
詳細記録型:文章量が多いパターン
詳細記録型の議事録は、発言の詳細や背景情報、議論のプロセスまで含む包括的な記録です。全社会議や重要な意思決定会議、新規プロジェクトのキックオフ会議などが典型例となります。
このタイプの議事録では、「誰が何を発言したか」「どのような議論を経て結論に至ったか」という詳細な記録が求められます。AIによる文字起こしは非常に有効ですが、発言者の特定や文脈の整理、重要度の判断などは人の手による編集が必要となります。
要点整理型:文章量が少ないパターン
要点整理型の議事録は、決定事項や要点のみを簡潔にまとめた記録です。定例会議や進捗確認会議、短時間の打ち合わせなどが典型例となります。
このタイプでは、「何が決まったか」「次に何をすべきか」という結論とアクションに焦点を当てた記録が求められます。AIの要約機能を最大限活用できるため、高い削減効果が期待できます。また、元々の作業時間が短いため、絶対的な削減時間は限定的ですが、効率化の実感は得られやすいパターンです。
4つのパターン別|現実的な削減効果と最適戦略
2つの分類軸を組み合わせることで、4つのパターンが生まれます。それぞれのパターンには特徴的な削減効果があり、この傾向を理解することで、より現実的な導入計画を立てることができます。
なお、実際の削減効果は、会議の内容、参加者数、音声環境、既存の議事録フォーマット、担当者のスキルなど、様々な要因により企業様ごとに異なることをご理解ください。
パターン1:社内完結×要点整理型
定例会議や社内打ち合わせの振り返り議事録が典型的な例となります。このパターンでは、要点整理が主目的のため、AIの要約機能が最大限活用でき、削減率は80-90%と高くなりやすい傾向にあります。
特に注目すべきは、AI議事録ツールの音声検索機能を活用することで、必要な箇所をピンポイントで確認できる点です。この機能により、従来の文字ベースの議事録作成を完全に省略し、音声記録のみで情報共有を行う企業も増えています。
ただし、元々の作業時間が30分から1時間程度と短いことも多く、削減される時間は30-50分程度となります。それでも、毎週実施する会議であれば月4回で約3時間の削減効果となり、効率化の実感は高く得られます。週次の定例会議を担当している方にとっては、月単位で見た時の効果が顕著に現れるパターンです。
パターン2:社内完結×詳細記録型
全社会議や重要な意思決定会議の議事録が典型的な例となります。このパターンでは、一定の編集作業は必要ですが、大幅な削減効果を期待できます。
詳細な記録が必要なため削減率はパターン1よりやや下がりますが、元の作業時間が1-3時間程度であることが多く、削減時間は1-2.5時間と実質的な効果が高くなります。削減率と削減時間のバランスが良く、最も費用対効果を実感しやすいパターンといえるでしょう。
月1回の実施でも年間24時間の削減効果となり、業務改善効果が顕著に現れます。また、AIが生成した詳細な文字起こしをベースに編集できるため、聞き逃しや記録漏れを防げるという副次的なメリットも得られます。
パターン3:対外共有×要点整理型
クライアントとの決定事項を共有する議事録などが典型的な例となります。外部関係者との共有のため、一定の正確性担保が必要となり、削減率は中程度になります。
削減率は中程度ですが、確認作業を含めても相当な時短効果を実感できます。特に、クライアントとの重要な打ち合わせ後の迅速な情報共有が可能になるため、顧客満足度の向上にもつながる可能性があります。
外部共有という性質上、AIが生成した内容の確認に時間をかける必要がありますが、音声をもとにした正確な文字起こしをベースにできるため、従来の手書きメモからの作成と比較すると大幅な効率化が実現できます。
パターン4:対外共有×詳細記録型
株主総会やクライアントとの要件定義議事録が典型的な例となります。このパターンでは、最も高い正確性が求められ、人の手による入念な確認が前提となるため、削減率は最も控えめになります。
しかし、元の作業時間が長時間であることが多いため、削減時間が控えめであっても、実際の削減時間は大きくなりやすい傾向があります。月1回実施でも大幅な時短効果が得られるため、「削減率は最も低いが、削減される時間は最も多い」という重要な特徴を持つパターンです。
このパターンでは、編集のしやすさが特に重要になります。AIが生成した文字起こしを効率的に編集できる機能を持つツールを選択することで、削減効果を最大化できます。また、発言者の自動識別機能や、重要な発言のハイライト機能なども活用することで、編集作業の効率を大幅に向上させることが可能です。
まとめ|あなたの議事録に合った現実的な削減効果を知ることから始めよう
4つのパターンから分かるように、AI議事録の削減効果には明確な違いとその背景理由があります。社内完結型で要点整理中心の議事録では高い削減率が期待できる一方、対外共有型で詳細記録が必要な議事録では削減率は控えめになります。
重要なのは、一律の「最大○○%削減」という数字に惑わされることなく、自分の会社で作成している議事録のタイプに応じた現実的な効果を理解することです。パターン4のように削減率は低くても、絶対的な削減時間が大きければ十分な投資効果が得られます。
議事録の目的を正しく理解し、それに最適化されたツールを選択することで、期待値と現実のギャップを最小限に抑えることができます。また、削減効果を左右する要因を理解することで、導入後の運用改善や、より効果的なツールの使い方を見つけることも可能になります。
AI議事録ツールを検討される際は、まず自社の議事録がどのパターンに該当するかを確認し、そのパターンに適した現実的な削減効果を期待値として設定することをおすすめします。適切な期待値設定により、導入後の満足度も大きく向上するでしょう。
- 会議後の議事録作成に時間がかかっている
- 議事録を作成するために会議中にメモを取っているため、会議に集中できない
- 議事録作成後の言った言わないの確認に時間がかかっている
このような議事録に関するお悩みがあれば、ぜひ一度、使えば使うほどAIの精度が上がる「Otolio」をお試しください。
Otolioは特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、使えば使うほど各社に最適される高精度の文字起こしが可能です。高精度で文字起こしができるため、その後の自動要約や要点抽出などの精度も向上し、議事録作成時間の削減が可能です。
またその他にも、以下のような特徴があります。
- 様々な議事録やドキュメント作成に対応できる
- 要約文章の生成、要点や決定事項やToDo・質疑応答の自動抽出など複数の出力形式を選択できる
- 音声を含めた情報共有で会議の振り返りを効率化できる
- 対面会議、Web会議で利用が可能
- 「えー」や「あの」など意味をなさない発言を最大99%カット
- 発言内容をリアルタイムで文字起こし
- 最大20名までの発話を認識し、誰がどの発言をしたかをAIが自動で可視化
累計利用社数6,000社以上の実績、大手企業から自治体まで様々な組織で利用されており、セキュリティ面でも安心してご利用いただけます。まずは14日間の無料トライアルをお試しください。
よくある質問と回答
Q. AIによる文字起こしの精度はどのくらいですか?
AIによる文字起こしの精度は、音声環境や話者の明瞭さによって大きく左右されますが、一般的に70-90%程度の精度が期待できます。会議室での音声であれば、文脈から推測可能なレベルの精度を実現できています。精度向上のためには、雑音の少ない環境で録音することや、参加者が順番に発言するよう心がけることが効果的です。
Q. 削減効果が期待値より低かった場合の対処法は?
削減効果が期待値を下回る場合は、まず音声環境の改善から始めることをおすすめします。マイクの位置調整や雑音の除去により、文字起こし精度が向上し、編集時間を短縮できます。
また、議事録のフォーマットを見直すことも効果的です。AIの要約機能を最大限活用できるよう、詳細度のレベルを調整したり、定型的な項目を設定したりすることで、削減効果を向上させることができます。ツールの機能を十分に活用できているかも重要なポイントです。