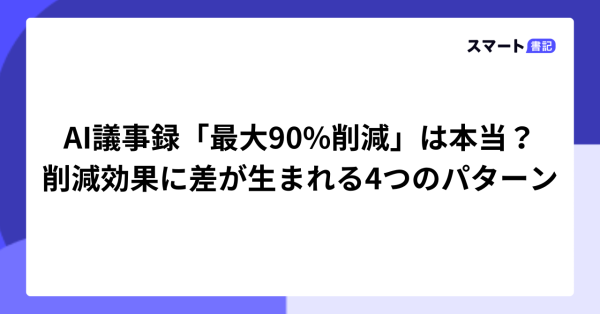「言った言わない」問題はなぜ起きる?5つの原因と対応方法を解説
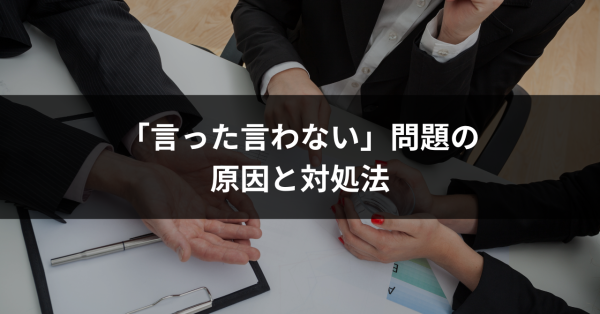
「あの件、確かに言ったはずなのに…」「そんなこと聞いていません」このような「言った言わない」問題は、どの職場でも起こりうるトラブルです。特に重要な業務や契約に関わる場面では、単なる行き違いでは済まされない深刻な問題に発展することもあります。
チームの信頼関係を損ない、業務効率を大幅に下げるこの問題に、多くの管理職や営業担当者が頭を悩ませているのではないでしょうか。実際に、プロジェクトの進行が止まったり、顧客との関係が悪化したりするケースも珍しくありません。
本記事では、「言った言わない」問題の根本原因から具体的な対処法、そして効果的な予防策まで、体系的に解説していきます。ぜひ「言った言わない」問題を未然に防ぎたい方はご覧ください。
また会議の音声をして「言った言わない」問題を防ぎたい、すぐに該当箇所の発言を確認できるツールを知りたいという方は、ぜひ一度AI議事録ツール「Otolio(旧:スマート書記)」のサービス資料もご覧ください。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or サービス資料をみる
Otolio(旧:スマート書記)がわかる人気3点セット資料(サービス概要・導入事例・機能詳細)をみる
言った言わない問題が起きる5つの根本原因
「言った言わない」問題は決して偶発的に起こるものではありません。その背景には、必ず明確な原因が存在します。問題を根本から解決するためには、まずこれらの原因を正しく理解することが重要です。
議事録などの記録を残していない
最も基本的でありながら、最も見落とされがちな原因が議事録などの記録を残していないケースです。特に社内の日常的な打ち合わせでは、「みんなが聞いているから大丈夫」という安易な考えから記録を怠ってしまうケースがあります。しかし、人間の記憶は曖昧で、時間の経過とともに詳細な内容は薄れていきます。さらに、参加者それぞれが異なる観点で話を聞いているため、同じ会議に参加していても理解や記憶に差が生じることは避けられません。
記録がない状況では、後から「誰が何を言ったのか」を客観的に確認する手段がないため、必然的に「言った言わない」の水掛け論に発展してしまいます。
口頭のみでのやり取りになっている
現代のビジネス環境では、メールやチャットツールなど、コミュニケーションを記録として残せる手段が豊富にあります。しかし、緊急性を理由に電話や対面での口頭連絡に頼ってしまうケースもいまだ多く見られます。
口頭でのやり取りは確かに迅速で効率的ですが、その内容が情報として残ることはありません。特に複雑な内容や数値を含む重要な情報を口頭だけで伝達すると、聞き手の理解不足や記憶違いが発生しやすくなります。
また、口頭での約束や指示は、その場の雰囲気や感情に左右されやすく、後から冷静に振り返ったときに解釈が変わってしまうこともあります。このような特性を理解せずに口頭コミュニケーションに依存し続けることが、「言った言わない」問題につながってしまうことがあることを理解しておきましょう。
非公式なコミュニケーションを取ってしまう
廊下での立ち話、喫煙所での雑談、飲み会での会話など、非公式な場でのコミュニケーションは職場の人間関係を良好に保つ上で重要な役割を果たします。しかし、こうした非公式な場で重要な業務の話が出てしまうと、大きな問題の原因となります。
非公式なコミュニケーションの特徴は、参加者が限定的で、内容が記録されず、正式な決定事項なのか単なる雑談なのかの境界が曖昧になることです。例えば、エレベーターでの短い会話で「来週までにあの資料を準備しておいてください」と言われた場合、これが正式な指示なのか、単なる相談なのかが不明確になります。
このような状況では、受け手は「正式な指示として受け取るべきか」「参考程度に聞いておけばよいのか」の判断に迷い、結果として認識のずれが生じてしまいます。
コミュニケーション不足
組織内のコミュニケーション不足は、「言った言わない」問題の根深い原因の一つです。日頃から十分なコミュニケーションが取れていない関係では、一度の会話で完全に意思疎通を図ることは非常に困難です。
コミュニケーション不足の職場では、相手の発言の真意を推測で補完してしまう傾向があります。「きっとこういう意味だろう」「おそらくこうしてほしいのだろう」といった憶測に基づいた理解は、後に大きな認識のずれを生み出します。
また、質問や確認を遠慮してしまう雰囲気がある職場では、不明な点があっても「今さら聞けない」という心理が働き、曖昧な理解のまま業務を進めてしまうことがあります。このような状況は、時間が経過してから深刻な問題として表面化することが多く、その際に「言った言わない」の争いが発生します。
そもそも認識がズレている
最も複雑で解決が困難な原因が、参加者間での根本的な認識のズレです。これは前提条件や言葉の定義が異なることで発生します。
たとえば、「来週中に完成させてください」という指示があった場合、発言者は「来週の金曜日まで」を想定していても、受け手は「来週の月曜日から始めて、いつかの段階で完成させればよい」と解釈する可能性があります。また、「品質を重視してください」という要求でも、依頼した人が想定している「品質」と受け手が理解する「品質」の基準が異なれば、期待される成果物にも大きな差が生じます。
このような認識のズレは、業界用語や専門用語、社内独自の表現を使用する際に特に発生しやすくなります。長年同じ組織にいると、「これくらいは常識」「みんな分かっているはず」という思い込みが生まれ、十分な説明を省略してしまうことがあります。しかし、経験年数や部署、役職が異なる相手には、その「常識」が通用しないケースが多々あります。
言った言わない問題がおきたときの4つの対応方法
「言った言わない」問題が現実に発生してしまった場合、感情的になったり、相手を責めたりすることは問題の解決には繋がりません。むしろ、冷静で建設的なアプローチを取ることで、問題を解決し、今後の関係改善にも繋げることができます。
現在進行形でこの問題に直面している方は、以下の対応方法を参考に、段階的に問題解決に取り組んでみてください。重要なのは、問題の解決だけでなく、再発防止と関係修復を同時に図ることです。
事実を確認する
問題が発生した際の最初のステップは、感情を抑えて客観的な事実確認を行うことです。この段階では、「誰が正しいか」を判断するのではなく、「何が起こったのか」を明確にすることに集中します。
まず、問題となっている出来事の詳細を整理しましょう。いつ、どこで、誰が参加して、どのような話し合いが行われたのかを時系列で確認します。この際、関係者全員から個別に話を聞き、それぞれの記憶や理解を整理することが重要です。
事実確認の過程では、相手の記憶や理解を否定するのではなく、「あなたはそのように理解されたのですね」という受容的な姿勢を示すことが大切です。このアプローチにより、相手も防御的にならず、より正確な情報を提供してくれる可能性が高まります。
また、問題の影響範囲も同時に確認しましょう。その認識のズレによって、どのような業務や関係者に影響が及んでいるのかを把握することで、対応の優先順位を決めることができます。
証拠を集める
事実確認と並行して、客観的な証拠の収集を行います。ここでいう証拠とは、相手を攻撃するためのものではなく、正確な状況把握と今後の改善策検討のための材料です。
メールやチャットの履歴、会議の資料、関連する文書など、問題となっている出来事に関連する記録を可能な限り収集します。直接的な記録がない場合でも、間接的に状況を推測できるスケジュール表、プロジェクト管理ツールの記録、関連する他の会議の議事録などの情報も有効です。
また第三者の証言も重要な証拠となります。問題となった会話や会議に同席していた他の参加者に、彼らの記憶や理解を確認しましょう。ただし、この際は「○○さんも私の言うことが正しいと言ってください」というような誘導的な聞き方ではなく、「あの時の会議で、どのような話し合いがあったか覚えていますか?」といった中立的な質問を心がけます。
証拠収集の過程で重要なのは、自分に有利な情報だけでなく、不利な情報も含めて公平に集めることです。この姿勢が、最終的な問題解決と信頼関係の回復に繋がります。
議論して解決する
事実確認と証拠収集が完了したら、関係者間での建設的な議論を行います。この段階の目的は、「誰が悪いか」を決めることではなく、「どうすれば問題を解決できるか」を見つけることです。
議論を始める前に、参加者全員で以下のルールを確認しましょう。まず、感情的な発言や相手を責める言葉は避けること、全員が平等に発言機会を持つこと、そして最終的な目標は問題解決と関係改善であることを共有します。
議論では、収集した事実と証拠を基に、それぞれの理解や記憶を照らし合わせます。完全に一致しない部分があっても、「なぜそのような理解の違いが生じたのか」を分析することで、根本的な改善策を見つけることができます。
この過程で、法的な証拠能力という観点も考慮に入れることが重要です。特に契約関連や重要な取引に関わる問題の場合、どのような記録が法的に有効とされるかを理解しておく必要があります。一般的に、日時が明確で、関係者の署名や承認がある文書、公式なメールでの確認、第三者の証言などが証拠能力を持つとされています。
原因の把握と改善
問題の解決策が見つかったら、次は根本原因の分析と改善策の検討を行います。この段階が最も重要で、同様の問題の再発防止に直結します。
まず、なぜこの問題が発生したのかを、先ほどご紹介した5つの根本原因の観点から分析します。記録の不備、口頭コミュニケーションへの過度な依存、非公式なやり取り、コミュニケーション不足、認識のズレのうち、どの要因が主な原因だったのかを特定します。
原因が特定できたら、具体的な改善策を検討します。例えば、記録の不備が原因だった場合は、今後の会議では必ず議事録を作成し、参加者全員で内容を確認するルールを設けます。コミュニケーション不足が原因だった場合は、定期的な1on1ミーティングの実施や、気軽に質問できる環境の整備を検討します。
改善策は具体的で実行可能なものにすることが重要です。「今後気をつける」といった抽象的な対策ではなく、「毎回の会議で議事録担当者を決める」「重要な口頭での指示は24時間以内にメールで確認する」といった具体的なアクションプランを策定します。
言った言わない問題の状況別の対応方法
「言った言わない」問題は、その発生する状況や関係者、影響の大きさによって適切な対応方法が異なります。画一的な対応ではなく、状況に応じた柔軟なアプローチを取ることで、より効果的な問題解決が可能になります。
社内の軽微な行き違い|即座に確認・謝罪をする
同僚や部下との間で発生した軽微な認識の違いについては、迅速で率直な対応が最も効果的です。この段階では、問題が大きくなる前に早期解決を図ることが重要です。
軽微な行き違いの場合、まず自分の理解や記憶に間違いがなかったかを素直に見直しましょう。人間である以上、誰でも記憶違いや理解不足は起こり得ます。「もしかすると私の理解が間違っていたかもしれません」という謙虚な姿勢で相手と話し合うことで、相手も防御的にならず、建設的な解決に向かいやすくなります。
相手との話し合いでは、「誰が正しいか」よりも「今後どうするか」に焦点を当てます。例えば、「今回のことで、お互いに認識の確認が不十分だったことが分かりました。今後は重要な点について、その場で確認し合うようにしませんか?」といった提案を行います。
もし自分に明らかな落ち度があった場合は、素直に謝罪し、改善策を提示します。逆に、相手に落ち度があったと思われる場合でも、相手の面子を潰さないような配慮を心がけます。「お忙しい中での対応だったので、細かい部分で行き違いが生じてしまったのかもしれませんね」といった表現で、相手を責めることなく問題を整理します。
重要業務の認識相違|上司・第三者を交えて協議する
プロジェクトの進行や重要な業務に関わる認識の相違については、当事者だけでの解決が困難な場合があります。このような状況では、客観的な視点を持つ第三者を交えた協議が効果的です。
まず、問題の整理と関係者への報告を行います。上司や関連部署の責任者に対して、問題の概要、現在の状況、想定される影響を簡潔に報告します。この際、感情的な表現は避け、事実に基づいた客観的な情報を提供することが重要です。
第三者を交えた協議では、まず全体の状況を共有し、それぞれの立場や理解を整理します。上司や第三者は、当事者間では見えない視点や、組織全体の観点から問題を分析することができます。また、権限を持つ第三者がいることで、最終的な判断や決定を下すことも可能になります。
この過程では、社内の信頼関係を損なわずに記録を残す方法についても検討します。例えば、「今後のプロジェクト管理の改善のため」「チーム全体の学習のため」といった前向きな理由を明示することで、記録を残すことが疑いや不信の表れではないことを示します。
協議の結果は、関係者全員が納得できる形で文書化し、今後の参考資料として保管します。また、類似の問題の再発防止策も合わせて検討し、チーム全体で共有します。
顧客・取引先との契約関連|法的証拠の確保・専門家へ相談する
顧客や取引先との間で発生した「言った言わない」問題は、企業の信用や経営に直接影響を与える可能性があるため、最も慎重な対応が求められます。
まず、法的な証拠能力を持つ記録の確保を最優先で行います。契約書、発注書、メールでのやり取り、議事録、録音データなど、問題となっている内容に関連するあらゆる記録を収集します。この際、証拠の改ざんを疑われないよう、原本の保管と複製の作成を適切に行います。
社内での対応体制を整備することも重要です。担当者個人の判断で対応するのではなく、上司、法務部門、必要に応じて経営陣も含めた対応チームを組織します。対外的な窓口を一本化することで、一貫した対応を保ち、さらなる混乱を避けることができます。
問題の影響が大きい場合や、法的な争いに発展する可能性がある場合は、早期に専門家への相談を検討します。弁護士や法務の専門家は、証拠の評価、法的リスクの分析、交渉戦略の策定などについて専門的なアドバイスを提供できます。
顧客や取引先との交渉では、長期的な関係維持の観点も重要です。法的に正しいことを主張するだけでなく、相手の立場や事情も考慮し、双方が納得できる解決策を模索します。時には、法的には自社が正しくても、関係維持のために譲歩することが結果的に最善の選択となる場合もあります。
そもそも言った言わないを防ぐためには?
「言った言わない」問題の最も効果的な解決策は、そもそも問題が発生しないような仕組みを構築することです。予防策は治療よりも効果的で、組織全体の生産性向上にも直結します。
必ず議事録を作成し確認をする
すべての会議や重要な打ち合わせにおいて、議事録の作成を必須のルールとして定着させるようにしましょう。議事録は単なる記録ではなく、参加者全員の理解を統一し、今後のアクションを明確にするためのツールとして活用します。
効果的な議事録には、会議の基本情報(日時、場所、参加者)、議題、決定事項、アクションアイテム(誰が何をいつまでに行うか)、次回の予定などを明確にします。特にアクションアイテムについては、担当者、期限、成果物を具体的に記載することで、後の「言った言わない」を防ぐことができます。
議事録の作成だけでなく、確認プロセスも重要です。会議終了後24時間以内に参加者全員に議事録を共有し、内容に間違いがないかを確認してもらいます。修正があれば速やかに反映し、最終版を再度共有します。このプロセスにより、参加者全員が同じ理解を持つことができます。
とはいえすべての会議の議事録を作成するのには、多くの時間が必要になります。議事録作成時間の削減を検討する場合は「Otolio」のようなAI議事録ツールの導入を検討するのも、一つの手段です。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or サービス資料をみる
業務上のやり取りをログに残す
日常的な業務コミュニケーションにおいても、重要な内容は必ず記録として残すルールを確立します。これは相手を疑うためではなく、お互いの理解を確実にし、効率的な業務進行を図るためです。
電話での重要な話し合いの後は、必ず内容をメールで確認します。「先ほどお電話でお話しした件について、私の理解が正しいか確認させてください」という前置きで、話し合った内容、決定事項、今後のアクションを整理してメールで送信します。
チャットツールを活用する場合は、重要な決定や指示については、必ず文字として記録に残します。音声メッセージや電話での連絡が多い職場でも、重要な内容については「念のため、テキストでも確認させてください」という習慣を定着させます。
また、業務上のやり取りをログとして残す際は、検索しやすい形で保管することも重要です。プロジェクト名、日付、関係者名などをキーワードとして、後から必要な情報を迅速に見つけられるような整理方法を確立します。
積極的にコミュニケーションを取る
「言った言わない」問題の多くは、コミュニケーション不足から生じます。日頃から積極的なコミュニケーションを心がけることで、小さな認識のズレを大きな問題になる前に解決できます。
定期的な1on1ミーティングの実施により、部下や同僚との理解の確認を行います。このミーティングでは、現在進行中の業務について、お互いの理解や期待を確認し、疑問点や不安な点があれば早期に解決します。
「分からないことがあったら気軽に聞いてください」という雰囲気作りも重要です。質問することを恥ずかしいことや迷惑なことと感じさせない環境を整備することで、小さな疑問が大きな問題に発展することを防げます。
また、重要な指示や依頼を行う際は、相手の理解度を確認する習慣を身につけます。「何か不明な点はありませんか?」だけでなく、「どのような手順で進める予定ですか?」「いつ頃完成予定ですか?」といった具体的な質問により、相手の理解を確認します。
情報共有のルールを決める
組織全体で統一された情報共有のルールを策定し、全員が同じ基準でコミュニケーションを行うようにします。このルールは、個人の判断に委ねるのではなく、組織として明文化し、定期的に見直しを行います。
会議の種類に応じた記録方法を定めます。例えば、正式な会議では詳細な議事録を作成し、簡単な打ち合わせではメモ程度でも構わないが、重要な決定事項があった場合は必ずメールで確認するなど、状況に応じたルールを設けます。
重要度に応じた確認方法も標準化します。緊急度が高い案件は電話で連絡しても構わないが、必ず後でメールやチャットで内容を確認する、契約に関わる内容は必ず文書での確認を行うなど、案件の性質に応じた対応方法を明確にします。
また、これらのルールは定期的に見直しを行い、実際の業務に適合しているかを検証します。ルールが形骸化しないよう、実際の問題事例を基にルールの改善を継続的に行うことが重要です。
言った言わないを防ぐことができるAI議事録ツールの活用も
現代のテクノロジーを活用することで、「言った言わない」問題の予防はより効率的かつ確実に行えるようになっています。特に、AI議事録ツールの導入は、記録作成の負担を軽減しながら、より正確で詳細な記録を残すことを可能にします。
AI議事録ツールの大きな利点は、人間の記憶や主観に左右されない客観的な記録を残せることです。誰が何を発言したかが正確に音声として記録されるため、後から「言った言わない」の議論が発生することを根本的に防ぐことができます。
さらに、多くのAI議事録ツールには、重要な決定事項やアクションアイテムを自動的に抽出する機能も搭載されています。これにより、会議後のフォローアップが容易になり、決定事項の実行漏れも防ぐことができます。
AI議事録ツールについて詳しく知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にご覧ください。
まとめ|仕組みで「言った言わない」をなくし、生産的なチームへ
「言った言わない」問題は、どの組織でも発生し得る課題ですが、適切な理解と対策により確実に解決・予防することができます。
問題の根本原因は、記録の不備、口頭コミュニケーションへの依存、非公式なやり取り、コミュニケーション不足、そして認識のズレにあります。これらの原因を正しく理解することで、効果的な対策を講じることが可能になります。
問題が発生した際は、感情的にならず、事実確認と証拠収集を冷静に行い、建設的な議論を通じて解決を図ります。状況に応じて、社内の軽微な問題は迅速な確認と謝罪で、重要業務の問題は第三者を交えた協議で、顧客・取引先との問題は法的証拠の確保と専門家への相談で対応します。
最も重要なのは予防策の確立です。すべての重要な会議での議事録作成、業務上のやり取りのログ化、積極的なコミュニケーション、そして統一された情報共有ルールの策定により、問題の発生を根本から防ぐことができます。
現代では、AI議事録ツールを活用することで、これらの予防策をより効率的に実行することが可能です。組織の特性や課題に応じて適切なツールを選択し、段階的に導入することで、「言った言わない」問題のない、信頼性の高いコミュニケーション環境を構築できるでしょう。
- 会議後の議事録作成に時間がかかっている
- 議事録を作成するために会議中にメモを取っているため、会議に集中できない
- 議事録作成後の言った言わないの確認に時間がかかっている
このような議事録に関するお悩みがあれば、ぜひ一度、使えば使うほどAIの精度が上がる「Otolio」をお試しください。
Otolioは特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、使えば使うほど各社に最適される高精度の文字起こしが可能です。高精度で文字起こしができるため、その後の自動要約や要点抽出などの精度も向上し、議事録作成時間の削減が可能です。
またその他にも、以下のような特徴があります。
- 様々な議事録やドキュメント作成に対応できる
- 要約文章の生成、要点や決定事項やToDo・質疑応答の自動抽出など複数の出力形式を選択できる
- 音声を含めた情報共有で会議の振り返りを効率化できる
- 対面会議、Web会議で利用が可能
- 「えー」や「あの」など意味をなさない発言を最大99%カット
- 発言内容をリアルタイムで文字起こし
- 最大20名までの発話を認識し、誰がどの発言をしたかをAIが自動で可視化
累計利用社数6,000社以上の実績、大手企業から自治体まで様々な組織で利用されており、セキュリティ面でも安心してご利用いただけます。まずは14日間の無料トライアルをお試しください。