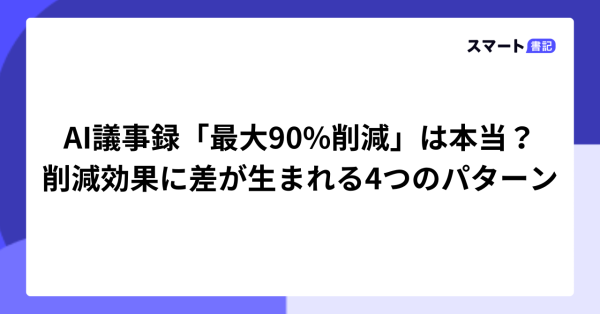会議で発言できない原因と対策を解説!おすすめのツールも紹介

この記事でわかること
- 会議で発言できない原因
- 会議で発言しないことによるリスク
- 会議で発言できるようになる方法
「会議中に発言できない」「チームメンバーが会議中に発言してくれない」こうした悩みを抱え、対策法を調べている方は多いのではないでしょうか。会議で発言しないメンバーがいると、本人の評価が下がるだけでなく、チーム全体の一体感が失われたり、多様な意見が得られにくくなったりするなど、さまざまな問題が生じます。
では、なぜ会議で発言できないのでしょうか。その原因としては、発言が的外れになることへの恐れや会議内容の理解不足、発言しにくい環境になっていること、議事録作成のためのメモで手いっぱいになっていることが挙げられます。
こうした課題に対しては、会議前の準備やルール作り、適切なツールの活用など、メンバー側とチーム側の双方で取り組める対策があります。
今回の記事では、会議中に発言できない方やその進行役・チームの方のために、会議中に発言できない原因とそのリスク、さらに明日から実践できる具体的な対策方法についてご紹介します。
まず、対策方法から知りたい方は、以下からご覧ください。
また会議中のメモや対応などに時間がかかり、発言ができないという方は、ぜひAI議事録ツールOtolio(旧:スマート書記)をお試しください。特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、使えば使うほど各社に最適化されたAIの活用ができ、議事録作成時間を大幅に削減させることができます。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or 資料を請求する
会議中に発言できない4つの原因
まずは、なぜご自身やメンバーが会議中に発言できないのか、その原因を理解しておくことが重要です。ここでは、会議中に発言できない原因を4つご紹介します。どれが当てはまっているか、確認してみましょう。
1. 会議内容に対する理解が浅い
会議の議題や背景を十分に理解していないことで、会議で発言することができなくなるパターンです。特に、事前資料を読み込む時間が短かったり専門知識が多かったりすると、会議についていくことができず、発言できなくなることがあります。
2. 発言が的外れであることへの恐れ
「自分の発言が的外れだったらどうしよう」「否定されたら恥ずかしい」といった不安から、発言を控えてしまうケースも少なくありません。特に上司や経験豊富なメンバーがいる会議では、意見を出しづらくなることがあります。
3. 発言しにくい環境になっている
会議の雰囲気や進行の仕方により、発言しにくい環境になっているパターンもあります。例えば、一部の人だけが話し続ける会議や、全員に意見を求められないまま進行する会議では、発言の機会が生まれにくくなります。また、オンライン会議では発言のタイミングが難しく、発言を躊躇してしまうこともあります。
4. 議事録作成やメモで手一杯になっている
会議中に議事録を取る役割を担っている場合、発言する余裕がなくなってしまうことがあります。メモを取ることに集中するあまり、議論に積極的に参加できなくなるのです。その結果、会議中に発言できないという状況になっています。
会議中に発言をしない3つのリスク
では、会議中に発言しないことでどのようなリスクがあるのでしょうか。本人、チーム双方にとってのリスクを3つご紹介します。
1. 評価が下がる・発言権をなくす
会議で発言しないと、周囲から「意見がない」「積極性が低い」と見なされ、評価が下がる可能性があります。また、発言しないことで存在感が薄れ、重要な場面で意見を求められなくなることになります。結果として、意思決定に関与する機会を失い、キャリアの成長にも影響を及ぼすことに繋がります。
2. 意欲が下がる
発言しないことで「自分の意見は必要ない」と感じ、次第に意欲が低下するリスクがあります。また、会議で意見を述べない人は、決定事項への関与が低くなりがちです。その結果、決まったことに対する責任感が薄れ、「自分ごと」として捉えにくくなる可能性があります。
3. 多様な意見が得にくくなる
発言しない人が増えると、会議での意見が偏り、多様な視点を取り入れることが難しくなります。特定の人だけが話す状況では、新たなアイデアや改善点が生まれにくく、チームの意思決定の質が低下する恐れがあります。その結果、組織全体の成長にも悪影響を及ぼします。
会議中に発言できるようにする方法
ここからは、明日から実践できる、会議中に発言できるようになる方法についてご紹介していきます。
会議で発言できるようにするためには、参加者側、進行役側双方で対策に取り組むことが重要です。そこで、ここでは、参加者と進行役それぞれにできる対策法をご紹介します。
参加者側
まずは、事前にできる対策をご紹介します。
事前準備1|議題を確認し、準備する
まず、事前に配られる資料やアジェンダで、その会議で何が話し合われるのか確認しておくようにしましょう。その際、専門用語や詳しくない分野の話が出てくるようであれば、あらかじめ軽く調べておきます。また、その時点で抱いた疑問をリストアップして、会議中に質問する準備をしておきましょう。
事前準備2|話を聞き逃さない工夫をする
会議に臨むにあたり、万全の状態で話を聞けるようにしておくことも重要です。Web会議であれば、あらかじめ音量の調整やイヤホンの音質を確認しましょう。
また、事後の振り返りのために、メモの準備をしておくのも重要です。もし、メモを取るのに夢中で肝心の話を聞き逃してしまう、という場合は、会議中のメモの負担を減らすには「AI議事録ツールがおすすめ」でご紹介するOtolioの導入をおすすめします。
次に、会議中にできる対策をご紹介します。
会議中1|自分の意見を持つ
発言するためには、自分の意見を持っていることが何よりも重要です。会議中は、常に、自分であればどうするか、問題点はないか、など議題について積極的に考えるようにしましょう。自分自身の意見を持つことで、まずは会議中に発言する内容がある状態にしておきます。
会議中2|発言に前置きする
自分の意見が的外れかもしれない、と思って発言できない方は、自身の発言に前置きをしてから話し始めましょう。たとえば、「初歩的な質問で恐縮ですが~」や「的外れかもしれませんが~」などです。前置きのおかげで発言内容へのハードルが下がるため、発言しやすくなります。
会議中3|他人の発言にコメントする
他の人の話に対してコメントすることも、一つの立派な発言です。他の人の発言内容を受けて、そこに自分の意見を加えましょう。発言内容に反対であったり、一部賛成したりする場合は、どこに、なぜ反対しているのかを発言します。
また、他の人の意見が自分のものと同じ場合でも、その意見に賛成の意を示して、なぜ自身がその意見に賛成なのかの理由も付け加えるようにしましょう。
会議中4|会議中に分からないことは質問する
会議中、分からないことは積極的に質問しましょう。事前準備でリストアップしていた疑問点はもちろん、会議中に抱いた疑問はその会議中になるべく解決するようにします。その質問によって自分の疑問が解消されるだけでなく、参加者の間の認識の差も埋めることができるため、気後れせずに質問するようにしましょう。
進行役側
まずは、事前にできる対策をご紹介します。
事前準備1|アジェンダを事前に共有しておく
アジェンダや会議資料は参加者に事前に共有しておきましょう。これにより参加者が事前に議題を確認し、内容について簡単に調べることができるため、議題に対する理解の差を埋めることができます。なお、アジェンダの書き方について知りたい方は以下の記事をご覧ください。
事前準備2|事前に意見を募る
会議前に、社内SNSなどで意見を募るのも一つの手です。会議中に発言しにくい人でも、文章であれば意見を伝えやすいこともあります。また、事前に議題についてある程度考えられるため、当日会議中になって考え込む時間が減り、効率的な会議運営にも繋がります。
事前準備3|日ごろから意見を出しやすい空気を作る
日ごろから、チーム内の雰囲気を良くして、意見を出しやすい空気を作っておくことも重要です。例えば、感謝やポジティブな言葉を増やして陰口や責める雰囲気をなくし、こまめにコミュニケーションを取るなどです。これによって、会議中にも参加者が臆することなく発言することができます。
会議中にできる対応は以下の通りです。
会議中1|発言の機会を均等にする
挙手制や順番制の導入により、発言の機会を均等にしましょう。一部の人だけが話していると、他の人が発言しにくくなるだけでなく、会議への意欲も下がってしまいます。あらかじめルールを作って均等に発言する機会を与えることで、普段は会議中に発言しない人でも発言しやすくなり、多様な意見を得られるでしょう。
会議中2|チャット機能を解放する
Web会議の場合は、チャット機能を解放しておき、そこでも自由に発言できるようにしましょう。一部の人だけが話していたり、話すのが苦手な人がいたりする場合は、文章で書き込めるチャット機能を利用することでより多くの人の意見を集めやすくなります。また、賛成意見に対してリアクションをつけることもできるため、会議の効率化も図れます。
会議中3|短い意見でもOKと伝えておく
参加者に意見を求める際には、短いものでも大丈夫だと伝えておきましょう。これによって発言へのハードルが下がり、率直に自分の意見を言いやすくなります。発言が苦手な人でも、短くても良いのであれば、と発言しやすくなるため、積極的に発言へのハードルを下げるようにしましょう。
会議中のメモの負担を減らすには「AI議事録ツール」がおすすめ
ここまで、会議内容に対する理解不足、発言が的外れであることの恐れ、発言しにくい環境への対応策を、参加者側と進行役側でそれぞれご紹介しました。一方で、「会議中に議事録作成のためのメモを取るため、発言する余裕がない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
そんな方におすすめなのが「AI議事録ツール」です。AI議事録ツールとは、会議の音声をAIが自動で文字起こし・要約するツールのことで、議事録作成作業のために会議に集中できない方にはぴったりのツールです。
AI議事録ツールには数多くの種類がありますが、その中でも特におすすめなのが、Otolioです。
おすすめのAI議事録ツール「Otolio(旧:スマート書記)」

引用:Otolio
Otolioは使えば使うほどAIの精度が上がるAI議事録ツールです。複雑な設定や用語登録を行わなくても、今まで通り議事録を作成するだけで、各社に最適化された高精度の文字起こしが可能です。
この高精度の文字起こしにより、自動要約や要点抽出が可能なOtolioの機能「AIアシスト」の精度も向上し、議事録やドキュメント作成にかかる時間を大幅に削減することができます。またこれらはAIに学習させることなくAI精度を向上させる特許取得済の独自アルゴリズムを活用しているためセキュリティ面でも安心してご利用できます。
Otolio(旧:スマート書記)の特徴
- 機密情報を学習させることなく、使えば使うほど各社に最適された高精度の文字起こしを提供
- 様々な議事録・ドキュメントの作成時間を削減できるように複数のAI出力形式に対応
- 累計6,000社以上の利用社数。大手企業から自治体まで様々な組織で利用されている信頼性の高いセキュリティ
その他のおすすめのAI議事録ツールを確認したい方や、そもそもどのような機能があるのか知りたい方はぜひ以下の記事もご覧ください。
まとめ|原因に合った対策で会議での発言を増やそう
本記事では、会議で発言できない方やそのメンバー・進行役の方に向けての解決策をご紹介しました。
会議で発言できない原因は主に、
- 会議内容に対する理解が浅い
- 発言内容が的外れになることへの恐れがある
- 発言しにくい環境になっている
- 議事録作成のためのメモで手一杯になっている
の4つが挙げられます。
理解不足は事前準備やアジェンダの用意、発言内容への不安は前置きや普段からの雰囲気づくり、発言しにくい環境は発言ルールの作成やチャット機能により改善します。
また、議事録作成のためのメモで手一杯になっている場合は、AI議事録ツール、特にOtolioの導入がおすすめです。
ぜひ、ご自身の状況に合った対策を行って、積極的に発言できるような会議を実現しましょう。
- 会議後の議事録作成に時間がかかっている
- 議事録を作成するために会議中にメモを取っているため、会議に集中できない
- 議事録作成後の言った言わないの確認に時間がかかっている
このような議事録に関するお悩みがあれば、ぜひ一度、使えば使うほどAIの精度が上がる「Otolio」をお試しください。
Otolioは特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、使えば使うほど各社に最適される高精度の文字起こしが可能です。高精度で文字起こしができるため、その後の自動要約や要点抽出などの精度も向上し、議事録作成時間の削減が可能です。
またその他にも、以下のような特徴があります。
- 様々な議事録やドキュメント作成に対応できる
- 要約文章の生成、要点や決定事項やToDo・質疑応答の自動抽出など複数の出力形式を選択できる
- 音声を含めた情報共有で会議の振り返りを効率化できる
- 対面会議、Web会議で利用が可能
- 「えー」や「あの」など意味をなさない発言を最大99%カット
- 発言内容をリアルタイムで文字起こし
- 最大20名までの発話を認識し、誰がどの発言をしたかをAIが自動で可視化
累計利用社数6,000社以上の実績、大手企業から自治体まで様々な組織で利用されており、セキュリティ面でも安心してご利用いただけます。まずは14日間の無料トライアルをお試しください。