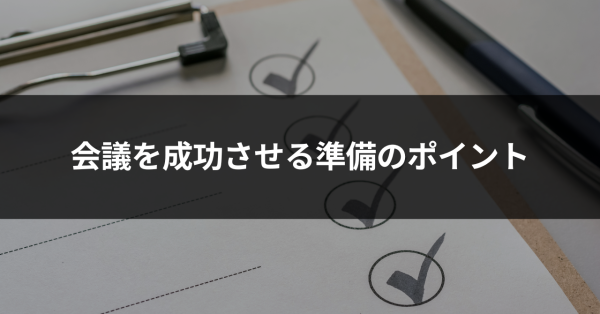営業が商談前に事前に準備すべき7つのこと|意識したい3つのポイントもご紹介

営業活動において、商談は受注を左右する重要なステップです。商品やサービスを紹介するだけではなく、お客様の課題を正しく理解し、最適な提案を行うための貴重な機会でもあります。しかし、何も準備せずにただ商談の場に臨むだけでは成果につながりません。事前にどれだけ準備ができているかによって、商談の質も結果も大きく変わってきます。
しかし、営業を初めて担当する方や、まだ商談の経験が少ない方にとっては、「何を準備すればよいのか分からない」「商談でどんなことを話せばよいのか不安」と感じることも多いのではないでしょうか。準備不足のまま商談に臨んでしまい、うまくヒアリングできなかったり、提案が相手のニーズとずれてしまったりすることで、チャンスを逃してしまうこともあります。
本記事では、商談における事前準備の重要性と、具体的にどのような項目を確認しておくべきかを分かりやすくご紹介します。「商談での成果を上げたい」「準備のポイントを体系的に知りたい」と考えている方はぜひ本記事をご覧ください。
- ミーティング中は話に集中したいため、メモが取れない
- ミーティング後に話をした内容をまとめるのに時間がかかっている
- ミーティングの発言の温度感やニュアンスを共有したい
このような議事録やメモに関するお悩みがあれば、ぜひ一度AI議事録サービス「Otolio」をお試しください。
Otolioは議事録などのドキュメント作成に関する作業を自動化・効率化することができ、作成時間を最大90%以上削減することが可能です。
商談前の事前準備が重要な3つの理由
商談を成功に導くためには、事前準備が欠かせません。どれだけ優れたサービスや商品を持っていても、準備不足の状態で商談に臨んでしまうと、相手の信頼を得られず、チャンスを逃す可能性があります。ここでは、商談前の事前準備がなぜ重要なのかを3つの観点からご紹介します。
1. 商談の目的を明確にできる
商談の準備をしっかり行う最大の理由の一つは、「商談の目的を明確にできる」という点です。初めて営業を担当する方の多くは、「とりあえず話を聞いてみよう」という気持ちで商談に臨む方も少なくありません。しかし、明確な目的がないまま商談に入ってしまうと、話の方向性が定まらず、相手に「この人は何をしに来たのか」と不信感を与えてしまうことがあります。
逆に、事前に「今日は課題をヒアリングし、次回以降の提案につなげる」といった目的を設定しておくことで、会話の軸がぶれず、相手にとっても価値のある時間を提供することが可能です。また、商談の目的を明確にすることで、同席するメンバーの役割分担や必要な資料の準備なども的確に行えます。たとえば「決裁者との顔合わせ」が目的であれば、上司に同席を依頼したり、「課題のヒアリング」が目的であれば、質問事項を整理するなど、事前準備次第で取るべきアクションが変わります。
2. 提案の質を上げることができる
商談の事前準備がしっかりできていると、提案の質を飛躍的に上げることが可能です。事前準備を行うことで、相手企業の課題やニーズをあらかじめ想定し、それに対する解決策を練っておくことができるようになります。これは、ただ自社のサービス内容を伝えるだけのプレゼンではなく、「相手の状況に即した具体的な解決策」を伝えることを意味します。
また、準備段階で仮説を立てておくことで、商談中に相手の反応を見ながら柔軟に話を展開できます。たとえば「業務の属人化が課題では?」という仮説を立て、それに基づく改善案を持っていけば、相手が「実はその点に困っていた」となったときに、すぐに次の提案へとつなげられます。このような事前準備をしておくことで、商談の展開力が格段に高まるため、商談の事前準備はとても重要です。
さらに、想定質問への回答もあらかじめ準備しておけば、当日のやり取りに余裕が生まれます。たとえば「料金体系」「導入実績」「他社との違い」など、よくある質問を事前に想定し、回答を整理しておくことで、スムーズに返答できるようになります。この対応力の高さが、提案の質を支える重要な要素となります。
3. 信頼感を得ることができる
商談における信頼関係の構築は、成果につながる最も重要な要素の一つです。そして、その信頼は「事前準備の質」によって大きく左右されます。相手企業の情報を丁寧に調べた上で、的確な質問や提案を行えば、「この人は私たちのことをよく理解してくれている」と感じてもらえます。
たとえば、相手の会社が最近リリースしたサービスや業界ニュースに言及するだけで、「しっかり調べてくれている」と印象づけられます。逆に、まったく予備知識がない状態で話を始めると、「準備不足」というマイナスの印象を持たれてしまい、その後の話も聞いてもらいにくくなります。
また、相手の担当者がどんなポジションで、何に責任を持っているかを把握しておくことも信頼構築の一環です。たとえば、現場の担当者にいきなり費用の話をしても「それは決裁者に聞いてください」となるだけで終わってしまいます。誰に対して、どのような話をすれば響くのか。その点を理解して臨むことが、信頼関係を築くための第一歩です。
商談前の事前準備で意識したい3つのポイント
では具体的にどのようなポイントを意識して事前準備すればいいのでしょうか。具体的な事前準備の方法を実践するとき前に、ぜひ以下の3つのポイントを意識してみてください。
1. 商談の目的とゴールを明確にする
商談の準備で最も意識したいポイントのひとつは、「商談の目的とゴールを明確にすること」です。これが曖昧なままだと、準備の中身も変わってしまい、成果に結びつかない可能性が出てきます。
たとえば、「製品の説明をする」「お客様の課題を聞く」といった曖昧な目的ではなく、「導入に向けたステップの確認をする」「導入意向の有無を判断する」「キーパーソンとの次回アポイントにつなげる」といったように、より具体的で行動に直結するゴールを設定を意識することが大切です。また、目的とゴールを明確にすることで、社内関係者とも情報共有がスムーズになり、上司やチームからのアドバイスも的確になります。
2. お客様の視点で準備をする
商談準備というと、どうしても「自社が伝えたいこと」「資料を整えること」に意識が向きがちですが、実際に大切なのは「お客様の立場で考えること」です。お客様は営業トークを聞くためではなく、自社の課題を解決するために商談の場に臨んでいます。そのため、お客様が何に困っているのか、どのような情報を求めているのかを事前に想像しながら準備することが欠かせません。
具体的には、事前にホームページやプレスリリース、SNSなどを調べて、お客様の業界動向や直近の取り組みを把握することが第一歩です。また、既にやり取りをしている場合は、過去のメールやチャット、前回の議事録を振り返って、お客様が何に関心を持っていたか、どのような表現を使っていたかなどの情報も有益です。
このように準備することで、お客様から「よく調べてくれているな」「話が通じやすい」と感じてもらえる可能性が高まり、信頼の獲得にもつながります。また、お客様視点で準備することで、自分本位な提案や見当違いの説明を避けることができ、商談の進行もスムーズになります。
3. 仮説思考で準備する
事前準備をするうえで常に意識しておきたいのは「仮説思考で準備すること」です。これは、お客様の状況やニーズを自分なりに想像し、「きっとこういう課題を抱えているのではないか」「こんな提案なら刺さるのではないか」と予測を立てておく考え方です。
仮説を立てることで、商談中の会話がより深く、具体的になりやすくなります。たとえば、「御社の最近の新サービス、集客が課題になっていませんか?」といったように、仮説をベースにした質問は、お客様の思考を引き出すきっかけになります。もちろん、仮説が間違っている可能性もあります。しかし、その場合でも「なるほど、実はそこじゃなくてこっちが課題なんです」と、お客様が真のニーズを語ってくれるきっかけになったりもするので、仮説が正しい・間違っているよりも、まずは仮説を持つことを意識するようにしましょう。
さらに、仮説思考には営業担当としての成長を加速させる効果もあります。お客様の反応を見ながら、「なぜこの仮説が外れたのか」「どんな情報が足りなかったのか」と振り返ることで、次回以降の精度が上がっていきます。「完璧な正解」を求めすぎず、むしろ「仮説を立てることで相手に話してもらう」ことを意識すると、会話が広がりやすくなります。準備段階で仮説を3つほど用意しておくと、どの方向に話が展開しても対応しやすくなるのでおすすめです。
商談前に事前に準備しておきたいこと7選
ここでは具体的に事前に何を調べ、準備をしておくべきか7つご紹介します。
1. 企業情報
商談前に必ず準備しておきたいのが、相手企業の情報です。企業名や所在地、業種といった基本情報だけでなく、事業内容や提供している商品・サービスの特徴、最近のニュースリリースやプレスリリース、さらには競合他社との違いなど、できる限り様々な視点で把握しておくことが大切です。これにより、相手に対して「御社のことをしっかり調べています」という誠実さが伝わり、第一印象で信頼を得やすくなります。
また、取引規模の見極めも重要です。上場企業と中小企業では、導入の決裁フローや課題の優先順位が異なるため、資本金や従業員数、拠点数なども把握しておきましょう。さらに、できれば企業のビジョンや経営理念まで調べておくと、提案内容にそれを絡めることもでき、相手に「自分たちに合わせて考えてくれている」と思ってもらえる可能性が高まります。
こうした準備は単なる情報収集ではなく、「相手企業の視点で仮説を立てる」ための土台でもあります。どんな課題を抱えていそうか、どのサービスがフィットしそうかといった仮説を持って商談に臨めば、対話の質は格段に高めることが可能です。
2. 担当者の情報
商談相手の担当者情報も、事前に可能な限り把握するようにしましょう。氏名や所属部署、役職だけでなく、過去のやり取りがある場合は、その内容も振り返ることが重要です。たとえば、以前のメールでどんなことに関心を持っていたのか、他社サービスと比較検討していたのか、トライアルを検討していたのかなどを整理しておくことで、無駄な説明を省くことができ、的確な話ができるようになります。
さらに、相手の立場を想像することもポイントです。営業担当者なのか、現場の責任者なのか、あるいは経営層に近い意思決定者なのかによって、関心事や判断基準が異なります。たとえば現場担当者なら「使いやすさ」や「運用のしやすさ」に興味がある一方で、経営層なら「ROI」や「コスト削減効果」に重きを置く傾向があります。その違いを意識した話し方を準備することで、より刺さる提案が可能になります。
3. 想定される課題
企業情報や担当者の情報から、相手企業が直面していそうな課題をあらかじめ想定するようにしましょう。「おそらくこんな課題をお持ちではないか」と仮説を立てておくことで、対話の主導権を握ることができます。想定課題は、企業規模や業界トレンドから推測ができます。たとえば、急成長中の企業であれば「人手不足」や「業務プロセスの標準化」が課題かもしれませんし、老舗企業であれば「属人化」や「システムの老朽化」などが該当するかもしれません。ニュースやIR情報、プレスリリース、業界紙などを活用して、最新の動向をキャッチアップしておくと、より精度の高い仮説が立てられます。
ここで意識したいのは、「課題=問題」ではないという点です。たとえば「より売上を伸ばしたい」「今よりも業務効率を上げたい」といった「成長のための課題」も重要な商談の入口になりえます。ネガティブな課題だけでなく、ポジティブな期待も視野に入れることで、相手に前向きな印象を与えることができます。
また、複数の課題を想定しておくことで、商談中に「そうではなく、実はこういう点がネックで…」という相手の本音を引き出すきっかけになります。仮説が外れることを恐れず、むしろ「仮説があるからこそ対話が深まる」と捉えてしっかりと想定される課題を洗い出すようにしましょう。
4. 商談の目的とゴール
商談の準備で最も大切なことのひとつが、「この商談を通じて何を達成したいのか」という「目的」と、「そのためにどこまで話を進めたいか」というゴールを明確にしておくことです。目的が曖昧なまま商談に臨むと、会話が散漫になり、相手も「この人は何がしたいのだろう?」と不信感を持ってしまいます。たとえば「課題のヒアリングがしたい」「提案の方向性を共有したい」「次回の打ち合わせに向けた材料を集めたい」など、目的は小さくても問題ありません。
重要なのは、商談後にどの状態になっていたいかをあらかじめイメージしておくことです。たとえば、「お客様が自社サービスに興味を持ち、次回の提案の場を快く了承してくれている」という状態をゴールに設定するのもよいでしょう。また、事前に目的とゴールを設定することで、商談中に話が脱線しそうになっても、軌道修正がしやすくなります。
さらに、「相手にとってのゴール」も意識できると、より信頼を得やすくなります。たとえば、「相手企業の課題解決の糸口が見える」あるいは「現状のサービスの課題が整理される」ことも、相手にとっての価値ある成果です。
5. ヒアリングしたいこと
商談は「売り込む場」ではなく「相手を深く理解する場」です。そのために、何をヒアリングしたいのかを事前に整理しておくことは、商談の成否を左右する重要な準備です。ヒアリング項目が明確であればあるほど、相手の課題や要望を的確に把握でき、それに応じた提案につなげやすくなります。
まず押さえておきたいのは、「なぜ自社に問い合わせをしてくれたのか」「現状の業務で困っていることは何か」「どのような理想状態を目指しているのか」などの基本的な質問です。これは、いわゆるニーズの深掘りにあたります。
ただし、それだけでは不十分です。顕在化している課題だけでなく、相手自身も気づいていない「潜在的な課題」を引き出せるような質問を用意しておくと、他の営業担当との差別化につながります。たとえば「もし今のやり方を2倍の規模に拡大したら、何がボトルネックになりそうですか?」といった仮説に基づく質問は、相手に新たな気づきを与えることができます。
また、ヒアリングする内容「誰に聞く」によっても変わります。現場担当者には具体的な運用の悩み、マネージャーにはコストや生産性、経営層には将来ビジョンや全社的な課題、といったように、立場によって関心事が異なるため、事前に調べた相手の役職や業務領域から仮説を出し、それに合わせた質問を準備しましょう。
6. 想定できる提案内容
商談前に「どんな提案ができるか」をあらかじめ整理しておくことは、相手の課題に対する解決策を明確に示すために不可欠です。提案内容は、商品やサービスそのものの紹介にとどまらず、相手企業の課題にどのようにフィットし、どのような価値を提供できるかという視点で準備する必要があります。
まず、過去の提案事例や導入実績などを参考にして、相手企業の業種や規模に合った提案パターンをいくつか用意しておきましょう。そのときに「価格」「納期」「カスタマイズの有無」「導入支援の体制」などの要素を整理し、相手が意思決定しやすい材料を準備することが重要です。
また、提案内容は1つに絞らず、複数の選択肢を用意しておくと、商談の場で柔軟に対応できます。たとえば、最小構成でコストを抑えたライトプラン、効果を最大化できる標準プランなど、顧客のニーズに応じて提案を切り替えられるようにしておくと効果的です。
7. 想定質問への回答
商談の場では、必ずといってよいほど顧客からの質問が飛んできます。そこで慌てないように、事前に「どんな質問が来るか」を想定し、回答を準備しておくことが重要です。よくある質問には、価格や納期、サポート体制、実績、契約条件などがあります。たとえば「月額いくらかかるの?」「サポートはどこまで対応してくれるの?」「うちの業種でも導入実績ある?」などが典型的です。これらの質問には、数字や実例を用いて端的かつ具体的に答えられるように準備しておきましょう。
さらに重要なのは「聞かれたら答えに詰まりそうな質問」への備えです。たとえば「御社の競合と何が違うの?」「失敗事例はある?」「価格が高いと思うが、理由は?」といった質問は、想定していないと答えづらくなりがちです。こうした質問に対しては、ネガティブな内容も含めて正直かつ前向きなスタンスで準備しておくと、誠実さが伝わりやすくなります。
また、「質問に答える」こと自体が目的になってしまうと、会話が受け身になってしまいます。そこで、「逆質問」を交えて商談を双方向にすることも意識してみてください。たとえば、「その点について詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか?」「他にも懸念されている点はありますか?」といった問いかけを準備しておくと、相手との信頼関係を築きやすくなります。
商談の準備で活用できるAI議事録ツールを活用した事例
最後に商談の準備で活用できるAI議事録ツールをご紹介します。AI議事録ツールを活用すれば、商談の音声をピンポイントで聞き直すことができるため、相手担当者が実際にどんな発言をしたのかをすぐに確認することができます。初回商談ではなく、あくまでも2回目以降の商談準備に限るケースですが、事前準備の参考例としてぜひご覧ください。
商談の音声をヒントに提案のクオリティを改善
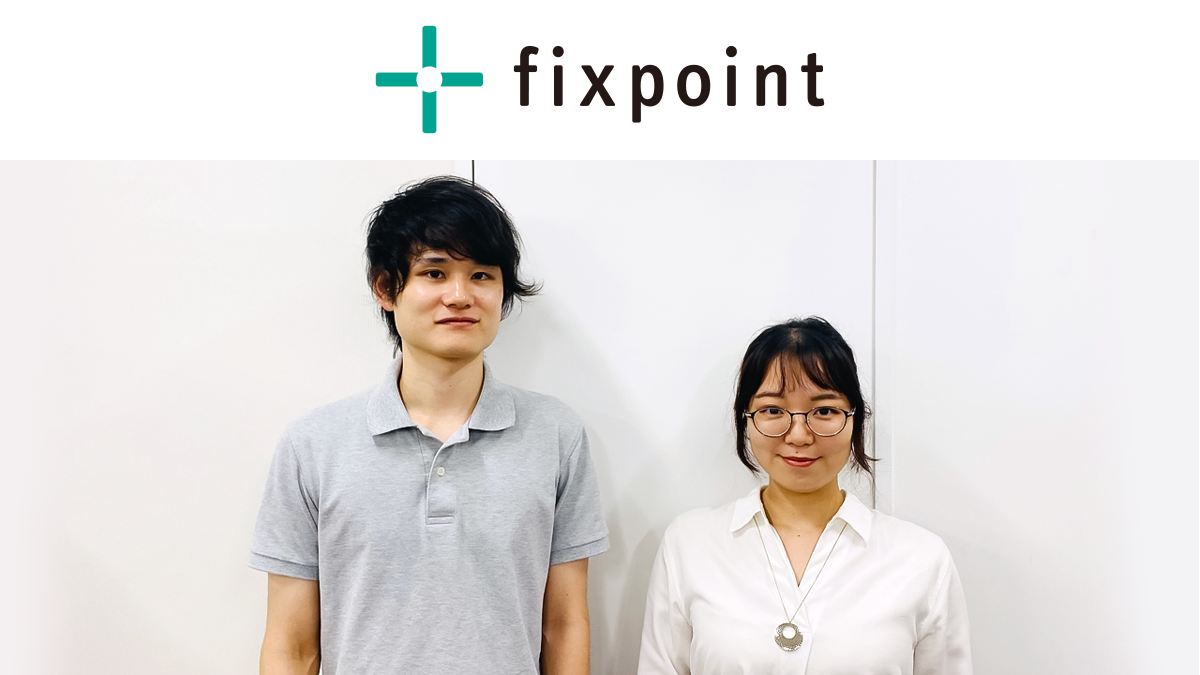
音声をすぐに聞き直すことができるようになって、今まで文字だけの議事録ではできなかった、お客様の発言の背景やニュアンスを汲み取ることができるようになりました。
実際に最近とあるメンバーから次回の商談のアプローチを考える上で「お客様がこういっていたけど、これってどういう意図ですか?」と質問がありました。今まではメンバーに「どんな発言だったの?」と当時の状況を聞くことしかできませんでしたが、今ではそのときの発言の音声を聞き直しながら発言の温度感、言い回しを一緒に確認し、次回アプローチを一緒に考えることができるようになっています。
まとめ
商談の成否は、事前の準備にかかっているといっても過言ではありません。相手企業や担当者の情報を丁寧に調べ、課題を仮説として立てておくことで、当日の提案の精度が大きく向上します。また、商談の目的とゴールを明確にしておくことで、会話がブレず、相手にとっても「価値ある時間だった」と感じてもらえる可能性が高まります。
商談準備で大切なのは、「自分たちが伝えたいこと」ではなく、「相手が何を求めているか」に視点を置くことです。お客様の立場を想像し、必要な情報を事前に整理しておくことで、信頼関係の構築にもつながります。さらに、「仮説思考」を取り入れることで、より深い対話や新たな気づきを引き出せるようになります。
この記事でご紹介した7つの項目は、どれも商談の質を高めるうえで欠かせない要素です。すべてを完璧に準備するのは難しいかもしれませんが、まずは自分が取り組みやすい項目から始めてみるのがおすすめです。商談はただ説明をする場ではなく、相手との信頼を築き、課題を共に解決していくための第一歩です。今回ご紹介した準備のポイントを押さえたうえで、商談に望めるようにしましょう。
- ミーティング中は話に集中したいため、メモが取れない
- ミーティング後に話をした内容をまとめるのに時間がかかっている
- ミーティングの発言の温度感やニュアンスを共有したい
このような議事録やメモに関するお悩みがあれば、ぜひ一度AI議事録サービス「Otolio」をお試しください。
Otolioは議事録などのドキュメント作成に関する作業を自動化・効率化することができ、作成時間を最大90%以上削減することが可能です。