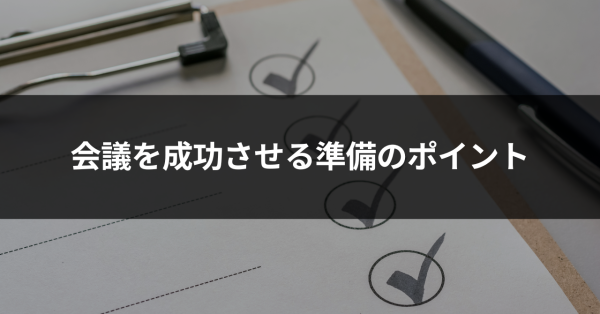【企業向け】カジュアル面談とは?目的やメリデメ、成功させるためのポイントも紹介
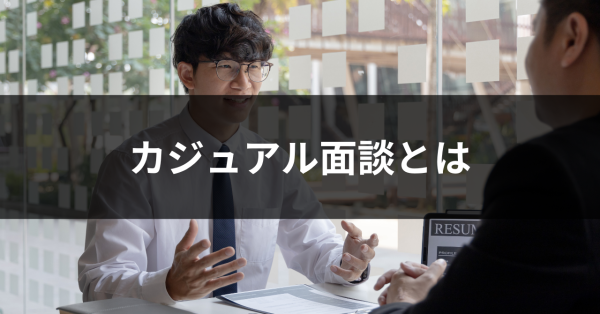
カジュアル面談とは、企業の担当者と候補者がリラックスした雰囲気の中で相互理解などを深めるという選考以外の目的で行われる面談のことです。近年、採用活動の場面で選考前に、カジュアル面談を実施する企業も増えてきていますが、「カジュアル面談の実施する目的を知りたい」「カジュアル面談をやることでどんなメリットがあるの?」「成功させるポイントや注意するポイントがあれば知りたい」と考えている方も多いと思います。
そこで本記事ではカジュアル面談とは何か、面接との違いやその目的、メリットなど幅広くご紹介します。これからカジュアル面談を行おうとしている方も、今のカジュアル面談をさらに良くしたい方もぜひ、本記事をご覧ください。
- ミーティング中は話に集中したいため、メモが取れない
- ミーティング後に話をした内容をまとめるのに時間がかかっている
- ミーティングの発言の温度感やニュアンスを共有したい
このような議事録やメモに関するお悩みがあれば、ぜひ一度AI議事録サービス「Otolio」をお試しください。
Otolioは議事録などのドキュメント作成に関する作業を自動化・効率化することができ、作成時間を最大90%以上削減することが可能です。
カジュアル面談とは
カジュアル面談とは、企業の担当者と候補者がリラックスした雰囲気の中で相互理解などを深めるという選考以外の目的で行われる面談です。今までの採用面接とは違い、採用選考の一環としてではなく、企業と候補者がお互いを知る「出会いの場」として設定されます。特にIT業界やスタートアップ企業を中心にカジュアル面談の普及が進んでいますが、近年では大企業でも取り入れられるようになっています。
カジュアル面談には様々な目的が存在しますが、主に「この会社はどんな会社なのか?」を候補者に伝え、候補者が企業を判断する材料を提供することにあります。また企業側も同様に、候補者の価値観や志向性、ポテンシャルを知る機会として活用しています。
またカジュアル面談は採用担当者だけではなく、現場の担当者が実施、または同席するケースがあります。入社したとしたら、一緒に働くことになる現場の担当者が同席することで、よりカジュアル面談の中で社員の人柄や雰囲気が伝わりやすくなります。
このように、カジュアル面談は単なる「選考前の面談」ではなく、採用活動の新しいアプローチとして、その重要性が増しています。企業と候補者、双方にとってメリットの多いコミュニケーションの場として、今後ますます活用されていくことが想定されています。
カジュアル面談が増えている背景
カジュアル面談が注目され、導入する企業が増えている背景には、採用市場におけるいくつかの大きな変化が関係しています。特に深刻な人材不足、候補者の転職活動スタイルの多様化、そして企業のブランディング戦略の進化が大きな要因です。
まず、労働人口の減少に伴い、優秀な人材の争奪戦は増々激化していっています。特に中途採用市場では、経験者・即戦力を確保することがとても難しくなってきており「求人を出せば応募が来る」という状態をすでに実現できなくなっています。そのため、まだ転職意欲が明確でない潜在層にもアプローチしていく必要がありますが、カジュアル面談は、その入口として非常に有効な手段となっています。
また、候補者の価値観や働き方に対する考え方が多様化しており、今までのように企業の規模や安定性ではなく、その企業のカルチャーや働きやすさ、自分らしいキャリアパスを描けるかどうかなど、多面的に企業を評価する候補者も増えています。こうした候補者に対して、企業側が一方的に情報を発信するだけでは、十分な発信とはなりません。そのためカジュアル面談で双方向で会話しながら、お互いを知ることはとても重要な活動となっています。
カジュアル面談と面接の違い
カジュアル面談と一般的な採用面接には、目的・進行・評価の有無など、さまざまな点で明確な違いがあります。この違いを理解しながらカジュアル面談を進めていくことが重要です。
まず大きな違いとして「目的の違い」が存在します。面接は採用選考の一環として、候補者のスキルや経験、志望動機などを評価し、採用の可否を判断する場です。一方で、カジュアル面談はあくまで相互理解を深めるための情報交換の場であり、即時の採用判断を行うことを目的としていません。そのため、候補者にとっても心理的負担が少なく、本音を語りやすい雰囲気が生まれやすいというメリットがあります。
カジュアル面談の3つの目的
カジュアル面談には重要な3つの目的が存在します。具体的にどんな目的なのかをご紹介します。
1. 企業や組織の魅力訴求
カジュアル面談は選考を前提としていない場で、候補者と企業が気軽に対話することができます。その中で重要な目的の一つが「企業や組織の魅力訴求」です。企業側にとって採用活動の一環として、自社の魅力を伝える機会はとても重要になります。
今までは、企業説明会や求人票、採用サイトなどでアピールするのが一般的でしたが、これでは、情報が一方通行になりがちになります。そのため、カジュアル面談という双方向のコミュニケーションを実施することで、候補者の関心や価値観を踏まえたうえで、自社のカルチャーや働き方、ビジョン、メンバーの雰囲気などをカスタマイズして伝えることができるため、深い共感や興味を引き出すことが可能になります。
またカジュアル面談では企業側がフィードバックを得ることができるというメリットも存在します。たとえば、候補者に自社の魅力を伝えたときに「思っていたイメージと違った」と感じた場合、そのギャップを聞くことで、採用広報の改善点を見つけることが可能になります。
逆に、自社が強みとして考えていなかったポイントに、候補者が強く魅力を感じていることに気づくケースもあります。こうした「他者の視点」は、社内だけでは得られない貴重な気づきを与えてくれます。
2. 潜在層へのアプローチ
カジュアル面談には「潜在層へアプローチ」という目的が存在します。潜在層とは、「現時点では転職を考えていないが、将来的に良い機会があれば動くかもしれない」といった層の人たちのことで、カジュアル面談はまさにこの潜在層との接点を築くための有効な手段といえます。
というのも、今までの採用活動では「今すぐに転職したい」と考えている顕在層へアプローチするのが一般的でした。求人サイトやスカウトメール、エージェント経由の応募者などがこれにあたります。しかし、この顕在層の候補者は競合も同じようにアプローチしていることが多く、限られた転職希望者の奪い合いが発生し、採用の難易度が高まる一方です。
そこでカジュアル面談を実施すると、競争が激化していない状態で優秀な人材にアプローチすることが可能になります。彼らはまだ転職市場には現れていないため、通常の採用活動では出会うことができません。カジュアル面談という柔らかな接点を用意することで、「情報収集の一環」として気軽に応じてもらうことが可能になります。
そうすることで面談後すぐに選考に進まなくても、数ヶ月後、あるいは数年後に「そういえばあの企業と話したな」と思い出してもらえる可能性が高まります。またカジュアル面談を実施して本人ではなく、その人の周りにいる別の人を紹介してくれる可能性もあります。カジュアル面談を通じて良好な関係が築ければ、「自分はまだ転職を考えていないけど、知り合いで興味ありそうな人がいる」といった形で、紹介が生まれるケースです。これは、通常の選考フローでは生まれにくい波及効果であり、このようにカジュアル面談を実施することで、今までアプローチが難しかった潜在層へのアプローチが可能になります。
3. 候補者の人柄を把握する
カジュアル面談が果たす目的のひとつに、未来の採用候補者となりうる人材と早い段階で関係を築くことができ、かつ、面談という場を通じて「人柄」を知ることができるという目的が存在します。
通常の書類選考や面接では、スキルや経験といった「目に見える情報」が評価の中心になってしまうケースも少なくはありません。しかし、組織にとって本当に重要なのは「この人と一緒に働けるか」「チームにフィットするか」といった、いわば「人柄」の部分で、カジュアル面談は、まさにその人柄を感じ取ることが可能です。
というのも、カジュアル面談という選考と切り離された場でプレッシャーがない環境だからこそ、求職者も肩の力を抜いて本音で話すことができ、自分らしい姿を見せやすくなります。一方、企業側も堅苦しい質問ではなく、日常の価値観や働き方のスタンス、将来像などについてざっくばらんに聞くことができ、単なるスキルシートでは判断できない「人間的な魅力」を知ることが可能になります。
カジュアル面談の3つのメリット
ではカジュアル面談を実施することで、具体的にどんなメリットが得られるのでしょうか。ここではカジュアル面談で得られるメリットを3つご紹介します。
1. 母集団の量と質を高める
カジュアル面談は転職の意向がなくとも候補者と話をすることができるため、潜在層も含めた今まで以上の候補者と出会うことが可能になります。またカジュアル面談で、候補者の価値観や志向性、これまでのキャリアに対する考え方が選考の場よりも自然な形で知ることができます。
そして企業側も「なぜこのポジションが必要なのか」「今後どんな方向を目指しているのか」などを率直に伝えることができるため、結果としてお互いの相性をより深く知ることができ、結果として採用活動の質を向上させることに繋がります。
2. ミスマッチを防止できる
採用活動において避けたいことの一つが「ミスマッチによる早期離職」です。期待していたスキルや企業文化へのフィット感が実際には合わず、早期に退職してしまうことは、企業にとっても候補者にとっても大きな損失となります。こうした事態を防ぐための手段として、カジュアル面談は非常に有効です。
選考の場では、候補者も企業側も「良く見せよう」という意識が強く働いてしまうケースがあります。その結果、互いに表面的な情報交換にとどまり、入社後に「思っていた職場と違った」「こういう仕事だとは思わなかった」といったギャップが生まれることがあります。
しかしカジュアル面談であれば、評価を気にせず本音で話すことが可能です。候補者にとっては、業務内容やチーム構成、評価制度、働き方などについて遠慮なく質問できる場であり、企業側も実際の課題や求めるスキルセット、文化的な特徴などを率直に伝えることができます。これにより、事前に期待値のすり合わせが可能となり、ミスマッチのリスクを大きく低減できます。
さらに、「候補者側の自己認識のズレを修正できる」というメリットも挙げられます。カジュアル面談を通じて話をする中で、自分のキャリアに対する理解が深まり、「自分にはこの仕事よりも別のポジションの方が向いているかもしれない」といった気づきを得ることがあります。これは候補者にとっても価値のある体験であり、企業としてもその人に最適なポジションの提案がしやすくなり、入社後のミスマッチを防ぐことが可能になります。
3. リファラル経由の接点を作ることができる
カジュアル面談にはリファラル経由の接点を作ることができるというメリットがあります。リファラルとは「推薦」「紹介」を意味しており、自社の社員や関係者から知人や友人を紹介してもらい、採用につなげる取り組みを指しています。近年、採用市場が売り手優位になる中で、信頼関係に基づくリファラル採用の価値はますます高まっていますが、紹介のハードルを下げる仕組みとしてカジュアル面談は非常に有効です。
たとえば、社員が「うちの会社、カジュアル面談やってるから、興味あれば一度話してみない?」と気軽に声をかけやすくなることで、これまでリーチできなかった層との接点が生まれやすくなります。選考のような堅苦しさがないからこそ、「話だけでも聞いてみようかな」と思ってもらえる可能性が高まり、紹介者・紹介される側双方の心理的なハードルを下げることが可能です。
カジュアル面談の3つのデメリット
カジュアル面談を実施することで様々なメリットが得られることが分かりましたが、一方でカジュアル面談にはデメリットも存在します。ここではカジュアル面談を行うことで起きてしまう3つのデメリットをご紹介します。
1. 対応工数が増える
カジュアル面談は候補者の応募のハードルを下げることができ、気軽に話ができるメリットがありますが、その裏側では企業側の対応工数が大幅に増えるというデメリットがあります。
今まで対応していた候補者とのやり取りや面談が純粋に増えてしまうため、採用担当者が別の業務時間を削って対応せざるを得ないケースも多く、積み重なると大きな負担となってしまいます。また、カジュアル面談の実施数が増えるにつれて、フォロー対応にも工数がかかります。選考に進むかどうかの判断を伝える、もしくは進まない場合でも感謝の気持ちを伝える工数が圧迫してしまい、結果として採用活動全体のスピードや質を下げてしまうリスクにもなり得ます。
このように、カジュアル面談は一見ライトに見える活動ですが、企業側の目線で見ると想像以上に工数がかかる取り組みであるという点を認識しておく必要があります。
2. 効果が見えづらい
カジュアル面談は、相互理解を深める場として活用されますが、この形式には成果が測定しづらいというデメリットがあります。
通常の選考プロセスであれば、履歴書や職務経歴書をもとに候補者のスキルや経験を評価し、それに対する企業側の面接官の評価も残ります。一方で、カジュアル面談は「選考ではない」ことが前提となっているため、何をもって良い面談だったのか、何を改善すべきだったのかという判断軸が曖昧になりがちです。
また、何件のカジュアル面談を実施し、そのうち何件が選考に進み、最終的に何名が入社したのかといったKPIを設定することは可能ですが、その数字が「面談の質」を反映しているかは別問題となります。面談を通じて好印象を持ったとしても、実際の選考でミスマッチが起こることもありますし、そもそも応募に至らないケースも多いため、成果との因果関係を特定しにくいのが現実です。
このように、カジュアル面談は定性的な成果への影響が大きい分、効果測定や改善が難しいという特性があります。導入にあたっては、実施目的を明確にし、その目的に沿ったKPIの設計や振り返りの仕組みをあらかじめ用意しておくことが不可欠です。
3. 担当者のスキルに依存する
カジュアル面談は、企業と候補者がフラットな立場で話す場として機能する反面、その成果は大きく担当者のスキルに左右されます。通常の面接では評価項目がある程度定まっていることも多く、質問内容や進行もある程度テンプレート化することが可能です。しかし、カジュアル面談においては、雑談の中から相手の本音や志向性を引き出す力、そして企業の魅力を自然体で伝える力が問われるため、このスキルが担当者次第になってしまいます。
たとえば、会話のキャッチボールがうまくできないと、ただの表面的な情報交換で終わってしまいます。候補者の不安や希望をうまく引き出すには、聞き手としてのスキルや共感力が不可欠です。特に、初対面の相手に対して信頼感を持たせるには、短時間で距離を縮めるコミュニケーション能力が求められます。
また他にも、企業側の魅力を伝える際にもスキルが問われます。カジュアル面談では、パンフレットや採用資料をただ読み上げるのではなく、自身の体験や具体的なエピソードを交えて話すことが求められます。たとえば、「この仕事のやりがい」や「入社前後のギャップ」など、実感のこもった話を聞くことで、求職者は企業への理解を深めることができます。しかし、そうした語り方ができる担当者のスキルのばらつきによって、面談の質が大きく変わってしまう可能性があることを理解しておくようにしましょう。
カジュアル面談の進め方6ステップ
具体的にカジュアル面談をどのように進めればいいかと悩んでいる方に、カジュアル面談の進め方をご紹介します。ここでご紹介する内容はあくまでも一例であり、参考にしつつ自社にとってベストな進め方はどうなのかをぜひ模索するようにしましょう。
1. 自己紹介
まずはお互いの自己紹介から始めるようにしましょう。カジュアル面談といっても候補者が緊張していることも多いため、単に形式的な自己紹介をするのではなく、共通の話題を雑談したり、この自己紹介で候補者がリラックスできるかがポイントになります。
2. カジュアル面談の目的とゴールの共有
自己紹介のあとはカジュアル面談の目的とゴールを共有します。たとえばカジュアル面談の目的は相互理解であるとしっかり伝え、そのため自社の事業について詳しく知ってほしいとゴールを明確に伝えます。ときにはゴールをここですり合わせることも重要です。たとえば候補者が事業よりも企業文化について詳しく知りたい場合は、その場でゴールを変更することも考えられます。またこのタイミングで選考の場ではないことを伝えることも重要です。
3. 採用候補者の状況把握
次に採用候補者の状況を必ずヒアリングするようにしましょう。すでに転職活動を実施している、転職意欲は強くはないが良い企業があれば転職してみたい、数年後の転職のために情報収集をしているなど、候補者によってカジュアル面談に参加する目的は異なります。また候補者に何か具体的に聞きたいことがないかを確認するのも重要なポイントです。これを実施することで候補者が知りたいことを、しっかりと伝えることができるようになるため、双方がメリットを感じることができるカジュアル面談を実施できるようになります。
4. 企業や組織・業務の説明
採用候補者が知りたいことが明確になれば、あとはその知りたいことに対してしっかりと自社の状況を伝えましょう。このときただ資料を読み上げるのではなく、採用候補者が知りたいことに合わせて細かい表現や、実際の事例などをチューニングしていくことが重要です。
5. 採用候補者の質問対応
説明が終わったあとは、他に具体的に聞きたいことがないかを確認する質問をするようにしましょう。また説明をしていく過程で追加で知りたいことや、今回のゴールとは関係ない疑問が生まれるケースもあります。そのため説明した内容以外の質問でも問題ないことを伝えることが重要です。
6. 今後の案内
カジュアル面談後にぜひ通常の選考に進んでほしい候補者の場合は、応募の手順や採用スケジュールを伝えるようにしましょう。このとき注意すべきなのが候補者の状況です。たとえば、現時点で全く転職意欲がない候補者に対して採用スケジュールを伝えたとしても、「転職するつもりはないのに…」と悪い体験になってしまう可能性があります。そのときは通常の選考を案内するのではなく、今後も接点を持ちたい旨や、何か採用イベントなどを開催していたらそこに招待するといった形で、定期的な接点を持てる工夫をしましょう
カジュアル面談を成功させる4つのポイント
カジュアル面談を成功させるためにはいくつかのポイントが存在します。ここではカジュアル面談を成功させるための具体的な方法を4つご紹介します。
1. 目的とゴールを伝える
進め方でもご紹介しましたが、「目的とゴール」を伝えることはカジュアル面談を成功させるためにも、とても重要なポイントです。ただ「気軽に話しましょう」と誘うだけでは、候補者の期待とのギャップが生まれ、思ったような成果は得られません。
たとえば、「選考ではない情報交換の場」と伝えたうえで、「当社の雰囲気を知ってもらい、今後のキャリアの選択肢の一つとして考えてもらえるような時間にしたい」と具体的なゴールを伝えれば、候補者も安心してカジュアル面談に臨むことができます。また、ゴールを伝えることは、自社側の準備にも直結します。ゴールが「会社の雰囲気を伝える」なら、社内の写真や社員インタビューなどのビジュアル素材を用意しておくと効果的です。
さらに「面談後にどんなアクションを想定しているか」を伝えておくことも大切です。たとえば、「面談後に選考へ進むかどうかはお互いに検討しましょう」と伝えることで、候補者が「この場で評価されているのか?」と身構えることを防げます。曖昧さを取り除くことで、リラックスした雰囲気を作り出し、より本音に近い対話が実現します。
2. 採用候補者の事前情報を把握する
カジュアル面談はあくまでカジュアルなもので、かしこまった面接とは違いますが、だからといって事前準備を怠ってよいわけではありません。むしろ、限られた時間の中で密度の濃い対話を行うためには、採用候補者の事前の情報収集が不可欠です。
まずは、候補者の履歴書や職務経歴書などを確認するようにします。カジュアル面談のときに書類がない場合は、SNSなどのプロフィール情報に目を通すようにしましょう。過去の職歴や現在の仕事内容、得意なスキル、興味のある分野などを把握することで、相手に合わせた話題を提供することが可能になります。たとえば、マーケティング経験が豊富な方であれば、自社のプロモーション施策の話題を出すことで、自然な共通点が生まれます。
また事前にチームメンバーとすり合わせを行うことも重要です。カジュアル面談では現場社員が登場するケースも多いため、候補者に何を伝えるべきか、何を聞いてほしいかをチーム内で確認しておくことで、一貫性のあるメッセージングが可能になります。逆にこれを怠ると、異なる立場から矛盾する説明がされてしまい、候補者が混乱する恐れがあります。
事前情報の把握は、単なる情報収集ではありません。候補者一人ひとりに真摯に向き合う姿勢を示すことで、会社に対する信頼感が生まれ、面談そのものの質も格段に向上するため、採用候補者の事前情報を把握することはカジュアル面談を成功させるためにも重要な取り組みです。
3. 対話のスタンスをフラットにする
カジュアル面談における大きな落とし穴のひとつが、「無意識の上下関係」です。採用する側とされる側、という構図が頭にあると、知らず知らずのうちに対話のスタンスに差が出てしまいます。しかし、カジュアル面談の本質は「相互理解」であり、どちらか一方が評価する場ではなく、双方がフラットに情報を交換し合う場であるべきです。
まずは物理的な雰囲気づくりから工夫するようにしてみましょう。また言葉遣いや態度にも気を配るようにしましょう。「何か質問ありますか?」といった一方通行な問いかけではなく、「実は私たちもこういったことを模索中なんですが、どう思いますか?」のように、共に考える姿勢を見せることで、候補者も対等な立場で会話に参加しやすくなります。
対話をフラットにするとは、単に丁寧に接することではありません。相手を「一緒に働くかもしれない仲間」としてリスペクトし、信頼に値する存在として扱う姿勢が何より重要です。そのスタンスが候補者にも伝われば、面談の質は自然と高まり、長期的な関係構築にもつながります。
4. ありのままの情報を伝える
カジュアル面談では企業側の見せ方が重要になります。つい魅力的な部分ばかりを強調し、課題や未整備な部分を伏せてしまうと、候補者との信頼関係は築けませんし、仮に入社したとしても「聞いていた話と違う」とミスマッチが生じる原因になります。
だからこそ、「ありのままの情報を伝える」ことが大切です。たとえば、「急成長しているベンチャーです!」という一言の裏には、「制度や仕組みがまだ整っていない」「業務が属人的になっている」などの現実もあるかもしれません。こうした実情を隠さず伝えることで、候補者は自分の価値観や働き方と照らし合わせ、より納得感を持って判断できるようになります。
ありのままを伝えることは、一見リスクのある行動に思えるかもしれません。しかし、その誠実さが候補者の心に響き、結果的に強いエンゲージメントにつながるという側面もあります。カジュアル面談を関係構築の入口であると捉えて、ありのままの情報提供は欠かせない要素になります。
カジュアル面談で注意したい3つのポイント
カジュアル面談を成功させるためのポイントをご紹介しましたが、では逆にどんな点に注意すべきなのでしょうか。ここではカジュアル面談で注意したいポイントを3つご紹介します。
1. 選考の場にしない
今までも度々ご紹介しましたが、カジュアル面談は選考ではありません。あくまで採用候補者と企業の相互理解が重要で、自社の働き方や雰囲気のイメージをもってもらうことが重要です。そのため、採用選考の場として扱わないように注意しましょう。
採用担当者がこの点を正しく理解しておかないと、候補者にとって混乱を招く可能性があります。たとえば、面談の途中で「これまでのご経歴を時系列で詳しく教えていただけますか?」など、まるで書類選考や一次面接のような質問をしてしまうと、「これは本当にカジュアル面談なのか? 実は選考が始まっているのでは?」と疑念を持たれてしまうかもしれません。
企業側が選考の場にしてしまう背景に「せっかく時間を取るのだから情報収集したい」「できるだけ早くジャッジしたい」という思いもあるかもしれません。しかし、これは中長期的な採用活動の観点では逆効果になることもあります。候補者との信頼関係を築き、選考に進まなかったとしても好印象を残すことができれば、将来的に再接点を持つことができたり、、別のポジションで声をかける機会が生まれる可能性もあります。だからこそ、短期的な視点ではなく、候補者との関係性構築を第一に考えたスタンスで臨むことが重要になります。
2. ラフすぎないようにする
カジュアル面談は、話しやすい空気感を作ることが重要です。ただし話し方や言葉遣いにも注意が必要です。話しやすい空気感を作ることは大切ですが、敬語が極端に崩れていたり、業界用語を多用しすぎると、候補者が置いてきぼりになる可能性があります。特に他業界から転職を考えている候補者の場合、自社特有の言葉や略語が理解できずに戸惑ってしまうこともあるでしょう。
そのためラフに対応しすぎないという点に注意しましょう。というのも、ラフすぎる振る舞いは、候補者に不信感を与えかねません。たとえば、私服で参加する場合でも、あまりにカジュアルすぎる服装だと、「この会社はビジネスの場としてのけじめがないのでは?」といった印象を持たれる可能性があります。
また時間管理にも注意が必要です。「カジュアルだから少しくらい遅れても大丈夫」と思ってしまうと、候補者側に「軽んじられているのでは?」と不快感を与えてしまいます。開始時間にはきっちりとログイン・到着し、終了時間も守ることで、信頼感を高めることができます。
このように「カジュアル=雑にしてよい」ではありません。むしろ、丁寧な対応をすることで、企業としての信頼感や組織の文化が伝わりやすくなります。候補者に「この会社はカジュアルな場でもしっかりしている」と思ってもらえるよう、プロフェッショナルとしての姿勢を持ちつつ、親しみやすさを演出するバランスが重要になります。
3. 自社のアピールだけにならないようにする
カジュアル面談は、企業が自社の魅力を伝える絶好のチャンスです。しかし、そのことに意識が向きすぎると、一方的にアピールしすぎてしまうリスクが存在することを意識しましょう。たとえば、自社のビジョンや福利厚生、働き方などを一方的に説明し続けてしまうと、候補者は受け身になってしまい、「営業されているようだ」「質問しにくい雰囲気だ」と感じてしまうことがあります。
重要なのは、自社のアピールだけにならないように「対話」をすることです。候補者の興味・関心に寄り添いながら話を進めることで、双方にとって有意義な時間になります。たとえば、「どのような観点で転職を考え始めたのか」「現職で感じている課題はどのようなことか」など、候補者の価値観やキャリア観に関する質問を通して、相手の思考を理解しようとする姿勢を見せることが大切です。
カジュアル面談においては、企業の魅力を伝えることと同じくらい、「候補者にとっての価値ある体験を提供すること」が大切です。一方的なプレゼンではなく、双方向のコミュニケーションを通じて、候補者の心に残るカジュアル面談を目指しましょう。
まとめ|カジュアル面談は中長期の採用活動にとっても重要な取り組み
カジュアル面談とは、企業の担当者と候補者がリラックスした雰囲気の中で相互理解などを深めるという選考以外の目的で行われる面談です。深刻な人材不足、候補者の転職活動スタイルの多様化、そして企業のブランディング戦略の進化していることなど、採用市場の変化に伴って、カジュアル面談を導入する企業が増えています。
カジュアル面談には「企業や組織の魅力訴求」「潜在層へのアプローチ」「候補者の人柄を把握する」といった目的があり、これらを実施することで母集団の量の確保と質を高めたり、ミスマッチを防止するというメリットが存在します。一方で、面談実施数は今まで以上に増えるため対応工数が増えてしまうなどのデメリットも存在します。
カジュアル面談のメリットとデメリットを理解しつつ、自社の採用活動をより良いものにできるように、本記事でご紹介した内容を参考にカジュアル面談の実施を検討してみてはいかがでしょうか。
- ミーティング中は話に集中したいため、メモが取れない
- ミーティング後に話をした内容をまとめるのに時間がかかっている
- ミーティングの発言の温度感やニュアンスを共有したい
このような議事録やメモに関するお悩みがあれば、ぜひ一度AI議事録サービス「Otolio」をお試しください。
Otolioは議事録などのドキュメント作成に関する作業を自動化・効率化することができ、作成時間を最大90%以上削減することが可能です。