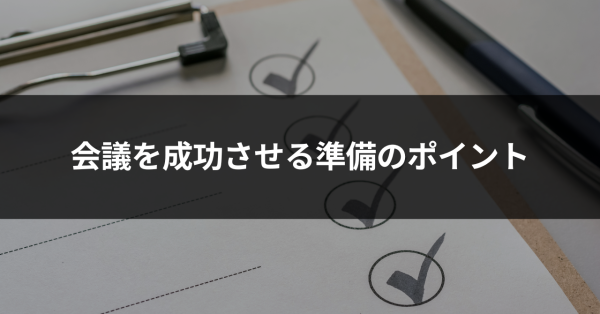フィードバック面談とは?重要性や目的・進め方を6ステップに分けてご紹介

フィードバック面談は、上司と部下が定期的にコミュニケーションをとり、業務に対する評価や課題、今後のキャリアについて話し合う重要な機会です。ただ評価を伝えるだけにとどまらず、社員一人ひとりの成長やモチベーション向上につなげるための「対話の場」として、近年その重要性が再認識されています。
ただ「フィードバック面談って、そもそも何のためにやるのかわからない」「面談の場を設けてはいるけれど、形だけになってしまっている」「伝えたいことはあるけれど、どう伝えれば良いのか迷っている」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、フィードバック面談に課題を感じているマネージャーや人事担当者に向けて、フィードバック面談の目的や進め方、実施時のポイントについてわかりやすく解説します。フィードバック面談をより良くしていきたいという方はぜひ本記事を参考にご覧ください。
- ミーティング中は話に集中したいため、メモが取れない
- ミーティング後に話をした内容をまとめるのに時間がかかっている
- ミーティングの発言の温度感やニュアンスを共有したい
このような議事録やメモに関するお悩みがあれば、ぜひ一度AI議事録サービス「Otolio」をお試しください。
Otolioは議事録などのドキュメント作成に関する作業を自動化・効率化することができ、作成時間を最大90%以上削減することが可能です。
フィードバック面談とは
フィードバック面談とは、上司やマネージャーが部下やチームメンバーに対して、業務の成果や行動に対する評価・意見を伝え、今後の改善や成長に向けたアドバイスを行う一対一の対話の場を指しています。多くの場合、人事評価のタイミングで実施されますが、定期的に行うことで、継続的な成長支援やモチベーション維持にも効果があります。
フィードバック面談では、ただ業績評価を伝えるだけでなく、「なぜその評価に至ったのか」「どのような点を評価しているのか」「改善のためにどのような行動が期待されているのか」といった、背景や具体的なアドバイスを丁寧に伝えることが重要です。これにより、メンバーは自身の行動や成果について納得感を得やすくなり、次の行動に移しやすくなります。
また、フィードバック面談はチームや組織の課題を発見する機会でもあります。面談を通じて「この業務プロセスに無駄がある」「チーム間で連携がうまくいっていない」といった現場のリアルな声を吸い上げることも可能です。
このように、フィードバック面談は従業員の成長を促すと同時に、組織としての課題発見・改善にも役立つ、非常に重要なコミュニケーション手段です。実施する目的や進め方をしっかりと理解し、意味のある面談を行うことが、組織全体の成長にも繋がるといえます。
フィードバック面談が重要な3つの理由
では次により具体的にフィードバック面談が重要な理由をご紹介します。ここでは代表的な理由を3つご紹介します。
1. パフォーマンス向上に繋がる
フィードバック面談が重要とされる最も大きな理由のひとつは、従業員のパフォーマンス向上に直結する点です。業務に対して上司からフィードバックを受けることで、本人が自覚していなかった課題や、伸ばすべき強みに気づくことができます。特に、自身では「当たり前」と思っていた行動や思考のクセが、実はチームに大きな価値をもたらしていたり、逆に負担をかけていたりするケースも少なくありません。第三者の視点を取り入れることで、日々の業務に対する客観的な評価が得られ、改善すべきポイントが明確になるのです。
また、フィードバック面談では単なる注意や指摘にとどまらず、今後のアクションや具体的な改善方法についても対話を通じて整理できます。これにより、従業員は自分の成長に対して前向きな気持ちを持ちやすくなり、結果として主体的な行動が生まれやすくなります。重要なのは、面談を通じて「成長を後押ししてくれる場」とメンバーが捉えることです。その意識づけこそが、フィードバック面談の効果を最大化するポイントとなります。
2. 人材の定着率を高める
人材の定着率を高めることは、企業の持続的成長において極めて重要です。優秀な人材が短期間で離職してしまうと、採用や育成にかけたコストが無駄になるだけでなく、組織のノウハウやチームワークも損なわれてしまいます。そうした中で、フィードバック面談は従業員との信頼関係を築き、離職リスクを低減する有効な手段の一つです。
フィードバック面談では、ただ業績やスキルについて話すだけでなく、上司が部下の悩みや不安に耳を傾ける貴重な機会でもあります。「自分のことを気にかけてくれている」「会社が自分の成長を本気で応援してくれている」と感じてもらえることで、心理的な安全性が高まり、エンゲージメントの向上にもつながります。このような関係性の構築は、特にリモートワークや多拠点での勤務が一般化する現代において、これまで以上に重要性を増しています。
また、フィードバック面談を継続的に実施することで、従業員がキャリアの中長期的なビジョンを描きやすくなるという効果もあります。たとえば「将来こうなりたい」という目標が共有されていれば、組織としても適切なアサインや育成機会を提供しやすくなります。このような「成長の道筋」が見えることで、従業員は組織との未来に希望を持ちやすくなり、離職の抑止力となるのです。
3. 課題を早期に発見できる
フィードバック面談は、組織や個人が抱える課題を早期に察知し、対処するためのセンサーのような役割も果たします。多くの問題は、表面化するまでに時間がかかり、深刻化してから発覚することも少なくありません。フィードバック面談を定期的に行い、日頃の悩みや違和感を対話の中で拾い上げることができれば、問題が顕在化する前に対策を打つことが可能になります。
たとえば、「最近モチベーションが上がらない」「チーム内で連携がうまくいっていない」といった小さな声も、フィードバック面談であれば拾うことができます。これらの声は、放置すれば生産性の低下や人間関係の悪化につながるリスクがありますが、早いタイミングでキャッチができれば、業務の調整やチームビルディング施策の見直しなど柔軟な対応が可能です。
また、フィードバック面談は「表に出づらい課題」を拾うこともできます。たとえば、特定の業務でツールが使いにくい、マニュアルが分かりづらいといった現場レベルの細かな不満は、日常業務の中では見過ごされがちですが、面談での対話を通じて明るみに出すことができます。これにより、業務改善や環境整備のスピードが格段に上がり、従業員の働きやすさ向上にもつながります。
フィードバック面談を実施する3つの目的
次にフィードバック面談を実施する主な3つの目的についてご紹介します。
1. 評価結果を共有する
フィードバック面談を実施する第一の目的は、上司から部下へ評価結果を正しく共有することです。これは、評価制度が形骸化しないためにも非常に重要なプロセスです。ただ評価を一方的に伝えるのではなく、なぜその評価に至ったのかという背景や根拠をしっかりと説明することで、納得感のあるフィードバックが可能になります。
たとえば、定量的なKPIの達成状況だけでなく、チーム内での役割や姿勢、他者への貢献度といった定性的な側面についても言語化して伝えることで、メンバーは自身の強みや改善点を立体的に理解できます。また、面談は評価の透明性を担保する場でもあります。
特に複数の評価者が関与している場合、どのような視点で評価されたのか、どのフィードバックが誰からのものなのかを可能な範囲で明確にすることで、相手との信頼関係を築きやすくなります。さらに、評価結果を共有することで、評価基準に対する認識のすり合わせも行えるため、次回の評価に向けた行動の指針を共有する意味でも有効です。
2. 課題解決を話し合う
フィードバック面談のもう一つの重要な目的は、目の前の課題や問題に対して、上司と部下が対話を通じて解決策を模索することです。これは一方的な指導ではなく、あくまで双方向のやりとりによって進めるべきものです。現場で発生している業務上の課題や、メンバーが抱えている悩みを深堀りし、具体的な打ち手や支援策を共に考える場として活用します。
たとえば、「最近モチベーションが下がっている」「業務量が多すぎて成果に繋がらない」といった漠然とした悩みも、丁寧に掘り下げていけば、ボトルネックや根本原因が明確になります。上司の側からも、業務の優先順位を見直す、負荷を軽減する、他メンバーと役割を調整するなど、具体的なアクションに繋げられます。
このようなフィードバック面談を通じた現場からの課題は、実は組織構造や業務プロセスそのものにあるケースも少なくありません。こうした場合、フィードバック面談を通じてより上位レイヤーへ課題を伝えるきっかけにもなり得ます。つまり、フィードバック面談は個人の課題から組織課題へと視野を広げる場でもあるのです。
3. キャリアプランを検討する
フィードバック面談の最後の目的は、メンバーの中長期的なキャリアについて話し合うことです。普段の業務ではなかなか話題に上がらないテーマですが、フィードバック面談の場だからこそ、将来の志向や希望を聞き出す絶好のタイミングになります。
たとえば、「今後マネジメントに挑戦したい」「もっと専門性を磨きたい」「他部署への異動に興味がある」といった本人の想いや展望を把握しておくことで、現業務のアサインや教育の方向性を調整できます。また、本人も「自分のキャリアを会社が一緒に考えてくれる」と感じることで、エンゲージメントの向上にも繋がります。
さらに、キャリアプランの検討は、離職リスクの低減にも寄与します。上司との対話を通じて「今のままで良いのだろうか」「将来に不安がある」といった漠然とした悩みを言語化できる場となり、早いタイミングでの対処が可能になります。
また、本人がまだキャリアについて明確なビジョンを持っていない場合も、対話の中で選択肢を提示したり、他メンバーの事例を紹介することで、視野を広げるサポートができます。特に若手や入社間もない社員にとっては、自分のキャリアを言語化する機会そのものが成長のきっかけになることも多いのです。
フィードバック面談の進め方6ステップ
フィードバック面談を効果的に行うには、明確なステップに沿って進めることが重要です。ここでは、初めて面談を行う人でも実践できるよう、6つのステップに分けて解説します。
1. フィードバック内容を整理する
フィードバック面談の前にまず、伝えたいフィードバックの内容を整理するようにしましょう。評価項目ごとに良かった点と改善が必要な点を明確に書き出します。このときに重要なのが、事実を根拠にまとめていくことです。感情や主観に偏った内容になってしまうと、受け手が納得感を得ることができず、せっかくのフィードバック面談が、逆効果になる可能性があります。
また、このときにその従業員の特性や過去のフィードバック履歴も振り返るようにしましょう。これにより、一貫性のある指摘や、成長の積み上げが伝えられるようになります。たとえば「昨年は○○に苦手意識があったけど、今回の○○の業務ではこう成長したね」といったように、成長の軌跡を踏まえたコメントは、モチベーション向上にもつながります。
2. 自己評価をしてもらう
フィードバックする内容を整理した後は、早速フィードバック面談を実施しましょう。フィードバック面談の冒頭では、まずこちらからいきなりフィードバックを伝えるのではなく、相手に自己評価をしてもらいます。自己評価によって、自身の成果や課題をどう捉えているのかが可視化され、上司との認識のズレを確認するきっかけにもなります。
ここでポイントになるのは、ただ相手の自己評価を聞くのではなく「どの仕事にやりがいを感じたか」「思うように成果が出なかった理由は何か」といった問いかけをすることです。これにより、より内省的なコメントを引き出すことができ、フィードバックの質が高まります。さらに、本人の言葉を尊重する姿勢は、心理的安全性の醸成にもつながり、面談の満足度も高まります。
3. フィードバック内容を伝える
自己評価を受けた後、整理しておいたフィードバックを伝えるようにしましょう。ここでは、ポジティブな点と改善点の両方をバランスよく取り上げることが重要です。特に改善点は、頭ごなしに否定するのではなく、「このようにすればさらに良くなる」という成長支援のスタンスで伝えることが重要です。
また、フィードバックを伝えるときには、伝えた内容がどう受け取られているかを適宜確認することも大切です。たとえば「今の話、どう感じましたか?」といった投げかけをすることで、相手の理解度や納得度を確認しながら進められます。
4. 課題の解決について話し合う
フィードバックを伝えた後は、改善点をどう乗り越えていくか、ポジティブな点をさらに伸ばすためにはどうするかを一緒に考えるステップに入ります。このときに、実現可能なアクションやサポート方法を共に話し合うことで、社員が前向きに取り組む土台を作ることができます。
たとえば「プレゼンが苦手」といった課題があれば、「月に一度、チーム内でのミニ発表会を設けるのはどうか」「OJTの機会を増やすのがよいか」といった具体的な打ち手を提案し、選択肢を一緒に検討していくとよいでしょう。
また、ここでは「誰が何をどうサポートするか」といった役割分担も明確にしておくと、課題解決が行動レベルに落とし込まれ、形骸化を防ぐことができます。さらに、本人の思考だけでなく、職場環境や制度面に課題がある場合も多いため、視点を広く持って対話することが重要です。
5. キャリアプランについて話し合う
フィードバック面談の最後に、従業員のキャリアプランについても話し合うようにしましょう。フィードバック面談は、評価や課題だけでなく、社員の将来について対話する重要な場でもあります。目の前の業務だけでなく、中長期的なキャリアの方向性を共有することで、本人の目標意識が高まり、エンゲージメントの向上にもつながります。
たとえば、「3年後にどんな仕事をしていたいか」「今の経験がその目標にどうつながるか」といった問いを投げかけることで、普段の業務では話しにくい将来像を引き出すことができます。また、本人が考えていないような選択肢や、社内での新しいロールなどを提示することで、意欲や視野の広がりを促せることもあります。
こうした対話は、上司にとっても社員の志向やモチベーションを理解する手がかりとなり、人材配置や育成計画にも活かせます。形式的な面談ではなく、互いに未来を描く時間として活用することが、キャリア面談としての価値を高めるポイントです。
6. ドキュメントに記録を残す
フィードバック面談が終わったら、話をした内容や今後のアクションプランについて、必ず記録に残すようにしましょう。この記録は、次回以降のフィードバック面談や、上司・人事間での情報共有に役立ちます。また、従業員本人が自分の成長過程を振り返る資料としても機能します。
記録には、ただ評価結果を記載するだけでなく、「どんな点に共感していたか」「どこに課題を感じていたか」といった、対話のニュアンスも盛り込むとよいでしょう。これにより、形式的な記録にとどまらず、次回の面談でのつながりが生まれ、継続的なフィードバックサイクルが形成されます。
さらに、記録を共有する際には、社員本人にも確認してもらい、相互に納得した状態で保存することが理想です。形式を整えることが目的ではなく、継続的な成長支援の基盤とすることが、記録の最大の意義といえるでしょう。
とはいえ記録だけでは、実際のニュアンスを理解するのに限界があります。ニュアンスを理解するためにそのときの発言を聞きたいという場合は、フィードバック面談の音声をピンポイントで聞き直すことができるAI議事録ツールの活用も検討しましょう。AI議事録ツールについて詳しく知りたい方は、以下の記事でご紹介しているので、ぜひ参考にご覧ください。
フィードバック面談で意識したい3つのポイント
フィードバック面談をただステップに沿って進めるだけではなく、以下の3つのポイントも意識してより効果的なフィードバック面談を実施しましょう。
1. 事実を根拠に伝える
フィードバック面談では、感情や印象ではなく、客観的な事実をもとに伝えることがとても重要です。たとえば「最近やる気がないように見える」という表現は主観的であり、相手に防衛的な反応を引き起こしてしまう可能性があります。このような表現ではなく「今まで発言があったのに、直近3回の定例会議で発言がなかったことに気づいている」といった具体的な事実を根拠に伝えることで、相手も納得しやすくなります。
また、事実に基づいたフィードバックは、受け手が自ら改善の余地を認識しやすくなるという効果もあります。人は他者の主観よりも、自分が実際に取った行動や数字といったデータの方を信頼する傾向があります。したがって、業務報告やKPIなどの記録をもとに、具体的な改善点を伝えると説得力が増します。
さらに一歩踏み込んだ観点として、事実を根拠にすることは、マネジメント側の思い込みや偏見に気づくきっかけにもなります。たとえば「この人はミスが多い」と感じていても、実際に記録を確認すると他のメンバーと大差ないということもあります。事実ベースで会話を組み立てることで、上司側の先入観にもブレーキがかかり、公平で健全なコミュニケーションを促進させることが可能です。
2. メンバーの成長が前提であることを意識する
フィードバック面談は評価を下す場ではなく、成長を促す機会であるという意識を持つことが欠かせません。ただ過去の行動を指摘するだけでは、相手に「ダメ出しされた」と感じさせてしまい、かえってモチベーションを下げるリスクがあります。重要なのは、フィードバックが「成長のきっかけ」となるような前向きな意図で行われるべきだということです。
そのためには、指摘にとどまらず「今後どうすればよくなるか」まで話すことが効果的です。たとえば「報告が遅れることが多い」という指摘をする場合には、「タスク管理の方法を一緒に見直してみようか」「報告用のテンプレートを整備してみよう」といった解決方法を具体的に提案することで、建設的な話し合いに変わります。
また、メンバーによって成長の方向性やスピードは異なるため、その人の特性やキャリア志向に合わせたフィードバックを心がけることも大切です。「もっとリーダーシップを発揮してほしい」という言葉も、人によってはプレッシャーになってしまうケースがあります。そこで、まずは小さな範囲で任せてみる、あるいは一緒に進めることで自信をつけてもらうなど、段階的なアプローチも検討するようにしましょう。
3. 対話を意識する
フィードバック面談は「伝える場」ではなく「話し合う場」であるという意識を持つことが重要です。一方的に意見を伝えるだけでは、相手にとって「評価されるだけの時間」となり、改善の糸口を見出すことが難しくなってしまいます。むしろ、相手の考えや感じていることを引き出しながら進めることで、より実効性のあるフィードバックが可能になります。
そのためには、質問を交えて進める姿勢が効果的です。たとえば「この点についてはどう感じている?」「何か原因に心当たりはある?」といった問いかけを通じて、相手の内省を促し、自分自身の行動や状況を客観視してもらうことができます。また、相手の話に対しては適度に相槌や要約を入れることで、しっかりと受け止めていることを示し、信頼関係の構築にも繋がります。
さらに、対話の姿勢には、マネージャー自身が学ぶ姿勢を持つという側面も含まれます。「どうすればもっと働きやすくなるか」「私の関わり方で改善できることはあるか」といった視点で、フィードバックを双方向の成長の機会として捉えることができれば、面談は単なる業務評価を超えた価値を持つ時間になります。
まとめ
フィードバック面談は、ただ結果を伝える場ではなく、部下の成長を支援する場です。フィードバック面談は従業員のパフォーマンス向上、人材の定着率の向上、課題を早いタイミングで発見できるなどの効果があるため、その重要性が増しています。
フィードバック面談には評価結果を共有するという目的だけではなく、課題解決を話し合う、キャリアプランを検討するなど、様々な目的を含んでいます。本記事ではそんなフィードバック面談の重要性から目的、進め方と意識するポイントについてご紹介しました。意味がある、より良いフィードバック面談にするためにも、ぜひ本記事でご紹介したステップやポイントを参考にしてみてください。
- ミーティング中は話に集中したいため、メモが取れない
- ミーティング後に話をした内容をまとめるのに時間がかかっている
- ミーティングの発言の温度感やニュアンスを共有したい
このような議事録やメモに関するお悩みがあれば、ぜひ一度AI議事録サービス「Otolio」をお試しください。
Otolioは議事録などのドキュメント作成に関する作業を自動化・効率化することができ、作成時間を最大90%以上削減することが可能です。