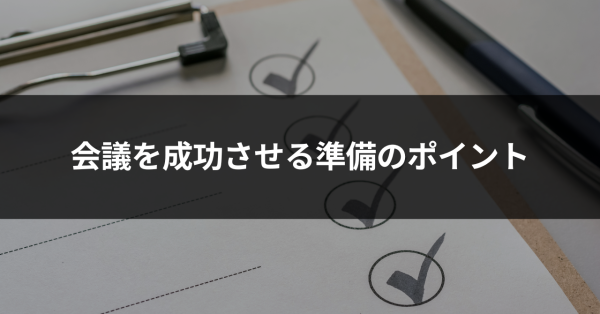【企業向け】内定者面談とは?目的や確認・注意するポイントも紹介

企業が優秀な人材を確保し、長期的に活躍してもらうためには、採用活動だけでなく、内定後に候補者のフォローアップを実施することがとても重要です。そんな中でも企業が内定を通知した人材に対して、入社前に個別で実施する「内定者面談」は、その後の入社・定着・活躍に大きな影響を与える大切なプロセスの一つとなっています。
本記事ではそんな「内定者面談」について幅広くご紹介します。「内定者面談をどのように進めればいいか分からない」「内定者面談を実施するうえで、どのようなことに気をつければいいのか」「内定者面談を企業として取り組むうえで目的を整理しておきたい」など内定者面談について、詳しく知りたい方は、ぜひ本記事をご覧ください。
- ミーティング中は話に集中したいため、メモが取れない
- ミーティング後に話をした内容をまとめるのに時間がかかっている
- ミーティングの発言の温度感やニュアンスを共有したい
このような議事録やメモに関するお悩みがあれば、ぜひ一度AI議事録サービス「Otolio」をお試しください。
Otolioは議事録などのドキュメント作成に関する作業を自動化・効率化することができ、作成時間を最大90%以上削減することが可能です。
内定者面談とは
内定者面談とは企業が内定を通知した人材に、入社前に個別で実施する面談のことです。この面談は採用選考の延長ではなく、あくまで内定後のフォローアップを目的としたものであり、相互理解を深めたり、不安を解消したりするために行われます。形式としては、1対1で行われることが一般的ですが、場合によっては複数の社員が同席したり、オンラインで実施されたりすることもあります。
企業にとっても内定者面談を実施することは、内定者のパーソナリティや価値観をより深く知ることができるとても貴重な機会です。また内定者にとっても、事前に不安や疑問に感じていることを解消できるなど、双方にとってメリットがある面談となっています。
内定者面談を行う4つの目的
内定者面談は、ただ入社前に内定者と面談を実施すればいいわけではありません。内定者面談をより良く実施するためにも目的の設定が重要になります。ここではそんな内定者面談を実施する目的を4つご紹介します。
1. 入社意思を再確認する
内定者面談を行う最大の目的の一つが、内定者の「入社意思」を再確認することです。選考が終わり、内定を出した後であっても、入社までの期間にはさまざまな心境の変化が起こります。たとえば他社からの内定や新たなキャリアの選択肢が出てくる、自分のキャリアへの再考など、内定承諾時点では想定していなかった状況が発生することも少なくありません。
このような背景から、内定者が本当に入社を希望しているのかを改めて確認する機会として、内定者面談はとても重要な面談となります。特に、内定者が自ら内定の辞退を申し出る前に、企業側が早期にサインをキャッチし、適切な対応を取ることができれば、採用計画や配属計画への影響を最小限に抑えることが可能になります。
2. 入社予定者の不安や疑問点を解消する
内定を出してから、入社までに数ヶ月の期間が空いてしまう場合、その間に内定者のモチベーションが低下したり、不安が膨らんだりすることが少なくありません。というのも、内定者にとって新しい環境に入社するという状況は人生の大きな環境変化です。
実際の仕事内容、人間関係、働き方、ワークライフバランス、将来のキャリアパスなど、入社前には分からないことばかりで、漠然とした不安を抱えていることがあります。こうした心理的な不安をそのままにしておくと、入社辞退や早期離職のリスクが高まる可能性があります。
そこで、面談を通じて直接内定者と対話し、何に対して不安を感じているのかを丁寧にヒアリングすることが重要です。例えば、「今、一番不安に思っていることは何ですか?」とストレートに聞いてみることで、内定者が話しやすくなるケースもあります。また、現場社員との座談会形式を取り入れることで、よりリアルな声を届けることができ、より具体的に自分の入社後のイメージを持つことができるようになるため、不安が解消されるケースもあります。
また、内定者の中には「不安を持っていること自体がよくない」と考え、悩みを打ち明けづらく感じている人もいます。こうしたケースでは、「みんな最初は不安を感じるものだよ」といった共感の姿勢を示すことで、相手の心理的なハードルを下げることができます。面談を通じて内定者の不安や疑問を丁寧にすくい上げ、個別に対応することは、結果的に内定者のエンゲージメントを高め、入社後の定着率向上にも繋がるため、内定者面談は「入社予定者の不安や疑問点を解消する」という目的を達成するためにも重要な面談です。
3. 企業理解を深めてもらう
内定者面談は、企業側が一方的に情報を得る場ではなく、内定者に企業の理解を深めてもらう絶好の機会でもあります。多くの企業が採用活動で企業説明会やWebサイト、パンフレットなどを通じて情報提供を行っていますが、実際には内定者の企業理解は浅い場合もあります。特に選考過程が短期で終わった場合や、オンライン中心の選考であった場合には、その傾向が高まりやすい傾向があります。
この状態を解決するためにも、内定者面談で「企業理解を深めてもらう」ことが重要です。たとえば、面談で、改めて企業のビジョンやミッション、バリュー、カルチャー、事業戦略などを丁寧に説明することで、内定者の理解を深めることが可能になります。ここでのポイントは単に情報を伝えるのではなく、内定者の関心や疑問に応じてカスタマイズしながら説明することで、情報がより主体的に理解されるようになります。
また、企業理解を深めるためには「企業のリアルな姿」を見せることも重要です。成功事例や表面的なポジティブな面だけでなく、現在抱えている課題や、仕事の中で大変なことなども正直に伝えることで、入社後のギャップを減らすことが可能になります。こうしたポジティブではない情報を伝えることは、企業の誠実さを伝えるだけでなく、内定者にとっても自身の価値観や適性とのすり合わせに役立ちます。
4. 配属や育成方針の検討材料を収集する
内定者面談は、内定者の入社後の配属先や育成方針を検討するための情報を得るための貴重な機会でもあります。採用活動や選考の段階では把握しきれなかった内定者の価値観やスキル、志向性をより深く理解することで、適切な配属や育成方針を決めることが可能になります。
たとえば、同じ職種の内定者であっても、「じっくりと一つの分野を掘り下げたいタイプ」もいれば、「多くの経験を積みたいタイプ」もいます。他にも、将来的にマネジメントを志望する人、専門性を追求したい人のようにそれぞれのキャリアの志向性は異なり、この情報によって企業としての最適なアプローチも異なってきます。
さらに、入社直後に内定者に最大限活躍してもらうためにも、どのポイントが苦手なのかを予測することも重要で、内定者面談はこれらの情報を収集するうえでも活用できます。たとえば、「人前で話すのが苦手」「マルチタスクが苦手」といった特性を把握しておくことで、育成担当者が入社後に配慮すべき点が見えてきます。これは、早期の離職防止にもつながる重要な視点です。
内定者面談を通じて得られる情報は、入社後の活躍を支える土台となります。人材を「配置する」のではなく、「活かす」ための第一歩として、面談の場を最大限に活用するようにしましょう。
内定者面談を実施するまでの5ステップ
では具体的にどのような進め方で内定者面談を実施するか、悩まれている方も多いと思います。ここでは内定者面談を実施するまでの流れを5つのステップに分けてご紹介します。
1. 面談の目的・ゴールを決める
内定者面談を行うにあたって、まず最初に取り組むべきなのは「この面談を通じて何を達成したいのか」という目的とゴールの明確化です。これは、単なる雑談や形式的な顔合わせで終わらないようにするためにも重要なステップです。先ほどご紹介した4つの目的を参考に、企業理解を深めるのか、不安を解消するのか、入社意思を再確認するのか、企業ごとの人材戦略や内定者の特性に応じて、目的は変わってきます。
たとえば「入社前の離脱リスクを下げること」を目的とするのであれば、本人の不安や疑問を解消するような面談設計が必要です。その他にも「配属のマッチ度を高めること」が目的ならば、本人の志向や価値観を深掘りするような質問を用意することになります。このように目的次第で準備や内定者面談で話をする内容が変わるため、まずは面談の目的とゴールを明確にするようにしましょう。
2. 内定者面談の開催時期を決める
次に重要なのが「いつ面談を実施するのか」という開催時期を決めることです。内定者面談は早すぎても、遅すぎても適切な効果を得ることが難しく、タイミングを見極めることが重要です。
よくあるケースとして、内定通知から1〜2ヶ月以内、もしくは年内に1回、年度末にもう1回といった形で複数回に分けて実施するケースが一般的です。内定通知直後は、企業や仕事に対する期待感が高まっている一方で、他社の選考を続けているケースがあるため、このタイミングでの面談は、企業へのロイヤルティを高める絶好の機会となります。
一方で、あまりに内定者面談の時間が空いてしまうと、内定者の関心が薄れたり、他社の内定先との比較の中でモチベーションが変化したりする可能性もあります。そのため、面談は内定者の心理的なタイミングや就職活動の進捗も踏まえて柔軟に設計することが重要です。
また複数回、内定者面談を予定する場合は、それぞれの回の目的やゴールも事前に明確にするようにしましょう。たとえば、1回目はキャリア観や価値観の共有、2回目は配属希望や働き方の確認など、ステップごとに目的やゴールを変えることで、内定者にとっても「この会社は自分のことをちゃんと見てくれている」という信頼感につながります。
3. 社内の担当者を決める
次に目的やゴールに沿って、社内の担当者を決めるようにしましょう。内定者面談を成功させるためにも、「誰が内定者面談を担当するのか」という人選はとても重要です。というのも、人事担当者だけでなく、現場の社員やマネージャー、あるいは役員クラスまで、関わる人物によって内定者の受け取る印象は大きく変わります。
まずは、面談の目的やゴール、実際に話しをする内容に応じた適切な担当者を選定するようにしましょう。たとえば、企業全体のビジョンや方針を伝える必要があるなら経営層が適任になります。その他にも、配属予定部署の仕事内容や職場環境についてのリアルな話を伝えるのであれば、現場社員が最も効果的です。
また社内で内定者面談に関わる全メンバーに対して、内定者面談の意義や全体方針をしっかり共有しておくことも忘れてはなりません。バラバラな対応になってしまうと、内定者に「この会社はまとまりがない」といった不信感を与えてしまう可能性があります。内定者面談の一貫性と質を担保するためにも、しっかりと社内で情報を共有するようにしましょう。
4. 資料や質問の準備をする
次に実際に内定者面談の場で使用する資料や質問への準備をするようにしましょう。ここでいう「質問」は企業から内定者への質問ではなく、内定者から企業への質問になります。というのも、 内定者面談の場で使用する資料や、面談時に投げかける質問の内容は、企業がどれだけ真摯に内定者を迎え入れようとしているかを示す重要な要素となります。
資料は、会社概要や事業内容、組織構成、内定者が配属予定の部署に関する説明資料を用意するだけではなく、一歩踏み込んだ内容として、実際の業務フローや、配属後に携わる可能性のあるプロジェクトの事例紹介を含めると、内定者はよりリアルな職場イメージを持つことができます。また、先輩社員の一日のスケジュールや、仕事のやりがい・大変さについてのコメントのような、リアリティを持った情報も資料として紹介することで内定者の不安を払拭する可能性があります。
さらに、資料はできる限り「読み物」ではなく「対話のきっかけ」として設計するのが理想的です。たとえば、資料の中に問いかけや選択肢を盛り込んでおくと、内定者との対話が自然に生まれることがあります。「このプロジェクトの中であなたが特に興味を持った点は?」「どのような働き方が自分に合っていると思いますか?」といった、本人の考えを引き出す導入になるように資料を設計するようにしましょう。
また企業側からの質問については、単なる履歴書の再確認ではなく、内定者の価値観やキャリアビジョン、企業文化とのマッチ度を引き出すような質問が効果的です。たとえば、「これまでの学生生活で特に成長を感じた瞬間は?」「将来どんな社会人になっていたい?」といったオープンな質問は、内定者の本音を引き出すきっかけになります。
内定者面談における資料と質問の準備は、単なる情報共有ではなく「対話の質を高めるための土台作り」と考えるようにしましょう。
5. 内定者面談を実施する
今までご紹介した準備が整ったら、いよいよ内定者面談を実施します。ここでは、面談そのものの進行だけでなく、面談後のフォローも含めた面談の全体の体験の質が重要になります。特に内定者が「この会社に入社して本当に良かった」と思ってもらえるかが重要です。
そのためにも、面談当日の雰囲気作りが大切です。内定者は多かれ少なかれ緊張しています。その緊張を和らげるために、笑顔で迎える、軽い雑談からスタートする、自己紹介の時間を設けるなど、最初の5分間の空気感がその後の会話の質を左右します。
また面談の進行は、あらかじめ決めていた流れに沿って進めつつも、柔軟性を持たせることが大切です。内定者の発言に耳を傾け、気になったことは随時深掘りをすることで、より質の高い対話が生まれます。面談の中では、準備した資料や質問を活用しますが、一方的に説明するのではなく、双方向のやり取りを意識するようにしましょう。「この資料を見て、どんな印象を持ちましたか?」「ここまでの話で不安に思う点はありますか?」といった問いかけが、内定者の本音を引き出す助けになります。
面談が終わった後は、必ずお礼とフォローを忘れずに行いましょう。感謝のメールを作業のように送るのではなく、「本日の面談で伺ったこういう話がとても印象的でした」といった一文を添えることで、内定者に対して個別に向き合っている姿勢が伝わります。また、面談を通じて出てきた質問や不安に対して、改めて社内で確認し、数日以内にフィードバックを返すようにすると、誠実な印象を残すことができます。
そして最後に、面談を通じて得た内定者の情報や声を、配属先や人事部門と共有し、今後のコミュニケーションや育成方針に活かしていくことで、組織全体としての「迎え入れ体制」が強化されていきます。
もし内定者面談の中で議事録やメモを作成するのが難しいという方は、面談中の音声を録音し、そのときの音声を共有できる、かつ文字起こしをしてAIが自動でまとめてくれるAI議事録ツールの導入も検討してみましょう。AI議事録ツールについて詳しく知りたい方は以下の記事で詳しくご紹介しているので、ぜひ参考にご覧ください。
内定者面談で確認すべき3つのポイント
では次に具体的に内定者面談でどのようなことを確認すべきか、3つのポイントに分けてご紹介します。
1. 活動状況
まずは活動状況を確認するようにしましょう。ここでいう活動状況は、就職活動にとどまらず、今までの学生生活や勉強状況、中途採用者であれば今までの実施してきた業務などを含みます。これらの情報を把握することで、入社前の過ごし方を理解することができ、入社後の準備状況や、業務へのスムーズな移行ができるかを見極めることができます。
ここで注意すべきなのは「活動状況」のヒアリングが、単なる事実確認ではなく、対話を通じた関係構築の一環であるという点です。活動を聞く中で、内定者の考え方や価値観、物事への取り組み姿勢など、表面的な情報では見えない一面を知ることができます。
2. 入社時の疑問や不安に感じていること
内定者面談では「入社時の疑問や不安に感じていること」を確認するようにしましょう。内定を得ることはつまり、新しい環境に飛び込むことになるため、少なからず不安を抱えています。その不安を言語化し、企業側が真摯に受け止めることが、早期離職を防ぎ、入社後の定着率を高める第一歩となります。
ここで大切なのは、不安を「払拭する」ことだけを目的としないという点です。不安を聞き出し、共有すること自体が、内定者にとっては安心材料になります。企業としても、どのような情報が足りていないのか、どのような説明の仕方に課題があるのかを知る機会にもなります。面談を通じて、双方向のフィードバックの場として捉えることで、よりよい内定者面談を実施することができます。
3. 将来のキャリアややりたいこと
最後に「将来のキャリアややりたいこと」も確認するようにしましょう。内定者がどのような未来像を持っているのか、何を目指して入社を決めたのかを知ることは、企業側にとっても非常に価値のある情報です。
多くの企業では、入社後の配属やキャリアパスは本人の適性や希望を加味しながら決定します。そのため、内定者自身のキャリア観を把握することは、その後の配置や育成方針を考える上で欠かせません。また、入社時点での志向はあくまで「そのときに考えているキャリア」であることを前提に、柔軟に受け止めることが大切です。固定されたものでなくても、「こんなふうになりたい」「こんな仕事をやってみたい」というレベルの話でも、十分に意味があります。また内定者を理解する上で「やりたくないこと」や「避けたいキャリア」についても聞くようにしましょう。ネガティブに捉えられがちですが、むしろ本人の価値観や志向を明確に理解する手がかりになります。
内定者面談で注意したい4つのポイント
内定者面談を成功させるためにも以下の4つのポイントに注意するようにしましょう。
1. 一方的な情報提供にならないようにする
内定者面談は、企業から内定者への情報提供の場と捉えられがちですが、それだけに留めてしまうと、非常にもったいない機会になってしまいます。確かに、入社後の業務内容や人事制度、キャリアパスなどを伝えることは重要ですが、一方的な説明ばかりになってしまうと、内定者は受け身の姿勢に留まり、本音や疑問を表に出しづらくなってしまいます。面談は「説明会」ではなく「対話の場」であるという意識が重要です。
今までご紹介したとおり、企業にとっても、内定者の不安や期待、価値観を知ることは、今後のフォローや配属検討の材料として、とても重要な情報になります。たとえば、将来的にどのようなキャリアを描きたいのか、働き方に対してどのような希望を持っているのかを聞くことで、ミスマッチの防止にもつながります。そのため内定者面談を実施するときは、できるだけ一方的な情報提供にならないようにしましょう。
2. 正しい情報を伝える
内定者面談では、企業に関する情報を正確に伝えることがとても重要です。特に入社後に「聞いていた話と違う」と感じさせてしまうと、早期離職やモチベーションの低下につながる可能性があります。企業としての誠実な姿勢を示すためにも、よく見せようと誇張したり、ネガティブな情報を隠したりするのは避けて、正しい情報を伝えるようにしましょう。
たとえば、「残業はほとんどありません」と曖昧に伝えるのではなく、「平均残業時間は月10時間ですが、時期によっては忙しくなり、10時間を超える部署や月間もあります」といった具体的なデータとともに説明することで、誤解を防ぐことができます。また、制度としては存在しているが実際には活用されていない福利厚生についても、実情を率直に伝えるなどが、正しい情報を伝えて、ミスマッチを防ぐようにしましょう。
3. 圧迫感がないようにする
内定者面談を成功させるためには、内定者にリラックスして臨んでもらうことが重要です。そのため圧迫感がない面談をするようにしましょう。本人が圧迫感を与えるつもりがなくても、形式ばった言葉遣いや一方的な質問攻め、無表情なリアクションなどは、内定者からすれば、圧迫感を感じてしまう可能性があります。
これを防ぐためにも、内定者面談を実施する担当者の表情や相槌、相手の話を聞こうとする姿勢が重要になります。またそもそも、圧迫感を与えないカジュアルなスペースで内定者面談を実施するのも有効です。
内定者が「きちんと聞いてもらえている」と感じることができて、信頼感の醸成につながり、結果としてより質の高い内定者面談を実施することができるようになります。
4. 企業として一貫性を持たせる
内定者面談では、複数回実施することも多く、そこで登場する担当者によって伝える内容やスタンスにばらつきが出てしまうことがあります。たとえば、人事部門では「風通しの良い組織」をアピールしているのに、現場のマネージャーは「指示通りに動いてもらいたい」と話してしまうと、内定者に混乱を与えてしまう可能性があります。またこうした情報の不一致は、「信頼できない会社」という印象を与えるリスクに繋がってしまいます。
このような状況を避けるためには、面談の目的や伝えるべきメッセージについて、社内で事前にしっかりとすり合わせておくことが重要です。面談のマニュアルを用意したり、担当者向けの簡単なガイドラインを作成したりすることで、基本的な軸を共有することが可能です。また内定者面談を実施したあとに、その面談でどんな話をしたのか、他の担当者に共有するのも有効です。
まとめ
内定者が入社後に活躍し、定着してもらうためには、採用後のフォローがとても重要です。その中でも「内定者面談」は、入社前の不安を解消し、企業理解を深め、将来の活躍を後押しする重要な機会となります。面談では入社意思の確認や不安のヒアリング、価値観やキャリア志向の把握を通じて、内定者と企業の相互理解を深めることができます。
また、配属や育成方針の検討材料としてもとても有効であり、面談で得た情報をもとに個別最適な対応を取ることで、早期離職の防止にもつながります。面談の質を高めるためには、目的の明確化、適切な時期の設定、担当者の選定、資料と質問の準備、そして面談後の丁寧なフォローが大切です。
内定者面談は単なる形式的な場ではなく、双方向のコミュニケーションを通じた「対話の場」として位置づけ、誠実で一貫性のある対応を心がけましょう。内定者面談は、内定者を「迎え入れる」だけでなく、「活かす」ための第一歩です。ぜひ本記事を参考により良い内定者面談を実施していきましょう。
- ミーティング中は話に集中したいため、メモが取れない
- ミーティング後に話をした内容をまとめるのに時間がかかっている
- ミーティングの発言の温度感やニュアンスを共有したい
このような議事録やメモに関するお悩みがあれば、ぜひ一度AI議事録サービス「Otolio」をお試しください。
Otolioは議事録などのドキュメント作成に関する作業を自動化・効率化することができ、作成時間を最大90%以上削減することが可能です。