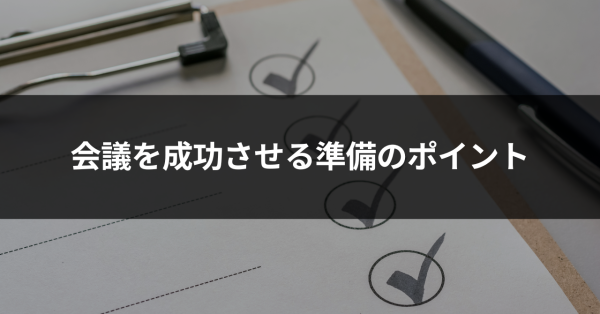ミーティングとは?目的や効率的に進める方法をそれぞれ7つご紹介
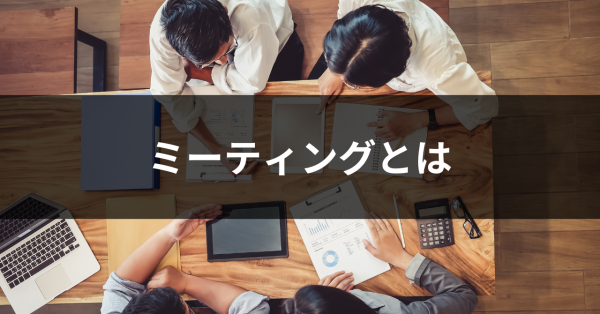
企業に所属していると、多くの場面で「ミーティング」を実施する方も多いと思います。また最近ではリモートワークも浸透し、対面ではなくオンラインで開催するケースも増え、今まで以上にミーティングを効率よく進める方法が求められてきています。
本記事ではミーティングとは何か?という基礎的なお話から、効率的に進める方法やそもそもの目的についてご紹介します。「ミーティングを開催しているけど、上手く開催できている感じがしない」「ミーティングのあり方を検討したい」「今開催しているミーティングを意味あるものにしたい」とミーティングをより良くしたいとお悩みの方はぜひ本記事をご覧ください。
- ミーティング中は話に集中したいため、メモが取れない
- ミーティング後に話をした内容をまとめるのに時間がかかっている
- ミーティングの発言の温度感やニュアンスを共有したい
このような議事録やメモに関するお悩みがあれば、ぜひ一度AI議事録サービス「Otolio」をお試しください。
Otolioは議事録などのドキュメント作成に関する作業を自動化・効率化することができ、作成時間を最大90%以上削減することが可能です。
ミーティングとは?会議との違いは
はじめに、そもそもミーティングとは何かについて整理していきましょう。ミーティングとは複数人が集まって特定のテーマや議題について話し合いを行い、情報共有や意思決定を行う場のことを指しています。英語の「meeting」が語源となっていて、ビジネスのグローバル化に伴って、日本でもミーティングという言葉が広く使われるようになりました。
またミーティングと似たような言葉として「打ち合わせ」という言葉が存在します。それぞれの言葉に明確な定義があるわけではありませんが、それぞれのシーンや目的に応じて使い分けるケースがあります。ミーティングは比較的カジュアルな雰囲気で行われ、意見を出し合う場のニュアンスが強い場合に使用されるケースが多いです。たとえば、1on1ミーティングやキックオフミーティングなどが該当します。
「会議」はミーティングよりもフォーマルな性質を持つことが多く、社内の決裁権を持っている人物が参加し、重要な意思決定がされる場として使用されるケースが多いです。たとえば経営会議や取締役会議があげられます。より形式的なものとしてイメージすると分かりやすいかもしれません。とはいえ、「ミーティング」でも意思決定を行うケースはあるため、あくまでもニュアンスが違うと理解しておくといいでしょう。
このようにその時々の状況によって、「ミーティング」と「会議」が使い分けられるケースがあるため、それぞれの言葉のニュアンスと性質を理解し、目的に応じて正しく使い分けることで、よりスムーズなコミュニケーションが可能になります。
ミーティングの主な7つの目的
ミーティングを行うときは具体的な目的を設定することが重要です。目的を明確にするからこそ、その場で会話したい内容が決まり、アジェンダや議題を決めることが可能になります。ここではミーティングを開催するときによく設定される目的を7つご紹介します。
1. 情報共有
ミーティングの最も基本的で頻繁に行われる目的のひとつが「情報共有」です。たとえば、チームのメンバーや関係者全体に対して、業務の進行状況、会社の方針、市場のトレンド、顧客の反応などの重要な情報を共有するイメージです。
情報共有を行うためにミーティングを開催する背景としては組織の規模拡大やリモートワークの普及など、物理的・心理的な距離が広がっている側面があげられます。メールやチャットだけではどうしても伝えきれないニュアンスや緊急性、優先度を、リアルタイムの会話を通じて伝えることで、誤解を防ぎ、意思のすれ違いを減らすことが可能になります。
また情報共有のミーティングは単に「伝える」ことにとどまりません。たとえば、マネージャーが全体に向けて今後の戦略を共有することで、一人ひとりのメンバーが自分の役割を再認識し、行動に一貫性を持たせることができます。逆に、現場の社員が持つリアルタイムの市場感覚や顧客の声を共有することで、経営層がより現実的で柔軟な判断を下す材料にもなります。
また、情報共有のミーティングを開催することで「心理的な安心感」を与えるというメリットも存在します。たとえば、会社の経営状況や人員体制の変更など、メンバーが不安を感じるような話も、ミーティングで丁寧に説明されることで、不安が軽減されます。このように、情報共有のミーティングは単なる業務連絡ではなく、組織内の信頼構築やエンゲージメント向上にも寄与しています。
2. 進捗確認
プロジェクトやタスクの進行状況を確認するための「進捗確認」も、ミーティングの代表的な目的です。進捗確認ミーティングでは、各メンバーが自分の担当範囲についてどれだけの作業を完了しているか、どこで問題が発生しているか、今後の見通しはどうかといった報告と確認が行われます。これにより、全体のスケジュールに対しての遅れやリスクを早めに察知することができ、それに対して適切な対処を打つことが可能になります。
また進捗確認を目的としたミーティングを開催するうえで、進捗確認を通じて各メンバー間で「対話」が生まれるようにするということが重要なポイントです。たとえば、あるメンバーが予定よりも業務が遅れていると報告した場合、それに対して他のメンバーがサポートを提案したり、ボトルネックとなっている要因について全員で意見を出し合ったりすることで、チーム全体の生産性を高めることができます。
さらに上手く業務を進めているメンバーの報告内容から、他のメンバーが効率的な進め方を学ぶことも可能になります。これは、ドキュメントやマニュアルでは得ることが難しい「暗黙知」を共有する場とも言えます。進捗確認を目的としたミーティングは、単なる進行管理の場ではなく、チームの知見を集約・伝播させる知的生産の場としても機能しているということを理解しておくようにしましょう。
3. 意思決定
企業が成長するために多くの意思決定が必要ですが、その意思決定を目的にミーティングを開催することがあります。意思決定を目的としたミーティングでは関係者全員の情報や意見を集約したうえで、合意形成を図ることが求められます。一方で、全員の意見を取り入れすぎると決定が遅れてしまうというリスクもあるため、効果的な意思決定のためには、事前の資料準備や議題の明確化、ファシリテーターの存在などが重要になります。
また、意思決定のミーティングに異なる部門のメンバーが参加することで、それぞれの違う視点からの知見が集まり、「多角的な判断」が可能になります。たとえば、営業部門が売れると確信している商品について、開発部門が技術的な制約を提示したり、マーケティング部門が市場トレンドと照らし合わせた意見を出すことで、より実現可能で競争力のある戦略が導き出されることもあります。
さらに意思決定を目的としたミーティングを開催することで「決定プロセスへの納得感の醸成」されるというメリットを得られます。たとえ自分の意見が採用されなかったとしても、その場で議論が尽くされたという実感があれば、決定に対する納得感は高まりやすくなります。これは、決定事項に対する実行力やチーム内の一体感にも大きく関わってくるため、ミーティングのプロセスも含めて重要な要素となります。
4. 問題解決や課題の検討
「問題解決や課題を検討する」ためにミーティングを開催することも重要な目的の一つです。問題解決や課題を検討するときには、あらゆる視点から物事を考える必要があります。そのためメールやチャットではなく、ミーティングという形式でその場を設けることが重要になります。
たとえば、技術的な問題や顧客対応に関するトラブルでは、複数の部門にまたがる知識や視点が必要になることが多く、テキスト情報だけでは背景や前提条件を共有が難しいケースが発生します。ミーティングを開催し、それぞれの立場から直接意見を伝え合うことで、よりスムーズに背景や前提条件の共有ができるようになり、関係者の視点を合わせることが可能になるため、問題の本質を見極めやすくなり、解決への道筋がより明確になります。
またテキスト情報ではなくミーティングを開催することで、安心して意見を伝えることができるというメリットがあります。問題解決や課題を検討するときは建設的な議論をすることが何よりも重要になります。「この情報を伝えるのは間違いではないのか?」と不安になって結局伝えないという状況を避けるためにも、テキストでのやり取りではなく発言しやすいミーティングを開催することで、より建設的な議論をすることが可能になります。
5. アイデア出し
ブレストミーティングという種類があるように、「アイデアを出す」を目的としてミーティングを開催することがあります。このミーティングでは、自由な発想を歓迎して、会話がしやすい雰囲気を作ることが何よりも重要です。あるアイデアに対して「そんなの無理じゃない?」「それって現実的?」といった否定的な意見は、アイデアの芽を摘んでしまう原因になってしまいます。
そのため、アイデア出しのミーティングをするときの初期段階では質より量を重視し、どんな発想でも受け入れる姿勢が重要になります。ブレインストーミングやマインドマップ、付箋を使ったワークショップ形式など、手法を工夫することで参加者の発想が広がりやすくなります。
また、アイデア出しを目的としてミーティングで「採用されなかったアイデア」も重要な材料になります。アイデアを出して、それがそのまま上手くいくケースはなく、ほとんどが試行錯誤を繰り返しながらアイデアをブラッシュアップしていくことが重要になります。そのためそのミーティングで出たアイデアを蓄積してくことで「この間の別のアイデアだとどうなるのか?」という新たな気づきが得られることもケースも少なくはありません。採用されたかどうかにかかわらず、ミーティングで出たアイデアそのものに価値があるため、ミーティングで出たアイデアはしっかりと情報として残すことが重要になります。
6. 相談や壁打ち
ミーティングは必ずしも「結論を出す」ための場ではなく、「相談や壁打ち」を目的としたミーティングも、組織にとって欠かせないコミュニケーションの手段です。このタイプのミーティングは、特定のテーマについて話し合うというよりも、「自分の考えを整理したい」「誰かに意見をもらいたい」といった個人のニーズに基づいて開催されます。開催を企画した人が一方的に情報を提供するというより、参加者との対話を通じて新たな視点を得ることが目的となっています。
たとえば、新しい提案を上司に相談するときや、プロジェクトの方向性に迷ったときに、他のメンバーと壁打ちをすることで、頭の中がクリアになることがあります。自分の言葉で相手に説明する過程で、自分でも気づいていなかった論点が浮かび上がってくることも多く、これは一人では得られない効果です。ミーティングは「自分の考えを外に出すこと」そのものが価値になる場にもなっています。
また、壁打ちミーティングの意外なメリットとして、「相談される側」のスキル向上があげられます。適切なフィードバックをするためには、相手の立場や背景を理解し、整理された形で意見を返す必要がありますが、これは言い換えれば、「相手の意図を正しく読み取り、自分の知識を再構築する」プロセスであり、結果としてチーム全体の思考力や伝達力の底上げにもつながります。
7. 関係構築やチームビルディング
最後に紹介するのが、「関係構築やチームビルディング」を目的としたミーティングです。一見すると業務と直接関係のない雑談や、飲み会、オフサイトミーティングなども、広義にはこのカテゴリーに含まれます。実際、仕事の生産性やチームの成果は、メンバー同士の信頼関係や相互理解によって大きく左右されます。そうした関係性を築くためには、日常的なコミュニケーションが欠かせません。
特にリモートワークが普及している中で、意識的に関係構築やチームビルディングを目的としたミーティングを設けることは企業にとっても重要な取り組みの一つです。Web会議ではどうしても対面よりも、感情やニュアンスが伝わりづらく、業務上の連携にも影響が出ることがあります。そのため、仕事とは直接関係のない話題を共有する「雑談タイム」や、「最近の気づき」を語り合う時間などが、チーム内の結束を高める手段として注目されています。
このミーティングでは、役職や経験に関係なくフラットに話せる空気感がとても重要です。若手がベテランに気軽に話しかけられる環境や、他部署との偶発的な会話の機会があることで、新たな連携や発想が生まれやすくなります。こうした空間づくりは、意識しなければ生まれにくいものですが、長期的には組織全体の風通しを良くし、働きやすさや定着率の向上にもつながります。
ミーティングを効率的に進めるための7つのポイント
ミーティングの目的は理解して、実践してみてたけど、上手くいかないと悩んでいる方もいると思います。ここではミーティングを効率的に進めるための方法を7つ紹介します。
1. 必要なメンバーだけ参加してもらう
ミーティングを効率的に進めるために、参加メンバーの選定を見直すことも重要です。よくあるケースとして、「一応参加してもらった方がいいと思って…」という曖昧な理由で多くの人を招集してしまうことがありますが、これは逆効果になる可能性があります。というのも、発言の機会がないままミーティングを終えてしまうメンバーが増えると、本人の時間が無駄になるだけでなく、会議自体のテンポも落ちてしまう可能性があるからです。
ミーティングの参加メンバーにおいて理想的なのは、「意思決定に関与する人」「その場で情報を提供できる人」「決定内容の実行に直接関係する人」だけを招集することです。それ以外の関係者には、会議後に議事録や決定事項を共有することで十分カバーすることが可能です。
また参加人数を最小限にしたほうが、発言がしやすいというメリットも生まれます。たとえば上司や他部門のメンバーが多く参加していると、発言をためらってしまう人が出てくることがあります。そのため、必要最小限のメンバー構成にすることで、発言しやすい環境をつくることができ、結果的に建設的な議論へとつながります。ミーティングは「多くの人を巻き込む場」ではなく「最小限で最適なアウトプットを出す場」であるという意識を持つことが、ミーティングを効率的に進めるためにも重要です。
2. 事前にアジェンダを共有する
アジェンダを事前に共有することは、ミーティングの成功を左右するもっとも重要な準備のひとつです。アジェンダがないまま会議が始まってしまうと、話題があちこちに飛び、最終的に「結局何を話したんだっけ?」という状態になってしまうケースがあります。アジェンダを事前に共有することで、参加者が自分の役割や話すべき内容を事前に整理しておくことができるようになるため、会議中の議論もスムーズに進行することができます。
アジェンダを準備するときは「何を話すか」だけではなく「どの順番で話すか」「各トピックにどのくらいの時間をかけるか」まで含めて設計するのが理想的です。たとえば、最初に共有事項、次に意思決定が必要な議題、最後に質疑応答というように流れを組むことで、会議の時間配分もしやすくなります。
また、アジェンダは参加者の「準備」を促すメリットもあります。たとえば「この議題について自分の意見を整理しておこう」「数値を持参しよう」といった意識が生まれやすくなり、当日の会議での議論の質が上がります。議題によっては、事前に調査や関係部署とのすり合わせが必要になることもあり、こうした準備が間に合わないと、結局その議題は持ち越しになってしまい、再度会議を開くという二度手間が発生してしまいます、
さらに、アジェンダを事前に共有することで、無駄を減らすことができる可能性があります。事前にアジェンダを確認した段階で「この議題はメールで済むのでは?」「この内容は別の会議で扱った方がよいのでは?」といったフィードバックが来ることがあります。そうすると、そもそもその会議自体を見直すきっかけにもなり、無駄な会議を減らすことも可能です。会議の無駄を減らし、成果を最大化するためにも、アジェンダの事前共有はとても重要です。「忙しいからこそ、準備に時間をかける」という逆説的な姿勢が、ミーティングを効率的に行う鍵を握っています。
3. 目的を明確にする
ミーティングを始める前に「今日の会議の目的は何か?」を明確にすることはとても重要です。目的があいまいなままミーティングを開催してしまうと、「結局何が決まったのか」「何が解決されたのか」と無駄な会議になってしまいます。
ミーティングの目的は先ほどご紹介したとおり、「意思決定をする」「情報を共有する」「アイデアを出す」といった形でいくつかのパターンが存在します。一つのミーティングで複数の目的を設定するケースもあるので、そのミーティングで何が目的なのか?をしっかり考えたうえで開催するようにしましょう。
また目的を明確にすることで、事前準備も変わってきます。たとえば意思決定が目的のミーティングであれば、選択肢や判断基準を事前に準備しておく必要がありますし、アイデア出しが目的であれば、自由に意見を出しやすい雰囲気づくりが重要になります。
さらに目的を明確にすることで、参加者全員が同じ方向を向いてミーティングに臨むことができるようになります。また、進行役も「この議題は本日の目的に関係ないので、次回に回しましょう」といった判断がしやすくなり、時間の無駄を防ぐことができます。
4. 時間配分を事前に意識しておく
「ミーティングが時間通りに終わらない」「十分にアジェンダを会話する時間がなかった」という状態を防ぐためにも事前にミーティングの時間配分を決め、その場で意識することで効率的なミーティングを実現することが可能になります。
たとえば、最初の10分は現状の共有、次の20分は課題の洗い出し、最後の10分で結論とToDo整理、というような明確な時間配分を作ることで、時間内に必要な議論を収めるという意識が参加者全員に共有され、集中力も高まります。
ただし、時間配分はあくまで「目安」であることも理解しておくことが重要です。あまりにも厳格に時間を守ることにこだわりすぎると、かえって柔軟な議論ができなくなるケースがあります。状況に応じて柔軟に調整する余地を持たせることも、効率的なミーティングを実施するうえでは欠かせません。
5. 発言しやすい雰囲気を作る
今までご紹介したミーティングを効率的に進めるための方法を実践したとしても、参加メンバーが自由に意見を言えない雰囲気であれば、ミーティングの質は大きく損なわれてしまいます。そのため発言しやすい空気を作ることは、効率的なミーティングを実現するために欠かせない重要な要素のひとつです。
まず、基本的なこととして、対面であれば、参加者全員の顔が見えるような座席の配置を工夫する、オンラインであればカメラONでの参加を推奨するようにしましょう。顔が見えることで、非言語的なコミュニケーションも取りやすくなり、安心感が生まれます。また、ミーティングの冒頭でファシリテーターが「どんな意見でも歓迎です」「発言に遠慮は不要です」といった一言を添えるだけでも、心理的なハードルは下がります。
加えて、「話しても遮られない」「誰かが話しているときに被せて発言しない」といったルールを共有することで、安心して意見を述べられる環境を整えることが可能になります。特に、上下関係が明確な職場では、若手や新入りメンバーが発言を遠慮しがちです。こうした人たちにあえて意見を求めることも大切です。
6. 議論をするときに目的を共有する
ミーティングではアジェンダごとに目的が設定されているケースがあります。そのため各アジェンダがどんな目的を達成したいのかを議論する前に共有することが重要です。「このアジェンダは今後の施策を決めるための話し合いです」と議論を始める前に事前に共有するだけでも、議論の方向性が大きく変わります。目的がはっきりすれば、必要な情報の取捨選択も行いやすくなり、議論の脱線を防ぐことにもつながります。
また、感情的な意見が出やすい場面では、「目的の再確認」が特に重要になります。議論が白熱してくると、誰が正しいか、誰が悪いかといった「勝ち負け」の構図に陥ってし合うケースがあります。「この議論は何のためにやっているのか」という目的に立ち返ることで、冷静な建設的対話に戻ることが可能になります。アジェンダに入る前の一言、そして途中での目的の再確認、これらの積み重ねが、ミーティングの質を大きく左右します。
7. 決定事項とToDoを明確にする
ミーティングが終わったあとに「で、結局何が決まったんだっけ?」「誰が何をするんだっけ?」という会話が生まれてしまっている場合は、そのミーティングは効率的とは言えません。時間をかけて話し合いを行ったのであれば、必ず「決定事項」と「具体的なToDo」を明らかにし、全員に共有することが重要です。
決定事項については、「誰が」「何を」「いつまでに」といった要素が含まれているミーティングで話し合うことが理想です。たとえば「次回の展示会には新しいパンフレットを配布する」という決定事項であれば、「マーケティング部が」「新しいパンフレットを制作し」「いつまでに印刷を完了する」といったレベルまで落とし込んで初めて、実行可能な決定事項と言えます。
ToDoについても同様で、担当者が不明確だったり、期限が設定されていない場合、形だけの「やることリスト」になってしまうケースも少なくありません。具体的なアクションプランとして機能させるには、ToDoの粒度を揃え、担当者や期限を必ず明記するようにしましょう。
また、決定事項やToDoを記録した議事録は、できるだけミーティング終了直後に共有するのが理想的です。時間が経つほど記憶は曖昧になり、共有された情報の精度も落ちていきます。最近では、ミーティング終了後にすぐに決定事項やToDoを整理してくれるAI議事録ツールもあるため、ミーティングの効率化のために検討するのも一つの手段です。詳しくAI議事録ツールについて知りたい方は以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
より詳細な事例も確認したい方はぜひ以下の記事も参考にご覧ください。
ミーティングの意味がないと言われてしまう5つの理由
ミーティングを開催するのは企業にとっても重要な取り組みである一方、「このミーティングって何の意味があるの?」「ミーティングをしている時間で別の業務をしたい」という意見が取り上げられるケースも存在します。ここではなぜそういう状況になってしまうのか、ミーティングの意味がないと言われてしまう5つの理由としてご紹介します。
1. 目的が明確になっていない
ミーティングが「意味ない」と言われる最も多い理由の一つが、「目的が明確でないまま開催されている」というケースです。たとえば、上司から「とりあえず今週の進捗を確認しよう」とだけ言われて集められたミーティングでは、参加者の多くが「何のためにこの会議をしているのか?」と疑問を持ちながら参加してしまいます。目的があいまいなままだと、何を話せば良いのか、何を持ち帰れば良いのかが分からず、結果として「意味がなかった」と感じられてしまいます。
さらにこのような目的が明確になっていないミーティングを継続的に実施してしまうと「会議=意味がないもの」という先入観が企業全体に広がってしまう可能性があります。そうすると、本当に必要なミーティングさえも軽視されるようになり、重要な意思決定や課題解決のチャンスを逃してしまうリスクがあります。
ミーティングを開催するときは効率的に進める方法でもご紹介したとおり「この会議の目的は何か?」と目的を明確にしておくことがとても重要です。
2. アジェンダが準備されていない
アジェンダがないミーティングでは、話の順序がバラバラになってしまい、誰が何を話すべきかが分からず沈黙が続いたり、または逆に一部の話題だけが過剰に掘り下げられてしまい、時間が足りなくなるといった問題が起きてしまいます。
アジェンダは、ただ議題を並べるだけではありません。各議題に対して「何分使うのか」「誰がリードするのか」「どのような目的があるのか」まで明確にすることで、参加者全員が同じゴールに向かって進行することが可能になります。また、アジェンダがあることで、ミーティング中に話が脱線したとしても、「本題に戻りましょう」と軌道修正しやすくなります。
アジェンダはミーティングを成功に導くための地図のような役割を担っています。地図がなければ、いかに有能な参加者が集まっても、迷走してしまうのは当然の結果と言えるため、アジェンダを事前に準備するようにしましょう。
3. 発言者が限定的になっている
「会議ではいつも同じ人しか話していない」「結局、上司の意見で決まってしまう」このような声があがるミーティングは、参加者の関与が限定的であり、「意味がない」と感じられる要因となります。また発言者が偏っている会議では、多様な視点やアイデアが出にくく、結果として一方向的な議論になり、ミーティングの質を下げる可能性にも繋がります。
発言者が限定的になってしまう背景には、組織文化や上下関係、時間の使い方の問題など、さまざまな要因があります。たとえば、「上司が発言し終わるまで意見を言ってはいけない」「間違ったことを言ってはいけない」という空気があると、特に若手社員は発言しづらくなります。また、「毎回同じような話題だから、自分は関係ないだろう」と思ってしまうような内容設計になっている場合も、参加者が発言しづらくなる原因になります。
これらの状況を解決するためにも、ファシリテーターの役割が極めて重要になります。「この議題について、Aさんの部門ではどう思いますか?」といったように、指名して発言を促すだけでも、議論のバランスは大きく変わります。また、あらかじめ発言の順番や役割を決めておくと、自然と参加者の意識が高まり、会議全体が活性化します。
ミーティングは「全員で考える場」として設計することが重要です。発言の偏りを防ぎ、多様な視点を取り入れることで、初めて「意味のある会議」としての価値が生まれるため、発言者が限定的になっていると感じられた場合は注意するようにしましょう。
4. 開催時間が長い
時間が長く、ダラダラしたミーティングを開催してしまうと、意味がないミーティングとして感じられてしまうことがあります。多くの企業では「会議は1時間」と無意識に設定してしまいがちですが、本当にその時間が必要なのか?と事前に考えることはとても重要です。必要以上に長いミーティングは、参加者の集中力を奪い、結果として生産性を著しく下げてしまいます。
人間の集中力は一般的に15分〜30分が限界と言われています。たとえば、60分間の会議をしても、最初の20分以降は多くの参加者が他の業務のことを考えていたり、、注意力が散漫になることが少なくありません。長時間の会議は、実は「話し合っているように見えて、何も決まっていない」という事態を引き起こしがちです。
ミーティングを価値あるものにするためにも、必要最小限の時間で最大の成果を出すという意識が欠かせません。時間を制限することで、自然と発言も要点を押さえたものになり、集中力も維持しやすくなります。「この会議は30分で終わらせよう」という制限を設けるだけで、議論の密度が高まり、参加者にとって「意味がある」と実感できる会議にすることができるため、開催時間は常に見直すようにしましょう。
5. テキスト情報だけで完了してしまう内容を実施してしまう
ミーティングを開催すると、お互いの顔が見え、非言語的なコミュニケーションも取りやすくなり、安心感が生まれるというメリットがありますが、すべてをミーティングという形で開催してしまうと、多くの時間を無駄にしてしまう可能性があります。
最近ではメールだけではなく、SlackやTeamsといったテキストコミュニケーションツールも多く普及し、簡単な情報共有や確認であれば、これらで十分に対応することが可能です。簡単な情報共有や確認をするためにミーティングを開催してしまうと「これ、ミーティングじゃなくてもよかったよね?」と感じられてしまい、ミーティングの価値そのものが疑問視されてしまうことがあります。
また「ミーティングを開催すること自体が目的になってしまっている」パターンも存在します。たとえば、定例ミーティングなどでは「とりあえず集まる」「決まっているからやる」という形式的な開催が繰り返されると、実質的には内容の薄い時間だけがすぎる形となってしまいます。
この状況を防ぐためにも、事前に会議の目的とアジェンダを参加者に共有することが重要です。また「この内容は本当にミーティングでやるべきなのか?」という問いを、ミーティングのたびに自問する姿勢も大切になります。
まとめ|意義のある効率的なミーティングを開催しよう
複数人が集まって特定のテーマや議題について話し合いを行い、情報共有や意思決定を行うミーティングには様々な目的が存在します。「情報共有」や「進捗確認」、「意思決定」といったミーティングの目的を開催前にしっかりと明確にすることが、とても重要です。
またミーティングを効率的に進めるためにも、必要なメンバーだけに参加してもらったり、事前にアジェンダを共有する、発言しやすい雰囲気を作るといった工夫が必要です。これらの工夫がなく、「ミーティングを開催することが目的になってしまっている」場合は、改めて本記事で紹介した内容を参考にミーティングを見直すようにしましょう。
- ミーティング中は話に集中したいため、メモが取れない
- ミーティング後に話をした内容をまとめるのに時間がかかっている
- ミーティングの発言の温度感やニュアンスを共有したい
このような議事録やメモに関するお悩みがあれば、ぜひ一度AI議事録サービス「Otolio」をお試しください。
Otolioは議事録などのドキュメント作成に関する作業を自動化・効率化することができ、作成時間を最大90%以上削減することが可能です。