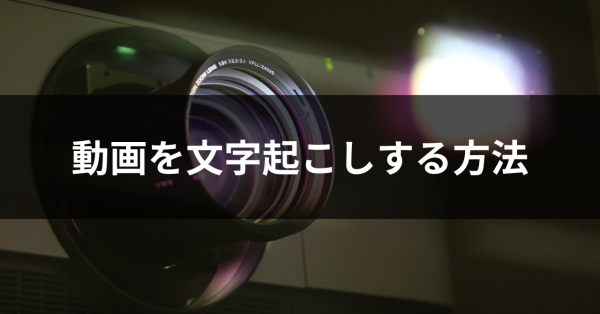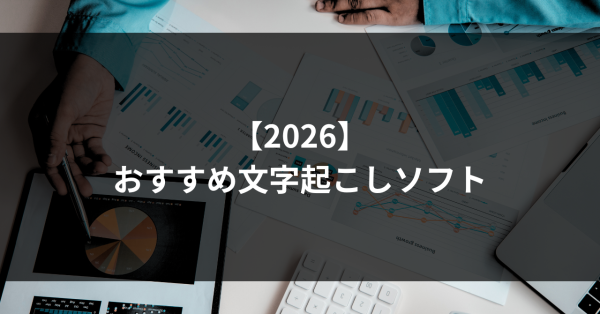AIで文字起こしをする2つの方法を解説|精度を上がるための工夫や注意したいポイントも紹介
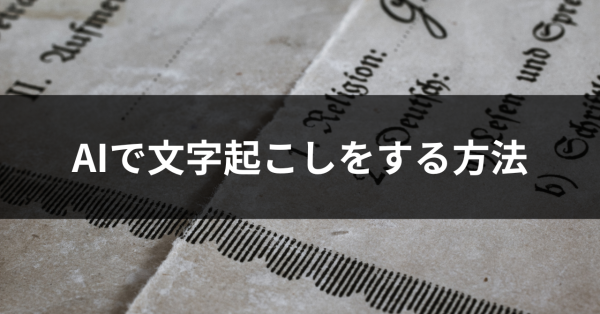
近年、デジタル化やAI技術の発展により、さまざまな業務の自動化・効率化が進んでいます。その中でも特に注目されているのが「AIで文字起こしをする方法」です。会議やインタビュー、講演などの音声データを自動で文字に変換する技術として、多くの企業や個人が活用を始めています。
今までの文字起こし作業は人手に頼る部分が多く、長時間の音声データを文字に変換するためには膨大な時間と労力が必要でした。しかし、AI技術の進化により、これらの作業が大幅に効率化され、今では数分で完了できるケースも珍しくありません。人材不足の影響で業務の効率化が一層求められている現在、AIで文字起こしをする方法はその解決策として大きな期待を集めています。
一方で、「AIで文字起こしをするためにはどのような方法があるのか」「どうすれば精度を高められるのか」「導入する際の注意点は何か」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。本記事では、AIで文字起こしをする方法、精度向上のポイント、注意すべき点まで、幅広く解説いたします。業務効率化を検討されている方、会議の議事録作成にお困りの方、AI技術の活用を模索されている方まで、ぜひ参考に本記事をご覧ください。
またAIで精度高く文字起こしをしたい方は、ぜひ使えば使うほど精度が上がるOtolio(旧:スマート書記)をお試しください。Otolioは特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、社内の専門用語や固有名詞の認識精度を向上させることが可能です。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or サービス資料をみる
Otolio(旧:スマート書記)がわかる人気3点セット資料(サービス概要・導入事例・機能詳細)をみる
AIによる文字起こしが求められるようになった背景
現代のビジネス環境において、文字起こしの重要性が高まっている理由には、複数の要因が関係しています。まず第一に、人材不足の影響で業務の効率化が一層求められている点があげられます。少子高齢化が進む中、多くの企業では限られた人材でより多くの業務をこなさなければならない状況が続いています。
今までは、会議の議事録作成やインタビューの文字起こしなどは、参加者や専門スタッフが手作業で行うことが一般的でした。しかし、このような作業は時間と労力が必要になるため、他の重要な業務に割くべきリソースが不足してしまうケースが多発しています。そのため、これらの作業を自動化・効率化する手段として、AIで文字起こしをする方法に注目が集まっています。
また、リモートワークの普及により、オンライン会議やWeb会議が日常的に行われるようになったことも、文字起こしニーズの増加につながっています。対面での会議とは異なり、オンライン会議では参加者が音声を聞き取りにくい場合があり、後から内容を確認できるようにする重要性が高まっています。
さらに、コンプライアンス意識の高まりにより、会議内容の記録保存が重要視されるようになったことも背景としてあげられます。決定事項や議論の経緯を正確に記録しておくことで、後々のトラブルを防ぎ、透明性のある意思決定プロセスを実現できます。このように、人材不足による効率化の必要性、働き方の変化、コンプライアンス要求の高まりなど、複数の要因が相まって、AIによる文字起こしが求められるようになっています。
AIで文字起こしをする2つの方法
AIで文字起こしをする方法は、大きく分けて2つのアプローチがあります。それぞれに特徴や適用場面が異なるため、用途に応じて最適な方法を選択することが重要です。
1. 音声や動画ファイルからAIツールで文字起こしをする
最初の方法は、既に録音・録画された音声や動画ファイルを、Google AI Studioなどの生成AIにアップロードして文字起こしを行う方法です。Web会議ツールの動画ファイルやICレコーダーの音声ファイルを生成AIにアップロードして文字起こしをすることで、手軽に文字起こしを実現できます。この方法によるAIの文字起こしにはメリットとデメリットが存在するため、以下で詳しく解説します。
メリット|すぐに試すことができる
この方法の最大のメリットは、すでに多くの人が使用している汎用的なAIツールを活用できることです。特別なソフトウェアを新たに導入する必要がなく、既存のツールを使って文字起こしを開始できるため、導入コストを抑えることが可能です。また、生成AIは文字起こしだけでなく、得られたテキストの要約や整理といった追加の処理も同時に行えるため、その後のまとめる作業の時間も削減することができます。
デメリット|アップロードに手間や時間がかかる
一方で、この方法にはデメリットも存在します。まず、アップロード処理に時間がかかるケースがあることです。特に長時間の音声や高画質の動画ファイルの場合、アップロード自体に相当な時間を要することがあります。また、わざわざファイルをアップロードする必要があるため、会議終了後すぐに内容を確認したい場合には不向きです。
さらに、ファイルサイズの制限により、長時間の録音・録画データを分割しなければならない場合もあり、その際には複数回の作業が必要になります。加えて、アップロード先のサーバーやサービスの処理能力によって、文字起こしの速度にばらつきが生じることも考慮する必要があります。このように、手軽さと引き換えに、時間効率の面では課題があることを理解しておく必要があります。
2. 録音から文字起こしまで一気に対応できるAI議事録ツールで文字起こしをする
もう一つの方法は、録音機能と文字起こし機能が統合されたAI議事録ツールを活用することです。これらのツールの多くは、会議の開始と同時に録音を開始し、リアルタイムで文字起こしを行うことができます。会議中に発言内容がテキストとして表示されるため、参加者は発言の流れを視覚的に確認しながら議論を進めることができます。先ほどと同じように、この方法にもメリットとデメリットが存在するため、以下で詳しく解説します。
またAI議事録ツールについてもっと詳しく知りたい、どんなツールがあるのか知りたいという方は以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にご覧ください。
メリット|会議終了後すぐに文字起こしを確認できる
AI議事録ツールの最大のメリットは、リアルタイム文字起こしであるツールが多く、会議中に文字起こしを確認できることです。会議が終了すると同時に、発言内容がテキスト化されているため、参加者は即座に議論の内容を振り返ることができます。これにより、記憶が鮮明なうちに重要なポイントを確認・共有でき、後日の振り返りも効率的に行えます。
また、AI議事録ツールという名前のとおり、文字起こしをまとめるためのAIが簡単に使える仕様になっているのもメリットの一つです。生成AIを活用したやり方では、都度プロンプトを入力する必要がありますが、AI議事録ツールであれば、ボタンをクリックするだけで要約文章や要点を整理することが可能です。そのため文字起こしを会議後すぐに確認することができるだけではなく、要点など今までの議事録形式に合わせた情報をすぐに確認することもできます。
議事録形式に合わせて「要約」「箇条書きで要点を整理」「決定事項・ToDo・質疑応答のみを抽出」できるAI議事録ツールを試したい方は、ぜひ一度Otolioの無料トライアルをお試しください。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or サービス資料をみる
デメリット|コストがかかる
一方で、AI議事録ツールの導入には一定のコストがかかることがデメリットとしてあげられます。AI議事録ツールは文字起こしの利便性が高い分、その分ツールの利用料がかかることがあります。月額料金や年間契約料金が発生するケースが多く、利用頻度や会議の規模によっては、コスト負担が大きくなる可能性があります。
また、ツールによっては、文字起こしの精度や機能に差があるため、自社のニーズに適したツールを選択するための検討時間も必要です。さらに、チーム全体でのツール導入となると、使い方の習得や運用ルールの策定など、初期の準備工程も発生します。これらの点を総合的に考慮して、コストパフォーマンスを評価する必要があります。
AIで文字起こしをするときに精度を高める2つの工夫
AIで文字起こしをするときに、皆さんが最も気にする部分は「精度の高さ」だと思います。文字起こし精度は録音環境と使用しているAIツールの性能を組み合わせて決まるため、これらの要素を最適化することで、より正確な文字起こしを実現できます。
文字起こしの精度が低いと、後から修正作業に多くの時間を費やすことになり、結果的に効率化の効果が薄れてしまいます。逆に、高精度な文字起こしが実現できれば、そのまま議事録として活用できるレベルまで品質を高めることが可能です。ここでは、AIで文字起こしの精度を向上させるための具体的な方法を2つご紹介します。
より詳しく知りたい方は、以下の記事で別で詳しくご紹介していますので、こちらも参考にご覧ください。
1. 録音環境を整える
AIで文字起こしをするときに最も重要な要素の一つが「録音環境」です。どれほど高性能なAIを使用しても、元となる音声の品質が低ければ正確な文字起こしは困難になります。そのため、録音環境を整えることは、精度向上の基本中の基本といえます。
まず、録音を行うときには、外部ノイズをできるだけ排除することが重要です。エアコンの音、交通騒音、隣室からの音などは、AIが音声を認識する際の妨げとなります。可能であれば、静かな環境で録音を行うか、ノイズキャンセリング機能付きのマイクを使用することをお勧めします。
また、マイクと話者の距離も精度に大きく影響します。マイクから遠すぎると音声が不明瞭になり、近すぎると息づかいや雑音が入りやすくなります。適切な距離を保つことで、クリアな音声を録音できます。さらに、複数人が参加する会議では、全員の声が均等に録音されるよう、マイクの配置を工夫することも重要です。
さらに録音デバイスの選択も精度に影響します。スマートフォンの内蔵マイクよりも、専用の録音機器やPCの高品質マイクを使用することで、より鮮明な音声を取得できます。また、録音フォーマットや音質設定も適切に行うことで、AIが処理しやすい音声データを作成することが可能です。
2. 文字起こし精度の高いAIを活用する
録音環境を整え、音声の品質が良くなったとしてもAIの性能が低ければ文字起こし精度は下がってしまいます。そのため当たり前の話になりますが、文字起こし精度の高いAIを活用することで、精度向上を実現することが可能です。しかし実際にはどのAIが精度高く文字起こしができるのかを調査、検証するのには多くの時間が必要になります。
これらの時間をかけることができない方は、これらの調査を行い、製品に組み込まれているAI議事録ツールの利用をおすすめします。先ほどお伝えしたとおり、AI議事録サービスは文字起こしに特化しているため、各製品を提供している企業がどのAIであれば精度高く文字起こしをしているのかを調整し、お客様たちに提供しています。とはいえ、AIの技術は日々進化し、そのとき精度が高いと判断したものであっても、時間の経過とともに、他に精度高く文字起こしができるAIが登場することも珍しくはありません。
常に精度高く文字起こしができるAIを利用したいと考えている方は、各種AIの調査を定期的に行い、状況に合わせて最も精度の高いAIを採用しているAI議事録ツール「Otolio」をぜひお試しください。Otolioは各種認識エンジンの調査を定期的に実施しており、状況に合わせて最も精度の高いAIを採用するように調整しています。
そのため、Otolioでは常に最高レベルの精度で文字起こしを利用することができ、かつ要約などのAI機能の常に精度が高いものをご利用いただけるようになっております。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or サービス資料をみる
AIで文字起こしをするときに注意したい3つのポイント
AIで文字起こしする方法は、多くのメリットがある一方で、いくつかの注意点も存在します。これらのポイントを事前に理解し、時には対策を打つことで、AIでの文字起こしをより安全かつ効果的に活用できます。
1. セキュリティリスク
AIで文字起こしをするときに最も重要な注意点の一つが、セキュリティリスクです。会議の音声が学習データとして使用される可能性があるため、機密情報や個人情報を含む内容の取り扱いには細心の注意が必要です。
多くのAIでは、アップロードされた音声データやテキストデータを、サービス改善のための学習データとして活用する場合があります。これにより、企業の機密情報が意図せず外部に流出したり、第三者に利用されたりするリスクが存在します。特に、経営会議や人事評価、契約交渉などの重要な会議では、このようなリスクを十分に考慮する必要があります。
対策としては、利用するAIサービスの利用規約やプライバシーポリシーを詳細に確認し、データの取り扱い方針を理解することが重要です。可能であれば、学習データとして利用されない設定を選択するか、そもそも学習データとして利用されないサービスを選択することをおすすめします。また、社内での利用ルールを策定し、どのような内容の会議でAI文字起こしを使用するかを明確にしておくことも重要です。
2. 固有名詞や専門用語の変換は難しい
AIによる文字起こしは日常的な会話や一般的なビジネス用語については高い精度を誇りますが、固有名詞や専門用語の認識については引き続き課題が残っています。人名、地名、商品名、業界特有の専門用語などは、正確に文字起こしされないケースが多く見られます。
特に、日本語の場合は同音異義語が多いため、文脈から適切な漢字を選択する必要がありますが、AIが業界や企業の文脈を完全に理解することは困難です。たとえば、「こうじょう」が「工場」なのか「向上」なのか、「かいしゃ」が「会社」なのか「改社」なのかといった判断は、難しく誤変換してしまうケースも多くみられます。
AI議事録ツールの場合は、この問題への対策として、事前に重要な固有名詞や専門用語をツールに登録できる機能を活用し、誤変換されたものを正確に変換する仕組みを提供しているケースが多いです。とはいえ、企業の専門用語や固有名詞をすべて登録するのにも多くの時間がかかってしまいます。こうした用語を登録する時間も削減したい方はぜひ、Otolioをお試しください。Otolioは特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、使えば使うほど各社の専門用語や固有名詞の認識精度が上がる仕組みを提供しているため、この時間を削減することが可能です。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or サービス資料をみる
3. 誤変換が多い場合は修正に手間がかかる
AIによる文字起こしの精度が低い場合、誤変換の修正作業に多くの時間を費やすことになり、効率化の効果が薄れてしまう可能性があります。特に、音声品質が悪い場合や、複数人が同時に発言する場面では、誤変換が頻発することがあります。
誤変換の修正作業は、単に文字を置き換えるだけでなく、文脈を理解して適切な表現に変更する必要があるため、思った以上に時間がかかります。また、発言者の意図を正確に汲み取るためには、元の音声を聞き直しながら修正を行う必要があり、結果的に通常の議事録作成と同程度の時間がかかってしまうケースもあります。
まとめ
AIによる文字起こしは、現代のビジネス環境において重要な役割を果たすようになっています。人材不足による業務効率化の必要性、リモートワークの普及、コンプライアンス要求の高まりなど、さまざまな要因により、文字起こしの重要性はますます高まっています。
本記事では、AI文字起こしを実現するための2つの方法について詳しく解説しました。既存のファイルを汎用AIツールにアップロードする方法は、手軽に始められる一方で、時間効率の面で課題があります。一方、AI議事録ツールを活用する方法は、リアルタイム文字起こしにより会議終了後すぐに内容を確認できる利便性がありますが、コストがかかるという側面もあります。
文字起こしの精度向上のポイントとしては、録音環境の整備と認識精度の高いAIを活用することが重要です。とはいえ認識精度の高いAIに調査は時間がかかるため、まず試したい方は、AI議事録ツールの活用をおすすめします。導入を検討される際は、自社の用途や予算、セキュリティ要件などを総合的に考慮し、最適な方法を選択することが成功の鍵となります。AI技術の進歩により、今後さらに精度や機能が向上することが期待されるため、継続的な情報収集と活用方法の見直しを行いながら、業務改善に取り組んでいけるようにしましょう。
色々と文字起こしを試してみたけど
- 固有名詞や専門用語の変換が上手くいかない
- 「えー」や「あの」などの意味をなさない言葉も文字起こしされてしまう
- 話し言葉で文字起こしされて、読みづらい
というお悩みを抱えている方は、ぜひ一度、使えば使うほど文字起こし精度が上がる「Otolio」をお試しください。
Otolioには、以下のような特徴があります。
- 特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、固有名詞や社内用語の認識精度を向上
- 「えー」や「あの」など意味をなさない発言を最大99%カット
- 発言内容をリアルタイムで文字起こし
- 最大20名までの発話を認識し、誰がどの発言をしたかをAIが自動で可視化
- Zoom、Microsoft teamsなど全てのWeb会議ツールと連携可能
- モバイルアプリによる対面での利用が可能
また議事録やドキュメントにまとめる作業も、OtolioのAIアシスト機能を活用して自動化することが可能です。AIアシストを活用すれば以下を自動化することができます。
- 要約文章の生成
- 要点の自動抽出
- 決定事項やToDo、質疑応答の抽出
累計利用社数6,000社以上の実績、大手企業から自治体まで様々な組織で利用されており、セキュリティ面でも安心してご利用いただけます。