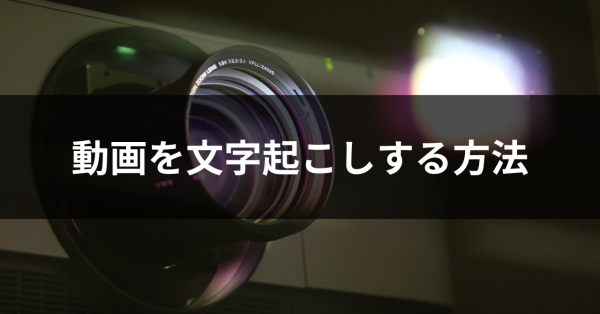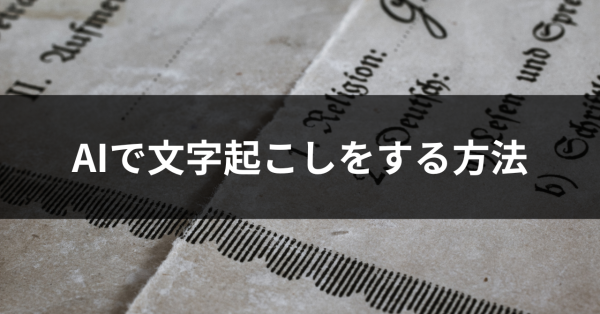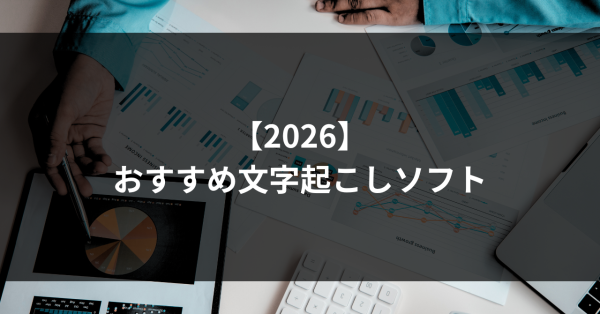文字起こし精度を上げる方法を2つの要素で解説|音声品質を上げるための4つの方法も紹介

会議の議事録作成やインタビューの記録で文字起こしアプリやソフトを活用している方の中には、「文字起こしの精度をもう少し上げたい」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。文字起こしの精度を上げるためには、ただAIの性能だけが良ければいいというわけではなく、音声データの品質とAIの品質という2つの要素を理解して適切に対策することが重要です。特に音声データの品質は文字起こしの精度に大きな影響を与えるため、録音環境や話し方を工夫することで大幅に精度を向上させることができます。
本記事では、すでに文字起こしアプリやWeb会議ツールの文字起こしなど、ツールを活用して文字起こしをしているが、精度に不満を抱えている方に向けて、文字起こし精度を上げるための方法を解説します。文字起こし精度を上げるための2つの要素とそれぞれを改善または確認する方法についてもご紹介します。文字起こしの精度にお悩みの方はぜひ本記事を最後までご覧ください。
また精度高く文字起こしをしたい方は、ぜひ使えば使うほど精度が上がるOtolio(旧:スマート書記)をお試しください。Otolioは特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、社内の専門用語や固有名詞の認識精度を向上させることが可能です。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or サービス資料をみる
Otolio(旧:スマート書記)がわかる人気3点セット資料(サービス概要・導入事例・機能詳細)をみる
文字起こし精度を上げるための重要な2つの要素
文字起こしの精度を効果的に上げるためには、2つの重要な要素の組み合わせで決まるということを理解する必要があります。この2つの要素とは、「音声データの品質」と「製品が提供するAIの品質」です。
まず重要なのは、これらの要素は相互に影響し合うという点です。音声データの品質が高いものに対してAIの品質が上がると文字起こしの精度は大幅に向上しますが、音声品質が低いものに対してAIの品質を向上させても、精度はほとんど改善されないという特徴があります。
音声データの品質が文字起こし精度に与える影響について、独自調査を実施した結果、同じAIを活用しても音声品質による文字起こしの正答率には±16%もの差が生じることが分かっています。(ただし、この数値は検証データによって多少の変動が発生する可能性があります)
この調査結果からも分かるように、文字起こしの精度を上げたい場合は、まず音声データの品質向上に集中的に取り組むことが最も効果的なアプローチといえます。その上で、AIの品質も考慮することで、より高い精度の文字起こしを実現できるのです。
1. 音声データの品質
音声データの品質は、文字起こしの精度に最も大きな影響を与える要素といえます。どれだけ高性能なAIを使用していても、音声データの品質が低ければ正確な文字起こしは難しくなってしまいます。
音声データの品質を左右する要因はさまざまです。録音環境の静かさ、マイクと話者の距離、話者の声の大きさや明瞭さ、周囲の雑音レベルなど、多くの要素が複合的に影響します。これらの要因を一つひとつ改善していくことで、文字起こしの精度を大幅に向上させることが可能になります。
また、音声データの品質は録音時点で決まってしまうため、後から修正することが困難という特徴もあります。そのため、録音前の準備段階で音声品質を向上させる対策を講じることが非常に重要になってきます。
2. 製品が提供するAIの品質
文字起こしの精度を決めるもう一つの重要な要素が、文字起こしアプリやWeb会議ツールなどの製品側が提供するAIの品質です。この品質は各製品によって大きく異なり、同じ音声データを使用しても製品によって文字起こしの精度に差が生じることがあります。
AIの品質を決める要因としては、使用している音声認識エンジンの種類、学習データの量と質、言語モデルの精度、ノイズ除去機能の性能などが挙げられます。特に日本語の文字起こしにおいては、ひらがな、カタカナ、漢字の使い分けや、同音異義語の判別能力がAIの品質を大きく左右します。
製品を選択するときに注意したいのは、AIの品質には一定の上限があるということです。どれだけ高品質な音声データを用意しても、製品のAI自体の性能に限界があれば、それ以上の精度向上は期待できません。そのため、自分の用途に適したAI品質を持つ製品を選ぶことが重要といえます。
また、AI技術は日々進歩しているため、定期的にアップデートされる製品を選ぶことで、継続的な精度向上のメリットを受けることができます。製品比較の際は、現在の性能だけでなく、今後の技術向上への対応可能性も考慮に入れることをおすすめします。
音声データの品質を上げるための4つの方法
文字起こしの精度向上において最も効果的な「音声データの品質向上」について、具体的な4つの方法をご紹介します。これらの方法を実践することで、文字起こしの精度を大幅に改善することができるので、文字起こしの精度にお悩みの方はぜひ参考にご覧ください。
1. マイクの距離
マイクと話者の距離は、音声データの品質に最も直接的な影響を与える要因の一つです。基本的に、距離が近ければ近いほど精度が上がるという原則があります。
理想的な距離は、マイクから話者の口元まで15-30cmとされています。とはいえ、集音マイクなどでは口元15-30cmの距離を確保することは難しいため、手が届くくらいの距離を目安とするといいでしょう。この距離であれば、話者の声を十分な音量で録音でき、同時に周囲の雑音の影響を最小限に抑えることができます。特に大きい会議室で会議を実施する場合は、この距離の確保に注意が必要です。
大きな会議室では、どうしても話者とマイクの距離が離れがちになってしまいます。そのような場合は、ピンマイクやヘッドセットマイクの使用を検討することをおすすめします。また、会議の参加者全員にマイクを配布することが難しい場合は、発言者が順番にマイクを使用するルールを設けることも効果的でしょう。
距離の問題は、単純に音量の問題だけではありません。距離が離れることで、反響音や室内の残響音がマイクに入りやすくなり、これが文字起こしの精度低下につながってしまいます。そのため、物理的にマイクと話者の距離を近づけることは、文字起こし精度向上の基本中の基本といえます。
2. マイクの向き
マイクの距離と同じくらい重要なのが、マイクの向きです。話者とマイクの向きが一致していないと、距離が近くても精度が下がってしまう可能性があります。
話者とマイクの距離が近くても、喋っている方向がマイクに向いていなかったら音声の品質は大幅に低下します。これは、人の声には指向性があり、正面から発せられる音と横や後ろから聞こえる音では、音質や音量に大きな差があるためです。
この問題が特に起きやすいのは、ホワイトボードやモニターなど、マイク以外のものに注目しながら会議をするときです。プレゼンテーションを行う際に、発表者がスクリーンに向かって話してしまい、マイクに背を向けた状態で発言することがよくあります。
対策としては、発言者がマイクの方向を意識して話すことが基本ですが、会議の進行によってはそれが困難な場合もあると思います。そのような場合は、複数のマイクを設置して、発言者がどの方向を向いても音声を拾えるような環境を整えることも一つの解決策といえます。
3. 環境音とノイズ
録音環境における環境音とノイズの影響は、文字起こしの精度に大きな影響を与える要因です。これらの雑音は、AIが人の声と区別することを困難にし、誤変換の原因となってしまいます。
まず注意すべきは、録音場所の選択です。窓際やエアコンの近くは避けることをおすすめします。窓際では交通音や工事音などの外部ノイズが入りやすく、エアコンの近くでは機械音が常に録音されてしまいます。これらのノイズは、AIにとって特に処理が困難な音源となってしまいます。
また、会議中に発生する音にも注意が必要です。紙をめくる音やタイピングの音も、文字起こしの精度に影響を与えることがあります。これらの音は一見小さく感じられますが、マイクに近い位置で発生すると、話者の声よりも大きく録音されてしまうことがあります。
録音環境を整えるときは、できるだけ静かな部屋を選び、参加者には録音中は不要な動作を控えてもらうようにするのが効果的です。完全に無音の環境を作ることは難しいですが、これらの対策により環境音とノイズの影響を最小限に抑えることができます。
4. 話し方
話し方も音声データの品質に大きく影響する要素です。特に複数人が参加する会議においては、発言が重なることで誤変換が発生しやすくなってしまいます。
発言が被ると、AIは複数の音声を分離して認識することが困難になります。人間の聴覚であれば、ある程度は聞き分けることができますが、現在のAI技術では複数人の同時発言を正確に文字起こしすることは非常に困難です。そのため、会議では一人ずつ順番に発言するルールを設けることが重要です。
また、発言の仕方にも工夫の余地があります。はっきりと明瞭に話すことで、AIが音声を正確に認識しやすくなります。早口になりすぎないよう注意し、適度な間を設けながら話すことも効果的です。
さらに、専門用語や固有名詞を使用する際は、特に明瞭に発音することを心がけることをおすすめします。これらの言葉は、一般的な辞書に登録されていない場合があり、AIにとって認識が困難な語彙となることが多いためです。ゆっくりとはっきりと発音することで、誤変換のリスクを減らすことができるようになります。
製品が提供するAIの品質を確認する2つの方法
音声データの品質を向上させる方法について理解したところで、次に重要なのが使用する製品のAI品質を正確に把握することです。AIの品質を現場で上げることはできませんが、AI品質を確認することで、その製品で期待できる文字起こし精度の上限を知ることができます。
1. 静かな環境で1分ほど文章を読み上げて精度を確認する
製品のAI品質を確認する最も効果的な方法は、特定の条件下でのテストを実施することです。まず静かな環境で1分ほどの文章を読み上げて、その文字起こし精度を確認する方法をおすすめします。
このテストを実施する際は、できるだけ理想的な録音条件を整えることが重要です。静かな部屋でマイクと口元の距離を適切に保ち、はっきりとした発音で既知の文章を読み上げます。使用する文章は、新聞記事や書籍の一部や過去の議事録の文章など、身近なもので問題ありません。
テスト結果として得られた文字起こしデータを、元の文章と詳細に比較します。正確に変換された文字数と誤変換された文字数を数えて、正答率を計算することで、そのAIの基本的な性能を把握することができます。この際、句読点の有無や、ひらがな・カタカナ・漢字の使い分けの精度も併せて確認することをおすすめします。
複数の製品を比較検討している場合は、同じ文章を使用して同じ条件でテストを実施することで、客観的な品質比較が可能になります。このテスト結果は、製品選択の重要な判断材料となるでしょう。
2. 精度が不十分な場合はそれ以上精度は上がらない
静かな環境で読み上げた文章の精度を確認して、その結果が不十分な場合は、基本的にそれ以上は精度が上がることはないケースがほとんどです。理想的な条件下でのテスト結果が、その製品で実現可能な文字起こし精度の上限となります。実際の使用場面では、様々なノイズや録音条件の制約があるため、精度はこの上限値よりも低くなることが一般的です。
たとえば、理想的な条件下でのテストで90%の精度が得られた製品の場合、実際の会議録音では80-85%程度の精度になることが予想されます。一方、理想的な条件でも70%の精度しか得られない製品では、実際の使用場面での精度はさらに低くなってしまいます。
この原則を理解することで、製品選択時により適切な判断ができるようになります。自分の用途で必要な精度レベルを明確にした上で、それを上回る性能を理想的条件下で発揮できる製品を選ぶことが重要といえます。
文字起こし精度を確認するときの2つの注意点
文字起こしの精度を正確に評価するためには、いくつかの注意点があります。これらの点を理解しておくことで、より客観的で有用な精度評価を行うことができるでしょう。
1. 社内の固有名詞や専門用語は誤変換されやすい
文字起こし精度を確認する際に最も注意すべき点の一つが、社内の固有名詞や専門用語の扱いです。これらの語彙は一般的な辞書に登録されていないことが多く、AIにとって認識が困難な語彙となります。
社内の人名、部署名、プロジェクト名、製品名などの固有名詞は、どれだけ高性能なAIでも正確に変換することは困難です。たとえば、「田中マネージャー」が「たなかまねーじゃー」とひらがなで変換されたり、「新規事業部」が「新規事業ぶ」と誤変換されたりすることがよくあります。
専門用語についても同様の課題があります。業界特有の専門用語や、新しい技術用語などは、AIの学習データに含まれていない可能性が高く、誤変換の原因となりやすいといえるでしょう。「デジタルトランスフォーメーション」が「でじたるとらんすふぉーめーしょん」とカタカナで変換されたり、略語の「DX」が「でぃーえっくす」となったりするケースもあります。
このような誤変換は、文字起こし精度の評価において考慮すべき要因です。社内固有の語彙については、別途辞書登録機能やカスタマイズ機能を活用して対応することを検討することをおすすめします。
とはいえ辞書登録機能などで、わざわざ社内の専門用語や固有名詞を登録するのには、莫大な時間がかかってしまいます。この時間を削減したい方は独自アルゴリズムを活用して、過去の議事録を参照し、AIに機械学習させることなく、社内の専門用語や固有名詞の認識精度を向上させることが可能です。気になる方はぜひ一度14日間の無料トライアルまたは資料をご確認ください。
Otolio(旧:スマート書記)を14日間無料で試す or サービス資料をみる
2. 文脈を理解しての変換が難しい
もう一つの重要な注意点は、AIは文脈を理解して、正しく変換するのが難しいという点です。人間であれば前後の文脈から適切な漢字を選択できる場合でも、AIにとってはそれが困難なケースが多くあります。
同音異義語の変換は、この問題の典型例といえるます。「こうじょう」という音に対して、「工場」「向上」「口上」「好調」など複数の候補がある場合、文脈によって適切な漢字を選択する必要があります。しかし、AIは必ずしも正確な文脈理解ができるわけではありません。
また、敬語表現や丁寧語の使い分けについても、AIは完璧に対応できるわけではありません。話者の意図した敬語レベルとは異なる表現に変換されることもあり、特にビジネスシーンでの議事録作成においては注意が必要な点といえるでしょう。
これらの制約を理解した上で文字起こし精度を評価することで、より現実的で有用な品質評価が可能になります。完璧な文字起こしを期待するのではなく、人的な修正作業が必要な部分を事前に想定しておくことが重要です。
まとめ
文字起こしの精度を上げるためには、音声データの品質とAIの品質という2つの要素を理解し、適切に対策することが重要であると解説しました。特に音声データの品質は文字起こし精度に最も大きな影響を与える要素であり、この品質向上に集中的に取り組むことが最も効果的なアプローチといえます。
音声データの品質向上については、マイクの距離と向きの調整、環境音とノイズの除去、話し方の工夫という4つの方法をご紹介しました。これらの対策は比較的簡単に実施できるものばかりですが、文字起こしの精度に与える影響は非常に大きいものです。会議や録音の前に、これらのポイントを確認することで、大幅な精度向上が期待できるでしょう。
また、製品選択においては、静かな環境でのテストを実施してAIの品質を確認することが重要です。理想的な条件下での精度がその製品の上限となるため、自分の用途に必要な精度レベルを明確にした上で製品を選択することをおすすめします。
文字起こし精度の確認時には、社内の固有名詞や専門用語の誤変換、文脈理解の限界といった注意点があることも理解しておく必要があります。これらの制約を踏まえた上で、人的な修正作業とのバランスを考慮しながら文字起こしツールを活用することで、より効率的な業務運営が可能になるでしょう。文字起こしの精度向上は、適切な知識と対策により確実に実現できるものです。ぜひ今回ご紹介した方法を実践して、より精度の高い文字起こしを実現してください。
色々と文字起こしを試してみたけど
- 固有名詞や専門用語の変換が上手くいかない
- 「えー」や「あの」などの意味をなさない言葉も文字起こしされてしまう
- 話し言葉で文字起こしされて、読みづらい
というお悩みを抱えている方は、ぜひ一度、使えば使うほど文字起こし精度が上がる「Otolio」をお試しください。
Otolioには、以下のような特徴があります。
- 特許取得済の独自アルゴリズムを活用し、機密情報を学習させることなく、固有名詞や社内用語の認識精度を向上
- 「えー」や「あの」など意味をなさない発言を最大99%カット
- 発言内容をリアルタイムで文字起こし
- 最大20名までの発話を認識し、誰がどの発言をしたかをAIが自動で可視化
- Zoom、Microsoft teamsなど全てのWeb会議ツールと連携可能
- モバイルアプリによる対面での利用が可能
また議事録やドキュメントにまとめる作業も、OtolioのAIアシスト機能を活用して自動化することが可能です。AIアシストを活用すれば以下を自動化することができます。
- 要約文章の生成
- 要点の自動抽出
- 決定事項やToDo、質疑応答の抽出
累計利用社数6,000社以上の実績、大手企業から自治体まで様々な組織で利用されており、セキュリティ面でも安心してご利用いただけます。